
長編小説『くちびるリビドー』第12話/2.トンネルの先が白く光って見えるのは(6)
「実は、ちょっと話があるんだ」
恒士朗がそう口にしたとき、私たちは並んで目の前の激流に見入っているところだった。
旅行二日目。日光東照宮を巡ったあと、下調べもろくにしてこなかった私たちは、たまたま目にした案内看板を頼りに、特に期待もないままに「竜頭の滝」へと歩き出した。
しかし気づいたときは「もっと近くで感じたい!」という欲望に駆られるようにして、よりよく見える場所を求めながら滝に沿って続く横道を興奮気味に登っていた。
普通の滝とは異なり、岩肌の斜面をごうごうと這うようにして猛烈な勢いで下っていくその流れは圧巻だった。私たちは飽きることなく柵の前に身を乗り出し、しばらくの間、湧き立つ水しぶきに心を奪われていた。
恒士朗が自分から話をはじめるなんて、滅多にないことだった。
なになに? これって別れ話の雰囲気じゃないよね? それなら突然のプロポーズ? いやいや、どっちも恒士朗に限ってはないでしょう。じゃあ、なんだろう……なにごと?
告白の気配を前に、私の頭は瞬間的にフルスピードで回転しはじめた。
なんだか訳もなく怖くなってきて、思わず「ちょっと待って」と彼の言葉を遮る。
「やだやだ。なんか嫌なニュースでしょ、こわい!」
「うーん……別にこわくはないと思うけど」
「えぇ~、待って待って。心を整えないことには何も聞けないよ」
「……はい、じゃあ深呼吸して~」
こんなやり取りのあと、普段どおりの落ち着きで恒士朗が切り出したのは、転勤についての話だった。勤務先は、まさかの海外。シンガポール。
突然の報告に、心臓がぎゅっと縮み上がる。自分でも驚くほど。
☆
☆
☆
くちびるリビドー
湖臣かなた
☆
☆
☆
〜 目 次 〜
1 もしも求めることなく与えられたなら
(1)→(6)
2 トンネルの先が白く光って見えるのは
(1)→(6)
3 まだ見ぬ景色の匂いを運ぶ風
(1)→(8)
2
トンネルの先が
白く光って見えるのは
(6)
建築事務所で働くこと六年。雑用ばかりだった新人の頃(懐かしい。私たちが再会を果たした頃)を過ぎ、ここ数年の彼の忙しさは爆発的な増加傾向にあった。恒士朗が自分から仕事の大変さなどを口にすることはほとんどなかったが、一緒にいられる時間はぐんぐん減っていき、その寝つきの良さはもはや怖いレベルにまで達していた。
しかしどんなにハードな毎日でも、その場所は恒士朗の目指していた就職先の一つだった。彼は憧れの建築家のもと、無我夢中で(おそらく深いところでは楽しさも感じていただろう)日々の仕事に没頭していった。
業界ではかなり名の知れた建築家が代表を務めていることもあり、仕事の依頼は国内にとどまらず、建築ラッシュに沸く諸外国からも舞い込んでくるらしい(その建築家が言うには「いつの時代も、世界のどこかは必ず景気がいい」とのこと。広く世界に目を向けていれば、日本では不可能なような大きな仕事にも出会うことができ、勢いに乗っている国との間で行われる仕事はスピード感がありエネルギッシュで面白いとのことだった)。
シンガポールで建設が予定されている美術館のプロジェクト・チームに選ばれてからというもの、海外へ出張する機会も増え、恒士朗の内なる情熱は人知れず燃え上がっているように思えた。
この転勤話を断る理由などあるはずがないことは、私が一番知っていた。
「もちろん行くんでしょ?」
探りではなく確信を持って、私は尋ねた。
「そのつもり……だけどね」
淡々と、しかし何らかの含みを持たせた感じで彼は答えた。
「シンガポールかぁ。マーライオンしか浮かんでこないな……。どのくらい、行くの?」
「二~三年、かな」
「いいんじゃない? 人生一度くらい、ほかのことは全部ほっぽり出してでも、やりたいことに突っ走る――ってときがあっていいはずだよ」
心からそう思っているはずなのに、喋る私の目からは涙が溢れ出す。
「一緒に、行く?」
「行かない、行かない。勝手に涙が出てくるだけ」
嘘じゃなかった。困ったような、心配そうな、いつものあの顔でこちらを覗き込む恒士朗に泣きながら笑って答えて、頭ではもう「シンガポールに遊びに行くのも楽しそうだな」なんて考えていた。
遠距離なんて、全然平気。たったの二~三年でしょ。ここらで私も、人生見つめ直すタイミングなのかもね。そう考えている頭と涙を流させる心がバラバラで、次の言葉がうまく出てこない。
恒士朗の忙しさと逆行するように、専門学校での二年間を終えてしまった私は(いちおう写真に関わる職には就いたものの)仕事への面白さを見出せぬまま要領ばかりよくなって、彼との交際がはじまってからはもう、あり余るエネルギーを「お疲れの恒士朗に、何か美味しいものでも作ってあげよう」と消費することでなんとかやり過ごしているような日々だった(ここ最近は落ち込むことに忙しく、さっぱりと彼を遠ざけていたけれど)。
カメラに対する熱い何かが自分の中からすうっと遠ざかっていくのを、職探しをはじめた時点で気づいていた。依頼されたものを撮影する仕事なんて、本当はまったく興味を持てなかった。だけど写真以外の仕事にはもっと関心がなく、たとえばフリーの写真家としてやっていこうというようなチャレンジ精神も、あの頃はまるで湧いてこなかった。
私はただ写真を撮るのが好きで、撮りたいものを撮りたいように撮影し、それを自分で現像して、そこに写し出される自分だけの美意識みたいなものに酔いしれるという遊びを楽しんでいただけなのだろう。
だけど、この道に進んだおかげで恒士朗と再会できたのだから、後悔はない。
就職した写真スタジオは十数名のスタッフからなる小さな会社で、風通しのいい職場を求めていた私には理想的な環境だった。先輩たちは常に忙しく、ざっくりとした研修を受けただけで、あとはもう「仕事は現場で覚えろ」と言わんばかりに連日さまざまな撮影現場に同行するようになった。そして一ヵ月も経たないうちに私は、フリーペーパーなどに掲載されるモデルハウスの撮影現場へと単独で向かうようになっていた(実際のところ、ざらざらの紙に小さく印刷されるだけの写真など、そこそこの技術があれば誰が撮っても変わりなく、新人に与える最初の仕事としてはぴったりなのだろう)。それは気負うことのない分、やりがいも感じられない、実に退屈な仕事だった。
そんなふうにして入社後半年くらいは、事前に打ち合わせの必要もないくらいの簡単な仕事をとにかく数多くこなした。私は三脚さえ持つことなく、時間に遅れぬよう注意して現場へと向かい、新築物件の外観やリビング、新しくオープンしたカフェのランチセットなど、物言わぬ対象に向かって依頼者の指示どおりにシャッターボタンを押し続けていればよかった。撮影は便利なデジタルカメラ、画像データは後日メールで送るだけ。
それからすぐ、残暑厳しい九月のことだった。
長年のクライアントであるA建築事務所からの依頼で、私は珍しく社長に声をかけられ一緒に打ち合わせへと向かった。その建築家とうちの社長は昔からの知り合いらしく、彼が個人からの依頼で建てた住宅のほとんどを社長が撮影し、基本的には会社用の資料として(とはいえ有名な建築家であるA氏が建てた家ということもあり、それは立派なフォトブックのような仕上がりになるわけだが)、またときにはA氏の建築物を特集した雑誌などに、社長の写真が使われることもあった。それらはすべてフィルムで撮影されており、社長の写真が好きだった私にとって、この仕事に同行できることは大きな喜びだった。
「これ、うちの新人。今回はこいつに進行もろもろやらせるんで、よろしく頼みます」と名刺交換もしないうちに社長に紹介され、私は慌てて挨拶をした。
多忙のA氏に代わって現れた五十歳くらいの担当者(元ラガーマンっぽい)は、うちの社長とにこやかに言葉を交わしながら、こんなことを言った。
「うちも新人にやらせようと思ってるんですがね、なんせほら、最初はとにかく掃除と現場だから。今日も現場でコキ使われてるはずですわ」
まさか、それが恒士朗だなんて――そのときの私はもちろん知るはずもなく、さくさくと進んでいく打ち合わせの内容を聞き漏らすまいと必死にメモを取り続けていた。
そうして撮影日が決まり、間取り図などを受け取って(仕事のできる人たちは、無駄話などにダラダラと時間を費やしたりはしないのだ)、打ち合わせは三十分もしないうちに終了した。
帰り道。普段の移動手段は地下鉄やバスがほとんどだったが、この日は社長が車を出してくれていた。
「写真は全部、俺の責任で俺の好きなように撮る。当日はアシスタントみたいなこともしなくていい。この仕事は本来、俺一人でやるはずのものだからな。おまえの仕事はクライアントとの連絡係で、向こうもそれは新人に任せると言ってたな?」
「はい。それなら私は当日、社長の仕事ぶりを、ありがた~く見学しているだけでいいんでしょうか?」
私は助手席から聞き返した。職場では先輩たちに「変わり者」と苦笑いされている社長だったが、私は父親くらい歳の離れた彼に不思議と親しみやすさを感じていた。そして彼も、屈託なく接してくる私のことをなかなか気に入ってくれていたと思う。
「おまえはおまえで好きに撮って、俺と勝負してみるか?」
「えぇ~、勝てるわけないじゃないですか。フィルムの無駄遣いになりますよ」
「どうせ会社のフィルムだろ。かわいい新人育成のために、使わせてやってもいいぞ」
その言葉を真に受けて、本当にカメラを持参した新人は私が初めてだったらしい(あとになって私は先輩たちに大笑いされながら、その事実を知った。もちろん社長に張り合おうなんて気はさらさらなく、単純に面白そうだったのと本当に勉強になると思い、自前のライカで参戦することにしたわけだが……結果的に私も「変わり者」の仲間入りを果たすことになってしまった)。
迎えた当日。A氏がデザインした完成したばかりの「S様邸」で、不慣れな感じで名刺を差し出す恒士朗を前にしたときの私の気持ちといったら、どう表現したらいいか!
ただひとつ、はっきりと「やっぱり会えた」と思ったことだけは忘れない。
受け取った小さな長方形の紙には『楢戸恒士朗』という名前が記されていて、私はその五つの文字を脳のどこか特別な場所に保存し、その音を心の中で繰り返しながら、彼の瞳を一瞬だけ覗き込んだ。
――今度こそ覚えてますか?
だけど、その真相を垣間見ることはできなかった。
そして私は地面から数ミリだけ浮いているような気持ちのまま、その「家」と呼ぶには斬新すぎるコンクリートの箱のような空間で精一杯、自分を仕事モードに変換させながらシャッターを切り続けた。この胸の高鳴りを知っているのは、愛しのライカだけ。
後日。出来上がった写真を前に、社長は首を傾げて言った。
「おまえ、熱でもあったのか? それともあの家、そんなにもおまえ好みだったか?」
「社長の横で写真撮るなんて、これでも緊張してたんですよ」
私は適当な言葉を返して、自分の顔が赤くなるのを誤魔化した。
*
月と太陽が同じ方角に位置するとき。
そう。「新月」の姿を、私たちは目にすることができない。
一度死に、真っ暗な闇に呑まれ、そこから再び生み出されるとき、暮れてゆく西の空にそうっと現れるそれは針のように細く、だけどどうしてだろう、儚げな印象は与えない。
愛用している手帳には月の満ち欠けだけでなく、水星の逆行期間や木星の移動日など惑星に関する情報も記載されていて、迎える新月が「日食」という特別なものであることを私は知っていた(今回は「部分日食」で、日本からは観測できないらしいけど)。
たとえ目にすることができなくても、世界のどこかの空では本当に、太陽に月が重なる壮大な天体ショーが繰り広げられる。
その現象を「これまでの大きな流れが一新される再生のタイミング」だと捉え、それに意識的でありたいと思うとき、人はどれだけ自分の人生に「宇宙のリズム」のようなものを取り込んでいけるだろう(また、それを取り込めたとして、人生に訪れる数々の荒波をスムースに乗り越えていくことが少しは可能になるのだろうか。それは人にどれほどの「生きやすさ」のようなものを与えるだろう……)。
そして私は今、恒士朗によって突如投げ込まれた変化球を、どれだけ柔軟に受け止められているだろう。このボールは、ここから広がる私たちの未来を大きく変えるような一球となるのだろうか。
あいたスペースには、新しい何かが流れ込んでくる。
「私がこんなにも満たされなさを抱えているのは、たっぷりの母乳を与えてもらえなかったからに違いない」と、長らく胸の一部を占領し続けていたドス黒い塊がようやく消え去り、そこに誕生したまっさらなスペース。
未来の私(「運命」と呼ぶより、こっちのほうがずっといい)は、この瞬間を見逃したりはしないのだろう。
自分の中で古びつつある何かが終わり、同時に新しい何かが生まれ出ようとしている感触に、私の心は戸惑っている。こんなふうに先の見えない状況に立たされたとき、私はいつだって好奇心よりも不安感のほうに強く引っぱられてしまう。
だけど。特別な新月を前にもたらされたこの展開を、私は信じたい。
それはきっと私たち二人を正しいスタートラインへと導いてくれるはずだ。
そう信じたいから、この心を裏切ることのない嘘のない選択を――「しなくては」でも「すべきなのだ」でもなく、「しよう」と言える自分でありたい。
そして。
私はやっぱり、恒士朗を失いたくなんかない。
◆
2 トンネルの先が白く光って見えるのは
↓
↓
↓
3 まだ見ぬ景色の匂いを運ぶ風
〜第13話へつづく〜
Copyright KanataCoomi All rights reserved.
ここから先は
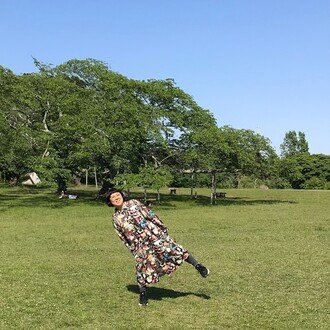
長編小説『くちびるリビドー』を楽しROOM
「私がウニみたいなギザギザの丸だとしたら、恒士朗は完璧な丸。すべすべで滑らかで、ゴムボールのように柔らかくて軽いの。どんな地面の上でもポン…
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
“はじめまして”のnoteに綴っていたのは「消えない灯火と初夏の風が、私の持ち味、使える魔法のはずだから」という言葉だった。なんだ……私、ちゃんとわかっていたんじゃないか。ここからは完成した『本』を手に、約束の仲間たちに出会いに行きます♪ この地球で、素敵なこと。そして《循環》☆

