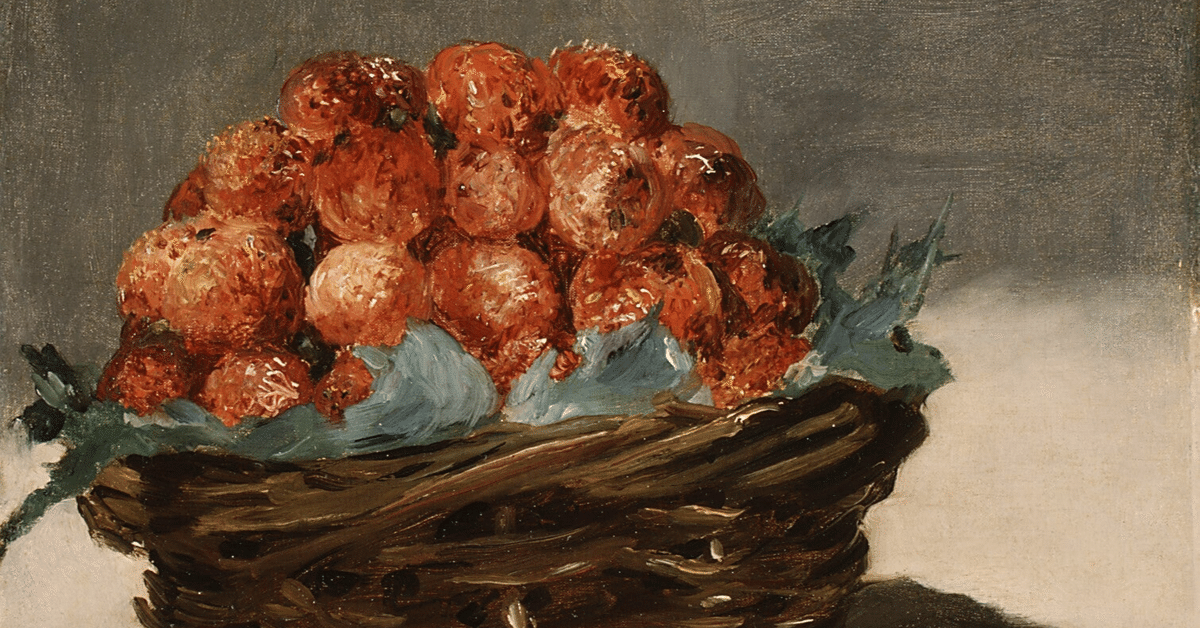
2,3月の読書記録「堕落論」再読など
今月は乱読の月だった。
複数の勉強をすることで基礎代謝をあげていれば、単に国試の勉強をだらだらするよりも総勉強量は増えるはずだ。来るべき日にはこのリソースを国試に集中投下することで本業の医学も捗ろうというもの。そのための暖機運転と思う。
『堕落論』坂口安吾(再読)
高校時代に読んだ堕落論の再読。
当然と思っていた体制や権威、平和が崩れる時代。冷戦後の核抑止すらぐらつき、ゼレンスキーが第三次大戦を憂う現在、歴史が繰り返されることを僕たちは否応なく痛感する。戦争の存在感が増す中、戦中戦後の文学を読み返して滋養としたい。
坂口安吾は日本民族の堕落の先に新境地を説き、戦後日本の再興を後押ししたのだろう。「堕落」を「分裂」「脱領土化」と読み替えて、ドゥルーズ・ガタリ的な読み方もできる。
ナチスや現在のロシアの失敗を経て、民族主義が堕落と再興を繰り返すなか、僕たちが見出す「あらたな武士道」「あらたな天皇」は、民族主義の枠から脱した、もっとラディカルなものでありたい。それが何かはわからないが……。
『不如意の身体ー病障害とある社会』立岩真也
青土社、2018年。
医学部図書館に並んでいた障害学の本で、赤いカバーが目を引いた。著者は立命館大学の社会学の教授。この本ではじめて知ったが、実習先の児童精神科医の先生はご存じで、今度学会にお呼びするとのことだった。
僕は「治す」ことよりも「生きる」こと、病院よりも社会生活、医療よりも福祉に興味がある。障害学はそういった興味をこれまでもさまざまな点で助けてくれた。
著者が発表してきたコラムを本にしたもので、一貫性はうすく通読には向かない。序文を読んで気になったところをつまみ読みするのが楽だと思う。
僕がひとまず読んださわりの1~3章では、身体(立岩の『身体』は精神も含む)と社会とがかかわる五つの契機をあげることで、障害の扱いかたが病と異なる議論を必要とすることをわかりやすく示している。
「障害はない方がいい、とはいえない」という主張もここから導かれる。できないことは他人や社会システムによって代替可能であり、その方が楽な場合もあるからだ。しかし、社会や他人のリソースにも限度がある。このことは障害以外の「できないこと」一般についても言える。ふつう障害は「インペアメント(機能障害)」を前提とし、「ディスアビリティ(不利益)」をそれと分けて考えるが、立岩はインペアメントが無くとも、我々が抱えている「できないこと」一般(能力の個人差)に対して議論を拡大しようとしている。
立岩にとって障害は議論対象の一部でこそあれ、全体ではない。生活一般とそれに付随する「できなさ」「苦しさ」を対象とする姿勢に共感する。
過去の議論の流れも説明があり、巻末にはブックガイドもある。障害学を問いの立て方から勉強できる良書だと思う。
『医療人類学入門』波平恵美子
朝日選書、1994年。
去年、研究実習でお世話になった先生から借りたままになっている本。
医療人類学とは、医療を各文明・社会のもつ「文化」と捉え、それらをアーカイブし、比較する学問である。医療人類学は多文化相対主義の立場をとる。その立場では、西洋医学は沢山の医療文化のひとつでこそあれ、絶対のものではない。
これは医療実践においてよく理解される話だと思う。医療者が患者と向き合うとき、患者のもつ「医療文化」に注意を傾けない者は、本当の意味で患者や社会を医せないだろう。
これはアフリカの儀式と西洋医学のようなわかりやすい「異文化」だけでなく、日本に住む我々においても同様だ。人類学では「シンクレティズム」という言葉がある。ひとつの社会が複数の文化や信仰を受け入れる状態のことだ。日本人が盆とハロウィンとクリスマスをすべて祝うのもシンクレティズム。医療においても、西洋医学と漢方医学、「痛いの痛いのとんでけー」のようなまじない、「火傷にアロエを貼る」のような民間療法、そして迷信や疑似科学が混在しており、我々はそれらに順位付けをして場面ごとに様々な医療文化を採用しているのだ。
現実世界で医療を行う者として、自分が医す地域や、目の前の患者の文化を知ることは実践上重要だ。本書は簡潔で読みやすく、良質な入門書だと思う。
