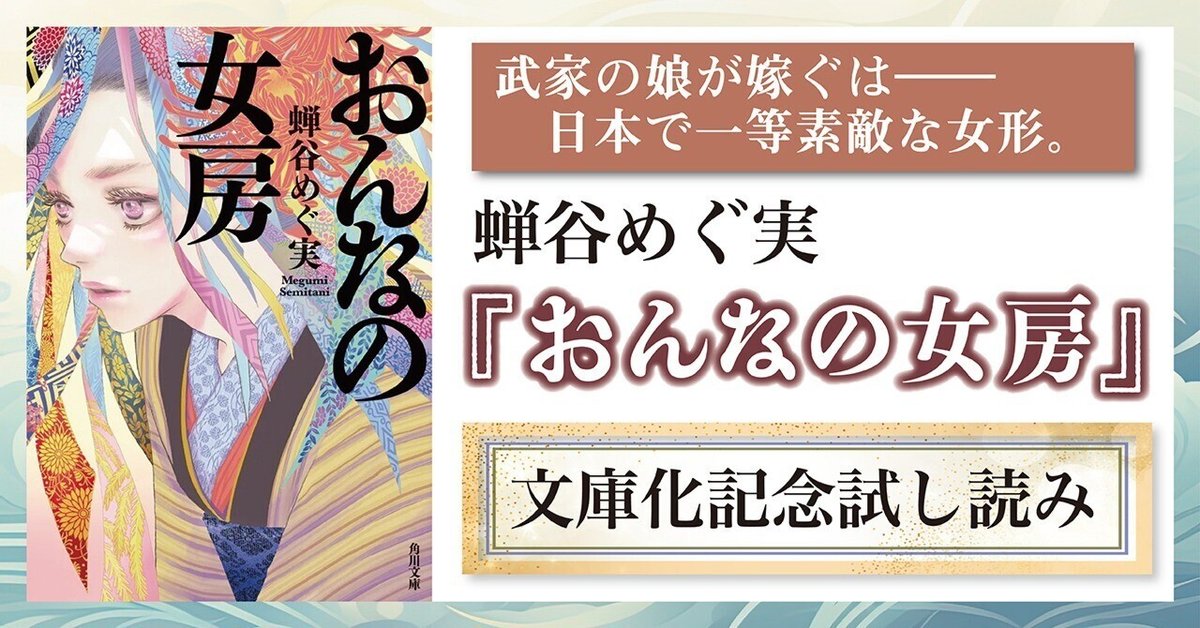
【試し読み】蝉谷めぐ実『おんなの女房』第一章特別公開!【文庫化記念】
武家の娘が嫁ぐは――日本で一等素敵な女形。
蝉谷めぐ実による江戸歌舞伎恋愛譚『おんなの女房』が待望の文庫化!
文庫版の発売を記念して、第一章「時姫」の終わりまでを特別公開します。
歌舞伎を知らぬ武家の娘と、女よりも美しい若手女形。
いびつな夫婦の恋物語の幕開けを、どうぞお楽しみください。
あらすじ
ときは文政、ところは江戸。武家の娘・志乃は、歌舞伎を知らないままに役者のもとへ嫁ぐ。夫となった喜多村燕弥は、江戸三座のひとつ、森田座で評判の女形。家でも女としてふるまう、女よりも美しい燕弥を前に、志乃は尻を落ち着ける場所がわからない。
私はなぜこの人に求められたのか――。
芝居にすべてを注ぐ燕弥の隣で、志乃はわが身の、そして燕弥との生き方に思いをめぐらす。
女房とは、女とは、己とはいったい何なのか。
いびつな夫婦の、唯一無二の恋物語が幕を開ける。
蝉谷めぐ実『おんなの女房』試し読み
呼込
おっとそこ行く鎌輪ぬ文様の大旦那。
ちょいとあちら行く高麗屋格子の別嬪さん。
足を止めなすったね、こちら行く斧琴菊のご家族一行。
台の上から御免なすって、道行く皆々様方のお耳をちいとご拝借。
この森田座の木戸芸者が二人、本日の芝居のご案内ご案内ぃ。
あら、絵本番付を茶屋で購って、役割をきちんと頭に入れてきた?
だめだめ、そいつで満足していちゃあ芝居の素人。
あっしの読み立てにこいつの役者声色真似尽くしを聞いてはじめて、今日の芝居を楽しめるってもんだ。なにせあっしは声千両……おや、いつの間にやらこんなにお人が。よしよし、そんなら、こほんと一つ。
とざい、とーざい。
ときは文政、頃は皐月。
一人のある若女形が春の雷の如く、ぴしゃりと檜舞台に現れるところから、芝居は始まるのでござります。この女形を芯に据えたいところではありやすが、残念至極、この女形の女房というのがしゃしゃり出て、女房の語りで話は進む。武家から嫁いだこの女、芝居を知らず、役者も知らず、武家のお仕来りを舞台に持ち込む面皮の厚さ。ああ、なんと哀れな若女形。それでも、女形は芝居に命をかけている。周りの役者たちの助けも借りて、難役をこなしてのし上がっていくのです。しかし、女房は金子のことしか考えちゃあおりやせん。小屋に乗り込み、舞台に上がり、己の夫の足を引っ張る様はまるで獄卒。
さあさ、この女形とその女房、一体どんな大詰めを迎えるのか。
是非に是非に、皆々様の御目でしかとお確かめぇ。
あ、いちどきに鼠木戸に押し寄せないで。木戸札はきちんと袂から出して木戸番にお渡しを。順繰りにくぐってくださいましね。
一、時姫
燕に菖蒲の絵付けがされたお猪口が二つ、こちり、こちりと目の前に置かれる。猪口から指を離す際、人差し指の爪でざりんと畳の目を引っ搔いていくところは、いかにも苛立っておりますといった感じだが、志乃はいくらかほっとしていた。先月みたく煙管の灰をそこら中に撒き散らされることはないし、「その右のお猪口」と言いつつ、指で指し示してくれる気遣いも、先月とはまるでお人が変わったようにお優しい。
「こちらが昨日、お志乃さんが購われた紅」
志乃は猪口ににじりより、おずおずと中を覗き込む。猪口の内側には紅が塗り込められている。赤で、艶々、金箔はなし。うん、と一つ志乃は頷く。
「こちらが今日までわたしが使っておりました紅」
左の猪口に首を動かす。赤で、艶々、金箔はなし。うんうん、と二つ志乃は頷く。
「なにが違うか分かりませぬか」
言われて、志乃はびくりと肩を震わせた。
「分かりませぬか」
重ねて問われても、揃った三拍子に指折り満足していた志乃には、まったくもって分からない。ふうと深いため息が聞こえて思わず身構えたが、煙草盆が引き倒される音は聞こえてこない。
こわごわ顔を上げるとその人は、唇の端で薬指の先を食んでいた。志乃の目に気づくと、袖口で口元をそっと隠し、濡れた薬指の腹で左の猪口の内側を素早く撫ぜる。ほら、どうです、と手の甲に擦り付けられた赤は、その人の、新芽の薄皮を一枚剝いたかのような透いた肌にはよく映えた。
「色がきれいに伸びるでしょう。これこそ質の良い紅の証立て。最上の紅花で作った紅餅は粘りがあって、こいつを絞ってできた赤は、唇の皺の間に吸い付いて離れない」
そこで一旦言葉が切れて、小首がちょんと傾げられる。志乃が慌てて袂から杉原紙を取り出せば、目の前にある口端は分かりやすくつり上がる。
「左の伊勢屋も右の玉屋もどちらも吸い付きのいい上物ではありますが、わたしの唇は上より下がほんのぽっちり厚いので、より赤の濃い伊勢屋のものが入用です」
言われたことを手元の紙に書きつけながら、志乃はちらりとその人を見やる。どうやら今回のお人は随分とおとなしい女人らしい。やっぱり、先月とはまるでお人が変わったよう、と思ったところで、志乃はううん、と首を横に振る。まるで、も、よう、も必要がない。
だって、この人は本当に、お人が変わっているんだもの。
「お志乃さんなら、わたしが使っている紅くらいお分かりになると思っていたのですけれど」
その下がり眉にもお初にお目にかかりまして、と思いつつ、志乃は額を畳に近づける。
「申し訳ございません。次は必ず手抜かりのないよう」
「それはようございました」
体を起こせば、そこには卵の白身だけを泡立てたような柔い笑み。志乃がほうっと胸を撫で下ろしたのも束の間のことで、
「では、お気をつけて」
「え」
志乃は思わず声を上げた。その人は口の端に笑みを泡立たせたまま、なおも言葉を繰り返す。
「お気をつけて、いってらっしゃいまし」
「ですが、今日はその、蛭子屋さん、質屋が家に訪ねてくることになっていて……」
「蛭子屋ならよかった。馴染みになら、わたし、紅なしでも顔を出せますもの」
「顔を出すって、蛭子屋さんに会われるおつもりですか?」
あなたのようなお姫様が。
口からぽとり零れ落ちた体で呟いてみたが、その人の顔の上では眉毛の一本たりとも動かない。
「だって、誰かが蛭子屋に言付けなければいけないでしょう。お志乃さんなら伊勢屋に紅を購いに行っていて、家内にはおりませんよと」
ここで志乃は確信した。
今日は随分漬け込まれている日だ。
こうまで漬かっていれば、志乃のどんなご提言にも耳を傾けてはもらえまい。諦め、志乃は紅猪口を袂に入れて立ち上がった。部屋の出口に足を進めつつ、はしたなくともしようがないのと自分に三度言い聞かせてから、畳の上の物々へと視線を走らせる。
手毬が金刺繡のその白綸子は見覚えがあるから良しとする。横に、花喰鳥が羽を広げた縮緬帯、その横、紺鼠色の煙管入れ。開きっ放しの鏡台の抽斗にきしきしに詰め込まれている簪まで目をやって、やだ、その御所車柄の絽羽織はいつの間に仕立てあげなさったの。冷や汗が一筋背中を流れたが、先月のお人と比べればその泣き言は飲み込めた。羽織一枚なら、志乃が傘張りを頑張ればどうにか支払える。質草を入れて金を用立てた様子もないから、今日のように質屋が押しかけてくることもないだろう。おまけに畳の上の着物は畳まれ折り目がつけられて、積まれた浮世絵の山は端が揃えられている。おとなしい上に綺麗好きなお人だなんて、万々歳だ。
部屋を出るなり紙入れを引っ摑んで外に出たが、志乃は一寸立ち止まり、閉めた格子戸へ貼り紙をしておいた。『姫様おわし〼』との一文を見れば、蛭子屋も尻尾を巻いて逃げ帰るにちがいない。先月、家に上がったところを捕まえられて、貝合わせに雛遊びと半日付き合わされたことは、絞れば泣き言が滴るほどに骨身に染み込んでいるはずだ。
四月の風は、人の肌を撫でていく春先のものとは違って力強い。捲れ上がった貼り紙にもう一度米粒をつけ直そうとしたその時、後ろから袂をぐいと引かれた。振り向きざまにその手を右手で押さえ込み、素早く体を回す。すると女子の顔が目の前に現れて、志乃は慌てて手を放した。己の丸髷に伸ばしていた左手もそろそろと下ろす。
よくよく見れば女子の顔は三つほど並んでいて、春ちゃんが言ってよ、うそ、清ちゃんが言う約束だったじゃない、同じ色の着物を纏った体で押し合いへし合い戯れている。飛び跳ねるたびに簪に括り付けられた鳥の羽がしゃらしゃらと鳴って、あんなに飾りがあっては摑みにくいでしょうに、と志乃は人知れず思ったりもする。燕の喉のような赤錆色の着物の団子からついに一人が押し出され、志乃の顔をもじもじと見上げた。
「この家の女中の方ですよね?」
志乃が言葉を詰まらせたのをどうやら頷きと受け取ったようで、女子たちから甲高い声が上がる。
「ねえねえ女中のお姉さま。これを渡して指の形をもらってくださいな」
猫撫で声で渡された一枚の浮世絵には、畳の上に横座りをする女子の姿が描かれていた。いくつも並べられた紅猪口の中身を吟味するためか、その目はそっと伏せられている。女子は顔のあたりへ右手を寄せて、薬指の先を柔らかに食み――、
「口元! この絵の口元のあたりに指墨が欲しいんです! 墨をつけた薬指の先を押し付けるだけでいいの」
いつの間にやら女子は志乃の背中に回り込んでいて、肩から顔を覗かせようとしている。志乃が少し腰を折ってやれば、爪紅を塗った指先が薄い紙をとんとんと叩く。
「あなたの指じゃないですからね。燕様の指よ、燕様、喜多村燕弥様」
何も答えられずにいると、「なるほどね」と紙を叩いていた指がいきなりついっと志乃に向く。
「あたしがもどきの燕弥贔屓じゃないか疑ってるってえ、そういうわけね」
途端、女子の小さな舌が上唇を勢いよく湿らせる。
「お江戸三座のうち一つ、森田座に春の雷の如くぴしゃりと現れた若女形。如月狂言で演った初姫は上も上吉。今はまだ大部屋役者の中二階で名は知られていないが、唾をつけておいて損はないってのが芝居好きの評。燕弥贔屓は薬指の先を食んでから、唇に紅をのせるのよ」
もちろんそいつは初姫の真似ね、と女子はふふんと鼻を鳴らす。
「役者紋は抱き燕で、屋号は乙鳥屋。好きな紅は日本橋玉屋の小町紅!」
ああ、惜しい。出かかった言葉は口の中で磨り潰す。玉屋でなくって伊勢屋です。ついでに今からその伊勢屋へお使いに、なんて漏らしたが最後、この女子たちなら、志乃が袂に忍ばせている紅猪口を奪い取りにきかねない。
役者絵を手拭いの上に載せてやり、「お預かりいたします」と頭を下げれば、燕弥贔屓たちはまたきゃいきゃいと団子に戻って、家の前から去っていった。絵を受け取りにくる日をきちんと言い置くところは抜け目ない。団子が大通りの角を曲がるのを見届けてから、志乃はもう一度紙に目を落とす。
これを描いた絵師は大したお腕だと志乃は思う。燕弥の輪郭ははっきりしているから、あえて墨汁をたっぷりと含ませた太筆で、でもその顔の中身を描くなら細い筆に持ち替えて。とがった鼻も薄い唇も一筆描きでしか許されないような繊細さで。特に目元は息を詰め、まるで毛先で蝶の腹を撫でるようにして一皮目を描き上げる。この薬指を食む初姫の役者絵は、燕弥贔屓の中でも評が高い。
かわって志乃のこの指だ。ささくれは捲れ、潰れた肉刺は色が変わっていて、志乃は思わず肉刺ごと手のひらを握り込む。
やっぱり言わないでよかったんだわ。
歩き出しながら、静かに喉を摩り上げる。
燕弥が好きな紅屋は伊勢屋であることも、今からそこの紅を購いに行くことも、それから。
己が燕弥の女房であることも。
縁談のお話が父親の舌の上に乗せられてから、己が畳に手をつくまでのその時間の短さを、志乃は今でも誇りに思っている。
煤払いも終えた年の暮れのこと、お前に縁談がきていると、父親が言い終わらぬうちに志乃は額を畳につけて、よろしくお願いしますと告げていた。相手のことも婚家のことも決して尋ねない。尋ねる必要がない。父親が決めた相手であるならば、志乃はその人の隣にできるだけ物静かにお行儀よく尻を落ち着ければいい。頭を上げると、そこには思い描いた通りの父親の満足そうな顔があって、志乃は嬉しくなったものだ。
そうだ、それでこそ堀田の女子、武家の娘。そんな風にして志乃を褒める父親の声音は優しかった。母親は父親の後ろで黙っている。喜びの声をあげるようなそんなはしたない真似はしない。目を伏せ、紙で作られた女雛のように、折り目正しく夫の言葉を聞いている。尋常なら嫁側の家が娘に持たせる持参金を、なぜか夫が嫁側の家に支払った。その金子がごろごろと父親の喉を撫でていたのかもしれないが、それでもよかった。年増と呼ばれる二十になる手前で嫁入りができることも志乃には最高の上がり目で、数日経つと己の出した目が信じられなくなっていた。でも、それも夫に会えば解決するもの。いつだって父親の三歩後ろで添うている母親を見習い、己も、女房としての収まりどころを早々と見つけ出して、女の役目をきちんと果たしていこう。そう思っていた。
祝言は挙げず、顔も見ぬまま木挽町の夫の家に移り住んで、二タ月が経つ。なのに志乃は今でも、己の尻を落ち着ける場所が分からない。この人の隣か後ろか、それとも前か。
なぜってこの人が、常に女子の姿でいるからだ。
道すがらすれ違う棒手振りの、空桶の底がきらきらと光り始めれば、そこはもう日本橋にほど近い。江戸橋を渡れば、空桶の底といわず、大八車の荷台に、大通りの地面にと、剝がれた鱗がきらめいて志乃を誘ってくる。しかし今は魚河岸に寄っている暇はない。足を動かすたびに袂の中で紅猪口が揺れている。大通りを曲がったところで、
「お志乃ちゃん」と声がかかった。
振り向けば、表に店を構える煮売り屋から男が手を振っている。木曾屋と墨書きがされた看板の下には、こんにゃくに焼き豆腐、煮豆に蛸に大根にと盛り付けられた丼鉢が見世棚に所狭しと並んでいる。
「芋の煮っ転ばし、今日はいくつ持ってくんだい」
男が差し出した丼鉢の中の里芋は目一杯煮汁を吸っていて、てらてらと春の日差しを弾いていた。
かかあは贅沢せずに飯をつくれが口癖の亭主方も、木曾屋のお菜が夕餉に出れば、口をつぐんでかっ食らうとの評判だから、木曾屋には独り者の男だけでなく所帯を持った女も並ぶ。志乃も木曾屋のお菜には、幾度かお世話になっていた。だが、
「すみません、煮っ転ばしはもう」
志乃が口籠ると、木曾屋の店主は肉に埋もれている米粒目をぱちくりとさせた。
「あれ、あのお人はこいつが好物じゃあなかったかい」
そうなのだ。そこが難しいところなのだ。
「いえ、その、前のお人はたしかにお好きだったんですけれど」
尻すぼみになる志乃の言葉に「ああ」と木曾屋は声を上げ、ぽんと手を打ち鳴らす。
「そういや、如月狂言は終わっていたね」
燕弥は常から女子の格好をしている。燕弥が一生のお師さんとする女形、芳沢あやめとやらが言うには、「平生を女子にて暮らさねば、上手の女形とは言われがたし」。その教えに従って、燕弥は舞台を降りても振袖を着、化粧をし、髪を結い上げ、女子の言葉を舌に乗せる。そこまでであれば、志乃だって、女形ってのは大変なものなんですねぇ、と神妙に頷くことができたと思う。実際、平生を女子で過ごす女形は少なくないらしい。しかし、野心溢れる若女形には、それを守るだけでは物足りなかった。
「新しい芝居に入るたび、演じる役に成り代わっちまうってのは、何度聞いてもどうにも飲み込めやしねえなあ」
言いながら、木曾屋は丼鉢の中身を木匙でぐるりとかき混ぜた。山になっていた芋が次々と煮汁の中に転がり落ちる。
「そのお芋と同じなんです」
志乃の言葉に、木曾屋は黙って煮っ転ばしに目を落とす。
「成り代わるというよりは、そのお芋のように役が染み込んでいると言った方が近いかもしれません。だから日によって漬けが甘い日と漬けが深い日がございます。漬けが甘い日は、元の燕弥さまの性の根で、衣も食も燕弥さまの好みが出ますが、漬けが深い日なぞは演じていらっしゃる人物が燕弥と名を変え、現に生きているかのようで」
その上、その漬けの甘い深いは日毎に変わって、当て込めないのも困りどころ。
「そりゃあ、同じ屋根の下、過ごすのは骨が折れるね」
「所作や口捌きで判じるしかありません。それでも分からない時は、お姫様と呼びかけてみるんです。少しでも燕弥さまが残っていれば、なんだいその呼び方はと眉間に皺が寄ったり、お口がへの字に曲がったりするんですが、今日はちっとも」
「姫様と呼ばれることを一寸たりとも疑っていない。姫様に成り切っている漬けの深い日だってえ、そういうこったな」
志乃は、動くことのなかった燕弥の柳眉を思い出しながら、こっくり頷く。
「ですが、今日は苛々があっても煙草盆をひっくり返されませんでしたので、丼鉢の底の煮崩れしたお芋ほどひたひたではいらっしゃらない」
「煙草の灰をぶちまけるなんて真似、赤ん坊であっても拳骨もんだぜ。そんなことができるのは、城下の火事の恐ろしさを知らねえ、いや、知ったこっちゃねえ世間知らずのお姫様だけだ」
「ええ」と志乃はもう一度こっくりとした。
「ちなみに此度のお姫さんの名は?」
「確か、時姫だとか」
すると、木曾屋の米粒目がかっ開く。
「時姫かい! へえ、そうかいそうかい。大きな役をもらったもんだ。こいつはなんとも楽しみじゃねえか」
時姫をご存知なんですか。口に出しそうになった言葉は間一髪舌でくるりと巻き取った。飲み下してから志乃は、いけないと己の腹をそっと押す。いけない、これは女のやることではない。言い聞かせていると、木曾屋のくふくふと笑みを嚙み殺したかのような声がある。
「そんじゃあ、時姫とそのお内儀さんの好物を教えてもらおうかい」
どうやら腹の虫を抑えていると思われたらしい。志乃が顔を赤くすると木曾屋は笑って、そんならちょっとずつ取り分けてあげるよ、とお菜をいくらか持たせてくれた。礼を言いながら、ふと木曾屋の腰に視線を落とした。帯に挟み込んだ煙草入れから木彫りの根付が揺れている。その四つの花菱紋は高麗屋、松本幸四郎の贔屓だそうだが、これが抱き燕の役者紋を持つ相手となると、志乃は胸の内でふん、と気合を入れねばならぬ。
煮売り屋からそのまま二町ほど北へ下れば、間口の一際広い大店が見えてくる。伊勢屋の文字が白く抜かれた暖簾をくぐり、笑みを浮かべて辞儀をした女の前で、志乃はふんふんと二回ほど気合を入れた。
「紅猪口をお渡しくださいませ」
志乃を店の奥へと案内した伊勢屋のお内儀は、志乃が足を畳むなり、両手を出した。志乃が慌てて袂から取り出した猪口を持ち上げるその手拭いは案の定、燕の喉の如く赤錆色で、燕が何羽も飛んでいる。
「やはり玉屋さんの紅では燕弥様はお気に召しませんでしたでしょう」
志乃は勢いよく顔を上げたが、お内儀は羽二重絹を敷いた長方形の蒸籠を手前に引き寄せ、中身を木べらで混ぜるので忙しくって、なんてご様子で己の手元に目を落としたままだ。
志乃は邪魔をせぬよう、「よく知っていらっしゃいますね」とそっと返したが、そいつはお内儀の中のなにかを引っ搔いたらしい。
「御新造さん」とお内儀が志乃に呼びかける。その声は川の水を吸った着物のように重く冷たい。
「もしや御新造さんは、世間の芝居好きをご存知でない?」
存じないわけがない。実家のある出羽から江戸へ嫁入りしてから、志乃は江戸の芝居好きたちの、その熱狂振りに日々驚かされている。だが、芝居と己の間に一線引くことを心掛けている手前、知っていると言うのもどうか。もごもごとする志乃にしびれを切らしたか、お内儀は紅刷毛を手にとって、柄の部分で蒸籠のへりをこんと叩いた。
「役者は船頭でございます。舞台で何気なく身につけた物一つで江戸に渦巻く潮目が変わる。やれ團十郎が江戸紫の手拭いを頭に巻いたと右に押し寄せ、やれ辰之助が変わった帯の結び方をしたと左に押し返し、皆がこぞって役者の真似をする。商い人がこれを逃すわけがありません」
刷毛を蒸籠の紅にゆっくり浸し、猪口の内側に塗りつけていく。その手際の良さは他のなによりも伊勢屋の商いの太さを物語る。
「私だって紅商いを生業としている大店の内儀、役者が唇に乗せる紅にはいつも目を光らせております。それに、役者も己の屋号で化粧の品を出したりするでしょう。こちらにとっちゃあ商売敵でもあるんです。役者がどんな紅を使うのか、皆が知りたくてたまらない」
こいつはお得意様の御新造さんを思っての言葉だと思ってくださいましね。お内儀はそう前置きしてから、志乃に向かって上品な笑みを浮かべた。
「ですからね、よく知っていらっしゃいますね、だなんてそんな素っ頓狂なこと、役者の女房ともあろうお人がお口に出してはいけません」
柔らかい物言いだ。だが、その紅の塗られた口の中で動く舌が、志乃には二股に見えるときがある。
「ましてや、御新造さんはあの燕弥様の女房なんですよ。ええ、あの燕弥様と、私はそう呼ばせていただきます。今は中通り、十把一絡げの役者ではありますが、今に世を狂わすような女形になる。私にはその絵図が見えているのでございます。だからこそ、その女形の女房がそんなでは燕弥様のためにならないと言うのです」
猪口に塗った紅が乾ききると、お内儀は紅猪口を浮世絵で包む。その浮世絵も先程の押し掛け贔屓たちが持ってきたのと同じものだ。お内儀は熱の入った燕弥贔屓で、だからこそ余計に志乃の存在が疎ましいのだろう。
金子を渡し背を向ける志乃に、決まってこの人は口にする。
「どうして燕弥様は、あなたみたいなお人を女房にしたんでしょうねえ」
怒りなぞ湧いてくるわけがない。背を向けたままでもちろん口に出すことはないけれど、その胸の内で決まって志乃も口にしている。
ええ、私もそう思います。
家に戻った時分にはまだ日は落ちていなかった。
志乃はまず燕弥の部屋の前で膝を揃えた。「戻りました」と声をかけ、一、二、三まで数えて応えがないのを確認してから、浮世絵包の紅猪口を襖の前に置く。今日も燕弥は芝居小屋へと稽古に出かけているようだ。ならば、部屋には決して入らない。煙草盆の灰を替えようと燕弥の居ぬ間に部屋に入った際には、怒った燕弥に障子の一升一升に指で穴を開けられた。一人で障子を張り替えた腰の痛みは未だ記憶に新しい。
台所に立ち、竈にとろりと火を入れたところで、表戸を叩く音がある。だが、火から離れるわけにもいかず、志乃はその場で「すみません」と声を張り上げる。
「今日の夕餉は煮売り屋で購ってまいりましたので」
表戸を叩く音はぴたりと止んで、じゃりりじゃりりと草履が路地をゆっくり擦る音が小さくなっていく。お菜の一つでも持ってってもらえばよかったわ。根深葱を刻みながら、志乃ははたと気づいて一寸ばかりへしょげたが、それならお菜を具にしたおにぎりを拵えておこうと気を取り直す。昨日はせっかく来て下すったのにごめんなさいと朝餉のときにでも渡せばいい。
志乃が嫁入りして初めて用意した夕餉は、部屋に入ってきた燕弥に横目でちらりとやられるなり、眉をこれでもかと寄せられた。燕弥はそのまま踵を返し戻ってこなかった。その次の日には通いの婆を紹介された。
実家で言い聞かされてきた、質素であることこそ食の第一義との考えを志乃は思い切ってえいやっと頭から追い出して、朝晩、家にやってくるお民に料理を習っている。近頃はようやく志乃の作った飯に箸を伸ばしてくれるようになったものの、やっぱり木曾屋のお菜は、箸の運びがいつもとは段違い。八杯豆腐より田楽がお好き。なるほど、味噌はあまりおつけにならない。ここで味噌汁の椀を手にとって、あら、叩き納豆を汁の実にしたのはまずかったかしら。
「おやめくださいと言ったはずですけれど」
燕弥の言葉に志乃は、びくりと背筋を伸ばす。
「ちろちろと目玉で舐められるのは、檜舞台の上でもう十分味わっております」
燕弥の眉間に皺が寄ったのは汁の実が理由でなかったようで、志乃は「申し訳ございません……」と消え入りそうな声で謝ってから、燕弥の箱膳から己の膝へと目を落とす。
「今日も食べないのですか」
顔を上げると、燕弥の箸は箱膳を指している。
「もちろんです」
志乃は力強く頷いた。
「殿方が食べ終わるまで妻は殿方の傍で控え、食事の手伝いをするものと実家で教えられてきましたので」
燕弥は志乃の顔をじっと見て、「ふうん」と小さく呟いた。それきり黙って、箸で田楽を細かく刻む。田楽を摘み上げ、左手で口元を隠しながら、ゆるくほどけた唇へと持っていく。その美しさが志乃は恐ろしい。
どうしてこのお人は私を女房にしたのだろう。
志乃は燕弥を眺めながら、ぼんやりと考える。
燕弥には聞かない。聞けない。なぜって志乃は女房だからだ。夫に従い、夫のために行動をする。飯をつくり、汚れ物を洗い、温く柔らかい肉で夫の労をねぎらって、ぽんぽん子を産む生きものだ。それに、己はどうやらそれなりの顔らしいから、見目で夫を癒やすこともできるはずとそう志乃は、一寸自信もあって嫁いできたはずなのに。
目の前には女の己より美しい女がいる。
ならば、私はなんのためにこの家にいるのだろうか。私の価値は一体どこにある。
志乃は行灯の火を消し、布団の中にもぐりこむ。燕弥とは寝所を別にしている。燕弥がそう申し付けたからだ。志乃は体を丸め、右手を己の胸に当てる。思ったよりもそいつは柔らかく、志乃はほうっと息が吐けた。
「口入屋に頼んで、通いの女中を呼んでおきました。朝餉と夕餉時に訪ねて来るかと思いますので、そのお人から洗濯や台所のことをきちんと習ってくださいまし」
燕弥にそう告げられたとき、志乃はうなずくほかはなかった。たち縫い、茶の湯、聞き香に薙刀なんぞは実家で厳しく躾けられたが、町娘の稽古事の定石らしい三味線、料理方、小唄は武家の娘に必要がないと言われて、庖丁はほとんど握ってこなかった。くわえて役者の家には役者なりの仕来りというものがあるはずで、お民はそれを教えてくれるために雇われたに違いない。
豆を煮るお民の箸遣いを杉原紙に書き込みつつ朝餉の用意をしたあとは、米のとぎ汁を盥に入れ、洗い物を抱えて井戸端へ行く。このところ、志乃はこのお民からの手習いの時間が好きだった。
お民に言われたとおりに盥の中でとぎ汁を襦袢にすり込んでいると、案の定今日も後ろに気配があって、志乃は寸の間手を止める。すぐに振り返っては逃げられる。そうこの人はお猫さま、お猫さま。言い聞かせ、志乃は盥のへりにかけた手拭いで手を拭いて時を稼いでから、ゆっくりと首を動かす。
「あの、なにかございましたでしょうか」
志乃の傍に立つ燕弥は、にこにこと笑っている。
「いいのよ、わたしのことはお気にせず、そのまま続けてくださいな」
そう言って後ろで手を組み、盥を覗き込む燕弥の髪はゆるめに結わえられていて、はらりと一本こめかみにかかる。
漬けが時姫になってからというもの、燕弥はこうして、志乃がお民から手習いを受けている様子を見にくるようになっていた。どんなにつんけんしている日でも、志乃が飯櫃から米をよそったり、着物をさいかちの実で揉み込んだりしているとふらりと現れ、にこにことしながら志乃を見ている。手習いが終われば、途端なにかを思案するような顔つきになり、声もかけずに去っていく。
稽古場へ向かう燕弥を見送ってすぐ、志乃の頭にはぴいんときた。
やっぱり時姫は綺麗好きでいらっしゃるんだわ、そうなんだわ。
部屋の整い具合からも薄々は勘付いていたけれど、時姫は綺麗好きで、だから汚れ物がきれいになっていく様を見ているのは気持ちがいいってそういうわけじゃないかしら。
ならば、と志乃は襷をかけた。蚤の糞さえ残すまじの心意気で家中雑巾をかけて回ったが、小体であるから一刻ほどで終わってしまう。志乃は少し悩んでから、張り替えたばかりの障子を開けた。
燕弥の部屋は、紅の件で入った時と相も変わらず、整然としていた。繕い立ての雑巾で簞笥を擦るが、汚れもあまりつかない。鏡台には手拭いをつかったが、汚れよりもその抽斗の隙間から見える化粧道具が目を引いた。伏せられた紅猪口が何十と並び、ふと行李の中に目をやれば、三段重の円筒形の陶器が敷き詰められている。花文様が描かれているそれらにはどうやら白粉が入っているらしい。ほのかに梅の香りがする小袖に襦袢は、そのどれもが女物。
役者ってのはとんでもない生業だと、つくづく志乃は思うのだ。世間の目を一身に集めてはいるが所詮は河原者。笠をかぶってしか人様の前を歩けやしないと父親は散々なじっていたが、女子を演ずるために平生から女子であることを選んだその胆力は素敵で、そいつが裏返って、おそろしくもあったりする。
燕弥は決して男の部分を見せようとしない。
志乃は小袖が掛けられたままの伏籠を持ち上げる。
女形とはそういうものか。
志乃は箱枕に顔を近づけすんと鼻を動かしてみる。
そういうもので終わらせてよいのか。
志乃は己の手が、掃除というよりなにかを探し回る手つきになっていることにふと気づいた。気づいたならば、こりゃもう開き直りで、部屋のあちらこちらをかき回す。と、つんと饐えた臭いが鼻面を掠めた。鼻を動かしながら近づいた部屋の隅には伏籠が置かれ、上に掛けられた手拭いは湿っている。伏籠をどけると、お椀が一口。半分ほど盛られた米は黄色く、饐えた臭いは部屋中に広がって、志乃は思わず笑ってしまった。小腹の虫を養った後で片付けるのを忘れたか、あのお人にもこんな物臭なところがあらっしゃる。腐った飯はあのお人が男だと言ってくれているようで、志乃は何やら嬉しかった。
飯を捨て、洗った椀が乾く頃合いに、燕弥の帰りを告げる声が格子戸の外に聞こえてきて、志乃は肩を張る。皐月狂言の幕開きが近いためか、稽古終わりの燕弥はご機嫌が悪い。板間に上がって、志乃の差し出した茶碗で唇を湿らしてすぐさま口を引き結ぶ。そのまま自室に向かう後ろ姿を見送るのが志乃の常だが、今日ばかりは部屋の入り口までついて行く。その紅の塗られた横一文字が、にこにこに変わる瞬間が見たい。燕弥が障子を開ける隣で志乃は胸を高鳴らせる。部屋に入った燕弥は中を見回し、はたと動きを止めた。飛びつくようにして伏籠を開けたかと思うと、伏籠を壁に叩きつけた。
「なぜ捨てやがった!」
煮立った油の玉が破裂したかのような勢いに、志乃はひっと息を詰まらせる。
「く、腐っておりましたから」
「この頓馬!」
顔が美しくあればあるほど、怒りをたたえた際に凄まじくなることを志乃は初めて思い知る。
「腐らせていたに決まっているだろうが!」
怒鳴り散らして涎の泡が飛んだ口を燕弥は己の手でぐっと拭う。手の甲にべたりとついた紅に眉を寄せ、ふうと己を落ち着かせるかのように、細い息を吐き出した。
「あの飯はわざと腐らせていたんです」
一瞬の内に喉をすげ替えたような、その柔らかな声音はいつもの馴染みのあるもので、志乃の忙しない胸の内も少しだけおさまった。
「どうしてそんなことを」
「決まっているでしょう」と燕弥は窘めるように言う。
「芝居に使うんですよ。芝居ってのは言ってしまえば虚事でございますから、そこにどれだけ実を紛れ込ませられるかが要所。だからこそ、腐った飯は舞台の米櫃に入れようと思っていたのです。開けた際に饐えた臭いをかいだ客は、これは現のことかと芝居にどっぷり浸かれる」
爛々と目を光らせていた燕弥だが、「でも、おじゃんです」伏せた睫毛の影で目の光が遮られる。
「とてもよい色とよい匂いになっていたのですけれど」
志乃はただただ板に額を擦り付けることしかできなかった。
離縁だ。志乃は自室の布団の上で座り込んだまま、ぼんやりと考える。離縁に違いない。三行半は明日渡されるのだろうか。理由の文言はなんだろう。夫の仕事の邪魔をしたのだ、不都合なことを書かれても文句はいえまいが、せめて再縁だけはと志乃は膝に置いた拳を固く握る。どこぞにいるかもしれないお人との再縁だけは認めてもらわねば、志乃は女の役目を果たせない。
次の朝、朝餉の品数を増やす小賢しい真似をしてから、志乃は燕弥の箱膳の前で手をつき、三行半を待った。
「豆腐が食べたい」
志乃が顔を上げると、燕弥は少し顔を背けていた。口が鳥の嘴のように尖っている。
「夕餉は豆腐が食べたいと言ってるの」
志乃は泣きそうになった。ああ、求められている。この人はとってもお優しいお方だ。きちんと自分に役割をくれる。女房として己を使ってくれる。
「初屋の豆腐でよろしいですか」
燕弥の朝餉が終わるのを待たずして、紙入れを手に取った。土間へ駆け下りると、「お待ちを」と志乃を引き留める声がある。
「こいつを使ってくださいな」
燕弥に渡されたのは丸盆で、志乃は黙って受け取った。意図など問うはずがございませんの一文字の口を見てもらいたくって、志乃はゆっくりと頷いてみせる。
「酒もつけてもらおうかいね」
言って、燕弥は徳利を丸盆の上にのせる。
「酒でも回れば、昨日のことなんてぽーんと飛んでってしまうさね」
台所横で目についた笊を引っ摑む。丸盆と笊を胸に抱え、徳利は手に提げ、下駄を突っ掛けたところで、
「志乃!」と一際大きな声が背中にぶつけられた。
心持ちは軽く、なんでも御座れと振り返った志乃を待っていたのは、酷く冷たい目であった。燕弥の視線は鋭く、固まった志乃の体に次々と刺さっていく。足の甲、手の首、着物の袂、耳のたぶ、最後は目玉にぷっすり刺し込み終えて、
「お帰りをお待ちしております」と燕弥は優しげな笑みを見せた。
「戸口の前でお待ちしております。ずうっとずうっとお待ちしておりますから」
志乃は通りを飛ぶように走った。
家に戻ってきたとき、燕弥は告げた通りに戸口の前に立っていた。肩で息をする志乃の姿を見つけると、笑みの形に細まっていた目が開き、まるで針のように輝いた。
豆腐を盆にのせて戻ってきたあの日は醬油をぽっちり垂らして食べた。次の日も豆腐がご所望とのことだったから、豆腐を崩して酒と醬油で炒りつけて、山椒をまぶした荒金豆腐にして食べた。飽きませんかと聞いたら、飽きませんと旦那さまが言うので、志乃は『豆腐百珍』を購った。百種もの豆腐料理が記された本だが、まあ、あと二、三種ほどで鍋敷に様変わりするだろう。そう高を括っていたというのに、まさか、こんなに使い込むことになろうとは。
醬油染みのついた紙をめくったところで、がらりと格子戸を開ける音がして、志乃は大きなため息を吐く。
「御新造さん、お届けにあがりましたよう」
「またですか」
弾ける声に、志乃は洗い桶に水を張る。抱えて板間まで運んではみたが、桶行列に横入りさせる隙間がない。だというのに、男は志乃の抱える桶の中へといくつもそれを滑り込ませる。
「こいつが北紺屋町の遠野屋さん。一代で成り上がった呉服屋さんです。女子衆人気が欲しいんでしょうねえ。そんでこいつが扇町の三谷屋さんだ。ここで舐める温燗が旨えのなんのって」
店の名前は慌てて書きつけたが、この家にはもう桶を置くところなぞどこにもないし、腹の中は骨と肉の間だって隙がない。そう訴えたが、男はその大きい団栗目をぱちくりとさせる。
「いえいえ、御新造さん。これからじゃあねえですかい」
この男が胡座を組むと、家が余計に狭くなったように見えてならない。大柄な上背に合わせて、にっかり歯を出して笑うその口も大きい。
「幕が上がってまだ十日も経っていやしません。森田座にとんでもねえ若女形が出てきたってんで、やっとこさ上方まで噂が流れついた頃合いだ」
志乃は己の腹に手を当てた。おそらく腹の虫は昨日か一昨日かで、死んでいる。
「もっともっと届けられるはずですぜ」
家の中に並べられていく、大量のこの豆腐に押し潰されて。
この男が突然家を訪ねてきたのは五日前のことだった。豆腐をどっさりと持ってきて、贔屓からの祝儀でごぜえやす。笑みのまま出て行こうとするものだから、袂を引っ張り名を聞けば、善吉、燕弥の奥役をしていると言う。奥役というのは役者の世話役らしいが、志乃はここで待ったをかけた。夫の仕事を深くは聞かない。次の日にまた善吉が来ても、志乃は女らしく部屋の奥に引っ込んで黙っていた。しかし、豆腐がどんどんと玄関に届けられていく。このままでは布団も敷けなくなってしまう。仕方なく、志乃は応対するようになった。
土間に座り込む善吉に麦湯を出しながら、志乃は聞く。
「役者への祝儀は、豆腐と決まっているものなんですか」
えっ、と善吉は茶碗から口を離した。
「決まってやしませんよ。豆腐を祝儀として運んだことなんて初めてのこってす」
「あら、それならどうして豆腐なの」
尋ねると、御新造さん、と一寸ばかり硬めの声が返される。
「もしや、役者の女房さまでいらっしゃるのに此度の芝居の内容をご存じでない?」
押し黙る志乃に、善吉は「噓です噓です大丈夫ですよう」とへらりとする。
「そういうお内儀さまもおりやすからね。舞台の上であっても、自分の旦那が誰かと口説き口説かれて、終いにゃお布団に二人包まっての濡れ場なんざ見たくないってんで、一生芝居小屋には足を運ばない方もいらっしゃいますから」
「それは当たり前のことでしょう?」
強い物言いになっていることは己でもわかった。
「旦那の仕事場に女房が顔を出すなんて言語道断でございます」
「なるほどなるほど」善吉の顔が近づいて、目頭についた目やにまでがよく見える。「そういうところが良いんですねえ」
「そういうところ?」
一人うんうんと頷く善吉に眉を寄せると、「でも、御新造さんはどうなんです?」と善吉はまたもや志乃の顔を覗き込んでくる。
「御新造さんは此度の芝居のお話、聞きたいとは思いやせんか?」
「ですから、女房がそんなこと」
己の声が揺れている。合わせて腹の内も揺れている。実家で教え込まれた女としてのお役目や規範がずっしり腹の真ん中に居座っていたはずなのに、こう面と向かって言われるとなぜだかそいつがぐらぐらとしてくる。
近頃のこの芝居町の雰囲気も悪いのだ。志乃は己の親指をきりりと嚙む。
時姫、ありゃあ上上吉だ。先の初姫で目をつけていたが、いやはや、こいつは大当たり。馬鹿だね、あんなぽっと出、すぐに消えるよ。三浦之助義村の男振りったらありゃしない。いやいや、長門に目がいかねえとはとんだ節穴。
皆が芝居のことを語っていて、その熱気がこれまた志乃の腹の内を揺らす。
「内緒内緒。ばれやしませんよ」と善吉が囁く。
「ばれるって誰にです」
「いや、わからねえですが」
この問答で何やら志乃は気が抜けた。
そうよ、聞いたところで私が腹に据えているものは変わりっこない。
「いいでしょう、どうぞお聞かせください」
板間の桶と桶の間にようやく二つ体を落ち着けると、善吉が、おいらは木戸芸者ではねえですから、下手くそでも堪忍してくださいね、と言い置いた。なにを思ったか豆腐の入っていない空桶を片手で摑み、それを板間にコン、と打ちつける。
「……なんですか」
「遮っちゃあいけねえや、御新造さん。こういうのは空気ってのが肝要なんだから」
コン、と打つ。続けてコンコンと打つ。コンココココココ……コン。
ココン。
「ときは鎌倉。こいつは源頼朝亡き後のお話にござります」
演目は『鎌倉三代記』。北条時政と御家人との戦いが芝居の軸ではございますが、まあ、そいつはちょいと置いておきやしょう。なにせ此度の森田座皐月狂言で大事なのは燕弥の演ずる時姫様。時姫は時政の娘でございますが、なんと敵将三浦之助義村を慕って一人家を出、絹川村に身を寄せている。この村に身を置いているのは三浦之助の母、長門。時姫は長門の看病をしているのです。
「ちょっとお待ちください」
何やらいきなり開いた善吉芝居の幕を慌てて閉じる。へえ、と善吉は素直に応じて口を閉じるが、頰は少し膨らんでいる。
「時姫という女は己の父を裏切って、敵方の男に身を寄せているわけですか」
「そうですけど」
「なんという筋書きですか! この本を書いたお人は女の三従を知らないのですか!」
家にあっては父に従い、嫁しては夫に従い、夫死しては子に従う。こんなこと、手習い子でさえ誦じる。嫁入り前の女子が慕う男の許に走るなど、孝のかけらもない。だが、善吉は、すごいですよねえ、と間延びした口をきいている。
「恋心はなにもかもをひっくり返しちまえるんだもの」
すごいものか。志乃は己の背中の産毛が逆立つのがわかる。
「こんなものが江戸のお人たちに受けているんですか」
「だって、ほうらこの通り」
善吉の指の先にある豆腐の山には、志乃も黙るしかない。
「恋心を抱える時姫は可愛らしい。だからこうして皆が祝儀を贈ってくるんです。だが、三浦之助はそうではなかった」
善吉は、空桶をココンとやる。
病気の母を思って、三浦之助は村に帰ってまいります。だがそのお体は傷だらけ。時姫は駆け寄って介抱しますが、母、長門は障子を締め切り、三浦之助に会おうとはいたしません。武門に生まれながらに戦場を離れた息子の未練を𠮟ります。
ココン。
この障子の内は母が城郭、その狼狽えた魂で薄紙一重のこの城が、破るるものなら破ってみよ。
なんてえ重く鋭い母親の啖呵じゃあございませんか。もう良いと傷だらけの息子の体を抱き込めればどんなに幸せか。戦さに行かずこの母の傍に居ってくれ。それができぬならせめて一目会いたい。頭を撫でたい。しかし、長門はそんな母親の情を己の内で切って捨て、部屋に籠って障子を開けない。病に伏した母のこの啖呵に三浦之助は己を恥じた。涙しつつ戦場に戻ろうとする三浦之助をちょいとお待ちになって、と引き留めるのは燕弥の時姫。
ココン。
コレのう、せっかく見た甲斐ものう、もう別るるとは曲もない。親に背いてこがれた殿御、夫婦の固めないうちは、どうやらつんと心が済まぬ。
こちらはなんてえ可愛らしく切ない恋人のお願いじゃあございませんか。一晩だけでも布団の中で夫婦として明かしたい。いえ、はしたないなんて言っちゃあいけやせん。なにせ時姫が三浦之助から受け取ったその兜からは、薫きしめた香がぷんとしている。
「時姫は三浦之助が討ち死にする心胆だと気づいたのね」
「ははあ、さすがは御新造さんだ」
戦場に向かう武士は死臭を隠すため、己の兜に香を薫く。時姫はこれを嗅ぎ、夫と今生で会うのは今宵切りと悟ったのでありました。時姫だって武家の女。縋ったりなぞはいたしません。ただ今宵だけ、今宵だけでも夫婦の契りを交わしたい。短い夏の一夜さに、忠義の欠くることもあるまい。時姫の口説きには胸がぐぐうとなっちまう。しかし、三浦之助は冷てえのなんのって。敵の娘ゆえ信用できぬと振り払い、戦さに戻ろうといたしますが、母の咳がごぼごぼと耳に残っている。悩んだ末に、暫し屋敷に留まることにしたのです。
「敵の男になんぞ恋心を持つから、そういうことになるのです」
「そうです。時姫の父親だって怒り心頭だ。だから追っ手をよこします」
「追っ手ですか」と聞けば善吉が嬉しそうに空桶を振り上げるので、志乃は思わず手で制した。
「そいつを、おやめください」
「はい?」
「それです、その空桶でのココンです」
すると、善吉は恥ずかしそうに盆の窪をぽりぽりと搔いた。
「お気に障っちまいましたかね。芝居者の性ってやつで、音と拍子を入れ込むだけでずんと気持ちが入るもんですから」
それが嫌だと志乃は言うのだ。芝居者でなくっても、自然と気持ちが昂ってきてしまう。
「お詫びに、追っ手の正体を明かしやしょう」
志乃の喉がごくりと鳴って、ああ、またしても、善吉がココンとやる。
追っ手の名は藤三郎。すでに村に潜り込んでいる手練の男。一人途方にくれている姫に襲いかかった。姫の白い耳元にこいつはお父上の言と藤三郎は囁きます。時姫は殺してしまって構わない。だが、姫を捕まえた暁にはお前と夫婦にさせてやると、そうお父上は申されましたぞ。驚く時姫に藤三郎はなおも言い募る。三浦殿は今日明日の内に首がころりじゃ。首のない胴ばかりの男を抱いて寝てなんになる。如何に下の方が肝心じゃてじゃて。これには時姫も目を吊り上げた。懐刀を抜き、斬りかかる。藤三郎は頭を抱えて逃げ出した。
お可哀想な時姫様、ああ、父親からのあまりのお仕打ち。目から涙をはらはらと、刀を胸にひしと抱く。こいつは父の懐刀。これで死すれば、父に殺されたと同じこと。三浦様の女房としてこの世を逝ける。
明日を限りの夫の命、疑われても添われいでも、想い極めた夫は一人。
己の喉に突き立てようとしたそのとき、現れるのは夫、三浦之助義村。
お前の心、しかと受け止めた。ならば我が敵、お主が父親、北条時政を討て。
「時姫に親不孝の罪を課すおつもりですか!」
いいえ。時政を討ったあと、その刀で己の命をたてば、不孝には当たるまい。
頼みと言うはこれひとつ。親につくか。
さあ、それは。
夫につくか。
さあ。
さあ、さあ、さあ。
落ち着く道はたった一つ。返答はなんとなんと。
成程、討って差し上げましょう。
すりゃ、北条時政を。
北条時政、私が討って差し上げましょう。
ココン、と一際大きく空桶を打ちつけると、善吉は照れたように空咳をした。
「父様赦して下さりませと、わっと叫ぶところ含めてこの燕弥さんが大層お美しいってんで、声色連はこぞって真似をしておりやすよ」
善吉の声はどこか遠くの方で鳴っていた。志乃の頭の中では三浦之助と時姫の刀を握りしめてのやり取りが繰り返されている。ぎゅうと志乃は眉間に皺を寄せて、麦湯を飲んで一息ついている善吉を睨みつけた。そんなに語りがお上手なんて聞いていない。頭の中にへばりついたこのお姫様をどうしてくれる。
「まあ、この後は藤三郎が実は味方であることが明かされたり、長門が時姫の持つ槍を己の胸にぐいと突き立てたりと色々とあるんですけれど、おいらはここがいっち好きでして」
茶碗に麦湯のおかわりを注ぐふりで志乃が板間から離れても、善吉の声は志乃の背中を追っかけてくる。
「そして、此度の燕弥さんの大当たりは、時姫のその健気さ」
「健気さ?」
振り向こうとして、表戸を叩く音に動きを止める。昼餉時にお民を呼んでいたのを思い出し、志乃はわざと大きな声で応えを返した。よかった、お民の訪いで善吉の芝居語りは一旦幕引きと思ったところで、
「時姫もそうなんですよ」
志乃は善吉を見た。善吉はにこにこと志乃を見返している。
「時姫も近所の百姓の女房に飯の炊き方や味噌汁の作り方を教わっているんです」
三浦之助が戦場から戻ってくる前、絹川村で長門を看病しているときの場面だと言う。
「時政から時姫を連れ戻すよう申し付かった御殿女中が侍を引き連れやってくるんですが、肝心の時姫がどこにもいない。すると、道の向こうから、時姫様が豆腐を盆にのせ、酒を入れた徳利を手に提げながらやってくる」
善吉は懐から一枚の浮世絵を出し、志乃に向かってぺろりと広げた。
赤振袖の美しい女子が侍を引き連れ田舎道を歩く。その両手で支えている丸盆の上、笊を被せられた豆腐が編み目の間から覗いている。
「豆腐が崩れちまうってんで笊を被せてるんですよ。そんなことで豆腐が崩れるわけがねえのに」
崩れるわけがないではないですか。たしかに燕弥もそう言った。豆腐を盆にのせ、徳利を手に提げ帰ってきた志乃に向かって。戸口の前に立ち、志乃の体に目で針を刺し込みながら。
「でも、そういうところがいいんです。そういうところが世間を知らねえお姫様、健気な女房振りで江戸雀たちの心をきゅっと摑んだ」
私だと志乃は思った。あの日の志乃がこの浮世絵の中にいる。
「絹川村での魚の振り売りとのやり取りも、これまでの鎌三にはなかったものでしてね。燕弥さんの思い付きに森田座付きの狂言作者が、おう、そりゃいいねと正本に取り入れたそうで」
御新造さん、魚はどうだい。あら、夕餉にはなにがよろしいんでしょう。コノシロ、フグにマグロってとこですかい。
「すると、時姫がその振り売りをきっと睨みつけ、無礼者! と叫ぶところが痺れるんでさ」
善吉は胡座をかいた膝小僧にぴしりと手のひらを打ち付けて、
「どういうことか分かりやすか」と志乃を見る。
いつの間にやら表戸を叩く音は消えていた。
「……コノシロもフグもマグロも全部、武士には法度の食べ物です」
コノシロはこの城を食うに通ず。戦場にて死すべき武士がフグの毒にあたって死ぬのはもってのほかで、マグロの又の名、シビは死日に聞こえるとの理由から。
「さすがですよう」と善吉はまたぴしりぴしりと膝を叩く。
「この場面は城にお勤めの御殿女中たちのお気に入りなんですぜ。その人気で割りを食ってるのが振り売りだ。なんでも町の女子たちがこぞってこのやり取りをしたがるとかで、日に何十回も、ねえおじさん、あたしに魚を勧めてよ。そんなら、この魚なんてどうですかい。無礼者! ってなもんで、詰られるんだとか」
志乃は無礼者とは言わなかった。戸口の前でコノシロを勧めてきた振り売りに、思いっきり眉根を寄せて、お帰りくださいましとそう撥ね除けただけだ。あのとき、たまたま家に居た燕弥は、どうしたんだい、と鼻息を荒くして志乃に詰め寄った。問われると、魚一匹に声を荒らげたことがどうにも恥ずかしく思えてくる。言葉を濁す志乃に燕弥は舌打ち、思い切り畳表を叩いた。志乃は口ごもりつつもコノシロを厭う理由を説明し、聞いた燕弥はにこにことしていたが、赤く腫れた燕弥の手のひらは、今でも志乃の頭をふっとよぎる時がある。
「旦那方がいっちお好きなのは、百姓女房の手解きによる時姫様の米研ぎに味噌すりに違いねえ。姫様の世話女房振りが健気でいいって輩もおりやすが、男は品くだるいきものですからね。そんなすりこ木の持ちようで、よく殿御が抱けるもんだ、なんて時姫が詰られるのを、やんややんやと囃し立てる。ああ、駄目だよ、御新造さん、引いちゃあいけねえや。こいつは男の性ってもんなんだから」
志乃は確かに血の気が引いている。
阿呆だ、阿呆じゃないか。通いの女中を志乃につけた理由を、燕弥の優しさだなんて、そんな己に都合のいい解釈をして。
燕弥は、此度の芝居のために、志乃を時姫に仕立て上げた。そうして、時姫もどきと相成った志乃から、仕草や口癖を吸い上げたのだ。
ああ、そうか。あの人は、己の芸のために私と一緒になったのか。
私が武家の娘であるから。
私は武家の娘であるから、あの人に買われたのだ。
燕弥に持たされていた駄賃を善吉に渡し、ぼんやりと飯を炊き、気づいたら目の前で燕弥が夕餉を食っていた。志乃にはどうにも拵えた覚えがないが、今宵の菜は餡かけ豆腐だ。豆腐を細かく箸で割り、皿の底に溜まった葛餡に軽く擦り付ける。燕弥は口を椀に寄せ、とぅるりと口に流し込む。
「武家の娘であるから、あなたは私を娶ったのですか」
言葉はとぅるりと志乃の口から出ていた。志乃は震える手で己の口を押さえたが、もう遅い。燕弥は口の端から一寸ばかり葛をこぼしたが、取り出した懐紙で拭うと、膳の上に箸を置いた。
「姫と名のつく役は芝居に数々ございます」
桜姫、鷺姫に雲の絶え間姫。燕弥の舌は葛が塗られて、滑らかに動く。
「姫様役は緋色の振袖を着ることが多いのもありまして、まとめて赤姫とも呼ばれておりますが、中でも、時姫、雪姫、八重垣姫。この三人はちいと特別。このお三方は三姫と呼ばれ、女形でも殊更難しい役とされている。座の中でも実力があって貫禄もある格の高い女形しか演らせてはもらえません」
遠くで木戸番が鳴らす送り拍子木の音が聞こえている。日はすでに落ちた。行灯の光が燕弥の顔を撫で上げて、志乃は初めて燕弥の頰に小さな黒子があることに気がついた。
「その時姫がいる鎌三、鎌倉三代記を次の芝居でやるらしいとの噂を聞いたとき、わたしは頭の中で、お稲荷さんの神棚に貯めた小金を数えていた。いくら渡しゃあいい役がもらえるかしらん、ってね。狂言作者には常から愛嬌振りまいて尻尾を振ってやってんだ。小金を袂に落としてやれば、百姓の女房役くらいには捩じ込んでもらえるはずだ」
それだけ燕弥は狂言作者に気に入られているという。
お前の芝居にゃあ、時々きらりとするものがある。狂言作者は燕弥に飯を食わせるたびにそう言ったが、そんなおべんちゃらを信じるほど己に時間は残されていない。
「小金は全枚はたいてやったってよかったんだよ。なにせわたしはもう二十三だ。ここいらで芽を出しておかないと、わたしは種粒のまま終わる」
先の如月狂言での初姫は一寸ばかり芝居好きたちの中で話題に上ったようだが、あれは正月の初春狂言が終ねて大立者たちが休みを取っている間、若手を集めて興行を行なっただけのお茶濁し。己は、名前のある役なんてもらえるはずもない役者ばかりが押し込められた中二階で枯れて死んでゆく。
「時姫は座で最高位の女形が演じます。だから、時姫役は決まっておりました。森田座の立女形は玉村宵之丞。こいつが名跡をついだだけの凡々でしてね。踊りはど下手くそ。首は太くて色っぽさもへちまもねえ」
燕弥は口端を嫌な角度にあげていたが、「あら、いけない」と口元を袖口でそっと隠した。
「駄目だわ。仏さまにこんなことを言っちゃあ」
「……仏さま?」
思わず燕弥の言葉を追いかけた志乃に、燕弥は膝でにじり寄る。そうして、燕弥は志乃の耳たぶに掠れた声を擦り付けるようにして、
「宵之丞はおっ死んだんですよう」
弾かれたようにして尻を退った志乃を見て、燕弥は笑っている。
「ところてんで当たったらしい。稽古帰りの永代橋あたりの屋台で食べたそうで、夏でもないのに運が悪いねえ。稽古に出てこねえから奥役が家を訪ねてみれば、泡吹いて蛙みたいにひっくり返ってお陀仏だ。それが幕開きの一ト月前のこと。尋常なら演目を変えるところだが、元々皐月狂言はそれほど力を入れねえ興行だ。上方から代わりの役者を呼ぶのも金がかかるばかりでなんだってんで、お偉方は悩みに悩んでお頭がおかしくなっちまったんだろうさ。思いもよらねえ道を選んだ」
ある朝、燕弥は狂言作者に呼び出され、部屋まで出向くとそこにはお偉方が座っている。
「時姫をやれ、燕弥」
言われて、燕弥は頭の中で、江戸にある質屋の数を数えていた。いくら渡しゃあこいつらを、お頭のおかしいままにしておけるかしらん。
「それだけの大役だったのさ。この時姫で当てることができなきゃ、もう二度とこんな好機はめぐってきやしない。わたしは何を擲ってでも、この芝居で成り上がらなきゃいけなかった」
だから娶った。燕弥は言う。
「お師さんのように一生を女として過ごし、誰とも添い遂げない心算でおりましたが、背に腹は替えられません。時姫役をいただいた日から、わたしは稽古終わりに町に出た」
口入屋に出入りし居酒屋に入り浸り、武家町で追い回されながら、燕弥は居酒屋で一人の男にたどり着く。男は藩士で江戸にはお勤めで滞在しているらしい。三人の同輩と席を一緒にしておきながら、目の前の料理に一切手をつけない。いいねえ、と燕弥は舌舐りをする。手拭いを顔に巻き、笠を被って顔を隠すたあ、町人が食う飯を食らうのは武士としてみっともねえってそういうわけかい。男に娘がいることを知れば、もう吟味している時間も惜しい。燕弥が芝居者と聞いて男は渋い顔をしたが、質屋で借りた金子で黙らせた。すぐさま娘を呼びつけてみれば、婚礼もあげぬままでも江戸入りをする。
いい女だった。
化粧も知らず、親の言いつけのみを守り、礼やら忠やらそんなことばかり考えている、いい女だった。
「豆腐に笊を被せるなんて、そんな頓馬なこと町の娘は絶対にしない。嫁入り修業でみっちり親から仕込まれるからね。豆腐の扱い方がわからないなんて、武家の娘ならでこそだ」
そいつを燕弥は芝居に取り入れた。へえ、とお偉方は片方の口端を上げた。よくもこの大作に中二階風情が小細工を。だが、やってみな。お偉方はそう言った。
「コノシロを振り売りから勧められた時の顔も思わず鼻息が荒くなっちまうほど素晴らしかった。だから使わせてもらったんだよ」
芝居にはすぐに火がついた。名も知らぬ女形の立身に、どれ、どんなものかと皆がこぞって森田座の木戸札を購った。
「いい買い物をした」と燕弥は志乃の膝につつつぅと指を滑らせる。
「だが、わたしには貫禄がない。今、江戸の芝居好きがやんややんやと持ち上げてくれるのは、いきなり綺麗なべべを着て舞台に乗せられた野良犬を面白がっているだけなのさ」
実際、目の肥えた見巧者たちからは、小手先だけのちんけな芸との批判も多い。だが、森田座は次の芝居も燕弥を中心に据えることに決めた。代わりの女形を立てることをやめ、またもや燕弥を舞台に上げる。
「野良犬がどこまでやれるのかご覧になりたいらしいねえ。舞台でさんざ踊らせたあとは、野良犬が無様に舞台から落っこちる様を見たいんだと」
だからこそ、森田座は次も燕弥に赤姫を用意する。芝居の演目というものは、一月は曾我もの、三月は奥女中ものと季節によって大枠が大体定められている。此度森田座がその慣いに従わないことに決めたのは、三姫という難しい大役を燕弥に演らせるためだという。
「わたしの牙がどれだけ鋭いか、思い知ればいいんだわ」
燕弥は袖で口元を隠してうふふ、と笑った。
「一度嚙み付いたら、首だけになってでも離しやしませんのに」
笑みを浮かべたままの女形には喉仏がない。いや、違う。薄暗闇の中、志乃はぐっと目をこらす。この女形は喉仏が見えない角度をきちんと学んでいるのだ。
「だからね、お志乃さん。あなた、わたしのために傍にいておくれな」
実をいうと志乃は、この告白にほっとしていた。志乃がここにいて良い理由を、夫自らが教えてくれた。志乃が武家の娘としての価値で買われたというならば、志乃は武家の娘として生きればいい。なんてぇわかりやすいこと。なんてぇ道理が通っていること。
家に通って志乃に飯炊きを教えていたお民が、来なくなったのもこういうわけだったのだ。己の芸のためにとしゃぶる部分がなくなれば、すぐに切って捨てられる。
志乃は黙って畳に手をつき、頭を下げる。
燕弥のために、私は武家の女でいよう。
畳のささくれに、己の手の肉刺を押し付けた。
(続きはぜひ本書でお楽しみください)
書誌情報

書名:おんなの女房
著者:蝉谷めぐ実
発売日:2025年01月24日
定価:858円 (本体780円+税)
ページ数:288ページ
判型:文庫判
ISBNコード:9784041157589
発行:KADOKAWA
装画:おかざき真里
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322409000508/
★全国の書店で好評発売中!
★ネット書店・電子書籍ストアでも取り扱い中!
Amazon
楽天ブックス
電子書籍ストアBOOK☆WALKER
※取り扱い状況は店舗により異なります。ご了承ください。
