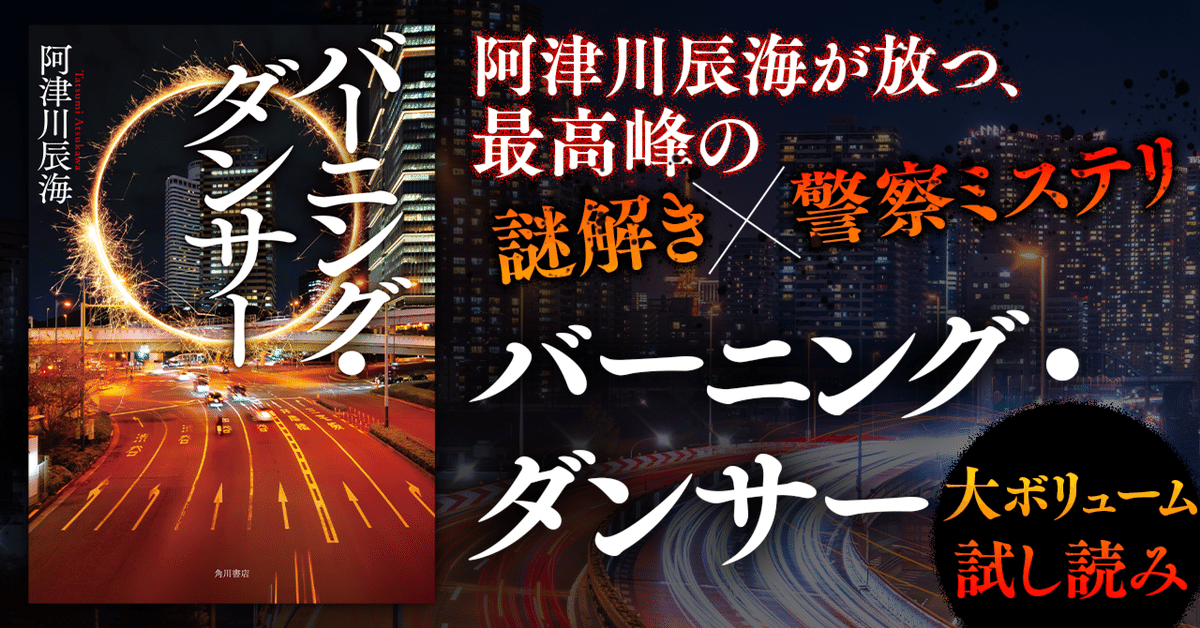
【試し読み】阿津川辰海が放つ、最高峰の謎解き×警察ミステリ『バーニング・ダンサー』冒頭特別公開!
本格ミステリ大賞(評論・研究部門)を受賞した『阿津川辰海 読書日記 かくしてミステリー作家は語る〈新鋭奮闘編〉』、超絶技巧を凝らした青春ミステリ『午後のチャイムが鳴るまでは』と、話題作の刊行が続く阿津川辰海さん。7月26日発売の新刊『バーニング・ダンサー』は、ドンデン返し連発の警察ミステリです。冒頭大ボリュームためし読み、ぜひお楽しみください。
あらすじ
全身の血液が沸騰した死体と、炭化するほど燃やされた死体が発見された。元捜査一課刑事の永嶺は、捜査経験がほぼない「警視庁公安部第五課 コトダマ犯罪調査課」のメンバーと捜査を開始する。彼らの共通点はただ一つ。ある能力を保持していることだった――。
『バーニング・ダンサー』試し読み
1 セッション ──始まり
言葉には力が宿る。
古代日本では、強くそう信じられていた。良い言葉には良いものが宿り、悪い言葉には悪いものが宿った。だからこそ、祝詞では一切のミスが許されなかった。
言葉には力が宿る。
そうなってから、かれこれ二年が経つ。
厳冬の二月だが、幸い、室内は暖房が効いている。俺は待合室では身に着けていたマフラーと手袋を外す。待合室は広すぎ、温風が行き届いていなかった。
セッション。
欺瞞だ、と俺は思った。これは精神科の診察なのだ。セッションなどという言い方をしたって、この現実は誤魔化せない。
俺はメンタルクリニックの診察室で、メガネをかけた不愛想な男性医師と向かい合っている。病院だというのに、室内は書斎のようになっていて、医師が座っている椅子や机は、海外製の高級家具のようだった。羽根ペンまで置いてあって、つい鼻白んでしまう。医学書の類が棚に並んでいるが、木目調の空間が効いているのか、不思議と威圧的な感じはしない。
これが診察を「セッション」と呼ぶ男の部屋だ、と俺は思う。
「本日担当する、高倉です。お名前は?」
医師はメガネを光らせながら言う。病院というところは、やたらと名前を確認したがる。
「永嶺スバル」
「生年月日は?」
「一九九二年五月五日」
「こどもの日だね」
「だから、誕生日をクラスメートに祝われたことがない」
高倉はにこりともしなかった。
「ご職業は?」
問診票にも書いたことを、何度も、何度も。ここに来るまでにも、精神保健福祉士とやらの面談を受け、ペーパーテストも受けさせられている。死にたくなることがあるか、とか、会社に行きたくないと感じる時があるか、という質問がびっしりと書かれたテストだ。
無力感を感じる時はあるか。今ならこう答えるだろう。「とても当てはまる」
「公務員です」
「部署は?」
「……捜査一課です」
「ほう」高倉の目がぎらっと光る。「じゃあ、刑事さんだ」
「はい」
「死体を見ることなんかもあるのかい?」
「そりゃ、仕事ですから」
「怖いね。私は血を見るのが嫌で、精神科医を選んだ」
ジョークなら笑ってやってもいいのに、医師は淡々と言う。俺はこいつが苦手だ。
「で、なんで来たの?」
俺はショックを受ける。
「ペーパーテストも非常に優秀だ。うちにかかる必要があるとは思えないくらいにね」
「問診票に書きました」
「君自身の口から聞くことに意味がある」
高倉は言い、組み合わせた両手の上に顎を載せた。
俺は唾を吞み込む。
「コトダマについては、知っていますか」
高倉は視線だけで続きを促す。
「全世界に突如、百人の能力者が現れるようになった。二年前、某国に謎の隕石が落下してからのことです。能力者たちは、百の言葉……つまり、コトダマの力を持ち、言葉に応じた能力を発揮することが出来る。そういう能力者たちを、『コトダマ遣い』と呼ぶ」
ごく簡単な説明だったが、それでもなお、高倉の怪訝な表情が気になった。
高倉は机の上に置いてあったボールペンを弄び始めた。
「誇大妄想だと言いたいところだね。うちにも、自分はコトダマを遣えるという妄想を抱いてやってくる人間がいる」
「ですが……」
「知っている。妄想ではない。現に世界中で、能力者による悲惨な犯罪が起きている」
「俺は一年半前、殺人事件の捜査中にコトダマを遣えるようになりました。『入れ替える』という言葉の力です」
高倉はボールペンを手の中で転がしていた。
「コトダマがこの世に存在する。それは私も信じよう。だが、君が能力者だということは信じられない」
彼の手から、ボールペンがぽろっと落ちる。
俺は親指と中指をすり合わせ、パチン、と指を鳴らした。
すると、俺は高倉の椅子に座り、高倉は俺の椅子に座っている。患者と医師の入れ替え。これだけで充分滑稽だが、もう一発鼻を明かしてやりたい。
同時に、高倉の持っていたボールペンが机に落ち、コトン、という音を立てる。俺は高級な椅子の座り心地を一瞬堪能してから、ボールペンを高倉の背後に投げ、羽根ペンを握った。
もう一度指を鳴らす。一瞬の後、俺は高倉の背後に立っている。高倉の首に羽根ペンを突き付け、頸動脈のあるあたりに添える。
「納得してくれます?」
高倉はフン、と鼻を鳴らし、蚊を払うような仕草で羽根ペンを弾いた。
「すごい速度だ」
彼は立ち上がり、自分の席からボールペンを拾い上げた。
「まず、君と私の座っていた位置を『入れ替え』た。ボールペンは私の手を離れていたから、そのまま落下して机に落ちる。君は私の椅子に座ると、ボールペンを拾い、私の背後に投げる。そしてそのまま、今度はボールペンと自分の位置を『入れ替える』。私の首に突き付けるため、羽根ペンを摑むのを忘れずに、だ」
「さすがお医者さん。頭がよろしいことで」
知らずに皮肉が漏れる。
人間は通常、目の前で起きている異常事態を正しく把握出来ない。物理法則に、常識に反したことを即座に理解出来ないのだ。だから、今俺がやったようなパフォーマンスを見せると、大抵はまごついているうちに制圧される。高倉のように、最初から冷静に受け止め、分析し、論理立てて再構成するような人間は珍しい。おまけに、コトダマの存在自体は疑っていない。普通は、そこでも常識が邪魔をする。
俺は羽根ペンを机の上にきちんと戻してから、自分の椅子に戻った。
「初めは、誰にも知られないようにしようと思っていました」
「今はオープンにしているんだね」
「ええ。職場の同僚も知っています。犯人確保の際に遣ってしまったのが原因でした。家が包囲されていることに気付き、窓から逃げようとした犯人を、このコトダマで追いかけ、捕らえた」
「便利な能力だ。しかし、普通に捕まえることも出来そうなケースだね」
「ねこだましのようなものです。相手が動揺している間に勝負をかける」
「ふむ」
「田渕が認めてくれたのも大きかった」
「田渕というのは?」
俺は次の言葉につっかえた。
「……刑事は二人一組で行動します。その、ペアです」
「なるほど。相棒のようなものだね」
さらっと放たれた言葉に、チクリと胸が痛む。
「コトダマ遣いは、化け物であると恐れられています。強大な力に溺れ、犯罪に走るものが多いことも、その偏見を助長している」
そのせいで、コトダマ遣いであることを打ち明けられない人も、この世にはかなりいるだろう。各国に充実した設備の研究機関が出来ているが、そうしたところに助けを求めることも出来ず、悩んでいる人が。
「しかし、君は警察官だ」
「田渕が言ったことも同じです」
照れ隠しでそう言うが、俺は一言一句正確に覚えている。
──すごいことじゃないか。遣い方次第で人を救うことも出来る、そんな素晴らしい力を、お前は持っている。そして、その力を生かせる時と場所に恵まれている。素晴らしいことだ。
素晴らしい、は彼の口癖だった。一日に十回以上聞いたこともある。小さなことにも幸せを見出し、毎日を元気に生き抜いていくような力に満ちた男だった。
時と場所。
それが俺の心に深く残った。そう、俺は警察官だ。だから、コトダマを犯罪に遣う奴らとは違う。むしろ、そういう存在を憎み、打倒していくべきだ。そう、気持ちを整理することが出来た。
「それで? 君はなぜ、今ここにいる?」
高倉は最前の質問を繰り返す。
俺は唾を吞み込んだ。話そうとすると、かあっと全身が熱くなる。
「──去年のクリスマスのことです」俺は言った。「殺人事件の被疑者が、とある半グレ集団と繫がっていた。麻薬を売りさばいている組織で、組対とせめぎ合いになった」
「組対というのは?」
「組織犯罪対策部組織犯罪対策課」
すらすらとそんな文字列が口から吐けることに、嫌気がさす。
「で、どうなったの」
「被疑者が組織と取引をする現場を押さえ、殺人事件については別件逮捕で解決する。同時に組織も根絶やしにする。そういうことになりました。取引場所は埠頭の倉庫です」
「古臭い刑事ものでも見ている気分だよ」
「しかし、問題があった。被疑者はコトダマ遣いだったんです」
「コトダマ遣い対コトダマ遣いだ」
「その通り」俺は頷いた。「それも、両方の主将がコトダマ遣いという状況での、集団戦です」
「相手の能力は?」
「『腐る』。触れたものを腐らせる、という厄介なものでした」
簡単に答えたが、そもそも、相手の能力も最初は分からない。目の前で起きる現象から推理し、解答を導かなければならない。相手の能力に翻弄されるうちに、殺されてもおかしくはないのだ。
それぞれの能力には、「限定条件」が存在する。こういう行動をしないと発動しない、こういう条件下では発動しない、というようなものだ。
俺の場合で言えば、『指を鳴らす』ことが発動条件になっており、ついでに、『半径五メートル以内』が効力範囲になっている。効力範囲がないものもあるので、振り幅は大きい。
今回の一件では、『腐る』のコトダマ遣いが、手で触れればなんでも腐らせられるのかを見抜くことに苦労させられた。触れただけで腐るなら、相手の体を壊死させることも簡単、ということになる。迂闊には近付けない。
だが、今回のケースでは、被疑者が手にかけた被害者の傷から、「両手で囲むように把持したもの」を、「触れた場所」のみ腐らせるのではないか、という見立てをすることが出来ていた。ここまで分かってくれば、相手に接近する限界が見えてくる。相手の片腕を切断して落とす、という手段も検討対象に上がってくる。実際には、切断するには至らなかったが。
「こちらは一課と組対の刑事、および機動隊。相手は被疑者を含む半グレ集団。互いに集団戦ですから、それも頭の痛い要因でした。警察側は、俺のことを信じて、命を預けてくれる人間だけで組織されていましたが──俺の役割は、倉庫の上階、キャットウォークから下の様子を見、危険な場所にいる刑事の位置を『入れ替え』、その命を守ることだった」
「責任重大だね」
「おまけに、上から見るというのが嫌だった。まるで将棋盤でも眺めているみたいなもんでしょう」
「全能感。万能感。神の視座に立つという優越感。君が感じたのはどれだろうね」
どれでもない。
強いて言えば、罪悪感だ。
「『入れ替える』を遣って、味方と敵の位置を替えれば、敵の攻撃は不意を衝かれて空を切るし、味方は『入れ替え』られることを予見しているから、敵より一拍早く反応し、相手を制圧することが出来る。事実、『入れ替える』と拳銃や警棒との掛け算は素晴らしかった」
田渕の口癖が口を突いて出てきたことに気付く。
「だったら、問題はないだろう」
「ですが──」
そこから先の言葉が続かなかった。突然、肺の中身が空っぽになったような気がして、呼吸が荒くなった。
高倉のボールペンが、コツン、コツンと机にあたって音を立てる。
「話して気が楽になることもあるが、話したくないなら、無理に話さなくていい」
高倉は言い、ここで初めて黒いファイルを開いた。
「問診票には、『会社に行こうとすると息が詰まって行けない』とあるね。具体的にはどういう症状? 時期はいつ頃?」
「……一週間前くらいから。クリスマス以降、例の組織の後処理に忙しかったのが、パッと終わったタイミングです」
「後処理というのは?」
「……『腐る』のコトダマ遣いに逃げられ、それを追いかけていました」
「作戦失敗がストレスになったということかな」
俺は答えない。
「行けないというけど、家からも出られないの?」
「家は普通に出ました。駅まで行って……電車に乗ろうとすると、息が詰まる」
実際には、息が詰まるなんてものではない。不快感で胸がいっぱいになり、頭がじんわりと痛み、胃の中身をそのあたりにぶちまける。だが、オフィススーツを着た女性の、ボロ雑巾を見るようなあの目つきを思い出すと、たとえ医師相手にでも言う気にはなれない。
「ひげは剃れる?」
「はい」
「今日も問題ないようだしね。お風呂は?」
「風呂? 入りますが」
そういえば、以前はシャワーを浴びる時間もなく、デオドラントを塗るだけで済ませていたこともあるな、と思い直す。今は休みを取っているが、休んでいる時の方が、人間らしい生活を送っている気がする。いつも獣のような体臭をさせながら、獲物を追っている。まるで、動物のような生活。
「適応障害」
「は?」
「鬱は気分が沈んでいる原因がハッキリしないことが多い。君のは明白だ。クリスマスに起きた埠頭での大捕り物。その失敗が身に応えている」
俺は黙り込んだ。
「それなら書けるよ。二カ月でどう?」
どう、とはなんだ。
よほど困惑した顔をしていたのだろう。高倉が眉根を寄せながら言う。
「あのね、うちは内科や外科とは違うんだから、レントゲンやMRIを撮ってどうというわけにいかないの。高齢の方で、脳の萎縮からくる認知症が疑われる時は、MRI、撮るけどね」
「はあ」
「でも、君だって、診断書取れないと困るんでしょ。産業医からは、そう聞いているよ。会社を休職したいからって」
高倉は、早口に話をまとめようとしている。話せない人間に、用はないとばかりに。煙に巻かれているような気分だった。
「適応障害なら書けるよ。そっちのほうが体裁が良いから、薬も出しておこう。夜は眠れているかな?」
「まあ、最近は少し浅いです」
本当はもっとひどい。よく悪夢を見るようになった。いつも同じ悪夢。
死の悪夢。
「なら、不眠症の気もあるね。睡眠薬を一週間分出そう。弱めのやつ。飲めとは言わない。飲みたくなったら飲めばいいが。もし飲み切ってしまって、追加の薬が欲しいようなら、またここに来なさい」
「薬が要らないなら、来なくていいんですか?」
診断書を書き始めようとしていた高倉の手が止まる。メガネの向こうの高倉の目が細められて、少し優しい表情になる。
「君に必要なのは医者じゃない」高倉は首を横に振る。「休息だ。そして、大抵はそれでなんとかなる」
待合室で待つように言われ、俺は診察室を出る。
不意に、もうこれで、高倉と会うことはないのかもしれないと思った。俺が薬を飲まなければ。欲しくもない薬なのだから。
だったら、あの話の続きをすることもないだろう。
俺が毎晩見る悪夢。
死の悪夢。
田渕を死なせてしまった、その瞬間の悪夢。
*
冷気が肌を刺すようだった。風に時折潮風の匂いが混じる。
キャットウォークから見る階下の景色が、煙っていく。
敵は俺の位置に気が付いていない。俺のコトダマに対応さえ出来ていない。俺を見つけ、俺を叩けば、一気に形勢を逆転出来るというのに。
この十分ほど、俺は凄まじい勢いで『入れ替える』を遣っている──これまで体験したことのないペースで。
銃声。怒号。破壊音。
あらゆるものが飛び交う現場を、俺は見下ろし、その生殺与奪の権を握っている。
『腐る』のコトダマ遣いが味方の刑事に近付いた時、味方と段ボール箱を『入れ替え』て防衛する。銃弾から守ってやったこともある。銃弾が放たれた後、発砲者と味方の位置を替えてしまえば、味方は撃たれない。それどころか、発砲者自身が、自分の放った銃弾に貫かれるという面白い事態さえ発生する。
面白い?
今、自分の思考によぎった発想に怖気を震う。命がかかった現場だ。面白いとは、何事か──。
しかし、動悸がし、全身が熱くなっているせいか、そんな発想さえ俺はあっさり受け入れてしまう。この高揚感のせいだ。俺がおかしくなってしまったのは──。
「永嶺!」
田渕の声だ。見ると、いつの間にか、キャットウォークに登ってきていた。
「気付かれた! 伏せるんだ!」
俺は階下を見る。
『腐る』のコトダマ遣いが、足元にいた。キャットウォークの足場となっている柱に取りついていた。
額から出血している。男は俺の視線に気付くと、ニヤリと笑って、柱を両手で摑んだ。
まずい!
俺は指を鳴らそうとして、親指と中指をすり合わせた。
だが──。
突然、心臓がギュッと締め付けられるように痛み、脂汗が止まらなくなった。直感で分かった。
俺は今、この指を鳴らしてはいけない。鳴らせば、俺がこの世から消える。
自分の感情の正体が分からなかった。今から思えば、あれは、能力を遣い過ぎたことによる代償だったのだと思う。ただ、強烈な忌避感が体を貫き、俺を硬直させた。一日のうちに数十回──数え切れないほど、能力を遣ったことはなかった。
俺の脳裏にあったのは、自分の体が引き裂かれ、この世ではないどこかに連れ去られるようなイメージだった。天国も地獄も信じちゃいないが、そういうものじゃない。暗く、何もなく、ただ無に塗り潰されたようなどこか。そこに迷い込んで、一生帰ってこられないような気がする。
鳴らせ!
鳴らすんだ!
今すぐ敵を止めないと、俺も田渕も殺される。田渕ももう、キャットウォークに上がってきてしまったのだ。俺がやらなければ──。
だが、出来ない。
指を鳴らす。それだけのことが、出来ない。
脂汗が目の中に入り、瞬間、視界が失われる。
「田渕!」
柱が『腐』り、ぐしゃっと骨の折れるような音を立てた。
俺は宙に放り出される。
……気が付いた時には、俺は倉庫の床に寝転がっていた。
全身が痛む。肋骨の一本や二本は折れているだろう。幸い、生きている。
体をゆっくり起こす。
そうして俺は目の当たりにする。
キャットウォークの足場であった鉄骨と柱の下敷きになり、無惨に潰れた田渕の姿。
何分気絶していたのか。そう思わせるほど、冷たくなったその体。
折れた鉄骨が体に刺さり、もうすっかり青ざめている田渕の顔。
俺は叫ぶ。
そうしていつも、自分の叫び声で、目が覚める。
*
三月最後の金曜日も、そうやって目が覚めた。
俺は痛む頭を押さえながら、電気ケトルに残った水で頭痛薬を飲み下す。
今日は面談のため、「出社」する必要があった。それだけで気が重いというのに、またあの悪夢を見た。
……俺と田渕がキャットウォークから墜落した後、隙を見て『腐る』のコトダマ遣いは逃げ出した。他の刑事も追うことは出来なかった。崩落したキャットウォークが、ちょうど、被疑者と刑事たちの間を分断し、向こう側に回るのに時間がかかったのだ。
全て、巡り合わせが悪かっただけ、ともいえる。
それでも、俺は自分を責め続けた。田渕の仇は必ず俺が討つと宣言し、日夜、あの男を追いかけ続けた。何日も眠らず張込みをすることもあった。新たな相棒からは愛想を尽かされ、今では名前も覚えていない。
しかし、仇は討った。
これで帳尻が合うはずだった、のに。
俺はまだ、このどん底の気分から帰ってきていない。
人が一人死んだ、その帳尻は、人を裁いたくらいでは取り返せないのだ。
休職期間の二カ月は、あまりにも無為に過ぎた。無為に、と感じるのが悪いのだろうか。実際には、体はしっかり休めることが出来たし、診断書を取っての休暇だから給与も出ており、金にも困っていない。普段は出来ない自炊に精を出したので、食事の状況は改善されたくらいだ。
余暇を潰す方法を知らず、図書館で適当な本を借りて読んでみたり、動画サービスに加入して映画を見たり、パチンコを打ったり、競馬場に行ってみたりしてみたが、どれにも熱中出来なかった。これも大きいかもしれない。いつ仕事用のスマートフォンが鳴り、現場に呼び戻されるか分からない世界で生きてきたので、たった二カ月でその習慣が抜けるわけもない。かけてくるやつがいるはずもないのに、スマートフォンを眺めていることに気付いて、自分で呆れたこともあった。
自分が仕事人間であることを意識させられるのが、これほどつらいとは思わなかった。パートナーもいなければ、家族もいない。両親は日頃の不摂生がたたり、早くに他界したし、兄弟姉妹もいなかった。
自分から仕事を取り上げたら、何が残るのか。
その問いに対する答えを、自分は持たない。
それに、その仕事さえ続けられるのか分からないのだ。最後の一線である「仕事」すら、奪われるのかもしれない。
休職中、何度か警視庁の近くまで足を運んだことがある。自宅の最寄り駅までしか行けない時、職場の最寄り駅で気持ちがくじける時、警視庁の建物を見た瞬間に踵を返したくなる時など、色々な時があったが、少しずつ距離を伸ばした。
あとは、今日の面談を無事乗り越えるだけだった。
扉をノックする。
「失礼します」
会議室の扉を開くと、見慣れた上司の姿とは別に、女性が一人立っていた。
黒のパンツスーツが似合う、すらっとした女性だった。だが、どこか不思議な雰囲気がある。
目だ。吞み込まれるような引力がある。その濡れたような輝きのせいか、あるいは、ブラックホールのような暗い光のせいか。目は大きいが、それが顔のバランスを崩すほどではなく、むしろ魅力になっている──。
「永嶺スバル君、だね」
凜と澄んだ声で呼ばれ、思わずハッとする。
書誌情報

書名:バーニング・ダンサー
著者:阿津川辰海
発売日:2024年07月26日
ISBNコード:9784041141779
定価:1,925円(本体1,750円+税)
総ページ数:376ページ
体裁:四六判 変形
発行:KADOKAWA
★全国の書店で好評発売中!
★ネット書店・電子書籍ストアでも取り扱い中!
Amazon
楽天ブックス
電子書籍ストアBOOK☆WALKER
※取り扱い状況は店舗により異なります。ご了承ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
