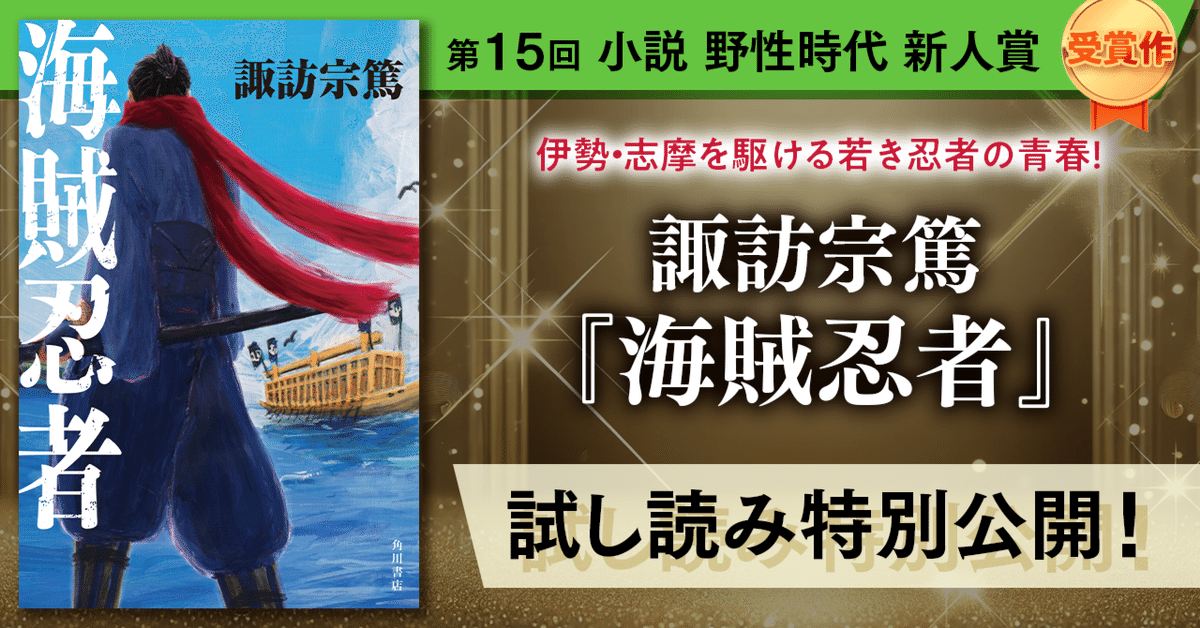
【試し読み】諏訪宗篤『海賊忍者』冒頭特別公開!
「第15回 小説 野性時代 新人賞」「第44回 横溝正史ミステリ&ホラー大賞」受賞3作品が、2024年9月28日(土)に同時発売!
本記事では「第15回 小説 野性時代 新人賞」受賞作『海賊忍者』(著:諏訪宗篤)の試し読みを特別公開!
物語の冒頭をどうぞお楽しみください。
あらすじ
伊賀忍者・向井正綱は、甲賀衆に襲われている市女笠の少女を助ける。少女――雪姫は伊勢の戦国大名・北畠具教の愛娘。織田信長の子・茶筅丸への輿入れが決まっていたが、不本意な婚礼を嫌い、織田家の非道を京の幕府に訴え出ようとして狙われたのだった。
「北畠を、伊勢を、お助けください!」
姫君の懇願を聞き入れた正綱。山野を駆け滄海を渡り、甲斐の武田を引き入れ熊野水軍をも動かす。敵は信長。織田の大軍との大勝負が、はじまる……!
『海賊忍者』試し読み
海賊之掟
一、共にあって共に栄ゆるべし
一、一人の大事は皆の大事なり。
一味同心の思をなし、身命を惜しむべからず
一、公事は衆議に依りこれを相計らい、依怙贔屓なく公正にし、
違背すべからざるべし
一、掟に違背せしものは、追放たるべし
伊賀古老遺訓
一、見識才覚古びぬものなし。教えを請うに憚ることなかれ
一、信は万事の基なり。猜疑受くるべからず、猜疑絶やすべからず
一、堪忍規律は向上の一路なり
一、切所突然なり。功名を第一とし、身命を第二とすべし
一、独孤恐るるべからず。思案を頼るも、決断を委ねることなかれ
第一章 磯千鳥
一
街道を疾駆する一騎があった。
女が二人。市女笠を被って横座りする少女を、小袖に濃茶の伊賀袴を穿いた女が後ろ抱きにし、厳しい声で馬を急き立てる。
馬の口からは泡が飛び、蹄が巻き起こす砂煙の後方に人影は無い。それでも伊賀袴の女は瞳を刃の如くに細めて、脇の細道に馬を突っ込ませた。手綱を緩めることなく、そのまま開けた野を突っ切る。
だが唐突に、馬が高くいなないてつんのめった。
蓮華の紫の花弁と緑葉が飛び散る中、伊賀袴の女は市女笠の少女を抱いて跳んだ。そして首を狙って飛んだ縄を、苦無を一閃して断ち切る。
「大人しく捕まるが身のためぞ」
小石を弄びながら、木立を割って並外れて巨躯の男が姿を現した。甲賀衆が好む柿渋染の単衣に脹脛を絞った袴を穿き、肩や胸元などはち切れんばかりに膨らんでいる。
「滝川の犬め」市女笠の少女を背中にかばい、伊賀袴の女は唇を歪めた。「下心の見え透いた物言い、反吐が出る」
「言うたであろう」
やはり柿渋染の装束を纏った男が巨躯の男の傍らに歩み出た。縄を捨て、腰から持ち上げた鎖鎌をじゃらりと鳴らす。
「血の気の多い伊賀の山猫には、きつい躾が入用よな」
言葉と共に鎖分銅が蛇の如くに飛んだ。
伊賀袴の女は分銅を苦無で打ち逸らし、自ら前へ駆けた。巨躯の男と対峙し、襲いかかる腕を低く身を沈めて掻い潜る。伸び上がりざまに勢いを乗せた苦無を脇腹に叩き込むが、鋼の刃は高い響きを上げて弾かれた。巨躯の男が再び両腕を大きく振り払う。鋭い鋲の無数に突き出た籠手が暴風を巻き起こし、伊賀袴の女を弾き飛ばした。
「姫様、お逃げください」
地面を二転し、血の滲む肩をかばって苦無を構え直す女の叫びに市女笠が揺れたが、駆け出た足は数歩と進まぬ内に止まった。更にもうひとり、柿渋染の装束を纏い顔の左半面に瞳をも飲み込む大きな傷の走った男が少女の前に立ちはだかっていた。
「輿入を控えた大事のお身体なれば、かかる遠乗りは感心いたしませぬな」
三人の甲賀衆の男が二人の女を取り囲み、ゆっくりとにじり寄る。
「――畑荒らしが偉そうに」
どこからともなくぶつけられた声に、隻眼の男は振り返りざま刃を抜き打ちに払った。だが切先は手応え無く空を切る。刹那、足元から巻き起こった土煙を刺し貫き、鋭い先端が隻眼の男に伸びた。
鑿と呼ばれる伊賀衆の使う工具である。巨大な針とも言うべき形状で、錠前破りや、木の幹に印を付ける為に使用されるが殺傷力も高い。掌を貫かれながらも咄嗟に顔を守った隻眼の男は、同胞の許まで跳び下がった。
「土遁か。油断したわ」
土煙から姿を現した少年は内懐に入れていた白い子狐を下ろし、先ほどまで身を覆っていた麻布をひと払いして腰帯に通した。
「邪魔立てするか」
「邪魔しているのはお前らだ」少年は三人の甲賀衆をにらみつけた。「よくも俺の畑を踏み荒らしやがって。蓮華も、蓬も、玄草も、ようやく育ってきたのによ」
怒りを込めた言葉に三人は足元に視線を落とした。甲賀衆にも馴染み深い薬効のある植物が、確かに草鞋の下で泥に塗れていた。
「それに俺は、女子供をいじめる輩が嫌いでね」
少年は鑿を手甲に収め、腰に帯びた刀を抜いた。刃長二尺(約六十センチメートル)ほどで反りが浅く身幅の厚い関物の打刀を構え、甲賀衆に切先を向ける。
「まあ、お愛ぽいさん」
だが鈴を転がすような声に、視線が脇に逸れた。じゃれる子狐に手を伸ばし、傾いた虫垂の隙間から覗いた少女の桜色の唇に、少年の胸が高鳴る。
「その、きれいな娘は特にな」
「でしゃばりおって、死ね」
放たれた鎖分銅を、少年は左手で抜いた鞘で受けた。そして鎖を巻きつかせたまま間合を詰めて鎌をかわし、唸りを上げる巨躯の男の右腕の、更にその上を跳ねる。着地と同時に鎖で隻眼の男の刃を受け流すと、腰袋をひとつ投げつけて大きく飛び退いた。
褐色の細かな粉煙が拡散した。三人が鼻口を覆うより早く、くしゃみが飛び出る。
「胡椒入りの、一番効くのを使った」少年は言った。「すぐにしびれが回る。さて、詫びを入れて去るか、更に痛い目を見るか。どちらにする」
高く鳴り響いた弦音が、少年の言葉を掻き消した。鋭い鏃が鎖鎌の男の喉に突き立ち、拳を固めて立ち向かう巨躯の男の両目、口と続けざまに射貫く。
林の奥から、鏃よりも鋭い光を瞳に湛えた直垂姿の老武者が進み出た。折烏帽子の下の髪も長い顎髭も白く、頬や目尻には深い皺が刻まれているが、足取りも右小指に挟んだ二本の矢さえ小動もしない。二人が倒れるより早く木立に飛び込んだ隻眼の男の行方をしばらく入念に追っていたが、やがて矢を外し、市女笠の少女のもとへ走り寄った。
「鳥屋尾様」
傷口から手を下ろして平伏する伊賀袴の女の前を通り過ぎ、老武者は市女笠の少女に片膝を突いて一礼した。
「姫様、ようご無事であらせられました。なれど、急ぎお戻りくださいませ。世に知られれば、いささか厄介なことになりますれば」
腹を見せて甘える子狐から指を離し、市女笠の少女がためらいながら立ち上がると、老武者は平伏したままの伊賀袴の女に鋭い視線を向けた。
「環はこの場にて召し放つ。何処なりとも立ち去れ」
「なりません」
市女笠の少女は鳥屋尾と環の間に割り入り、虫垂を大きく左右に揺らした。
「環は何も悪くありません。わらわが無理に頼んだのです。このままでは父上様が、あまりにご不憫でございます」
「その話は戻りて後に」
老武者はひとつ咳払いして、少年に視線を向けた。
「貴殿にはこの場の苦難をお助けいただいたと拝察いたす。些少ながら納められよ。そして今見たことはくれぐれも胸の内にお留めあるよう」
少年は、差し出された小袋を掌に乗せて上下させた。
「畑を荒らされ、そこな骸も片付けねばならん。この銭は迷惑料として貰っておこう。だが、気に入らんな」
眉間に皺を寄せる老武者に動じることなく、少年は言葉を続けた。
「おっさんよ、そこな女性は甲賀衆の手練三人を相手にし、己を犠牲にしてまで姫さんを逃がそうとしたのだ。伊賀衆の侍女だからと無下に扱えば伊勢国司家の名に傷がつこうぞ」
老武者は環の震える腕を伝う鮮血に目を留めたが、脇に回った右手指は鏃を挟んだ。
「伊勢国司家の家臣ならばなんとせよと」
「頭を下げて俺に頼め。我が家はこの近く。手当してやれる。それとも殿上人の家臣は人に頭も下げられぬのか」
「環をお助けください」市女笠の少女が進み出て、深く頭を下げた。「環はわらわのために傷を負ったのです。しっかり治療してやりとうございます」
「お言葉もったいのう……」
言葉の途中で環が崩れ落ちた。呼吸は続いているが、血の気が失せて首の脈も弱い。少年は、畑の端で怯えていた馬の轡を取って戻った。
「お頼みいたす。環を助けてやってくれ」
環の傷口をきつく縛ってから、頭を下げた老武者に少年は頷いた。二人して意識の無い環を鞍上に押し上げて手綱を取る。
「ついてきてくれ。今更だが、俺は正綱。伊賀向井の荘の正綱だ」
「爺、おさと」
伊賀と伊勢の境目にある加太峠の手前で南へ折れると、周囲を山に囲まれた小さな集落に出る。意識を失った環を支えながら馬を走らせてきた正綱が大きく呼ばわるや、門から腰の曲がりかけた老人と、その倍ほども背丈のある若い娘が飛び出てきた。
「血が止まってないな」
意識の無い環の体を、さとと共に馬から下ろすと正綱は眉を寄せて唸った。
「薬草を用意する。おさとは奥に運んで傷口を焼酎で洗ってくれ。爺は客人のもてなしを頼む」
「ガトよ、膳の支度も遅れるでないぞ」
丈に合わない帷子を着て、腕や太ももの大半をあらわにしたさとは、環を担いで駆けながら小さく頭を揺らした。
「ごねんきにお頼み申しまする」
鳥屋尾と同乗してきた市女笠の少女は、去りゆくさとの背中に頭を下げると、老人に向き直った。
「あの、ガトと聞こえましたが、聞き違えましたでしょうか」
「いえ、ガトと呼びましてございます。見たままでございましょう。いや、それにしてもお珍しや。お久しゅうございます、鳥屋尾様」
老人は鳥屋尾の馬の轡を取って頭を下げた。
「目の光は鳥羽城攻めの頃とお変わりございませぬな。今与一と評された弓の腕前、思い出すだけで胸が躍りまする」
「そなた、脇殿か」鳥屋尾は音高く膝を打って馬から降りた。「これは懐かしい。鳥羽城城内からの狼煙を見逃さず、先陣を切ったのが脇善兵衛殿であったな。向井の傍らに脇あり、とはかの折によく耳にしたものよ」
左手で幾度も顎髭をしごいた鳥屋尾は、大きく息を吐いた。
「しかし、あの戦は先々代様の頃、天文六年(一五三七)であったから、もう三十六年にもなるのか。時というものは一体どこにいってしまうのやらな。いや、ならば正綱殿とは向井正重殿のお身内か」
「御嫡男にございまする」
鳥屋尾と壺折装束を解いた少女が座敷の上座に座ると、さとが膳を運び入れた。緑鮮やかなよごみだんご、日野菜や蕨の塩漬けの傍らに粕漬け、ぬか漬け、味噌漬けの大根などが数切ずつ一皿に盛られていた。
「いささかお疲れのご様子、まずは一息入れてくださいませ」
善兵衛は徳利を取ったが、鳥屋尾の器に注ぐなり声を上げた。
「なんだ、薬草茶を出す奴があるか」
「いや、その方が良い。どうぞ構い無きよう」
「ありがとう」
少女は手を合わせて頭を下げると茶褐色の漬物を箸で摘んだ。そのまま持ち上げ、頬にかかった髪を揺らして小首を傾げる。
「これは初めて見ます。おこうこうのようなれど、とても色合いの美しい。まるで琥珀のようでございますね」
「鉄砲漬けと申しまする」
膳を並べるなり姿を消したさとに代わって善兵衛が答えた。白瓜の種とわたを抜き、代わりに刻んだ大根や茄子、人参、紫蘇の実と葉などを詰めて味噌に漬け、数年かけ幾度も漬け替えて茶色く羊羹のようになるまで漬け込んだものである。
「殿は遠江におわしますれば、こちらの台所は通いのガトに任せております。あのとおり礼儀知らずの山育ちなれど、まあ悪くない味を出すようになりましたわ。なんと申しても焚付と漬物を切らすは女の恥でございますれば」
「正重殿も息災でござったか。いや、なにより」
鉄砲漬けを舌に乗せた鳥屋尾は、幾度も頷きながら顎髭をしごいた。
「しかし遠江とは、また遠方に行かれましたな。旅でございまするか」
「仕官でございますよ」胸を張った善兵衛は頭を揺らした。「鳥羽城攻めの褒美に志摩の領家職をいただいて以来、正重様は船の扱いに熟達されましてな。海賊衆として是非にと今川家に請われ、桶狭間の後は武田家より駿河遠江の所領をそのまま安堵受けましてございます」
「では正重殿は、武田海賊衆の将であると」
目を瞠る鳥屋尾に、善兵衛は大きく頷いた。
「昔話が弾んでいるようだな」
手ぬぐいを使いながら室内に戻った正綱は円座に腰を下ろした。
「仕官の話でございますよ。伊賀の男は伝来の技を磨き、他国に出て稼ぐもの。正綱様も十六となり、元服なされたのです。正重様のようにいずこかで」
「やなこった」
正綱は薬草茶を呷り、肘で善兵衛からの視線を遮った。
足利将軍を頂点とする公儀は将軍に直接仕える奉公衆、奉行人、そして各国守護職とそれに仕える者のみが武士階級を形成して諸国の政を司り、他の多様な職種の者たちは年貢を納めるだけの被支配者とされた。地位や財力は血縁によって代々受け継がれ、豊かなも
のがより豊かになる仕組が隅々まで確立する。
だが地位も財宝も嫡男のみが継ぐとあれば、その座を巡って争いが起こるのは必定である。豪族、大名、管領家にて争いが頻発し、ついには将軍家においてさえ戦が勃発した。世にいう応仁文明の乱である。
そして長く続いた大乱は、それぞれの旗頭が相次いで死去した後も全国に飛び火して燃え続けた。将軍が幾人も暗殺されて公儀の威信は地に落ち、法も秩序も失われて地位ある者たちは我欲と保身に走る。世は底が抜けたように乱れ、争い、堕ち続けた。
一方、下位の者たちは頻繁に戦に駆り出される内に、自分を死なさず、豊かにしてくれる指導者を求めるようになった。血筋しか誇るもののない無能と見れば衆議を開いて別の者を担ぎ、あるいは自らが取って代わりもする。
それでも上には常に譜代の凡愚がいる。仮に栄達できても他人の顔色を窺ってへつらわねばならず、周りから足を引っ張られ、危険な役目ばかりを負わされることに変わりはなかった。
「こんな世で立身したいとは思わぬ。伊賀で狩りをし、志摩の海で釣りをして気ままに暮らす方がましだ」
「またそのような」正綱の言葉に善兵衛が大きく息を吐いた。「先日も百地様からのお声がけをお断り申したとか。評定衆の言付を受けず、伊賀衆の寄合にも出ずでは身代を失くしますぞ」
伊賀と甲賀は、紀伊山地の嶮しく連続した外弧隆起帯に位置する山里である。
山ひとつ越えねば隣村にも行けない地は独立不羈の気風を育み、山林での伐採運搬を生業として壮健軽捷な身体を養った人々は、紫香楽宮造営に伴い派遣された最先端の知識と技術を会得する様々な職工や匠、更には霊山を巡る修験者、遠く大陸から流れ着いた唐の散楽師や波斯の幻術士らとも交わって独特の技術を生み出した。そして政争に明け暮れる豪族らの求めに応じて敵方の屋敷に忍び込み、情報収集や暗殺をも請け負う者が現れる。
志能便、または忍者と呼ばれる者たちである。
伝承技術の練磨を重ね、更に革新を続ける伊賀衆甲賀衆は日本中の諸大名から引く手数多であった。
「正綱様はお若いながら指折りの手練にして、向井家世継たる御嫡男なのです。立身せねば宝の持ち腐れというもの。いや、正綱様は堪忍規律が足りませぬ。古老の遺訓にもあるように――」
「思案を頼るも、決断を委ねることなかれ、とも遺訓にはあるぞ」正綱はしかめ面で言葉を遮った。「それに向井の世継は義兄上だ。俺ではない」
「あの、環は」
「そう、環殿な」正綱は強引に咳払いすると、尋ねた少女に体ごと向き直った。「命に別条はない。だが血を多く失って、しばらくは歩くのも難しいはず。良ければ回復するまで我が家でお引き受けいたそう」
「安堵いたしました」
胸を撫で下ろす少女の膝に、正綱の懐から滑り降りた子狐が顔を寄せた。体の中で唯一黒い鼻をこすりつけて背の方へ回り、紅藤の地に花と手毬を大きく描いた小袖に前足を滑らせて幾度もねだる。
「ほんにお愛ぽいさんやね。お真魚がお好きさんやの」
少女が背負った包から油紙にくるまれた干鰺を取り出すと、子狐は筆のような尻尾を大きく左右に振った。
「シロが懐く訳だ」
苦笑する正綱の許しを得て少女が干鰺を与えると、子狐は両前足で押さえて頭からかぶりついた。
「シロはあの薬草畑の近くで見付けたんだ。白狐は山の神様のお使いだから留めおくべきではないんだけど、親も無いようだし、懐いてくれると手放せなくてな」
「シロは果報者でございます。怪我人を介抱するのも向井家のならいなれば苦言は申しますまい。ですがごまかしはなりませんぞ」
善兵衛が膝を進めて言葉を続けた。
「所領を勝ち得てこそ、男なのです。当たり前のことを当たり前にこなすことに、なんの障りがありましょう。良い機会です、鳥屋尾様からも意見してやってくださいませ」
眉を寄せて黙り込んだままの鳥屋尾を横目で見やって、正綱が首を振った。
「世が乱れるは、皆が所領を奪い合って争うが為ではないか。俺は所領なんぞに縛られるのは御免だ。いっそ、南蛮にでも行こうかとさえ考えている」
「また絵空事を」善兵衛は地の底に届くほど深く息を吐いた。「よいですか、最後に助けとなるのは一枚の田畑ですぞ。種を蒔き、水をやり、収穫した食物があるからこそ、妻子を養って生きていけるのです。なにより当節は腕一本、働き次第で所領を十倍百倍にも増やせる世なのです。男と生まれて一国一城の主を目指さずして、なんといたしましょう」
「もう天文や永禄じゃないんだよ」正綱は即座に反論した。「元亀の今日日、百地や服部らが大半を抜きやがる。命がけでこき使われて手元に残るのは一貫文ほどなんて、ばかばかしくてやってられるか」
「ならば正重様のように仕官なされませ。とにかくいい若い者が大願も志も持たず、ただのんべんだらりと暮らすなど生きながら死んでいるも同然。生きる張合をお持ちなされ、張合を」
顔を背け、耳をふさぐ正綱に善兵衛が床を叩いて迫ったが、眉間に皺を寄せたまま床の一点をにらみつけていた鳥屋尾が不意に大きく袖を払った。威儀を正し、両拳を膝前に突いて深く頭を下げる。
「向井正綱殿、ご賢察のとおり、それがしは鳥屋尾満栄、北畠家の侍大将を務めておりもうす。こちらは前の伊勢国司北畠具教公の御息女雪姫様。これまでの数々のご無礼、どうかご容赦くだされ」
「なんだよ、改まって急に」
「正綱殿は北畠家の窮状、ご存じあらせられるか」
瞬きを繰り返した正綱は膝を進める鳥屋尾、そして雪姫の視線を受けて頷いた。
「まあ、色々と聞こえてくるからな」
伊賀の隣国で北畠家が治める伊勢は温暖湿潤で作物が良く実なり、山の幸、海の幸にも恵まれた美国である。しかし、後醍醐天皇を支えた北畠家が国司に任じられて以来二百年ほど続いた平穏は、隣国尾張の領主織田信長によって踏みにじられていた。
激しい戦と籠城の末に勝ちきらぬまま信長は兵を引いたが、和睦の取り決めは信長次男茶筅丸に雪姫を娶せて北畠の養嗣子とするなど織田への将来的な併合をはらんでおり、更に後見の名目で派遣された滝川一益ら織田家家臣が伊勢の政を壟断し、戦によらぬ侵略が日毎に進んでいた。
「姫が命がけで京へ向かわんとされたは、三瀬御所に幽閉同然の大殿具教公の窮状を公儀に訴え出んとなされたのでありましょう」
大きく頷く雪姫を見やり、鳥屋尾は言葉を続けた。
「ですが将軍家とはかねて書状を取り交わして、織田の暴虐はすでに伝わっておるのです。北畠の命運を左右する秘事ゆえ姫様にはお伝えいたさず、かえって神襟を乱したてまつりましたること、鳥屋尾、伏してお詫び申し上げます。どうぞお許しくださいませ」
雪姫に詫びると、鳥屋尾は改めて正綱を見据え、声を一段落として言った。
「そしてそれがしと大殿様しか知らぬことながら、将軍家は北畠が立ち上がるならば力を尽くすとお約束くださいました」
「それは、おもしろいな」
正綱は口に運びかけた茶碗を止めて目を細めた。
兄である将軍義輝が討たれた後、命を狙われ流浪していた義昭を将軍位に就けて公儀を立て直したのは全て織田信長の功績である。義昭は信長を父とも称えて地位も恩賞も望み通りにと厚遇していたが、信長の専断が強まると関係が悪化した。北畠と織田の停戦和議も義昭の仲裁案でまとまりかけていたものを、信長が茶筅丸を養子に送り込むことを強硬に主張して反故にしたのである。面目を失った義昭と北畠の間で交わされる書状は、いつしか反信長蜂起の密謀となっていた。
「正綱殿、今一度我らをお助け願えまいか」
鳥屋尾は更に身を乗り出し、瞳の光を強めた。
「北畠家のため、いや、天下を乱す織田信長を討つため、それがしを甲斐の武田信玄公にお引き合わせくだされ」
二
早朝、旅装を纏った正綱は霧山の大木の枝から眼下を見下ろした。目指す北畠の三瀬御所は霧山の麓、山裾と南北に流れる川との間にあった。
「お前も姫さんの顔が見たいよな」
懐でまどろむシロの鼻面をなぞり、正綱は改めて三瀬御所を観察した。
北畠歴代で最も領土を広げた前国司の隠居所ながら、規模は小さく警備も薄い。篝火が焚かれているのも正門のみで、ただひとりの門衛が眠りこけている他は警邏する兵の姿も無い。鳥屋尾と約束があるのだから忍び込むのは愚かなことだとの自覚はあったが、それだけに見付かる訳にはいかなかった。
檜垣で囲われた南の端には米の字形に池を設けた庭園があり、北の搦手門から東の中央正門にかけて倉や武者の詰所と思しき建物が立ち並んでいる。正門の正面に玄関、隣接する最も大きな建物が謁見の間、廊下伝いに西側に続く檜皮葺の建物群が雪姫らの居室と目星を付けた。
正綱は鉤縄を頭上の枝に投げて飛んだ。振り子のように大きく宙を舞って音も無く檜垣の上に降り立ち、周囲を確認して庭へと足を踏み入れる。
「シロ、搜してくれ。姫さんはどこだ」
地面に降ろされたシロは前脚、後脚と続けて大きく伸びをして鼻を高く掲げた。途端、弾かれたように檜皮葺の建物が並ぶ方へ駆け出していく。
「どこの鼠だ」
後に続こうとする正綱の背に鋭い声が突き刺さった。
振り返ると古風な冠下一髻に髪を結い、狩衣を片肌脱ぎにした壮年の武者が立ってい
た。どうして気付かなかったのか正綱自身も理解できないが、幻でも幽鬼でもない。佇まいは優雅ながら、太い木刀が向けられただけで押し寄せた殺気が正綱の呼吸を止める。
「忍び込む先を間違えたのでもあるまい。正三位権中納言、前の伊勢国司北畠具教が直々に成敗してくれようぞ」
失敗を悟るより早く具教が歩を進めた。痛いほどに脈打つこめかみが逃げねばと告げていたが、正綱は動けなかった。見えない縄で搦め捕られたように足にも手にもまったく力が入らず、口の中まで乾ききって舌さえ自由にならない。
間合を詰める具教の手がゆっくりと持ち上がった。息苦しさに耐えきれず正綱が大きく息を吐くや、木刀が弧を描いて奔る。
「父上様」
黎明を裂く雪姫の叫びに、木刀が正綱の首寸前で止まった。
「そのお方は鳥屋尾殿をお導きになる向井正綱様であらしゃいます。どうかお打ちにならないでくださいませ」
「この男がか。なるほど、悪戯が過ぎたようだな」
具教は改めて正綱を一瞥し、木刀を外した。
「書状は鳥屋尾に預けてある。よろしく頼みおくぞ」
鋭い目線を正綱に付けたまま数歩下がり、具教は木刀を一振りして踵を返す。そして何事もなかったかのように庭へ戻っていった。
「あれが、具教公」
額を流れ落ちる汗の冷たさに、正綱の膝が崩れ落ちた。
北畠家は村上天皇の流れを汲む公家であり、後醍醐天皇の側近であった北畠親房は吉野朝の正統性を示す『神皇正統記』を著した文人として名高い。だが、その子孫ながら具教の身体は名工が岩で刻んだ仁王の如く厚く引き締まり、振るう木刀には荒々しいまでの覇気さえ宿っていた。
「決して恐ろしい人ではないのです」シロを抱いた雪姫が正綱に駆け寄った。「むしろお優しい父上様なのです。ただ兵法修行にご執心で、日々の稽古を欠かしたことがあらしゃらぬだけで」
武家政権を打ち立てた平清盛は伊勢平氏であり、多くの剣術流派の源となった陰流を創設した愛洲移香斎も伊勢南部の出身である。尚武は伊勢の気風であり、具教もまた兵法を好んだ。そして朝廷にも公儀にも顔が利き、かつ京へ続く街道上に所領を有する具教の許には数多の剣術修行者が立ち寄った。新陰流を創設した上泉信綱に宝蔵院胤栄を紹介したのも具教であり、鹿島新当流を開いた塚原卜伝からは奥義一之太刀さえ授けられていた。
「剣豪、それも天下でも指折りの腕前なのかもしれないな」
耳から離れない木刀の重い唸りに、正綱は改めて身震いした。雪姫が止めてくれなければ首をへし折られていたに違いない。
「ですが父上様の木刀を振る音は、以前とはお変わりになられてしまわれました」雪姫は瞳を伏せて頭を振った。「茶筅丸様の事があってからは、聞いているわらわが怖気に震えてしまうほど凄まじいのです。ですが、正綱様はどうしてここに。鳥屋尾殿とお約束では」
「早く着いたんだ。姫さんに会いたかったからさ」
「わらわに、であそばしますか……」
薄紅梅の寝間着に東雲色の打掛を羽織った雪姫は、目を瞬しばたたかせて頬を染める。だが声勢に困惑と悲しみを感じ取った正綱は慌てて首を振った。
「あ、いや、その、留守中にシロを預かって欲しくてさ。おさとも爺も手が離せないらしくて」
「そういうことでしたら、喜んで預からせていただきます。雪とシロですから、わらわ達は仲良しなのです」
シロの頭をなでる雪姫の背後で足音が鳴った。正綱の姿を認めた鳥屋尾の眉が急角度に跳ね上がり、右手指が太刀の柄にかかる。
「正綱殿には搦手門外で待ち合わせと申し伝えたはず。確かに案内はお願いしたが、御所に忍び込んで姫様と馴れ馴れしくいたすとは何事か」
「出立する前にはっきりさせておきたいことがあってな。なにせ気楽な道行じゃない」
「はっきりも何も、正綱殿の役目は道案内であろうに」
「では織田領内で苦境に陥ったら、俺ひとり逃げるが、よいか」
気色ばんだ鳥屋尾は、だが眉間の皺を深めて黙り込んだ。
武田信玄が信濃を征して所領が接するや、織田信長は和親と恭順を前面に打ち出して応じた。ご機嫌伺いの書状や付け届けは頻繁にして最高級品ばかりであり、京で流行りの柄の小袖を送った際には外箱にさえ幾重にも漆を塗り重ねて蒔絵まで施す。同盟者である徳川家康と信玄が干戈を交えても養女を武田勝頼に嫁がせ、信長の嫡男信忠と信玄の娘まつとの婚約さえ成立させていた。
信玄も信長による比叡山焼き討ちこそ非難したものの、朝倉攻めへの援兵依頼に応えられなかった際には丁重な詫び状を送り、上杉との和解を将軍家に働きかけるよう信長に請う一方で、相婿である本願寺十一世顕如と信長との和睦を仲介している。
この蜜月とも言うべき友好関係を信玄に破棄させ、反信長に引き込むことが北畠と足利将軍家の目的である。だが甲斐に至るまでには織田の勢力圏を通らざるを得ず、離間策を喜ばぬ全ての敵をやり過ごさねば信玄の許に辿り着くことはできない。
「もちろん、約束したからには必ず甲斐の躑躅ヶ崎まで連れて行く」
断言して正綱は鳥屋尾を見据えた。
「だが、どの道を行くかは俺が決める。何が必要か、何を知るべきかを決めるのも俺だ。そして俺が問うことには全て答えてもらう。でなければこの話は無しだ」
「ご懸命を蒙りまする」満面朱を注いで身を震わせる鳥屋尾に先んじて、雪姫は頭を下げた。「この道行、正綱様の合力無くては成しえませぬし、正綱様が全てを知るは道理でございましょう。鳥屋尾殿は何もかも包み隠さずお伝えし、無事に務めを果たしてくださいませ」
「承知、仕りました」鳥屋尾は片膝突いて雪姫に一礼した。「一命を賭しましても役目を果たしまする」
「よし、それならおいおい尋ねていくとして、まずその旅装束はいただけないな。誰がどう見たって北畠の侍大将じゃないか。武芸者みたいにもっと金銀綾錦で派手にするか、尾羽うち枯らした浪人を装ってもらわないとな。着替えを頼むぜ、とっさん」
「とっさんとは何だ、無礼な」
「ここから先はそういうのも無しだ。敵地で鳥屋尾満栄だと知れたら、その場で全部終わりだ。役目も、命も。解るよな」
鳥屋尾は左右の頬を引きつらせて苦虫をまとめて噛み潰したが、向けられた雪姫の視線に改めて深く頭を下げた。地味な旅装に着替え終わる頃には東の空が暁に染まり、館の外の小高い丘に大きく枝を広げる山桜を照らしだしていた。
「どうぞおするするにおすごしあそばしますよう」
東へ向かう二人を、雪姫は深く頭を下げて見送った。
正綱と鳥屋尾は、伊勢神宮への参拝路である伊勢本街道を東へ向かった。多くの巡礼者や商人らに紛れて志摩に入り、日のある内に伊勢湾に面した小浜浜に辿り着く。
「叔母上が小浜民部殿に嫁いでいる縁で、船を預かってもらっているんだ。気のいい人たちでさ」
茜空を映す夕凪の海に網を仕掛ける何艘もの船を見つめながら、正綱は言った。
「今夜は泊めてもらって、朝に船出しよう。小浜の鰺は美味いんだぜ。めひび汁にありつければ言うことなしだけど、時期がちょっと遅かったかもな」
正綱が砂浜に足を踏み入れるより早く、波打ち際で遊んでいた子供たちが駆け寄ってきた。普段なら共に遊んだり、伊賀の話をするところだが、ハサバ(網干場)で捌いた魚を干していた村の長も歩み寄って来る。跳び回ってはしゃぐ子供たちを制して正綱は頭を下げた。
「長殿、しばらくぶりだ。早速だが明日にも船を使いたい。だが、まずは今晩の寝床と飯を馳走して――」
「向井の若様、こちらへ」
ただならぬ口調に、正綱は眉をひそめて後について歩いた。懇意になって久しいが、長の表情も声音も、砂浜を踏みしめる足音さえ重い。
「頼まれた船が仕上がってございます」
「そうか、早かったな」正綱の頬に驚きと喜びが咲いた。「早速見せてくれ。ただ、まだ先だと思っていたから残りの銭を持ち合わせていないんだが」
「銭は要りませぬ」
長は立ち止まり、瞬きを繰り返す正綱をまっすぐに見つめた。
「その代わりに、わしらを民部様の許へお連れくださいませ。もう耐えられませぬのじゃ」
山と入江が複雑に入り組んで海岸線を形成する志摩の地は、奈良朝の頃より国主が定められていたが、実際には地頭と呼ばれる小領主が地域ごと湊ごとを治めていた。
魚や貝を捕り、廻船を出し、他湊からの船と交易する。船が入れば砂州や岩礁を避ける水先案内の礼金、港湾利用料、あるいは領海の通行料を課し、従わねば船を襲い荷を奪う。税を納めず、独自の法のもとに地域と海とを支配する地頭とその一党を、都の官人は海賊と呼んだ。
瀬戸内海を支配して四国九州の租庸調を京へ運ぶ船を襲う村上党、肥前を拠点に高麗や明の沿岸部を襲う松浦党とは性質が異なるが、壇ノ浦の合戦に船二百艘兵二千を率いて参加した熊野別当湛増をはじめとして、後醍醐天皇の皇子懐良親王を護って九州渡海に協力するなど、志摩熊野の海賊は九州から関東までの沿岸を我が物の如くに支配する。その神出鬼没ぶりと害の大きさから鬼とさえ呼ばれていた。
中でも悪行を重ねた志摩海賊に九鬼氏がある。
天文六年(一五三七)に志摩全域が北畠家の勢力下に入った後も他の海賊衆さえ襲う悪逆は止まず、ついに永禄三年(一五六〇)に北畠具教と十二地頭に討伐を受けて滅ぼされたが、地頭の弟嘉隆は包囲を掻い潜って織田信長を頼った。そして栄達の後に滝川一益に付き従って志摩に戻るや、かつて討伐に加わった小浜氏らを次々に攻め滅ぼして隷属させていく。
志摩の領主は北畠具教の子具房であり、九鬼嘉隆はその養嗣子茶筅丸の家臣でしかない。だが今や志摩一国は事実上、九鬼嘉隆の支配下にあった。
「九鬼のやりようが非道に過ぎるそうだ。税の取り立て、課する労務。それに魚もだ」
正綱は長の言葉に説明を加えて鳥屋尾に伝えた。
「日々の漁獲から一番良いものを奪い、他にも人を人とも思わぬ悪行三昧らしい。小浜浜の元の地頭小浜民部殿は九鬼の襲撃を辛くも逃げ延び、今は父と共に海賊衆として武田に仕えている。だから彼らも駿河へ行きたいと言うのだ」
「九鬼嘉隆は信長の威を借る外道」鳥屋尾は顎髭をしごいて唸った。「さりながら今の北畠家に奴を掣肘できる者はおらぬ。北畠の家臣が言うてはならんことだが、民の逃散もまたやむなしであろう。だが逃げたいのなら勝手に逃げればよいではないか」
「それがそう簡単にはいかんのさ」
九鬼嘉隆は家臣を各湊に派遣して伊勢湾を巡回警備するだけでなく、志摩から三河渥美半島への航路上にある大築海島に見張砦を造って兵船を常駐させていた。日頃沿岸部のみで漁をする漁民が大築海島より東へ向かえば怪しまれ、たとえ駐留船団を振り切れたとしても狼煙で伊勢大湊に拠点を構える巡回船団を呼ばれてしまえば逃げ切ることはできない。まして村総出の脱出となれば大きな犠牲が出かねなかった。
「待て待て、お主、漁民らの脱出行を手助けするつもりではあるまいな」
鳥屋尾は眉根を寄せて大きく息を吐いた。
「今が北畠にとってどのような時か、それがしが使者に向かうことにどのような意味があるのか、あれほど言うたではないか。民の難儀は確かに不憫である。だが今はそれがしを無事に、一日も早く甲斐へ送り届けることを優先せよ」
「それはできない」正綱は首を振った。「海賊の掟に反する」
日本には一万四千以上の島がある。海とは阻み隔てるものではなく、繋ぎ行き来する場所だと考えた海賊衆は誰でも交易相手あるいは仲間に迎え入れた。そして仲間を見捨てず、困難においては全員が全力を尽くし、共にあって共に栄えるとの掟を定め、いついかなる時も守ることを求めた。
「俺は伊賀に生まれたが、年の半分は海にあって海賊の掟を守るとも誓った。破れば追放だ。加えて小浜民部殿は義理の叔父で、小浜浜の皆には世話になっている。青海苔被ることはできん」
為さねばならぬ義理を果たさぬことを志摩では青海苔被るという。正綱の言葉に、鳥屋尾も小さく首を振って更なる反論を飲み込んだ。
「それほど掟が大切だというのなら、それもよかろう。だが、わしと小浜の民とを無事に送り届ける策があるのだろうな」
「無い」
断言した正綱は苦笑を浮かべて大きく伸びをした。
「俺もさっき話を聞いたところだ。そんなすぐに思いつくかよ」
正綱と鳥屋尾だけならば、見付かったとしても通行料を払えば済む。だが多数の小浜衆を逃がすとなれば多くの命を背負い、更なる危険を冒すことになる。口調は冗談めかしていたが、海に向けた正綱の瞳が鋭く細まった。
「北畠の侍大将なら、どのような策を用いる」
「海は広いのだ。大回りして大築海島から離れた海域を突っ切ればよかろう」
「無理だ。迷う」
正綱は首を振って即答した。
海の上に目印は無いため、漁民は湊や山の見える沿岸から離れることなく、日のある内に戻る。坂東などへ遠出する廻船も昼間に陸影や島影の見える沿岸部を伝い進み、天候が悪ければ船を出すことは無い。まして五艘以上の船団となれば、はぐれる船が出るのは必至だった。
「ならば数回に分けてはどうだ」
「村にも巡視が来るんだ。うまくごまかせればいいが、下手すれば半分も逃げられないな」
九鬼衆は漁の成果から税を徴収する際、浜に村人全員を集める。毎日のことではないが、数が減れば見咎められるのは必定だった。
「なるほどな。ならば、どうするか」
顎髭をしごいて鳥屋尾は唸った。
大築海島の見張砦から見付からぬように海を渡ることはできず、いっそ攻め込むとしても狼煙を上げられて巡回船団が集まってくれば小浜衆の命運は尽きる。少人数での奇襲ならば火攻めが有効だが、立ち上る煙と炎は狼煙以上に巡回船団の目を引くに違いない。
「さすれば、囮を使うしかあるまい」
囮の小浜衆が海域を横切れば、砦の九鬼衆は当然船を出す。だが自分たちで処理できる数ならば、狼煙を上げて巡回船団を呼ぶことはないだろう。その隙に小浜衆の本隊が伊勢湾を渡り、囮に紛れた鳥屋尾と正綱が九鬼衆を防ぎ、狼煙も阻止する。
「だよな。俺もそれしかないと思う」正綱も頷いた。「とはいえ、囮が軽すぎれば砦に多くの兵が残って狼煙を上げられてしまうし、重すぎて完全武装の上に総がかりでこられると抑えきれない。侮らせ、かつ全員で押し寄せるような囮じゃないとな」
「そんな都合のいい囮が有るものか。いや、待て。ならば老人や女子供ばかりの船を流された体で囮にするのはどうだ」
「確かにそれなら」呟いた正綱は考え込んだ末に首を大きく横に振った。「だめだ。砦から何人出てくるか読めないし、囮となった者を危険に晒すことになる。全員無事にとは望みすぎだとしても、はじめから犠牲にするような策は取りたくない」
「成就に犠牲は付きものぞ」厳しい声で告げた鳥屋尾は咳払いして言葉を続けた。「だが、こうなったからには言っておかねばなるまいが、それがしはその、船が苦手なのだ。どうにもあの揺れが吐き気を催してだな、弓を引くどころか、立っていることさえ叶わぬ」
「なんだって」
天を仰いだ正綱は、両腕を組んで唸った。
「仕方ないか。船酔いは気の持ちようだけではどうしようもないからな。それならとっさんには島に上陸してもらって、俺が船に残る策を考えてみよう」
正綱は右の人差指と中指を揃えて伸ばし、左手指で作った筒の中に差し入れた。瞑目して呼吸を鎮めると、刀を鞘から抜くように右手指を前へ払って縦横に空を切る。
「臨、兵、闘、者、皆、陣、列、在、前」
修験者から多くを学んだ伊賀衆に伝わる、精神統一のためのまじないである。そして指先を伸ばして揃えたまま啄木鳥のように幾度も額を叩いた。
だが正綱が答えを出すより早く海老網を仕掛けた船が戻り、浜小屋から赤胴色に肌の焼けた男たちを迎える良い匂いが漂いはじめた。正綱と鳥屋尾の鼻がひくつき、盛大に腹が鳴り響く。
「腹が減っては思案も痩せるな」
二人を呼ぶ声に応え、正綱は大きく息を吐き出して右手指を左手の鞘に収めた。
「まずは馳走になって英気を養うとしよう」
長の家に草鞋を脱いだ正綱の前に、色鮮やかに茹で上がった小海老が山盛りに置かれた。殻ごと口に放り込むと塩が効いてなお甘い肉と柔らかな皮が弾けて跳ね回り、飲み込むより早く次の手が伸びて止まらない。
続いて切り身の盛り合わせが大皿で置かれた。志摩は古来朝廷に海産物を献納する御食国であり、春先の伊勢湾では赤魚、目張、石持、鮎魚女などが豊富に捕れる。どれも先程
まで海で泳いでいたものばかりであり、透き通るように身の色合い美しく、箸で持ち上げても反り返るほどに身が締まっている。淡白な白身でさえ添えられた藻塩の一振りで目を瞠るほどに味わいが増した。
「めひび汁、やった」
両手を伸ばして汁椀を迎い受けた正綱は湯気と共に立ち上る香りを吸い込むや、口の端から弛みきった息を漏らした。
めかぶとも呼ばれる若布の根元を細く刻み、鰹だしを効かせたすまし汁である。箸で摘めぬほどにぬめりがあり、熱いのを息を吹きかけながら一気にすすると、えもいわれぬ旨味が打ち寄せた。
「確かに、うまいな」
先程からうまいとしか言わなくなった鳥屋尾も忙しく箸を動かし続け、二人の健啖ぶりに炊事場の慌ただしさが増した。炭火が爆ぜ、焼魚が饗される。伊勢海老、黒鯛、そしてうまいとはこれを食ってから言えとばかりに冬鰡の粕漬け、鯨の味噌漬けまでが皿に載る。水分が程よく抜けたところに味噌や酒粕が染み込み、旨味の熟成した取って置きの中の取って置きである。どれも溶けた脂が焼き目の付いた表面を滴り落ち、食欲を誘うように照り輝いていた。
そして顎髭を撫でるのも忘れて打ち震える鳥屋尾は、蛸飯を口に運び入れるや目をむいて大きくのけぞった。薄切りにした蛸の炊き込みご飯だが、伊勢湾の蛸は伊勢海老を食べて育つため、身の端々まで旨味と弾力に満ちている。そして米一粒一粒にまで染み込んだ芳潤な味わいが噛むほどに全身を駆け巡り、箸休めの岩のりでさえ歯ごたえ豊かで鼻から脳天へと潮の香りが吹き抜ける。鳥屋尾は一噛みごとに頭も体も揺らして口福を満喫した。
「わしはこの世で最後に食いたいものは鮑のすり流しと決めておったが、この蛸飯には決意が揺らぐな。腹がはちきれそうなのに、箸が止まらん。なあ、小浜衆は毎日こんな美味いものを食べて……」
二杯目を所望する鳥屋尾の傍らで、正綱は箸を置いたまま蛸飯をじっと見つめていた。瞳を大きく見開き、頬も、全身さえ細かく震わせる。
「熱い内にお食べくだされ」長が笑みと共に勧めた。「持って行けぬものは食べてしまわねば」
志摩は海と山が大半を占めて、漁民は日々食べる米でさえ伊勢や三河から買わざるをえない。日常は雑穀を八割近く混ぜた飯しか食べられないところへ九鬼嘉隆の重税である。生活は苦しく、蛸飯など正月か婚礼ぐらいにしか食べられないが、そうまでした蓄えも小舟では全てを運ぶことはできない。
まして小浜衆が置いて行くものは食糧だけではない。伊勢湾は波穏やかで、年間を通じて様々な海藻や魚介類、鯨まで捕れる豊かな漁場であり、網を仕掛ける海上の一角でさえ売り買いや質の対象に認められている。そうでなくとも先祖代々住み慣れた土地には、岩場や松の木一本にまで思い出が染み付いていた。
「いただきます」
正綱は身を正し、蛸飯を拝して口に運んだ。全力で噛み締めて味わい、一粒さえ残さぬよう次々と腹に収めていった。
不意に強い風が壁を揺らした。
「だしの風やと、明日は雨になるかもしれんな」
船を出すのも天気次第の漁民にとって、気象は最大の関心事である。長を含めた幾人もが浜辺に出て空を見上げた。
正綱も後に続くと北風が思いの外強く吹いていた。志摩では風を背にして左から右へ雲が動くのは天気が崩れる前触れと伝えられている。いつしか雲は厚みを増し、月や星を隠していた。
「まあ降っても春雨や。大降りはせんやろ」
それでも長の言葉に漁民らが浜辺に散った。夜闇に溶け込んで黒い小山に見紛うハサバに取り付くと、干していた海藻や魚を総出で集めにかかる。
「それだ」
唐突な叫び声に漁民らが振り返る中、正綱は鳥屋尾や長らを呼び集めて計画を話した。
「要は警戒させないことだ。ハサバに干物、それから若布を沢山用意してくれ。なにより皆が心を合わせて動いてくれることが肝要になる。できるか」
正綱は皆の顔を見回し、頷く瞳の光を見やって言葉を続けた。
「決行は明朝。舳乗は俺ととっさんが就く。もし、しくじったら皆は浜に漕ぎ戻ってくれ。それだけの時は稼ぐ」
舳乗とは船の前方先端部のことであり、船団の指揮を執ることも意味する。だが同時に最も危険の大きい持ち場でもあった。
「うまくいかせましょに」長は緊張を払うように笑い、幾度も頷いた。「青海苔ならず若布を被るとは良案至極。さあ、支度に取りかかろうぞ」
長の言葉に、改めて漁民らが散った。
「とっさん、巻き込んですまない」
「今更何をしおらしげに」鳥屋尾は低く声を上げて唸った。「先程の策、不備は無いように思うが、確信は持てぬ。いや、うまくいったところで蜘蛛舞ぞ」
蜘蛛舞とは綱渡りの曲芸を意味する。鳥屋尾の視線はこれまでになく厳しいが、正綱は眉を上げて笑った。
「綱ならば慣れたものさ。なにせ、俺は正綱だからな」
「まあよいわ」鳥屋尾は鼻を鳴らして顎髭をしごいた。「これこそ乗りかかった船か。甲斐へ無事に渡るためだ。全力で相勤めるまでよ」
降り始めた雨の中、小浜衆の船団は夜闇の残る浜を出港して北へ進んだ。東の空は漆黒から灰鼠へと次第に明度を上げていったが、太陽は一瞬姿を見せただけで雲に隠れ、濃い鈍色より明るくなることはなかった。
晴れていれば渥美半島まで見渡せる伊勢湾ながら、出港したばかりの小浜浜さえすぐに見えなくなる。今は背後に遠ざかる崖に焚いた大篝火しか方角を示すものは無かった。
「周りをよう見とれよ。答志島が見えたら、すぐ言うんやぞ」
「も、もし見えなかったら」長の言葉に青ざめきった鳥屋尾が、船べりを掴んだ指を白く強張らせて正綱に尋ねた。「そ、そそ、そのまま遠江まで辿り着けるということか」
「いや、西か北かに行き過ぎたということだ。大湊の巡回船団が鮫のようにうようよと集まる只中に飛び込むことになる」
鳥屋尾が大きく身震いした直後に声が上がった。右に霞む島影を答志島北西の平手﨑と見当を付け、雨が強まったり弱まったりを繰り返して霧さえかかる中を船団は答志島に沿うように向きを変える。
やがて答志島の東端を過ぎると、正綱と鳥屋尾、屈強な漕手二人を乗せた船が船団を離れた。
「ご武運を」
「皆も万事抜かり無く、怪我の無いようにな」
これ以降は連絡を取り合うことはできず、互いの状況を知ることさえできない。無事に伊勢湾を渡り切るためには、互いが策のとおりに進んでいくよう祈るしかなかった。
「さあ、急ごう」
正綱は四畳ほどの木綿帆を張った。
綿花は広い平野と温暖な気候、なにより伊勢湾で大量に捕れる鰯を肥料にすることで大量生産が可能となった伊勢の特産物である。収穫した綿を紡いで糸とし織り上げた木綿帆は、防水性、耐久性、速力などあらゆる面で従来の茣蓙帆を凌駕して伊勢志摩の海賊衆や廻船集団に大きな優位をもたらしており、正綱も向井家を示すひらがなのむの字の大きく描かれた帆を広げると、大築海島南西岸に舳先を向けて速度を上げた。
だがどれほども進まぬ内に、前方の陰影が不意に一艘の船の形を成した。小雨と霧に阻まれて音も聞こえなかったが、気付いた時には九鬼の船印さえ見分けられる距離にある。
「い、射倒すぞ」
青い顔のまま震える指を弓に伸ばす鳥屋尾を制し、正綱は立ち上がった。
「逃がしたら一巻の終わりだ。もっと近づくまで待って、油断を誘ってくれ。合図する」
帆柱を登り帆布に隠れた正綱が最上部から見やると、近づく小早船に四人の九鬼衆の姿があった。短い小袖をだらしなく着崩して胸から褌まではだけていたが、漕ぎ寄せる息に乱れはない。
そしてもはや逃げることもできない距離に近づいていた。この期に及んで砦の九鬼衆に報されては奇襲は成功し得ず、対応に手間取って小浜衆に遅れても多くの犠牲を出すことになる。正綱は足だけで帆柱にしがみつき、鉤縄を帆柱にきつく結わえた。
「そこな船、停まれ」
船べりに足をかけて九鬼衆が笑った。
「朝からいい獲物がかかったぜ。通行料を払ってもらおうか」
「つ、通行料とは、い、い、い、異なことを」鳥屋尾は首を振りつつ帆柱の上の正綱と視線を交わした。「こ、こ、この海が貴殿らのものだとでも。いや、いやいや、は、払ういわれは、な、な、な、無い」
「震えながらのその大言、気に入った。だが高くつくぜ。やい、帆を下ろしやがれ」
気勢を上げた九鬼衆は船を更に漕ぎ寄せて船槍を振りかざした。船槍は兵器であると同時に、穂先近くについた鉤を引っかけて接舷するのにも使われる。だが九鬼衆の船が間近に迫るや、合図を受けた鳥屋尾が大きく舵を切った。旋回する帆布の陰から縄にぶら下がって飛び出た正綱が、乗り込もうとする九鬼衆の胸板を蹴り飛ばす。そして反動で宙を回るやもうひとりの顎に膝を叩き込み、着船と同時に片側の側板に体重を乗せた。
山野を駆け、岩に登り枝を跳ぶ伊賀衆の日常は平衡感覚の鍛錬そのものであり、海にも船にも親しんだ正綱は波への対処も体に染み込んでいる。斬りかかろうとして大きくよろけた九鬼衆の刀に打刀を合わせ、返す刃で九鬼衆の腕の内側を斬り裂いて刀を弾き飛ばした。
「ひ、ひとり逃げるぞ」
鳥屋尾の叫びと水音が上がるのが同時だった。正綱も駆けながら打刀を置き、いくつもの小袋を結わえた革帯を外して海に飛び込む。抜き手を切って泳ぐ九鬼衆に蹴られないよう横に並ぶと、腰の短刀に伸ばそうとする手を掴んでそのまま腰に抱きついた。
「や、やめ……」
引き剥がそうとする動きを制し、正綱は暴れる九鬼衆を海中深くに引きずり込んだ。溺れまいとする激しい抵抗は、だが大きな泡を吐き出して短く終わる。意識を無くした体を抱えて浮上した正綱は漕手の力を借りて九鬼衆を船に押し上げた。
「急ごう」
船によじ登った正綱は海水を滴らせたまま艪を取った。ひとつなぎに縛り上げた四人の九鬼衆を曳航した船に放り込み、再び東へ船を走らせる。
やがて岩礁と砂州を縫うようにして南西から大築海島に船を着けると、正綱は鳥屋尾と頷きだけ交わして砦へと駆け上った。高さはさほどでもないが、切り立った岩場が連続して嶮しい上に足に刺さる。それでも頂上の砦を囲む風よけ程度の板壁にまで辿り着くと、身体をくっつけて中の様子を窺った。
「おい、鯨だ。鯨だぞ」
間をおかずに沸き立った叫びが砦で反響した。無数の海鳥のけたたましい鳴き声が近づく中、歓声と慌ただしい足音、銛を持ち出す金属音が砦の中を駆け巡る。
鯨は一頭捕れば七浦潤うといわれる一攫千金の獲物である。鯱に追われ、あるいは迷い込んで沿岸部に現れるのはごくまれであり、永禄十二年(一五六九)に織田信長が朝廷に献上したことが特記されるほど希少性が高い。食材格付では常の最上である鯉よりも上位とされ、髭は弓の弦、脂肪は油、歯は工芸品にともれなく活用される。砦中を駆け巡った無数の足音は次々と浜辺へなだれ降りた。
だが九鬼衆が鯨と見たのは小浜衆の船団である。連結した船上にハサバを打ち立て若布を被せて黒く覆い、雨と厚い雲と早朝の薄暗さとで偽装の粗さをごまかした上に、大量の干魚を載せて無数の海鳥を呼んでいた。鰯鯨や背美鯨は烏賊や魚の群れを海面付近にまで追い込んで一気に飲み込むため、横取りしようと海鳥が上空に群れなして集まる。経験豊富な漁民ほど、海鳥の群れを鯨の目印にすると正綱は知っていた。
なにより欲深な砦の九鬼衆であれば、鯨の利得を独占しようと狼煙を上げないとの予想が的中していた。
正綱は一転して静まり返った砦の板壁に鉤縄をかけてよじ登った。駆け回った足音の反響から、砦内部が壁や仕切りの無いひとつづきの広間だとの見当がついている。騙されたことに気付いて戻った九鬼衆に狼煙を上げさせないことが正綱の役目であり、欠伸をしながら外へと出てきた男に板壁の上から飛びかかるや無防備な脇腹を柄頭で突き上げ、意識を失った体を蹴り倒して内部に飛び込んだ。
浜辺からは早くも悲鳴が響いていた。
鯨を狩るつもりで銛と小刀しか持たぬ九鬼衆が船に乗り込んだところを、高い岩場に陣取った鳥屋尾が射倒す手筈である。船や身を隠すものの無い浜辺に鎧も着こまずにいては速射を避けようがなく、岩が切り立って散らばる浜辺は九鬼衆が逃げることも鳥屋尾に近づくことさえも阻む。
「やってくれたな」
広間の奥、刀掛から長大な大太刀を取った寝間着姿の男が正綱に振り返った。掻き鳴らされる弓弦の音と悲鳴とが立て続けに響く中、顔色ひとつ変えることなく大太刀を抜き放つ。
「逃げ場は無いぞ」
「あるとも」男は大太刀を右肩に担ぐようにして、鍔を口元まで持ち上げた。「貴様を斬り、狼煙を上げる。後はしばらく持ちこたえればよいだけのこと」
大きく踏み込むや、男は大太刀を横薙ぎに一閃した。後ろに跳んだ正綱は返す刃を潜ってかわしたが、頬に鋭い痛みが走る。更なる斬撃が皮一枚を切り裂き、小袖の胸元から切れた端が垂れ落ちた。避けてはいたが、大太刀か男の腕かが正綱の予想を超えて長く、速い。
「ちょこまかと」
男は左肩に担いだ刃で更に低く薙いだ。正綱は前へと跳んで刃をかわしたが、体が入れ替わるや男は外への唯一の出口に向かって駆け出した。
「待て」
反射的に追いかけた正綱の眼前で、男が立ち止まって振り返った。壮絶な笑みを浮かべて腰を深く沈め、膝を床に擦らせながら大上段に振りかぶる。
ここまでの斬撃が全て横薙ぎだったのは、振りかぶれば大太刀の長い切先が天井に食い込むからだと正綱は踏んでいた。ならばこそ追走したが、大太刀は正中線を真っ向から斬り下ろす軌道を予告している。そして前のめりに駆け込んだがゆえに、正綱は後ろにも横にも跳べず、致命的な一撃を避けきれない間合にあった。
「死ね」
(気になる続きは、ぜひ本書でお楽しみください)
書誌情報

書名:海賊忍者
著者:諏訪 宗篤
発売日:2024年09月28日
ISBNコード:9784041152874
定価:1,870円(本体1,700円+税)
ページ数:288ページ
判型:四六判
発行:KADOKAWA
★全国の書店で好評発売中!
★ネット書店・電子書籍ストアでも取り扱い中!
Amazon
楽天ブックス
電子書籍ストアBOOK☆WALKER
※取り扱い状況は店舗により異なります。ご了承ください。
