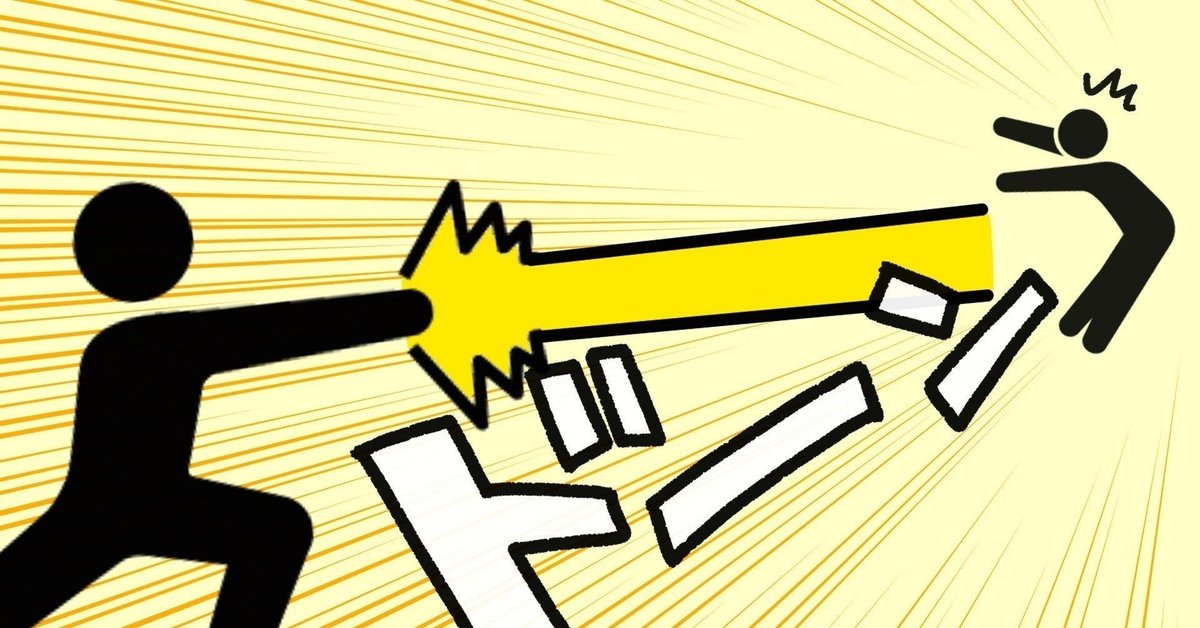
意外と大事なアクティビティ:じゃんけん
じゃんけんについて熱く語る記事を書きたいと思います。

じゃんけんは色んな国で遊ばれていますが、日本語教育においても「じゃんけん」は授業中何度もお世話になりますよね。
グーが石/岩、チョキがハサミ、パーは手というのが定番だと思います。チョキは国によって、地域によって形状が変わりますが、人差し指と中指を伸ばす形が日本では定番かなとも思います。

さて、このじゃんけんですが、日本語授業ではどんなアクティビティとして使えるでしょうか。勝ち負けを決めるだけじゃないですよ^^
「じゃんけん」が見せるリズムの重要性
じゃんけんの初めに皆さんはどんな掛け声で相手とのリズムを合わせていますか?
1.「最初はグー」と言うタイミングで合わせる
2.「じゃん、けん、ぽん!」で「ぽん」の時に出す
基本的に上記1、2がポイントになります。このとき自分とタイミングがあわない人は「1を言わずに2から始めてしまうVS1も2も言う」人同士。
しかし、日本人以外と同じ1、2のルールを説明したとしても、まだまだ弊害が続きます。それが「リズム」です。
なぜずれるのか
このズレこそが日本語のリズムと他言語のリズムの違いです。
一度言語化してみましょう。
1.「最初はグー」の「最初は」部分で拳を一旦振り子のように後ろにもっていく
2.その次、「グー」のタイミングで拳を出す
3.「じゃーん・けーん・ぽん」の3拍子であることを相手に伝える。その際、「ぽん」は本番なので、「じゃーん」と「けーん」の時間差により、最後の「ぽん」がどのくらいのタイミングで出すべきなのかを知らせる。

・・・・けっこう複雑なことをしています。
じゃんけんを出すタイミング=リズムの練習になる
このリズムを合わせるには
「じゃん」の”ん”が撥音、特殊拍であること
「じゃーん」「けーん」と相手との呼吸を合わせること
「じゃーん」と伸ばす相手の場合、長音の知覚が必要になること
※間違っても「じゃんー/けんー」という形式でないことにも気づく(気づかせる)こと
どうしたら直るのか/直せるのか
最初は手拍子を取ってもよいですね。
また、白板に書いて、リズムを確認しつつ実演するのも良いでしょう。
いかがでしたか。今回は長くなってしまったのでじゃんけんはリズムの練習アクティビティに使えるということで終わってしまいましたが、また次回機会があればじゃんけんを使った練習方法を紹介できると思います。その際にはどうぞよろしくお願いいたします。
いいなと思ったら応援しよう!

