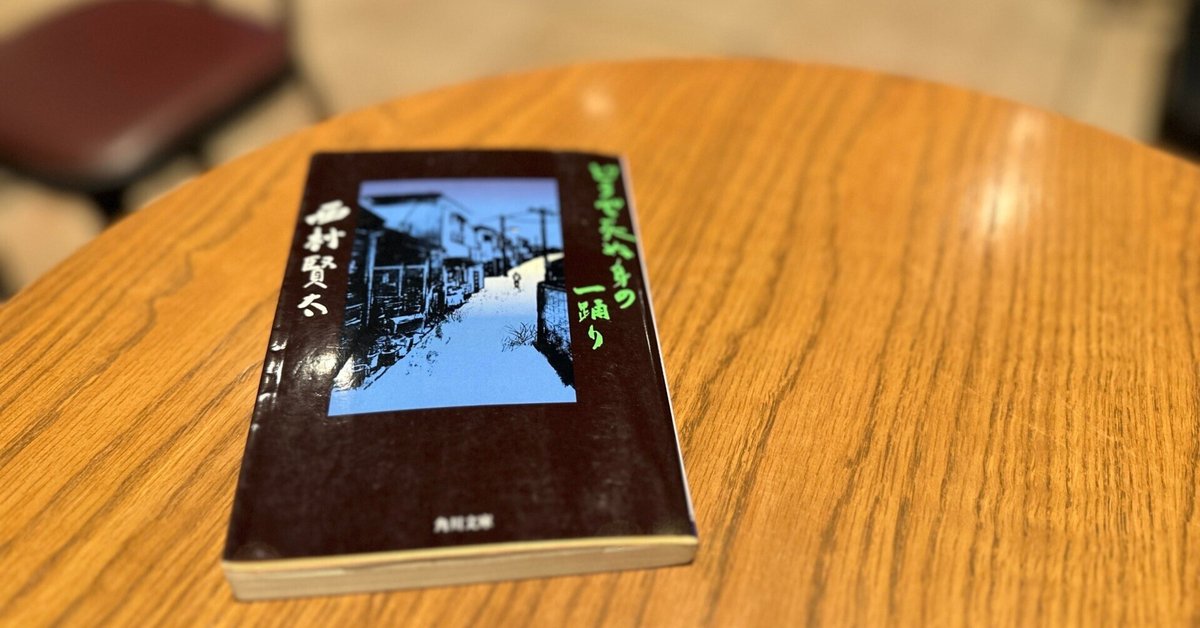
西村賢太『どうで死ぬ身の一踊り』を読んで。
すっかり忘れていた「西村賢太」
昨年の2月頃だっただろうか。突然、まるで発作のように「西村賢太」のことを思い出した。早速アマゾンで購入しょうと「西村賢太」で検索してみると、初期の小説ばかりか最近の小説までもが絶版となっていた。しかも中古本はとんでもない値段がふられていた。これは諦めるしかないなと思った。こんなに人気なのかと驚くとともに、最近の作品ですら重版もせずにあっさり絶版にしてしまう出版社の堪え性のなさに怒りを覚えるばかりであったが、この品切れは実は、西村賢太の急逝によるものであった。わたしは彼が急逝していたことを知らなかったのである。
西村賢太については芥川賞受賞作の『苦役電車』を読んだきりであった。そのクズっぽさと昭和後半の時代を感じさせる空気に面白さを感じたものの特別の感慨というものはなかった。むしろそのあとにおまけ程度に添えられていた短編のほうに興味が湧いた。編者との約束を反故にしたり、自身の怠惰を克明に描いたりしているこの短編のほうが芥川賞の作品よりもずっと魅力を感じたのであった。
その後十数年、西村賢太はわたしの興味の埒外に消えていた。芥川賞を取りTVに出まくっていた西村賢太の姿を目にする度に焦燥していたのだ。いままでの生活では考えられないTV出演料を手にし浮薄なタレントと交流している様を見るにつけ、奇跡的に発掘された作家が俗物世界へと馴致させられ、その稀有な作家性を腐敗させていくように感じられたからであった。そうした姿を観るのが耐えられず、その後は忘却にまかせるままにしていた。
しかし忘れていたとは言うものの、Amazonに掲載された読者レビューにあった「彼の本質は『苦役電車』ではなく、その前の初期の作品群にある」というようなコメントの記憶が長くわたしのなかで反響し続けていた。そしてたまたま前年に西村賢太編纂の『田中英光傑作選』を読んだことが、改めて西村健太を思い起こさせることになった。さらにそのあとがきに記された西村健太の極めて硬質で乾いた文体に驚きを覚えた。現代の作家とは思えない言葉遣いと文体であった。それで、やはり「西村賢太」は読まなくてはならぬと思い直すことになった訳だ。
それから数ヶ月、再度忘れかけ始めていた西村賢太の名前を発作のように思い出した訳であるが、明らかに私の財布とは不釣り合いの金額の表示に怯むばかりであった。しかしそれから数ヶ月すると、文庫本の重版が追いついたようでアマゾンには新品の文庫本が安価でずらりと並ぶようになっていた。
わたしがAmazonから入手したのは、彼の最初期の作品集『どうせ死ぬ身の一踊り』であった。読後、わたしは金槌で頭を叩かれたような衝撃を受けることになった。「西村賢太」は、わたしが求めている”魂の文学”そのものであったのだ。
実存の重み、"魂の書”だった。
これが本当に平成の作家なのだろうか。文学の世界が重みを失するさまに焦燥していただけに、「西村賢太」の小説との出会いは大きな衝撃に感じた。80年代あたりからなのだろうか、新しい文筆家たちは、掛け替えのない実存の重みを捨て去り、どれもこれもが決定的に重さを欠いた絵空事のように浅薄に響く文学ばかりになってしまったように思えて仕方がなかった。己の人生を縣けるような生真面目な文学は嘲笑の対象となり、ぶきっちょよりはスマートに、実直さよりは俗流化へと文学が流れていってしまったように感じて仕方がなかった。自分のなかの桎梏や闇を、その実存的な葛藤を描かずに一体何を描くのだろうかというのが最近の文学に対する私の焦燥であった。
しかし西村賢太は、いささかも自分を誤魔化さずに、いかなる粉飾もせずに己の実存の重みを描出することのみに傾注していた。そのバカ正直さに心地よさすらも感じられてしまうほでであった。いまの作家たちがとうに忘れてしまった、「己の人生」と「書くこと」が等価であるということが、いかに尊いことなのかを改めて”西村賢太”は教えてくれるように感じるのである。
現代の文学が実存を忘れ浮薄化していくのと同時に、もうひとつ、私が文学に感じる焦燥は、言葉がどんどんと軽量化され皮相に響く文体ばかりになってしまったことである。豊富で多彩な辞句や絢爛たる修辞を楽しめるような作品や作家を見出すことが極めて難しくなったように感じるのだ。それは小説家ばかりでなく、翻訳家であっても、学者であっても同様であり、どんどんと日本語が薄くなり、ありきたりの言葉だけで綴られるようになってしまった。大先生と呼ばれるほどの芥川賞作家の作品を読んでみても、そこに並ぶのは、中学生1、2年生であれば誰でも理解できる辞句や修辞ばかりで刺激を受けることがない。先人たちが賢明に切り開いてきた日本語の厚みは、難しくて分かりづらいという一点で、出版者の編集者からも、作家からも、さらには読者からも切り捨てられ、平明さばかりが追い求められる極めて薄口な世界に転じてしまったことに焦燥するばかりなのである。光文社古典新訳文庫などのように、何が何でも分かりやすく訳し直すことが本当に文学の豊かさにつながるとはとても思えない。
何もわたしは、昭和の一時期の読者が好んだように晦渋かつ高踏的な文体を良しとしているわけではない。捉えどころのない感情の澱や深い思考、難解な論理を精緻に描出するには、複雑さは避けて通れないということが云いたいのである。複雑な対象を無理に平明に描いたとしても、掴んだはずの砂がするすると指の間から零れ落ちていくがごとく、逆に実相から遠ざかるばかりだという当たり前のことを云いたいだけなのだ。精緻に描写するには複雑な文章構造は避けて通れないときもある。複雑な世界をいかに言葉で編むのか、それこそが文学や哲学の醍醐味ではないだろうか。そもそも一見難しい辞句や修辞ばかりが並んでいる文体であっても、名人の文体にあっては喉越しは極めて滑らかなものである。
不可逆的に退行していく言葉の軽量化を見せつけられるにつけ、文学の行く末に気鬱になるばかりであったが、この西村賢太の文学には、筆致の力強さ、己と文体との揺るぎない一致、そして決して晦渋な言葉ばかりを並べているわけではないが、時折われわれが忘れてしまっているような言葉を選び取る卓抜なる文体があったのだ。
「私小説」という小さなカテゴリーで片付けて欲しくない。
わたしが買ったこの本には、初期に綴られた3編が含まれている。著者は特段これを連作のように綴ったわけではなかったのだろうが、時系列に並んだこの小品は、結果的にひとつの物語を綴ることになっている。
----------------------------------------
女はいつもより小一時間位遅くパートから帰ってくると、早速台所にたってカレーの準備を始めたが、そも作り始めが出遅れた分、そのとき私はひどく腹を空かせていた。
やがて女の呼ぶ声に、待ってましたとばかりに食卓につくと、そのカレーの上にまた例によている。
いったいに女は、それまでの生活でそうした習慣がなく、外の食堂でカツカレーなぞを食べた経験もないとのことで、私と一緒に暮すようになってからその味を覚えて以降は、やたらとカレーに揚げ物を載っけたがるようになっていた。逆に私は、いかにも家庭的な、女性の手作り、といったシンプルなカレーのほうが全然ありがたいのだが、とあれ目も眩むほど空腹だったので、スプーンを取ると同時に、猛然とそれを口に運んでいった。
と女は突然、
「豚みたいな食べっぷりね」
と呟いたのであった。
無論、その口調は悪気を含まぬ、女にしてみればむしろ好意的な揶揄を、ふと口走っただけだと云うことは理解できたし、すぐと、「またたくさんあるから、おかわりしてね。カツはそれだけしかないけど」と、優しい声で続けたことからも、女は何んの深い思慮もなく、悪意もさらさらなかったものに違いないのだが、初めそれを聞き流そうと努力しかけた私は、その何気ないはずの言葉に対してわき上がってくる激しい怒りをどうにも抑えきれなくなり、スプーンをカレー皿に放るとそれを持って台所にゆき、半分近く残っていたのを流し台の中に叩きつけてしまった。そして傍らのガスレンジの上の、カレーの鍋も、流しの中にぶちまける。熱い液体は四散し、私の服にも飛沫がかかった。
無言でテーブルのところに戻ると、動きを止めて驚きの表情をあらわにしている女の皿も摑み、それはそのまま台所内の壁めがけて投げつけた。
----------------------------------------
荒ぶる気持ちを抑えきれなかった男の心情の流れとその生々しい醜態ぶりを読んで、ただならぬ癇癪持ちであったわたしは、自分が隠し持っている愚劣なる自身の過去の姿をそこに見る思いがした。ちょっとした何気ない女の言葉に発火し、それを抑えようと努力するものの追い打ちをかけて放たれた女の言葉に憤激し、せっかく作ったカレー鍋もろとも流しに捨てる様。この小説で示されたように全てをご破算にする “ちゃぶ台返し”を過去の自分も何度か経験してきたように思う。若かったということもあるだろう。西村賢太の姿やわたしの場合は苛烈なのかもしれないが、決して稀なことではないだろう。こうした摩擦は多くの男女間に常に存在するものではないか。
西村賢太のように女に手を上げるということは一度たりともなかったが、一方で西村賢太のようにその愚行のあとに、めそめそと傷つけた女を追い回すことも一度たりともなかった。こうして考えてみると、本当の意味で女を愛せないわたしのほうが、西村賢太よりもよっぽどクズな不具者ではないかとと考えてしまう。
自身を美化することも誤魔化すこともなく自身の浅ましく身勝手な心情をそのまま精細に描出する西村賢太文学を、「私小説」などというジャンル分けで片付けてほしくないなと思った。西村賢治文学には、まさに人生そのもの、紛う方なき実存の重みが濃厚に詰まっているではないか。これだけの重みと比肩しうるものが最近の小説にあるのだろうか。「私小説」などというカテゴライズで小さなジャンルのなかに閉じ込めようとすること自体、文学批評の劣化を疑わざるを得ないと思うのだ。
西村賢太の生と死
「ただでさえ私にとり、月一回藤澤清造の展墓をし、月回向の法要を行なうことは自分の唯一の矜持の立脚点となっていたが、あまつさえこの祥月命日には施主としての年回忌をひらけることがうれしくてたまらず、これで清造の全集と伝記さえ作成したら、もういつ果敢なくなってもかまわない気持ちになっている。」
藤澤清造の全集の編纂にかかわるだけでなく、藤澤清造の月回向の法要を企画し毎月東京から石川県に足繁く通ったり、行方不明となっていた藤澤清造の最初の墓標を探し出し自宅に飾ったり、そのただならぬ執着に驚かされるばかりだが、藤澤清造は、まさに彼が生きる上での唯一の救いであり光であったのだろう。西村賢太は、子供の頃から不幸を抱えていた。親からの愛情を得ることもなく父親の性犯罪により一家離散を余儀なくされ、中卒という最底辺のレッテルをまとい世間一般の幸せから隔絶されていたのだ。貧困という厳しい生活苦と孤絶のなか、西村の生をつなぎとめていたのが、唯一藤澤清造への思いであったのだろう。その思念の深さこそが、現代の作家たちが忘れてしまった文学の重み、実存の重みではないだろうか。
芥川賞受賞後、メディアへの露出するようになりレギュラー番組までをも仕留め、金銭的に大きな余裕が生まれたことは想像に難くないし、いままで実生活において関わることなどまるで考えられなかった著名人や人気タレントたちとの知己を得、彼の取り巻く環境は大きく変わったはずである。そのように俗世に塗れることで西村賢太の作家性が蝕まれていく様をわたしが勝手に焦燥していたわけだが、それは杞憂に過ぎなかったのかもしれない。この本を読んで西村賢太の異常とも思える一念の深さを知ることにより、彼が安易に俗世間に流されていくとは考えられなくなったのである。
西村賢太が生前執拗に追い求めた藤澤清造という作家を私は知らなかった。藤澤清造は、石川県七尾生まれ。同じ世代には、岡本かの子(岡本太郎の母)、室生犀星、内田百聞などがいるらしい。生涯貧困と病に苦しみながら作家活動を続けていたが、昭和七年一月、芝公園内で凍死という壮絶なる最期を遂げている。
この文庫版の文末には、作家や文芸評論家の解説が三編ほど掲載されていていずれも興味深い。以下は、いち早く西村賢太の才能に着眼した久世光彦氏の解説の一部である。
「貧困に喘ぎ、同棲している女に暴力を揮い、愛想を尽かした女が逃げ出すと、その前に土下座して涙を零して復縁を哀願する-西村のその姿は『根津権現裏』の藤澤清造に瓜二つである。つまり、西村は〈現代〉の実人生で、藤澤と同一化しようとしているとしか思えない。西村の文学は、身も世もなく悶える文学であり、その魂の姿勢は、いまは忘れ去られた〈文学の核〉なのではないかと思われる。」
タクシーのなかで急逝した西村賢太は、芝公園で凍死した藤澤清造の死をそのまま完璧なまでになぞられたかのようで驚きを禁じ得ない。西村賢太の死は、文學界における大きな損失であり、熱心な文学愛好家にとっての悲劇であることに疑いようはないが、彼の死は自分の生を貫徹した末の、強い思念の末での、終幕のかたちとして結晶したものであり、まさに彼の強い思念が恩寵のように死を招来したかと思うと感動すら覚えてしまうのである。まさにあっぱれな幕引きではなかっただろうか。
