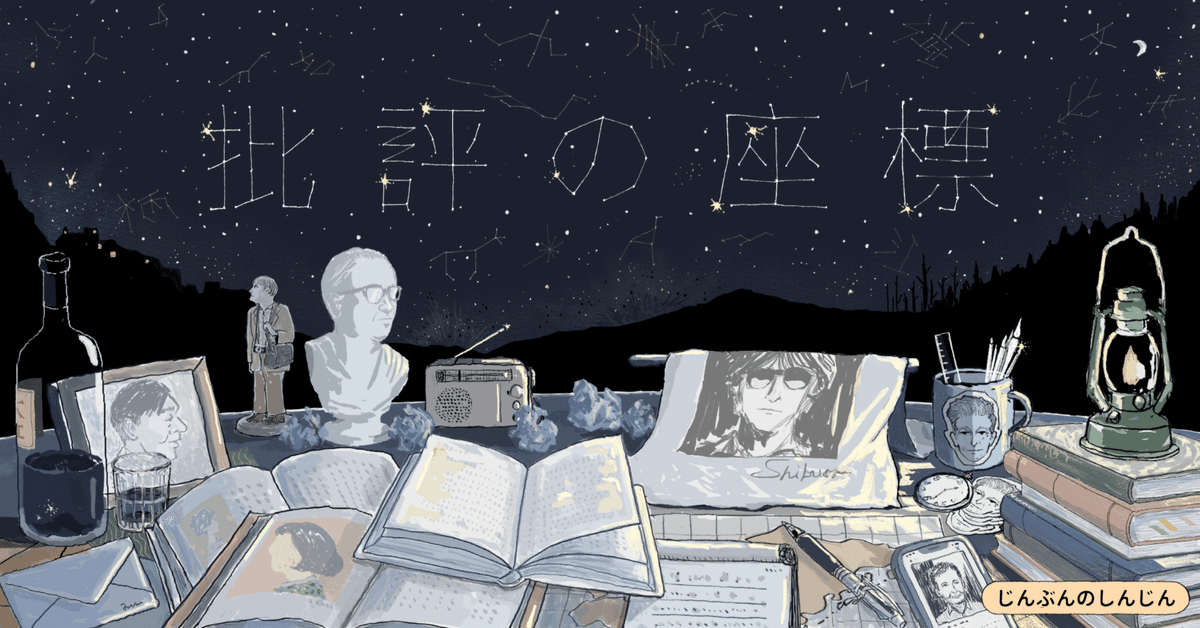
【批評の座標 第3回】最底人を生きる――80年代の浅田彰について(西村紗知)
第3回で取り上げるのは、『構造と力』『逃走論』等をはじめ、フランス現代思想の輸入とともにポップな批評でかつての若者たちのアイドルとなった浅田彰。「椎名林檎における母性の問題」で2021年にすばるクリティーク賞を受賞、その後も音楽やポップカルチャーをはじめ、幅広い分野で精緻な批評活動を続ける西村紗知が、80年代を風靡した浅田を論じます。
――批評の地勢図を引き直す
最底人を生きる(80年代の浅田彰について)
西村紗知
1.
日本における批判理論研究の先駆的存在である清水多吉がその昔、「ニュー・アカデミズムの人びと」[1]というタイトルで、浅田彰、栗本慎一郎、中沢新一の三人の存在に触れて、その当時の新しい知識人のモードについて考えるため、といっても社会科学のプレゼンス低下を嘆く論調が大半を占めるかたちで記事を書いていた。浅田などが責任編集を務めていた人文系雑誌『G・S』の売れ行きが好調で、岩波書店もそれと同系統の雑誌である『へるめす』を準備中だという産業界の状況にも触れつつ、清水は次のようにいう。
「70年代なかば以降、世界的な社会主義勢力の失態、魅力喪失で、「学」を社会主義の実現のために役立てるなどという考え自体が、破産してしまった。それとともに、社会科学の体系的学問性まであやしくなってきている。そこで、社会科学は、一方に、政策知と、他方に、あいも変らないマルクス文献学とに分極し、知的魅力を日に日に失っている有様である」[2]
こうした状況下、当時26歳の浅田彰(1957-)はめきめき頭角を現していった。デビュー作『構造と力』(1983年)は、まずもって大学批判の書であった。
浅田をはじめとする当時30歳前後の知識人が登場する時代背景はこうしたものである、というのを念のため確認しておこうと思い、清水のこの記事を引くのだが、清水の文句は、フランス系ばっかりでドイツ系の思想潮流を汲む人が少ない、というところに尽きるものかもしれない。構造主義と記号学に代表される「フランス現代思想」に対する批判意識が、そのままこの三人への批判の根拠となり彼らの具体的な仕事の紹介はほとんどされていない。
「この派の人たちは、微妙な所での論点ぼかし、論点ずらし、はぐらかしの術にたけてきている。念のために申し添えておくが、これは、この派の人たちを非難するために言っているのではない。現代の資本主義や、あるいは現行の社会主義を、はぐらかさずに真正面から批判する、また、現代文化のありようをパーフォーマンスとして批判するなどということが、いかにしんどいことか、この派の特に若い人たちは、よく知っているからである」[3]
「はぐらかし派」と「ぶつかり派」という二項対立の見立てでもって、そのはぐらかし派の方にその三人を含め、半ば唐突に、実名をあげることもなく、フランクフルト学派第二世代の状況並びに可能性について示唆してこの記事は締め括られる。
「私自身としては、フランス系の「はぐらかし派」とドイツ系の「ぶつかり派」が、それこそ、ある社会運動の地平で、ジャーナリズムの地平で、火花を散らす日がくるのを心待ちにしている」[4]
めいめいがはぐらかしつつぶつかればよいのではないかという率直な感想が浮かび上がると共に、判然としない心地が募る。
判然としないのはこれ以外にもある。当時、『「浅田彰」――「知」のアイドルの研究読本』(1984年7月)という言ってみればアンチ・浅田アンソロジーでもあり確実にファンブックでもある論集が刊行されていたのだったが、その中で作家・中島梓は「あたし、バカじゃない。 つまり。 それなのに……。 どうして、あたし。 わからなかったのかしら。なんにも。この本。 やっぱし、あたしの頭、わるいのかしら。 考えてしまった。 えーい、新井素子ごっこなんかしてる場合と違うわ(しかしこりゃラクでええの、もとこちゃん)。 でね、要するに、私は悩んでいるのだ。 この本がベストセラーだ、ということは、だ。 日本の大学生諸君って、そんなに頭いいの、え?」[5]と、呆然としていた。
このアンソロジーの目次には、それぞれの原稿から切り抜かれた各執筆者のキラーフレーズというより浅田に対するほとんど悪口に近いコメントが付されている。中上健次は「簡単に言うと、浅田彰は自分のチャート式ノートを本にして大量部数売り、ぬけぬけと金をつかんだということである」[6]。見も蓋もない。山口昌男の場合、「浅田君はいまの社会で一種の道化の役をしていると思う。そして、マスコミは、面白いようにふり回されている」[7]。確かに、批判の道筋としてマスコミ批判というのはありそうなものだ。そして四方田犬彦は「浅田彰は数多くの伝説に包まれている。京大の研究室にはピアノが二台あるだけ。空海の遠い血縁に当たり、脳細胞がエイズと化している」[8]。これはよくわからないが、84年の浅田、完全にナメられている。
なぜ、みなこぞって、はぐらかしているだのわからないだのと言ったり、あるいはわからないようなことをぶつけたりするのか。判然としない心地のまま『構造と力』の頁を捲っていく。第4章の「国家批判」から最終章のあの有名な「砂漠」に関する記述にかけて展開される切実な批判が通じないというなら、それってどういうことなのだ、と筆者は混乱する。ここが気分としてでも伝わらないなら、それは頭の良し悪し以前に消費社会での生き方の問題ではないか。消費社会とは距離感があって潔白ですからわからないとでも態度表明したいか、読者の側の批判意識の無さのせいではないか(この度筆者が80年代の浅田批判を調べてわかったのは、浅田のキャッチコピーとして流通するものでもある「逃走」というアイデアにのみ依拠するような浅田批判はもれなく無力である、ということだ。それは浅田の仕事を前に逃走している)。
マルクスの貨幣―商品のモデルをベースに(浅田は「クラインの壺」で、貨幣と商品を非拘束的かつ絶えず流動するものとして説明するのであったが)、精神分析理論を接続させ、国家と家族を同時に批判的に解体しようとする。あとはニーチェとフロイトが接続されてもいるので、この辺りがセットになっているのを見ると、「大衆の解放」のスタンダートな言説の系譜にある労作なのではないかと思うのだが、日本のホルクハイマー受容に重要な功績を残した清水多吉が首をかしげているのを見るに、違うのだろうか。「逃走」というキーワードについては、『逃走論』(1984年)という、より一般向けの著作でも説明されていると思うが、当世風のライフスタイルの提案であるよりもまず第一に、スキゾ=ギャンブラー、パラノ=吝嗇家として説明されているものであって、資本の解体のための理論から派生したものだというのは、それほど理解するのに難しくないのではないか。つまるところ、これは浅田なりの再分配へ向けた理論だったのではないのか。こうして浅田の理論的道具立ての多くは、フランクフルト学派第一世代に共通している。確かに芸術の趣味はより軽やかである。浅田が好んで上げる芸術家はケージ、グールド、坂田明といった具合で、「軽い」感じはするが「軽薄」ではない。浅田がベットするのは、最後の最後で現実との和解を棄却するタイプの芸術だと見える。それはつまり、モダニズムということだ。他にも「軽薄さ」に対峙するところのメディアである広告を、糸井重里に随伴するかたちで読み解いていた浅田だったが、それは浅田が軽薄だったことにはならない。
『構造と力』を読んで、同時に当時の浅田受容がわかるテクスト群と向き合い、浅田彰という知識人はあまり幸福な出発をしなかった、と筆者は思うに至った。批判理論的な道具立て(伝統的な左翼系知識人らしさといったほうが適切だろうか)と、固有名詞を屈託なくバラバラに陳列するような消費社会的感受性の結婚は、周囲に許されなかった。今でも本当に許されているわけではないだろう。
2.
確かに『構造と力』はチャート式に現代思想を図解するコンセプトに依って立つものだった。だが最後まで読み通せば、第1章で縦横無尽に解体されつくしたたくさんの固有名詞の数々が、いかに優先順位をつけられ、これらによって何が批判されるかは、それほど読むのに難しくないと思う。筆者にとって興味深いのは、『構造と力』の軽くはあるが軽薄ではない、ともすれば硬派でシリアスな「批判」はうまく受け入れられなかった、という事態である。
さて、これ以降浅田は消費される知識人として歩みを進めることとなった、と見える。つまりそれは、景気動向にきめ細やかに随伴し、それをそのまま批評となす活動に入っていった、ということでもある。
その能力が最も如実に発揮されたのは、当時(86年)のお笑い界への言及においてである。タモリ、ビートたけし、明石家さんまのいわゆる「ビッグ3」を、木村敏の理論を援用し、それぞれポスト・フェストゥム、アンテ・フェストゥム、イントラ・フェストゥム、と分析する。この「フェストゥム」とは要は好景気のことであり、つまりは彼ら三人の芸の特徴をその当時の景気動向に結び付ける批評である。70年代半ばに登場したタモリは不景気とイデオロギーの不安定さを反映している、といったように。
この中でもイントラ・フェストゥム(祭りの最中)が当時の浅田にとって最も重要と見える。というのも実際に社会がイントラ・フェストゥムなのであり、そしてここにとんねるずが入ってくるのであるから。86年10月の『広告批評』での糸井重里との対談「いまの笑いについて笑いながらしゃべろうか」で、浅田は「僕は、とんねるず、割と好きだな」と言い、糸井はこれに「面白いよ、かなり」と同意している[9]。浅田は、批評対象へのコミットメントを通じて対談相手と意気投合する傾向があるように見える。しかしこれは、活動の場をアカデミズムの外部に求め、喋ることを批評活動のメインに据えたとき、普通のことだろう。
他にも、とんねるずの存在が重要である理由がある。というのも、とんねるずに、浅田は「関西的なもの」へのつながりを見るのである。
「とんねるずになると、じつはだんだん関西に近づいていくんじゃないか。知的に状況を裏返すとか、相手をアタックしてみせるとかいうことを放棄して、ズボーンとなっちゃうわけでしょう。ズボーンとなっていくことが、ある意味で関西的なものに近づいていくってことがあると思う。 要するに関西の笑いって、よくわかんないけど、本質は何もないってことでしょ(笑い)」[10]
浅田にとって関西的なものとは、積極的な評価を与えられる面としては「逃走」というアイデアのヴァリアントであり、悪く言えば特に見も蓋もない反知性主義、といった具合だろうか。そこには関西のお笑いをはじめとした文化や気性をつっぱねるような姿勢もうかがえるのが微妙なところではあるが、この関西的なもの(大阪)はさらに「最底人主義」と接続される。
「例の「地表人、地底人」でいえばさ[…]、地表人に対する地底人じゃなくて、もう最底人までおりちゃった人がボワッといるっていうのが大阪の強さみたいなところはある」[11]
「最底人主義」とは、いしいひさいちの漫画『地底人』に登場するキャラクター「最底人」に由来するのだが、これは浅田の批評のスタンスと共鳴するものだった。時期が前後してしまうが、1984年1月4日、朝日新聞の若者向けコーナーの誌面特集「君だって○○主義者」に、芸能人やアーティストの中に混じり、総勢18人(組)の中で、浅田は次のような文言を寄せているのだった。
「主流と反主流、抑圧する側とされる側、時流に乗って勝利する者と敗北することを純粋性のあかしとする者、こんな同位対立にはもうウンザリだ。いしいひさいち流に言えば、そういう地上人と地底人の対立を尻目(しりめ)にかけて、非主流の最底人主義でおのおの勝手に勝利しよう。ルサンチマンよ、さようなら。」[12]
最底人主義とはルサンチマンと決別するためのひとつの方法であった。そして、浅田の標榜する最底人主義にとって、85年という年は重大な契機となったことだろう。この年阪神タイガースは21年ぶりにセ・リーグ優勝並びに日本一を達成した。阪神ファンと言えばあの柄谷行人なのだが、この年に「最底人主義」は柄谷に次のように共有されている。「いや、地底人より下なんだ。地底人はマゾなんだ。最底人というのはマゾ以下だよ、人間じゃないんだから」[13]。柄谷はほとんど冗談半分に、最下位を経験し続けると、サルトルのいう「想像力の優位」をこえて(これは柄谷曰くただのルサンチマンである)、フロイトのいう「フモール」に到達し、心理的には独自に優勝し続ける、と言う(「阪神はもうセ・リーグでやってないわけよ。西宮早朝リーグでやり出したわけね(笑い)。そこでは常に優勝してる」[14])。だから本当に阪神が優勝してしまうとなると、最下位であることを肯定する、マゾを突き抜けたその独自のロジックが崩壊するから、困るのだという。この柄谷の半ばふざけたアイデアを、現実の争いや対立の埒外で独自に勝利するための所信表明として、すでに前年に浅田が「最底人主義」として提出しているのは、興味深い。
ここまで駆け足で80年代の浅田の仕事を追ってみたが、84-86年と、これから簡単に確認するが、87-89年とでは論調が異なる。84-86年に標榜していた「最底人主義」は鳴りを潜め、87-89年、つまりは柄谷とより積極的に表立って仕事をするようになってから、「外部志向」へと切り替わっていく。
「祭のあとの消費社会論」(1987年1月)を読むと、消費社会というものに対し浅田はかなり冷淡で、目下の広告に対し批判的に接している。この論考の興味深いところは、「むずかしい批評について」(1988年7月)で提示される、加藤典洋・竹田青嗣に対する批判「「批評」は、「なんとなく、わかるでしょ?」というムラ人同士の挨拶になり果てようとしている」[15]と似たような主張がすでに出てきていることである。
「やはりあまり閉ざされた場所で弛緩しないほうがいいんだろうとは思いますね。ここ十数年の消費社会・情報社会の動きを見ている限りでは、非常に閉ざされたところで芸をやっているにすぎないようなところがある」[16]
そしてもう一つ注目したいのは、とんねるずに対する評価で別のモティーフが付け加わっていることだ。
「とんねるずなんて疑似的にファシズムをやってる感じですね。一種のカリスマとして自分を演出し、未来も過去もないいまだけのノリを全員で共有してしまう」[17]
共同体内部の馴れ合いに対する嫌悪感と、時間的切断の意識とが、とりわけとんねるずという対象に負わせるようにして、この頃から浅田の仕事に表れてくるようになった。これが浅田の「外部志向」への根拠となっているようなのだが、そして88年には、とうとう柄谷―浅田、加藤―竹田の対立が浮き彫りになっていく。加藤、竹田、高橋源一郎の座談会「批評は今なぜ、むずかしいか」に対し、浅田が「むずかしい批評について」でその内容に疑問を呈し、それに対し加藤と竹田がそれぞれ論考で反論した(「「外部」幻想のこと」(88年8月)、「夢の外部――ポスト・モダンのために――」(88年11月))。それぞれが相手に浴びせた罵倒を踏まえるなら加藤―竹田は「共同体でムラ同士馴れ合う」派で、柄谷―浅田は「外来思想で眩惑する」派、といった見立てのもと両者は対立した。
「最底人」とは、最もラディカルには、柄谷がいうには「人間じゃない」、つまりは言語の埒外への志向でもあったのだが、加藤の立場の方にある「なんとなく、わかるでしょ?」というある種非言語的になってしまっているコミュニケーションは、この時点で批判の対象になっている。
3.
そして柄谷・浅田の「外部志向」は、あの有名な浅田の「土人の国」発言に終着する。
これは『文學界』1989年2月号の柄谷行人との対談の冒頭に出てきた発言である。
「実をいうと、ぼくは昭和について語りたいとはまったく思わない。昨年の九月このかた、連日ニュースで皇居前で土下座する連中を見せられて、自分はなんという「土人」の国にいるんだろうと思ってゾッとするばかりです。それでもあえて考えようとすると、柄谷さんが前に『海燕』に書かれた、ほとんど無根拠な”明治・昭和反復説”というのが気になって、それでまた客観的に考えられないわけ(笑)」[18]
この発言には、二つの相反する要素がある。一つは「ゾッとするばかり」という、ナイーブな羞恥心。「皇居前で土下座する」ことは、「ムラ人同士の挨拶」の最たるものである。もう一つは「明治・昭和反復説」を前にし(そもそもこの発言の元ネタは、『国体論及び純正社会主義』(明治39年(1906))で北一輝が憲法学者である穂積八束を批判する際に用いた「土人部落の酋長」という表現である)、歴史的反復という相のもとで考えようとする態度。「未来も過去もないいまだけのノリを全員で共有してしまう」対象に、改めてここで向き合おうとしている。
そう考えると、浅田の「土人の国」発言は、単に87年以降の「外部志向」の変奏のひとつとして捉えられるに過ぎないのだが、少し変わった目線から反応する者もいた。江藤淳である。以下、文芸評論家・富岡幸一郎によるインタビューの受け答えである。
「孫引きで言うんですが、まだ崩御の前だから、御平癒の記帳に来ている皇居前に集まっている人びとを見て、「土人の国みたいだ」と言ったという。この“土人の国”という表現はなかなか面白い表現ですね。そこに、明治以来の日本人の、日本に対して天皇に対するアンビヴァレンツが集約されていて、記帳に来た連中が“土人”なら、“土人”を恥じる感情というのも、これも明治以来のものです。明治以来ですよ。幕末じゃないですね。幕末はそうじゃない。」[19]
「なかなか面白い表現ですね」と江藤は反応した。江藤はこのあと、安政7年初の渡米で使節団が無礼な扱いを受けたときのことを例示する。誰が、誰に対し「土人」と思うかは、日本の近代史に歴史的に規定されているという、その過程を鑑み、上記のように指摘している。そしてこれは「日本の近代のいちばん根本的な問題」とまで言う。
「……だから、そのときには、“蛮人の国”に来たと、日本人のほうが思っているのですよ。“土人”は向こうだ、と思っているのです。それがなぜ、日本人が“土人”だということになったのか、主客転倒というか、これは日本の近代のいちばん根本的な問題です」[20]
対象と批評家との間にも「主客転倒」は起こりうるだろう。筆者はこの江藤の発言に『啓蒙の弁証法』にあるumgeschlagen ist (転化した)という表現を想起する。そして、「土人の国」発言に85年の再演を見出すに至った。最底人は土人になり、敵になった。かつて最底人として捉え、やがてネガティブな批判対象として描き出されるに至ったとんねるずのように、浅田もまた時間的な切断意識のまま、ナイーブな恥の意識が発言として批評に上った。のみならず、いや実は、他ならぬ浅田自身もまた、やはり最底人だったのだ。
それはまたこの「土人の国」発言について触れる、富岡幸一郎の発言を通じてもわかる。奇しくも、この受け答えでインタビュアーの富岡が発した「まさに日本の近代の問題がそこに出てくる。皇居前広場に集まっている人を“土人”であると言って、自分は“土人”ではないと思い込んでいる“土人”がいるわけで……(笑)」[21]が、まさに最底人同士が会話している、いしいひさいちの漫画のひとコマの描写にそっくりなのだ。

4.
『構造と力』以降にこれに匹敵するほどの重量感の理論的著作が出ることがない浅田は、数多くのシンポジウムや対談に出席することをはじめ、専ら己の身体の現前でもって批評活動をやっている、ように見える。そうして、次のような誠に稀有な帰結に至った、と思える。それはつまり、自身がそのままリトマス試験紙のように、くるくる色を変えて、生き方自体でもって、いや、自らが率先して何かを引き起こすというより、何事かが起こる磁場に居合わせてしまう。84-86年と87-89年の違いとして、批評的地盤の重心が糸井重里から柄谷行人へ、などと捉えてみたくもなる。結局のところこの事柄を掘り下げるには、浅田の仕事を吉本隆明との思想的距離という見地から捉えなくてはならないのだが、どう考えても紙幅が足りないので、またどこか別の機会にしたい。しかも、浅田の転化は、そのまま歴史的に規定された何らかの出来事として、歴史的価値として素描されてしまう。江藤淳は実際にそう捉えた。
しかしながら以上のことが批評家としてみたときの浅田彰の、特に「主客転倒」は、瑕疵ではなくまさに能力なのではないか。そしてまた、その仕事は、今日では乗り越えられないのではないか。批評とはある一面では、真に時代と寝る力だからである。
[1] 清水多吉「ニュー・アカデミズムの人びと」『第三文明』(282)第三文明社、1984年10月、60―66頁。
[2] 同書、61頁。
[3] 同書、64頁。
[4] 同書、66頁。
[5] 「イルカの本」編集部[編]『「浅田彰」――「知」のアイドルの研究読本』プレジデント社、1984年、115―116頁。
[6] 同書、5頁。
[7] 同書、6頁。
[8] 同箇所。
[9] 糸井重里・浅田彰「いまの笑いについて笑いながらしゃべろうか」『広告批評』(87)マドラ出版、1986年10月、53頁。のちに浅田は実際にとんねるずと対談している。「なにからなにまで正反対なんだ。」『広告批評』(92)マドラ出版、1987年、22―37頁。
[10] 浅田彰「絶対的マゾヒズムの一方的勝利」『Asahi journal』28(43)、朝日新聞社[編]、1986年10月24日、12頁。
[11] 同書、13頁。
[12] 浅田彰「君だって〇〇主義者」『朝日新聞』1984年1月4日。
[13] 柄谷行人・高橋源一郎・渡部直己「阪神優勝を「哲学」する――マゾを突き抜けた倒錯が「想像力の危機」に襲われる日」『Asahi journal』27(42)、朝日新聞社[編]、1985年10月、1891頁。
[14] 同書、88頁。柄谷の発言。
[15] 浅田彰「むずかしい批評について」『すばる』10(8)集英社、1988年7月、159頁。
[16] 浅田彰「祭のあとの消費社会論」『広告批評』(90)マドラ出版、1987年1月、45頁。
[17] 同書、41-42頁。
[18] 柄谷行人・浅田彰「昭和精神史を検証する」『文學界』43(2)文藝春秋、1989年2月、73頁。
[19] 江藤淳『離脱と回帰と:昭和文学の時空間』日本文芸社、1989年、45頁。
[20] 同書、46頁。
[21] 同箇所。
関連書籍
著者プロフィール
西村紗知(にしむら・さち)1990年生まれ、鳥取県出身。東京学芸大学教育学部芸術スポーツ文化課程音楽専攻(ピアノ)卒業。東京藝術大学大学院美術研究科芸術学専攻(美学)修了。「椎名林檎における母性の問題」により、2021すばるクリティーク賞を受賞。その他の論考に、「お笑いの批評的方法論あるいはニッポンの社長について」(『文學界』2022年1月号)、「林光《原爆小景》に寄せて」(批評誌『ラッキーストライク』第2号)など。現在、『文學界』にて「成熟と○○」を連載中。『愛のある批評(仮)』(筑摩書房)が今年秋頃刊行予定。
次回は6月7日(水)更新予定です。松田樹さんが柄谷行人を論じます。
*バナーデザイン 太田陽博(GACCOH)
