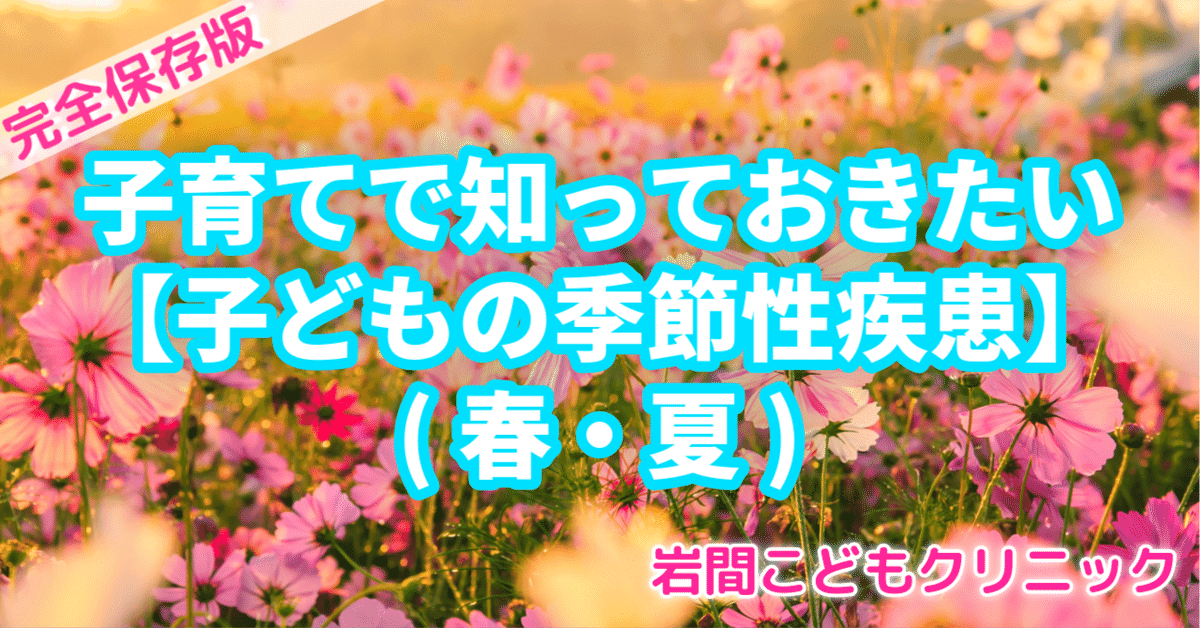
子育てで知っておきたい【子どもの季節性疾患(春・夏)】
こんにちは。
岩間こどもクリニック 院長の岩間義彦です。
今回、次回と【子どもの<季節性>疾患】にフォーカスしていきます。
患者さんからよく質問される内容をもとに、今回は春と夏に流行しやすい子どもの病気について特徴と注意点、その対処法について書いていきます。
※昨今の感染症は通年化している傾向にありますが、本記事では一般的にかかりやすいとされている時期を基準に記載しております。
【① 3歳の子どもの鼻水が止まりません。子どもでも花粉症になりますか?】
春先になると、花粉症を心配するママやパパといっしょに来院されるお子さんが増えます。結論からいうと、小さなお子さんも花粉症になります。
しかし、診断として確定するには条件があります。
お子さんの花粉症を心配するママやパパから質問をいただいたとき、花粉症と診断する条件として次の4つをお話ししています。
① 家族に花粉症と診断された人がいる(家族歴)
② <くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目の痒み>4つの症状すべてがある(花粉症の4症状)
③ 毎春、同じ時期に②の症状がでる(再現性)
④ 血液検査の結果、杉花粉などへの抗体が検出された(抗体)
ご質問のお子さんのケースでは症状が鼻水だけなので、これだけでは確定診断はできません。小児科を受診され、風邪や感染症の可能性も含めて診察してもらうことをおすすめします。
最初に花粉症を発症した春には③の再現性が満たされていないので、すぐに確定診断を受けるのは難しいと思います。
花粉症と診断された場合には、大人とほぼ同じ対策をすると効果があります。
・花粉が多い時は外出を控える
・花粉を室内に持ち込まない
・洗濯物の外干は避ける
・空気清浄機の使用
・部屋を加湿
・水分補給
・規則正しい生活・食生活をする

【② 春に気を付けるべき感染症はありますか?】
春はお子さん(赤ちゃん)が新しく集団生活を体験することの多い季節です。今まで家庭だけで生活していたお子さんが保育園や幼稚園、小学校などに入り、多くのお友達と生活するようになります。そうすると今までかかったことのない病気(感染症)にかかる機会も増えてきます。
よくある感染症の特徴と注意点、その対処法などを以下にまとめます。
また前述しておりますが、これらの感染症は通年化している傾向にあります。
溶連菌感染症
38度~39度の発熱と強い喉の痛み、舌に赤いブツブツができる(イチゴ舌)が特徴です。夏に流行することが多いアデノウイルスによる咽頭結膜熱、いわゆるプール熱と区別するのが難しいです。
溶連菌感染症の場合、心臓に障害を起こすリウマチ熱や、急性糸球体腎炎など重い合併症を起こす怖れがあるため、抗菌薬でしっかり治療する必要があります。
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
一般的な風邪による耳下腺(耳の下)の腫れと症状の似ている病気におたふくかぜがあります。おたふくかぜの場合は、腫れてから5日間は登園登校ができません。
登園登校するためには、医師の許可が必要となります。血液検査によって一般的な風邪とおたふくかぜを区別することが可能です。
おたふくかぜの合併症には、無菌性髄膜炎(100人に1人)や難聴(1000人に1人) があります。おたふくかぜによる難聴は、ほとんど治りません。お子さんの症状の経過には注意して見てあげてください。
感染予防と合併症予防のため、予防接種(任意接種)をお勧めします。1歳以上から接種が可能です。

【③ 夏に気を付けるべき感染症はありますか?】
<手足口病、ヘルパンギーナ、プール熱(咽頭結膜熱)>
この3つを指して「子どもの三大夏風邪」と呼ぶことがあります。
最近の感染症の流行を季節で区別をすることが難しくなってきています。これまでよりも季節性の特徴がなくなっています。
手足口病
手のひらや足の裏、足の甲、口の中の粘膜にできる水疱性の発疹が特徴で、1~3日程度発熱することもあります。
原因の主なウイルスはエンテロウイルスとコクサッキーウイルスですが、種類が多く何度もかかる可能性があります。まれに脳炎を伴って重症化することもあるので注意が必要です。
口の中にできた水疱がつぶれると口内炎をおこします。痛みのために、お子さんが食事や飲みものを受けつけなくなることがあります。
そんなときは脱水症状をおこさないように気をつけてあげてください。(水分の取らせ方のコツは後述します)
ヘルパンギーナ
ヘルパンギーナの特徴はのどの強い痛みと39度以上の熱が1~3日続くことです。感染すると発熱と同時にのどが赤く腫れ、小さな水疱ができます。
のどの強い痛みで、お子さんが食事や飲みものを受けつけなくなることがあります。手足口病と同じように脱水症状をおこす可能性がありますので、気をつけてあげてください。
原因のウイルスは主にコクサッキーウイルスA群と呼ばれます。これもウイルスの型がいくつかあるので、繰り返しかかってしまうことがあります。
症状は約5日程度でおさまります。
ただ、回復後も口(呼吸器)から1〜2週間、便から2〜4週間ウイルスが排出されます。おむつなどの交換の際には注意が必要です。
プール熱(咽頭結膜熱)
アデノウイルスがプールを介して感染することからブール熱と呼ばれます。発熱、のどの痛み(咽頭炎)、目の充血(結膜炎)の症状がある場合はプール熱と診断されます。登園登校するには、医師の許可が必要です。
子どもの三大夏風邪(手足口病、ヘルパンギーナ、プール熱)の中では、39℃前後の発熱が数日から1週間と長いのが特徴です。
そのため食事や飲みものを受けつけなくなる期間も長くなるので、十分なケアが必要です。

【④ 子どもが感染症になった時、水分補給や食事のケアはどうすればいいですか】
感染症を防ぐことは難しく、ウイルスによる感染症の場合は決定的な治療法がないことも少なくありません。感染症にかかってしまったお子さん(赤ちゃん)のケアは、安静と栄養価の高い食事、十分な水分補給が大切です。
なかでも一番大切なのは十分な水分補給です。
お子さんに脱水がなくて、高熱や下痢が続く場合でも、元気であれば大きな心配はありません。
とはいえ、体調が悪いお子さんはなかなか水分を摂取できないことがあります。そんな時は以下の方法を試してみてください。
・繰り返し飲ませてあげる
→お子さんが一度に水を飲めない場合は間隔を空けて飲ませてあげてください。5分~10分毎にひとさじずつというように、ゆっくり飲ませてあげます。
・温度をかえる
→常温では飲めなくても、冷たくする、生暖かくするなど、温度をかえるだけでお子さんが喜んで飲んでくれることがあります。(特にのどが腫れている場合は、冷たいと飲みやすくなります)
・器をかえてみる
→普通のコップでは嫌がるお子さんも、好みの色や模様のコップに移すだけでゴクゴク飲んでくれることがあります。小さなお子さんならマグマグなど器(入れ物)をかえてみるのもいいでしょう。
・味を変えてみる
→刺激の少ない果汁、牛乳、麦茶、冷たいスープなど、味を変えてみましょう。
・形状をかえる
→経口補水液を嫌がるお子さんには、ゼリー状やとろみの付いたものを飲んでくれることもあります。試してみてはいかがでしょうか。小さな氷をあたえることも有効です。
【⑤ 子どもが脱水状態になっていないか心配です】
脱水状態かどうかのサインは、いくつかあります。
元気がない、皮膚や口の中や舌が乾燥している。泣いても涙が出ていない。ぼんやりして、眠ることが多いなどです。
そして、お子さんがいつもと同じようにオシッコをしているかどうかを確認してください。
回数や量、尿の色を確認して普段とかわりなければ、水分はうまくとれていると考えていいです。
赤ちゃんならオムツで確認できます。
尿の回数や量が減ったり、色が濃くなったりしていれば、水分がうまくとれていないので、先に紹介したようにいろいろと工夫して飲ませてあげるようにしてください。
今回の記事は以上です。
いつもご覧になっていただき、ありがとうございます。
育児に向き合うママ・パパの参考になりましたら幸いです。
岩間こどもクリニック
院長 岩間 義彦
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
©Iwama-Clinic
※note内では個別のご相談・ご質問に対応することが出来かねます。何卒ご了承ください
