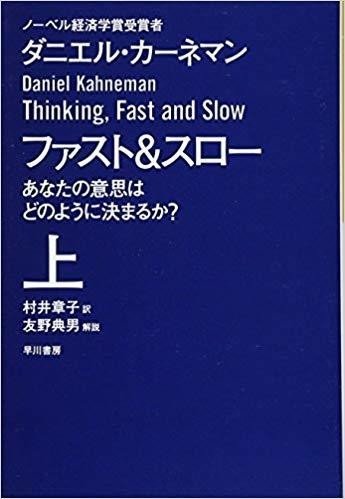ダニエル・カーネマン『ファスト&スロー(上) あなたの意思はどのように決まるか?』序章〜第5章
人間の直感は統計をうまく扱えるか?
ほとんど扱えない。なぜなら、人間の判断には〈バイアス〉がかかるから。思い出しやすさや入手しやすさなどの〈利用可能性ヒューリスティック〉を使ったり、難しい問題を類似した易しい問題に置き換える〈単純化ヒューリスティック〉を使うことで、解決への近道を見出そうとする。すると、統計とまったく違う答えにたどり着いてしまう。
人間は合理的で論理的である、とされていたが、そこに疑いが投げかけられた。
たとえば、メディアに取り上げられた情報は容易に記憶から呼び出すことができるが、そうした呼び出しやすい問題を、相対的に重大な問題と評価する傾向が人間にはある。メディアが扱う情報はたいてい「一般市民が興味を持っているだろうとメディアが判断した事柄」であり、ドラマ性に乏しい事柄は報道されない。そして人間は利用可能性の低い事柄はそもそも頭に思い浮かばない。
*
1982年、エイモス・トヴェルスキーとダニエル・カーネマンがサイエンス誌に発表した〈ヒューリスティクス〉と〈バイアス〉という概念は、医療診断、司法判断、情報解析、哲学、金融、統計、軍事戦略など多様な分野で活用されるに至っている。
この本では、認知心理学と社会心理学を踏まえて、脳の働きがどのように捉えられているかが紹介される。とくに直感的思考の驚嘆すべき点と、その欠陥について。また心理学の実験によって得られた判断と意思決定の知識に関して。
* * *
第1章「登場するキャラクター ―― システム1(速い思考)とシステム2(遅い思考)」
脳のなかには、システム1(速い思考)とシステム2(遅い思考)がある。これら二つのシステムは相互作用している。衝動的で直感的なシステム1はコントロールが効かず自動的に働き、論理思考能力を備えていて注意深いシステム2はよく怠けるので通常ごくわずかな働きしかしていない。
たとえば判断に問題がないとされるときには、システム1の印象や直感がそのままシステム2に受け入れられ、根拠のない確信に変わる。一方でシステム1では答えを出せないような問題に出会うと、ようやくシステム2が動員して注意力を発揮する。
こうして二つのシステムが仕事を分けることで、努力を最小化して成果を最適化する動きが脳にはある。慣れ親しんだ状況についてのシステム1の判断は正確で、目先の予測もおおむね正しい。しかしシステム1にはバイアスがかかる上、スイッチオフできないので、しばしば判断を間違う。そのため直感的思考のエラーを避けることは難しい。
緊急時にはシステム1が作動して、自分の身を守る行動を最優先させる。何が起きたか認識する前に、自動的に反応する。一方、深刻な脅威や有望なチャンスに注意力をもてば生き延びる可能性が高まる。長い進化の歴史を通じて、システム2は発展した。
人間は自分の考えを持って自ら選択し、何をどう考えて行動するかを決めていると思っている。そうした意識的で、論理的なシステム2が自分自身だと考えている。しかし実際のところシステム2は、バイアスのかかった誤りやすいシステム1の直感をそのまま自分の判断としていることが多いことがわかっている。
* * *
第2章「注意と努力 ―― 衝動的で直感的なシステム1」
肉体的な労力に限らず、脳の認知能力においても「最小努力の法則」は当てはまる。つまり、ある目標を達成するのに複数の方法があるときに、人間はもっとも少ない努力で済む方法を選ぶ。自動的なシステム1が作動することで、システム2の注意力を使わずに済むのであればそうする。システム1が苦手とすることは統計的な情報の扱いである。
システム2にできることは、ルールに従う、評価対象をいくつもの面から比較する、複数の選択肢のなかから熟慮の末に選ぶ、など。決定的なのは、〈タスク設定〉ができるということだ。慣れていない作業に対して、うまくこなせるよう注意力をセットし、実行するという努力をするプロセスをつくる。脳の中でも前頭前野の領域が機能を有し、他の霊長類に比べてヒトでよく発達した領域だということも特徴である。
あるタスクを習熟していくと、必要とするエネルギーは減っていく。何らかの行動に伴う脳の活動パターンは、スキルの向上とともに変化し、活性化される脳の領域が減っていく。才能も同じく、頭のいい人は同じ問題を解くのに通常の人ほど努力しないで解ける。瞳孔測定や脳の活動からこのことは実証されている。しかし努力はコストであり、スキルを習得するにもその利益とコストが天秤にかけられてから行われる。
* * *
第3章「怠け者のコントローラー ―― 論理思考能力を備えたシステム2」
人間はときに長時間にわたって、意志の力を発動することなく、すさまじい努力を苦もなく続けられることがある。これを〈フロー〉という。努力しなくてもタスクへの集中が続き、また注意力の集中を維持するのにセルフコントロールを必要としない。
こうした認知的努力とセルフコントロールは、知的作業の一形態として知られる。多くの心理学研究が、困難な認知的作業と誘惑が同時に直面してきたときに、誘惑に負ける可能性が高いことを示唆している。知的作業を行うシステム2が忙殺されていると、システム1が行動に大きな影響力を持つようになる。
たとえば認知的に忙しい状態では、利己的な選択をしやすく、挑発的な言葉遣いをしやすく、社会的な状況について表面的な判断をしやすい。
また今やっていることがうまくいくだろうかと心配すると、余計な心配によって短期記憶に負荷がかかるので、実際に出来が悪くなることがある。
システム2を使った強い意志やセルフコントロールの努力を続けると疲れる。これを〈自我消耗 ego depletion〉という。感情的な反応を抑えるように指示した上で、被験者に感動的な映画を見せると、その後握力計を握り続けるテストで成績が悪くなった。感情を抑える努力をしたため、筋収縮を保つ苦痛に耐える力が減ったのだ。
強力なインセンティブが与えられることで、自我消耗の影響にいくらか抵抗できる。また自我消耗の影響はブドウ糖の摂取で解消できる。神経系は身体の中でもっともブドウ糖を消費するから、ブドウ糖のレベルを補うことで脳の機能が回復する。
*
システム2の主な機能の一つは、システム1が提案した考えや行動を監視し、制御すること。そしてその提案の一部を許可し、また残りを却下したり修正を施したりする。入念なチェックと探索をどこまで行うかはシステム2次第で、人によってばらつきがある。
注意力をコントロールする能力は遺伝子が影響するほか、しつけも影響する。そしてこの能力は非言語知能テストの成績や、自分の感情をコントロールする能力とも密接に関連している。
* * *
第4章「連想マシン ―― 私たちを誘導するプライム(先行刺激)」
言葉が記憶を呼び覚まし、記憶は感情を掻き立て、感情は顔の表情や他の反応(緊張や回避行動)を促す。そしてそうした反応が感情をさらに強め、感情に即した考えをさらに強めることになる。こうしたことはごく短時間に同時に起き、認知的・感情的・肉体的反応の自己増殖パターンを生み出す。このプロセスを〈連想活性化〉という。
ヒュームによると、連想の原則は三つある。類似、時間と場所の近接性、因果律。
心理学的には、観念は広大なネットワークである〈連想記憶〉のなかに浮かび、ノード(節点)となって、他の多くの観念とリンクしていると考えられている。そのリンクにはさまざまなタイプがあり、たとえば原因と結果(ウイルスと風邪)、ものと属性(ライムとグリーン)、ものとカテゴリー(果物とカテゴリー)など。
一つの観念が活性化されると、ほかの多くの観念が活性化され、またさらに別の観念を活性化するというようにつながっていく。意識に上がってくるのは、そのうちのごくわずかで、〈連想思考〉の大半は意識的な自己からは隠されている。自分で自分の思考のすべてにアクセスできるわけではない。
「あなたは、自分で思っているよりずっと少ししか、自分について知らない」
*
ある単語に接すると、その関連語が想起されやすくなるという変化が認められた。これを〈プライミング効果 priming effect〉という。連想活性化が広がっていき、プライムで想起された観念が選択される。概念や言葉に限らず、自分で意識してもいなかった出来事がプライムとなり、行動や感情に影響を与えることもある。この現象はシステム1の中で起きるので、意識的にアクセスすることはできない。
連想ネットワークでは双方向の関係を導くことがある。楽しいと笑顔になり、笑顔になれば楽しくなる。鉛筆を横向きにして笑顔に近い表情で漫画を読むのと、鉛筆を縦向きにしてしかめ面に近い表情で同じ漫画を読むのとでは、面白さの度合いが笑顔に近い表情で読んだ被験者の方が高くなった。ありふれた身体的な動作や変化が、意識とは無関係に感情や判断に結びつけられた例である。
〈プライミング効果〉によって、自分の判断や選択を行っているのは自立した意識的な自分だという、私たちの自己像は覆されていった。
* * *
第5章「認知容易性 ―― 慣れ親しんだものが好き」
人間は意識のあるなしに関わらず、脳の中でたくさんの情報処理を同時に行っており、いくつもの重要な質問に対する答えを常時アップデートしている。何に注意を向けるべきか、危険な兆候はないか、など。
慣れ親しんだもののなかで認知が容易なときには、あまり深く考えようとはしない。直感が信用されており、自信を持っている。
一方認知負担を感じているときには、慎重で疑い深い状態となっており、ふだんより努力を払い、エラーを犯しづらい。直感に頼ることはあまりなく、創造性も発揮しない。
見覚え、聞き覚えがあるという感覚や、前に見た単語をまた見るとき、認知が容易になる。このような〈過去性〉という性質は錯覚である。
認知が容易で聞き慣れたことは、真実と混同されやすい。システム1がそうした印象を形成し、システム2は熟慮せずに判断してしまう。情報源を思い出せず、手元の情報と関連づけられなくとも、認知しやすさが手がかりとされてしまう。
読み手に真実だと思われやすくするためには、原則として認知負担をできるだけ減らせばよい。発音しやすい言葉、反復なども認知のしやすさに通じる。難しい言い回しをすると、読み手が疑い深く慎重になる。真剣で分析的に読まれる必要があるときには、認知負担をかければシステム2が駆り出されてくる。
*
単純接触効果は、まったく意識せずにみているときにより強い刺激として受ける。なじみのあるものへの経験には依存しない効果。たとえば単語や写真が反復され、それを受け手が気づかなかったとしても、いちばん頻繁に見せられた単語や写真が好きになる。
生命体は新たに出現した刺激に慎重に反応するものだが、反復して接触しても悪いことが起きなかったために単純接触効果が起きて、ポジティブな感情を持つのではないかと説明されている。なじみがあるかどうかで、生命体は安全性を区別している。単純接触効果は社会的組織や集団の基礎を形成し、心理的・社会的安定性の基盤となる。
*
気分は直感の正確性に大きな影響を及ぼす。システム1の働きを左右する。不機嫌だったり不幸だと、直感は不正確になる。機嫌がいいと直感が冴え、創造性が発揮される一方で、警戒心が薄れて論理的なエラーは犯しやすくなる。上機嫌、直感、創造性、騙されやすさなどは同じシステム1への依存を示している。
* * *
第6章〜につづく
* * *
ダニエル・カーネマン『ファスト&スロー(上) あなたの意思はどのように決まるか?』村井章子訳、ハヤカワ・ノンフィクション文庫、2014年
序章〜第5章