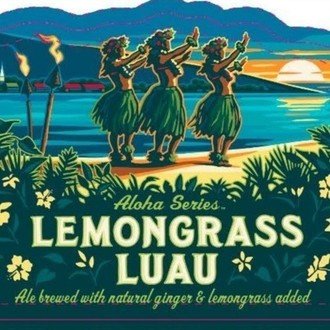掌編小説 『十年後の未来予想図』
次に書く小説のために、デスクに積み上げた資料の整理をしていると、スーツケースから無造作に取り出した資料の束から一冊のノートがはみ出しているのが見えた。
雑誌の切り抜きなどをコラージュしたノートの表紙を見ただけで、それがいつ頃使っていたものかはおおよそ見当がつく。
そのノートは東京で二度目のオリンピックが開かれた年に使い始めたものだった。
「五年後、十年後の理想」という内容に沿って短い文章を書く。
それは十年前に人気のあった「note」という文章創作のプラットホームで知り合った人がが企画したお題だった。
十年後にもまだ自分が生きているのかどうか半ば疑いつつ、僕は短い小説を書いた。
普段は言霊など信じもしなかったというのに、その時は何かに突き動かされるように一気に書き上げたのだった。
「俺に三年間、何の不安もなく、ひたすら創作に打ち込める自由が与えられたら、翌年の芥川賞の表彰式には俺が立っている」
これは僕の学生の頃の口癖だ。
周りが呆れるほど頻繁に口にしていたのは妄想でも過信でもなく、僕にとっては季節が巡るようにやがて当たり前にやってくる、予定された未来でしかなかった。
予定された未来とは、言うまでもなく小説家になることだ。それ以外のことはすべて通過点に過ぎない。努力目標ですらない。水が高いところから低いところへしか流れないように、否応なく僕は小説家というポジションへ辿り着いてしまう。
そしてその未来にたどり着いたのは、『十年後の未来予想図』を書いた翌年のことだった。
僕は還暦まで二年を残して「小説家」になった。
それからは日常のすべてが小説を書くことに繋がって行った。
小説家になった当初にあった半世紀近くの寄り道を取り返そうと焦る気持ちは、作品を書き上げていくに従って薄れていった。
愉快な思い出も、今はもう会う機会も減った仲間たちも、胃がねじれるようなトラブルも、今、思い出しても怒りしか湧かない幾人かの人間たちも、すべてが小説に投影される何かになっている。何一つ無駄になっていることはないと気づいたのだった。
僕は小説家と呼ばれる以前から小説家だったのだ。
執筆場所として使っている部屋の窓の外には、パームツリー越しにビーチが見える。
オアフに住む友人のパトリシアから紹介されて、ラハイナの外れのコンドミニアムを格安で手に入れたのは三年前のことだ。
高校の同級生だった写真家と共著で作ったクロスオーバー作品がベストセラーになり、まとまって入った印税で僕はハワイにも仕事場を手に入れたのだった。
パトリシアはかつてメリー・モナークで入賞したこともある優れたフラの踊り手だったが、今はフラを教える傍ら、不動産斡旋の仕事や個人旅行客向けのカスタムメイドのツアー企画などを手がけている。
彼女が見つけてくれたコンドミニアムは僕の要望をすべて満たす、文句のつけようのない物件だった。
以来、毎年九月の初めから十二月の半ばまで、ラハイナのコンドミニアムに滞在して小説を書く生活をしている。
夏が過ぎて観光シーズンが一段落したところで日本からやってきて、クリスマスから年末年始の騒がしいシーズンが始まる前に日本に戻る。
年の瀬から冬の間は古い友人の持つ湘南のアパートの一部屋を借りて過ごし、春から秋にかけては東北のこじんまりとした一軒家で暮らす。それが僕の一年間のサイクルになった。
「わざわざラハイナなんて不便なところに買わなくたって、カフルイだって似たような値段のコンドミニアムはあるのに」
パトリシアは自分で紹介していながら心配そうに言ったが、僕は二十年も前に一度だけ訪れたラハイナの町が気に入っていた。
「不便に感じたらいつでも言ってね。小説を書くだけなら、そこを売って買える物件はオアフにも必ずあるから」
今でも会うたびにパトリシアは最初と同じことを言う。だが小説を書くことが毎日の中心にある僕にとっては、ベッドルームが二つあるコンドミニアムでもワンルームでも大きな差はなかった。
小説家の便利なところは、世界のどこにいても仕事ができることだ。
インターネットの普及と共に、その便利さは拡大していったが、決定打になったのは十年前の感染症のパンデミックだった。
コロナウイルスの影響で世界は隔絶され、対面での接触は激減した。
副産物のように普及したオンラインのミーティングのおかげで、小説家はより一層、場所を選ばなくなった。
ある人は静かな環境を探して山間の古民家に移り住み、ある人は街の至るところを書斎がわりに小説を書くようになった。
そして僕は一年の間を季節風のように移り住みながら小説を書いている。
定住から半歩はみ出したおかげで、文体も作風も変化した。
それまでも湿度の高い日本文学の文脈に腰をおろしたような小説に近寄る気は無かったが、季節風生活をするようになってから、僕は吹き抜ける乾いた風のような心地良い小説が書けるようになった。
おかげで新刊を必ず読んでくれる読者も増えて、最近では「ロードムービー小説」と、よくわからないキャッチコピーで呼ばれるようになっている。
最近では映像作家から映像化の許諾依頼や、原作の執筆依頼をたくさんいただく。だがいろんな人から映像的な小説だと言われても、僕の書いたものが映像化に馴染むとは思えない。
後輩が作った数作の短編アニメーションを除いては、すべてお断りしている。
自分で企画を立てたインターネットラジオの番組はいまもウィークデーの夜の帯番組として続いている。
映像化には向いていない代わりに、音楽を織り込んだ朗読劇にはちょうど良いと考えたのだった。
声優だけではなく、朗読を希望する俳優の方もいくらかいてくれるそうで、しばらくは朗読劇に合わせた小説の執筆も続くことになる。
『十年後の未来予想図』を書いてから、僕の人生はかつて予想した通りの道筋を辿っている。
軌道修正も方向転換もなく、微かな疑問も迷いもないまま、半世紀前に夢中になって読んだあの人の作品の背中を追って今日までやってきた。それはこれからも変わりがない。
途中で踏みしめた轍もない雑草の茂っただけの土手も、きれいに舗装された道も、すべてがいまへ続く道の途中だったのだ。
来週には東京から件の写真家夫妻がやってくる。
毎年定例のハワイでのバカンスだ。
ベッドルームの掃除は明日中に済ませて、週末はカフルイのショッピングモールまで買い出しに行かなければ。
ついでにファーマーズ・マーケットで来週分の食料も仕入れてこよう。
だがまずは執筆だ。
その前にデスクの上をしっかり片付けなければ。
この掌編小説は、作中にもちらっと出てきたお知り合いの”紅茶と蜂蜜さん”が企画された「五年後、十年後の理想』に参加させていただくに当たって作ったものです。
十年後の未来予想図を想像するのは、実に楽しいことでした。
いいなと思ったら応援しよう!