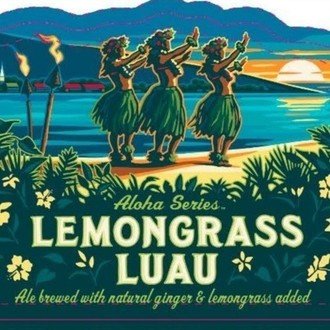読書記録『東京會舘とわたし(上下)』辻村深月
今年もまた結構な量の小説を読んでいるけれど、今日読んだ辻村深月の『東京會舘とわたし』は、今年、新たに読んだ小説の中では、現時点でのトップである。
世の中には一つの場所を舞台にした作品が結構ある。
ブックス・アンド・カンパニーを舞台にしたリン・ティルマンの『ブックストア』や、アリーゴ・チプリアーニの『ハリーズ・バー』はいまでも僕の愛読書だ。
良い場所には良い物語がある。
でもその物語が小説であることは少なくて、一つの場所を舞台にした作品は、小説ではなくノンフィクションやドキュメンタリーであることが多い。
本作も丸の内の東京會舘を舞台に、長い歴史の中で語りつがれてきたエピソードが下敷きになっているが、エピソードを元にフィクションとして再構成しているところが新鮮だ。
広義の歴史小説と言えるかもしれないし、事実とフィクションの汽水域と言えるかもしれない。
すべての小説は人間を物語ることで出来上がっているわけだから、舞台がどこであれ、どの時代であれ、構造は一緒だ。
人がいて、物語が始まり、人によって物語が締めくくられる。
でも一つの場を舞台にすると、世界が狭くなる分、濃度は濃くなっていく。
人間は複雑に交差し、交差することでまた新しい物語を紡いで行く。
その場所に惹かれて集まってくる人間たちが、その場所がどういったところであるのかを表すようになる。
辻村深月は東京會舘を舞台に選んだ。
だがハリーズ・バーやブックス・アンド・カンパニーに物語があったように、東京タワーでも、旧日劇でも、日比谷スカラ座でも同じような物語がきっとある。
商店街の片隅で細々と続いている碁会所や、地元で長く続いている中華屋にだって、未だ語られていない物語はあるはずだ。
『東京會舘とわたし』では上下巻を通じ、エピソードが互いの間を行き来して物語は進んでいく。
営業最終日のことを描いた最後の章の一つ前では、直木賞の発表のエピソードが語られる。
時は2012年。上期に辻村深月が『鍵のない夢を見る』で直木賞を受賞した年だ。
物語はフィクションだろうが、描写は辻村深月自身が発表や授賞式での経験を元に描かれているだろうし、登場する支配人の渡邊は、現東京會舘の社長の渡辺訓章氏がモデル、あるいは実在の人物として描かれている。
この辺の力量はさすがというほかない(そして大正から戦時中、戦後の占領期、行動経済成長の始まり、昭和を彩った出来事、東日本大震災と、エピソードを孤立させずに繋ぐ筆力、構想力は見事)。
東京會舘の脇など、これまで数え切れないほど通っているのに、東京に生まれて半世紀以上経っても、また一度も足を踏み入れたことがない。
小説を読むだけでも、東京會舘のホスピタリティと積み重ねられた歴史に支えられた誇りは容易に想像できる。
一度くらいメインダイニングのプルニエで舌平目のポンファムを食べないと、物見高い江戸っ子の名が廃るよなあと思ったのだった。
いやー、こういう正しく良い小説を読むと、気持ちが洗われる感じがしますね。もしかしたら小説そのものではなく、東京會舘に洗われたのかもしれないですが。
いいなと思ったら応援しよう!