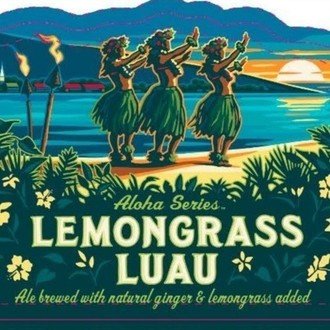ふりだしに戻る
何をやってもどうにも気が乗らない日がある。
何をしてもうまくいかない日もあれば、何もする気が起きないというのに次から次へとやらねばならないことに追い立てられる日もある。
毎日のパターンのサンプル帳があるとしたら、きっと今日は「気が乗らない日」のページに載っているサンプルそのままのような1日だった。
小説の続きを読もうと本を開けば、頭の中に短編小説くらいにはなりそうなエピソードが浮かび、食事を作ろうとキッチンに立って包丁を握ったと思ったら、今度は洗濯をしたまま干し忘れていることに気がつく。何かを始めると別の何かが邪魔をする。まるで日々の営みのミニチュアモデルか、コミカルなジオラマみたいなことの繰り返しで、何一つ先に進まない。
私は「今日やるべきこと」を書き出した箇条書きの上から6番目までをすべて諦めて、読みかけの小説を持って近所の古い喫茶店に出かけることにした。
コロナウイルスの流行が落ち着く気配もないというのに、商店街はウイルスが出現する以前と変わらない混雑だった。リモートワークとやらでオフィスに出かけもせずに、自宅で仕事をする人間が増えたせいなのかもしれない。
奴隷船のような満員電車に揺られることもなく、それでも仕事ができるならば、コロナウイルスは人生の大きな無駄を省き、世の中に変革をもたらした功労者なのかもしれない。だが商店街の人混みは、どこかオフィス街の混雑を他に移しただけのようにも見える。主婦連中は商店街のまん真ん中で立ち止まり、マスク越しに大きな声でワイドショーの受け売りの話を卓球のラリー並みの早さで繰り返している。
チェーンのコーヒーショップは自宅を追い出されたのか、あまりの居心地の悪さに自宅より見えないウイルスが蠢いているかもしれないコーヒーショップを選んだリモートワーカーたちでいっぱいだった。
感染の拡大を抑えたいのか、さらに広げたいのか、あるいはどちらも頭にないままの「やってますよ」というポーズなのか。私にはどれも正解のように思えた。
躍らせる側と踊らされる側の両方から逃れるように、私は古めかしい喫茶店のドアを開いた。外から見るよりはずっと広い店の中には客が二人だけいた。
一人は窓際の隅に、もう一人は一番奥まった4人がけのボックスに座って、どちらも顔を隠すように新聞を広げて読んでいる。キャッチャーがサードとファーストに指示を送るにしても90度で済むというのに、私が二人を見るには、左から右まで130度ほど首を回さなければならなかった。
ここはコロナの前も後も変わらない。
いつだって客は限界近くまでまばらだ
私はカウンターの右から2番目のスツールに座った。
カウンターの奥には薄いビニールのシートが吊るされている。5つあるカウンターの席に合わせて、左右にもアクリルの板が立てられていた。
透明なだけで、これじゃ遮眼帯かブロイラーの仕切りのようだな、と私は思った。
「出歩いて大丈夫なんですか?」
店主が注文より先に私に尋ねた。店主は私の心臓のことを知っている。
真剣に心配しているのではなく、自動的に口を突いて出る定型句のような抑揚のなさを微かに感じた。個人でささやかに経営している喫茶店なのだ。他人の心配よりも自分の店の先行きの方が心配だろう。当然のことだ。
「うん。ここなら大丈夫だろうと思ってね」と微かに皮肉を込めて返事をすると、店主は意味をしっかり受け取ったようだった。
「今日はどうにも気が乗らなくて、ここでまともなコーヒーでも飲めば、気分も変わるかと思って出てきたんだよ」
「ウチのコーヒーじゃ気分転換どころか、身体の調子まで悪くなるんじゃないですか?」
店主は唇の端にほんのわずかにシニカルな笑みを浮かべたのがわかった。私は暗闘をするために喫茶店まできたのではない。1勝1敗のところで勝負を引き取り、持ってきた小説を開いた。
「それにしてもコロナも困ったもんですねえ」
「商店街の影響も大きいんだろうね」
「こうしてビニール垂らしたり、アクリル板で仕切ったり、手間ばっかりかかって困ったもんですよ。店から感染者なんか出したら、商店街の連中から袋叩きになりますから、仕方ないですがね」
「さすがに私も気が滅入るよ。何をしようとしても全然先に進みやしない。サイコロ振って1の目が出て、ひとマス進んだら「ふりだしに戻る」って書かれてるみたいな感じでさ。しかも振るたびに1が出やがる」
「1の目が出るだけいいじゃないですか。うちなんてこの1年、振っても振ってもゼロの目しか出ないんですから。ふりだしに戻るどころか、振り出しから一歩も動きやしない」
「とはいえ、今は何もしようがないだろう? しばらくは私もアンタも堪えて踏ん張るしかないんだろうね」
私は気のない返事をしながら、ゼロの目のあるサイコロを想像して、何も彫られてない面を「ゼロの目がある」と言うのだろうかと考えていた。
---------------------------
ただ日記を書いてもつまらないので、小説を書く文体を使って書いた。
遊びのようなものだし、錆びつかないようにエンジンを回したままにしておくようなものだ。わざわざこんな書き方をしたことにさほどの意味はない。
読み直しも書き直しもしないままの書いて出しだから、あとで読んだらひどいシロモノにちがいない。
いいなと思ったら応援しよう!