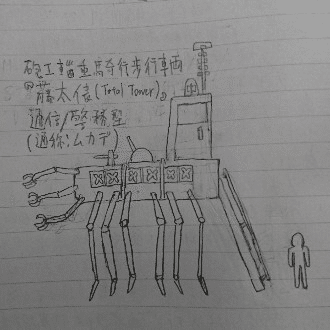随筆(2020/1/7):即物的な「見る」誠実の徳の人が、対人的な「伝える」誠実の徳をやることは、簡単ではない
(思いついたので忘れないうちに書き留める系の記事です)
自分を誠実だと思っている、少なくとも物事には誠実な人が、しょっちゅう陥りがちな罠として、
「自分の見た真実を、そのまま伝えれば、相手は聞いて、信じてくれる」
というのがあります。
***
そんなことあるわけねーだろ。
「本当である」ということと「信じられる」ということの間には非常に入り組んだ微妙な関係があるんです。
そこの仕組みに「不誠実」だったら、「信じられる」「真実」を「伝える」ことは、基本的に当たり外れの大きいバクチになる。
***
見て、やってみて、真実だと思ったことは、割と高い確率で真実だ。そこはもちろんいいでしょう。
だが、人が伝えたものが真実だと思うには、明らかにこれにプラスアルファの条件が要るでしょう。
要するに、「この人の言ってることは真実か」と同じくらい、「この人は信頼に値するか」ということが大事になってきます。
***
「何で?」
いや、そりゃそうでしょう。むしろ当たり前だと言えます。
「この人は真実を捻じ曲げて語ってはいないか」ということを疑わなければならない時点で、「伝える」という土俵で、真実がそのまま流通されると思いますか?
目の前の人が謎の人であり、理解を拒むオーラを放っている。理解を拒むということは、自分が理解している情報を相手に理解させていない、ということです。
そして、そんな人は「情報量の差で利益を得る、公正取引を壊す、レモン市場(アメリカにおける中古車市場のこと。転じて、情報格差を悪用して不良品を売りさばこうとする市場)の売り手」と、実際には区別がつかない。
相手は中古車を買いに来ているんじゃない。人の話を聞いているんだ。それで、「情報格差を悪用して不良情報を吹き込もうとしている語り手」なんか、真実を語っているようには到底思えないでしょう。そんな話は信用に値しない。
しかも自分がそう思われているんだ。「自分がどう思われているか」は気にしなくても、「自分の話が真実と思われていない」ことは、誠実の徳という観点からは、本当にマズイ。最悪やんけ。
***
という訳で、誠実の徳の人が、自分のやっていることを誠実に振り返った時に、それが即物的な「見る」誠実の徳なのか、対人的な「伝える」誠実の徳なのか、よく見極める必要があります。
前者は必要だ。そりゃあもちろんそうだ。だが、対人的にやっていくなら、後者をやっていて初めて意味がある。前者では到底足りない。
ということで、「「見る」誠実の徳の人が、「伝える」誠実の徳も出来るようになるには、どうするか」という課題が立ち上がってくる。
そういうロードマップを描くことを、ここしばらく試みてみようと思います。
いいなと思ったら応援しよう!