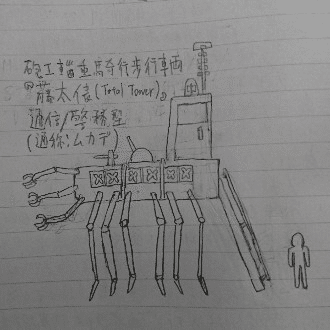日記(2020/3/2):よくばり宮保腰果鶏丁
(注:この料理を作ったり、記事を書いていたのは、3/1(日)昼飯時です)
体が疲労の極みで動かないので、白酒で手足の毛細血管を拡げ(何パーセントか破裂してやしまいか)、腰にタオルを挟んで十分間お湯をシャワーで当てたり、何とか動けるようになりました。大変だった…
ご存じの方はご存じでしょうが、石川県はたった今、新型コロナウイルス感染症の感染地域になってしまっているため、私も休日出勤があり得たのです。
ということで、何とか動けるようにしなければならなかったし、動けるようになってからは待機中だったんですよ。いつ何時でも電車で急行できるようでなければならん。
(そういう意味では、白酒は車出勤を不可能にするので、選択肢としては愚かだったのだが)
***
そんなわけで、昼、ありもので、体が動く、スタミナのつく、温かくて、美味しい、何らかの有り難みのあるものが食いたくなったんです。
で…

ありものから、何かが浮かび上がってきました。
・鶏胸肉がある
・ピーナッツがある
・カシューナッツ(の入ったミックスナッツ)がある
ここから、清の文武両道の四川総督・丁宝楨(丁宮保)が考案して宴会で振る舞ったと言われる、鶏肉とピーナッツの唐辛子炒め『宮保鶏丁』と、そのバリエーションである鶏肉とカシューナッツの唐辛子炒め『腰果鶏丁』が作れそうだ、ということが分かってきます(非存在空中ろくろを回しながら)
ナッツ系のカリカリした歯触りが嬉しいやつですが、他にもいろいろ食材があり、魔が語りかけて来ました。
「確かに宮保鶏丁や腰果鶏丁には、ネギとかピーマンとかパプリカとかが入っていることがあり、シャキシャキした歯触りが嬉しい。
で、ここにマイタケやタケノコやレンコンやヤマイモがあるじゃろ?
サクサク感にバリエーションがつけられるのではないか?
あとアスパラガスもどうだろうか。あれも独特のうま味が強い野菜だし、若いやつはサクサクしているからね」
こういう魔のささやき、たいていはそのまま取りつかれてやっていくと、地獄みたいな闇料理になっちゃうのですよね。
が、その時の俺の脳は『鉄鍋のジャン』の中国人観光客たちのように「脆! (ツォエイ。サクサクしてもろいの意)」という状態になっていたので、ついカッとなって…面白半分で…遊ぶ金欲しさに…料理、作ってしまいました。名付けて、「よくばり宮保腰果鶏丁」! (食費を節約して浮かせて遊興費に回すの、少なくとも体には良くないですよ。精神が荒むよ)(自炊出来るのは良い事です)
***
調理風景です。
野菜です。シャキシャキ感が最大限に活きるように、いろいろと「こんなもんでは?」というサイズに賽の目に切りました。(自分のためのメモだが、レンコンはもう少し大きい方が歯応えがあるよ)

鶏肉を、調味料と片栗粉を水に溶かした合わせ調味料、碗献(下の写真のウサギ型小皿にあらかじめ入れてあった。先に作っておくと、俺みたいな調理初心者にはものすごーく楽なんですね。それと、片栗粉はほっとくとすぐに固まるので時々かき混ぜる)に十分間漬け込み、時々満遍なく肉をコーティング出来ているようにすべく、手で混ぜます。(料理の前は手を念入りに洗いましょう。今はCOVID-19が流行っているので、皆様だいたいやっていらっしゃると思いますが…)

胡麻油で、以前東京旅行で調達した唐辛子の漬物、泡辣椒を炒めて、匂いが立ち上ってきたら、鶏肉をぶちこむ。
(注:失敗ポイント。片栗粉で焦げがついてしまった。
鍋を強火で空焚きし、一回目の油を満遍なく馴染ませて表面の小さなこびりつきを溶かし、二回目の別の油でコーティングする、連鍋をするべき。
また、素材をあらかじめ140℃程度の油にひたひたにして、ジュワーと泡立ってきたら掬い上げる、泡油もしっかりやるべき)
(『鉄鍋のジャン』知識だ…)
(だって今の俺には当時の小此木タカオほどのスペックもないんだぞ。本物の初心者なんだからな。基本通りにやるべき)

鶏肉は火が通るのが遅いし、通さないと食中毒の可能性がかなり高くなるので、しっかり火を通す。
その後、刻んだ野菜とナッツを入れ、しばらく炒める。
少し食ってみて、野菜が固くなく、美味しく炒められて来たと感じたら、そこで火を止め、終わりとする。

***
ババーン

母と一緒に食いました。
さすがにゴージャスに美味しかったし、工夫の大半は全部しっかりと効き目を発揮してくれて、大成功と言って良いでしょう。達成感! 85点あげちゃってもいいくらい!
しかし、これでは発狂した丁宝楨が魔改造したような、汎用性のない創作宮廷宴席料理でしかない。
私に限って言えば、料理スキルアップの本当の目標は、栄養バランスのまともな、味に飽きの来ない家庭料理を、毎日ノンストップで24時間・7日間・月毎・季節毎・年度毎に作ることなのだが、今回のこれでは家常料理(家庭料理)とはちょっと言いがたいですね…
まあ、素材や工程の省エネについてはこれからの工夫ですね。ナントカします。
(しばらく鍋を水に浸して、皿を全部洗って干して、しばし放心状態)
(これで職場から召集がかかったら、ひょっとしたらテンションがメキリと折れてしまうかもしれん(注:かかりませんでした))
いいなと思ったら応援しよう!