
『横山 睦の楽しくない話 vol.1』
「タイトル」
はじめまして、横山 睦(むつみ)です。
ずっとnoteを書いてみたかったんです。初めてのnoteにドキドキワクワクしています。Twitterの140文字では書ききれないことが書けると期待しています。

初めてだからこそ、タイトルの話をします。
『横山 睦(むつみ)の楽しくない話 vol.1』です。vol.2やvol.3と不定期更新ですが、これから続けていく予定です。宜しくお願いします。
note初心者のボクでもわかることがあります。
「『横山 睦の楽しくない話』っていうタイトル、なんじゃそりゃ?」と。
タイトルや見出しは重要だと思っています。
読者は、見出しで判断をします。ボクも読者で他の記事を読むので重要なことがわかります。
・わかりやすい内容なのか。
・面白い内容なのか。
・時間を使って読む価値がある内容なのか。
見出しだけを見て面白くなさそうと判断されてしまえば、本文を見ることなくスルーされてしまう確率が高くなると思います。
裏を返せば、タイトルや見出しを工夫することで、その人のことを表すことができたり、「ん? なんだ?」と、グッと興味や関心を持ってもらえることが出来ると思っています。
ボクは、このタイトルにしました。
基本的に、何かをやる時はこだわりを持って、ちゃんと考えてやります。極論を言えば、これはボクのnoteなんだから、どんなタイトルを付けたって別にいいでしょって思っています。ボクは、こんな人です。
では、なぜ『楽しくない話』なのか?
「楽しい話」や「楽しくありたい話」ではダメなのかと言うと、一言で言えば、人生は楽しくない話の方が圧倒的に多いから。
だからと言って、人生に悲観しているわけではありません。それをわかった上で、楽しいことを見つけたり挑戦したいと思うので。
最初に言っておきますが、noteで愚痴を書くつもりはありません。でも、楽しい話ばかりを書くつもりもありません。今後、考えさせられる話題を書くこともあると思います。ご理解いただけたらなぁと思います。
もう一つ。タイトルの話で。
ボクはHi-STANDARDが大好きです!
難波章浩さん、横山健さん、恒岡章さんの3人のバンドです。この『横山睦の楽しくない話』は、ハイスタの横山健さんの『横山健の別に危なくないコラム』から多大なる影響を受けています。結局そこかよ!(笑)
ハイスタと対談することが1つの夢です。
会うだけではなくて対談したいんです。会うことはライブに行けば会えます。一方的に見ることは出来ます。すでに何度もライブに足を運んでいます。それぞれのソロのライブにも行っています。うまく言えませんが、ボクはライブを通じて、本当にいろんなものをハイスタから受け取りました。「また明日からがんばろう」という気持ちになって、今も過ごしています。
ハイスタと対談することが1つの夢です。
大切なことなので2回言いました。
言い続けて行動すれば、いつか夢は叶うと信じています。会って聞いてみたいことがあります。話をしてみたいことがあります。今はハイスタの3人はボクのことを1ミリも知らないですが、未来の空想をすることはとっても楽しいですね!(笑)
でもボクは本気なんです。
多くの人から笑われることかもしれませんが、「届け!!!」と思っています。
忘れられない出来事として、2016年10月5日『Another Starting Line』のCDが発売されました。それは事前にリリース情報などが一切ない、いわゆるゲリラ発売。売る側として携われたことを誇りに思います。
えっと、そろそろ話を戻します。
ボクは小説を書く人です。文章を書く人です。
ボクが書いた本を多くの人に届けたいという夢を持っています。
「売れて有名になりたい!」という夢ではありません。多くの人に読んでもらう為には、「売れて有名になる」ことはたった1つの手段にしか過ぎないと思っています。便宜上、「売れて有名になりたい!」と言うことがあるかもしれませんが、それは多くの人に知ってもらいたいからです。
ハイスタがボクにしてくれたように、ボクが書いた本を読んで「また明日からがんばろう」と、少しでも勇気を届けられることができるのであれば、こんなにも嬉しいことはないと思っています。
言葉のニュアンスの違いですが、「また明日からがんばろう」と言われても、別にそんなに毎日がんばらなくてもいいと思っています。
感動して涙を流したり、面白おかしくて笑ったり、本の世界に入って休憩して、ボクの書いた本があなたに寄り添えることが出来たら幸いです。
ボクのことを知ってほしい。
ボクが書いた本と出会ってほしい。
そう思いました。思っているだけではなく勇気を出して行動に移してみました。今回、いわゆる即売会と呼ばれる『文学フリマ』に初めて参加したんです。
まえがきが長くなりました。やっとここから、文学フリマについてのことを書くのですが、とても長くなるので、お時間がある時に読んでいただけると幸いです。
↓ 友達に書いてもらった自画像 ↓

「文学フリマに参加して-申し込み-」
ボク自身が初めて参加した時のことを忘れない為に書き残します。そして、これから初めて文学フリマに参加する人や参加したいと考えている人へ、少しでも参考になればと思って書きます。
文学フリマに参加することにした経緯から話をしたいと思います。
小説を多くの人に向けて発表する場所として、ボクが最初に思い浮かんだのが『小説家になろう』という投稿サイトです。
(『カクヨム』、『ノベルアップ+』、『アルファポリス』、『エブリスタ』などは後になってから知りました)
でも、『小説家になろう』の傾向や強み、特徴みたいなものは、どうやら「ファンタジー」や「異世界モノ」らしいということでした。
(詳しくないので、もし間違っていたらすみません…)
偉そうにもボクはこう思いました。それでは書きたいことがあんまり書けない、ボクの強みが出せないんじゃないかなぁと。そう思ったので投稿しませんでした。
個人的な印象ですが、書いた小説を各文学新人賞に応募することに似ていると思いました。よく言われるじゃないですか。
手当たり次第に文学新人賞に送るなって。
それぞれの文学新人賞には傾向があるから、自分が書いた小説がどれに当てはまるのか、どこに応募したらベストなのか判断した方が良いって。ボクは感覚的に、各小説投稿サイトも同じような気がしました。
(本当に詳しくないので、ボクの感覚がズレていたらすみません…)
そう考えているうちに、インターネットに投稿するだけではなく、実際に多くの人に会いたいと思いました。ここで初めてボクは即売会に参加してみたいと思ったんです。
次に思い浮かんだのが『コミックマーケット』通称コミケです。
同人誌の即売会と言ったらコミケだと思ったからです。でもコミケ初心者のボクがコミケに対して抱くイメージは、コスプレと有名な絵師さんです。それと二次創作です。はたして、無名のボクが参加したところでオリジナルの小説が売れるのか? と思いました。
そして、コミケ初心者のボクが初参加することは相当ハードルが高い。
RPGゲーム序盤のLv.1の主人公が、いきなりLv.99の魔王がいる城に乗り込むみたいな無謀なことじゃない? と思いました(笑)
頭を抱えていた時に、文学フリマの存在を思い出しました。
『夫のちんぽが入らない』著者こだまさんの本で、ボクは文学フリマの存在を知っていました。
(なぜ『夫のちんぽが入らない』を知ったのかというと、ボクは元書店員で本を売っていたからです)

文学フリマのホームページを見てみました。
https://bunfree.net
第一印象は、初参加の人に優しそう! でした。
(実際に優しかったです。参加するにあたっての説明が丁寧でした)
すぐに【マイメニュー(出店申込はこちら)】をクリックしていました。正確には覚えていないですが、たしかその時は「11月東京」「1月京都」「2月広島」の3カ所の開催地で出店の募集をしていたと思います。時期と開催地を考えた上で「京都」に決めました。
申し込みの項目を入力していく段階で、ボクはいきなり躓きました。
「ブース数、椅子数」
ん? わからん! ブース数って?
「文学フリマ ブース 画像」でググりました。
過去に参加したことのある人のブースの写真がネットに多くありました。とても参考になりました。
後になってから、よくよくホームページを見てみると載っていました。

めちゃくちゃわかりやすい!
初参加の人はホームページをちゃんと読むことをおすすめします!(笑)
まぁ、いろんな人のブースの画像を見たことによって、当日のブース設営のイメージを掴むことが出来たので結果オーライでした。

即売会初心者の人や、文学フリマ初参加の人に優しいと思いました。その都度、お知らせや確認メールも届くので。出店料の入金をして、申し込みが完了しました。

文学フリマは、今は全国で9回あります。
あなたの住む近くで開催されますか?
自分が作った作品を発表してみませんか?
「文学フリマに参加して-書くこと-」
どういう内容の小説を文学フリマに持っていこうかと考えました。新しく書こうか、それとも、今まで書いた小説を手直しして出そうか…。
正直めちゃくちゃ悩みました。
だって、自信作は文学新人賞に出したいから。
(ほとんどの文学新人賞は、同人誌やネット上で発表した作品は選考から除外されるからです)
だからと言って、自信がない、手抜きの小説を持っていきたくない!
そう思ったからこそすごく悩みました。もし、どうでもいいと思っていたら、そもそも悩んでいなかったと思います。
ボクは箇条書きにしてみました。
・読みやすい話にする
・「面白そう」と思ってもらえる話にする
・名刺代わりの話にする
これに全て当てはまるネタ、卒業文集を設定にして改めて書いた話をボクは持っていくことにしました。
1つずつ詳しく説明していきます。
まず、読みやすい話にしようと思ったのはボクが初参加だからです。
例えば、メタファーやオマージュ、いろんな要素をぶち込んだガチの小説を書いて、文学フリマに持って行ったとしても、何を書いているか全くわからない無名で初参加の人の作品を買いたいと思わないと、ボクは思ったからです。少なくとも、ボクがお客さん(一般参加者)だったとしたら、よほどのことがない限り買わないです。お金も節約したいし…。
だからボクは、ガチな本(便宜上そう言っています。語彙力がなくてすみません)は初参加の時ではなく、2回目以降に出そうと考えました。「こういう本も書いてますよー」という感じで。
えっと、あくまでもボクはこう思っていましたというのを書いています。絶対にこうした方がいいよっていうアドバイスではありません。だって文学フリマのホームページにもこう書かれてあります。
文学フリマでの〈文学〉
「自分が〈文学〉と信じるもの」が文学フリマでの〈文学〉の定義です。
既成の文壇や文芸誌の枠にとらわれず〈文学〉を発表でき、作り手や読者が直接コミュニケートできる「場」を提供するため、プロ・アマなどの垣根も取り払って、すべての人が〈文学〉の担い手となれるイベントとして構想されました。
だから「自分が文学と信じるもの」でこれを絶対に出したい! という明確なものがあれば、ぜひ文学フリマに出すことをおすすめします!
2つ目の、「面白そう」と思ってもらえる話にするというのは文学フリマが即売会だからです。
それぞれのブースの前に導線(お客さんの通路)があり、興味を示してくれたお客さんたちが自分のブースに来てくれます。立ち止まってくれます。『興味を示してくれる』行為の中には様々な理由があると思います。ここでは、小説の内容の視点から話をします。
(別の視点からについては、次回以降に書きます)
統計のデータを取ったわけではなくて、完全にボクの感覚ですが、暗いだけの話や悲しいだけの話ではなく、面白そうな話が手に取ってくれやすいと思うからです。
たとえ暗い話でも、「話のベースは暗そうだけど何か面白そう」だったり「悲しい感じが漂っているけれど面白そう」と『面白そう』というのが重要だとボクは思っています。
細かいニュアンスの違いですが、『面白い』ではないです。
だってこの段階では、お客さんは小説の内容を全部読んでいないから。
見本の試し読みや、ブース前で作者と内容についての会話をすることによって、『面白そう』と思ってもらって買ってもらえればいいので。
そして後日、全部読んでもらった感想として『面白かったです』と言ってもらえれば、とても最高ですよね!
ここで、ボクが文学フリマ京都に参加して実際に体験した話を。
「試し読みをしてもいいですか?」
お客さんがボクのブースに、ふらっと来てくれたんです。
「はい、どうぞ」
ボクは試し読みの本をお客さんに渡して、少し様子をうかがっていました。パラパラっとページをめくって試し読みをしているお客さんの邪魔にならないように、それでいて興味を完全に失って試し読みの本を机に戻さないタイミングで、ボクはお客さんに声を掛けました。
「今回、卒業文集という設定で書いてみました。クラスの36人、言ってみれば36個分のショートショートです。でも、全部読むとそれで1つの話になっている小説です」
「面白そうですね! じゃあ、これ1つください」
「ありがとうございます!」
実際に、このお客さんは買ってくれました。
営業の実技コンテストの模範解答かよ! っていうくらい完璧な流れで本当に買ってくれました。
ここで何が言いたいかというと。短い時間内で、少ない情報量の中でも「面白そう」と思ってもらえる話かどうか、それが重要だとボクは思うからです。
3つ目の、名刺代わりの話にするというのは、そのままの意味で、ボクはこういう感じの小説を書いていますよと示すことが出来るからです。
ボクは、ジャンルを問わずに小説を書きます。文体もその小説に合わせて変えたりします。
でも、横山 睦という作家の普遍的なものは存在します。
例えば、このAの場合と、
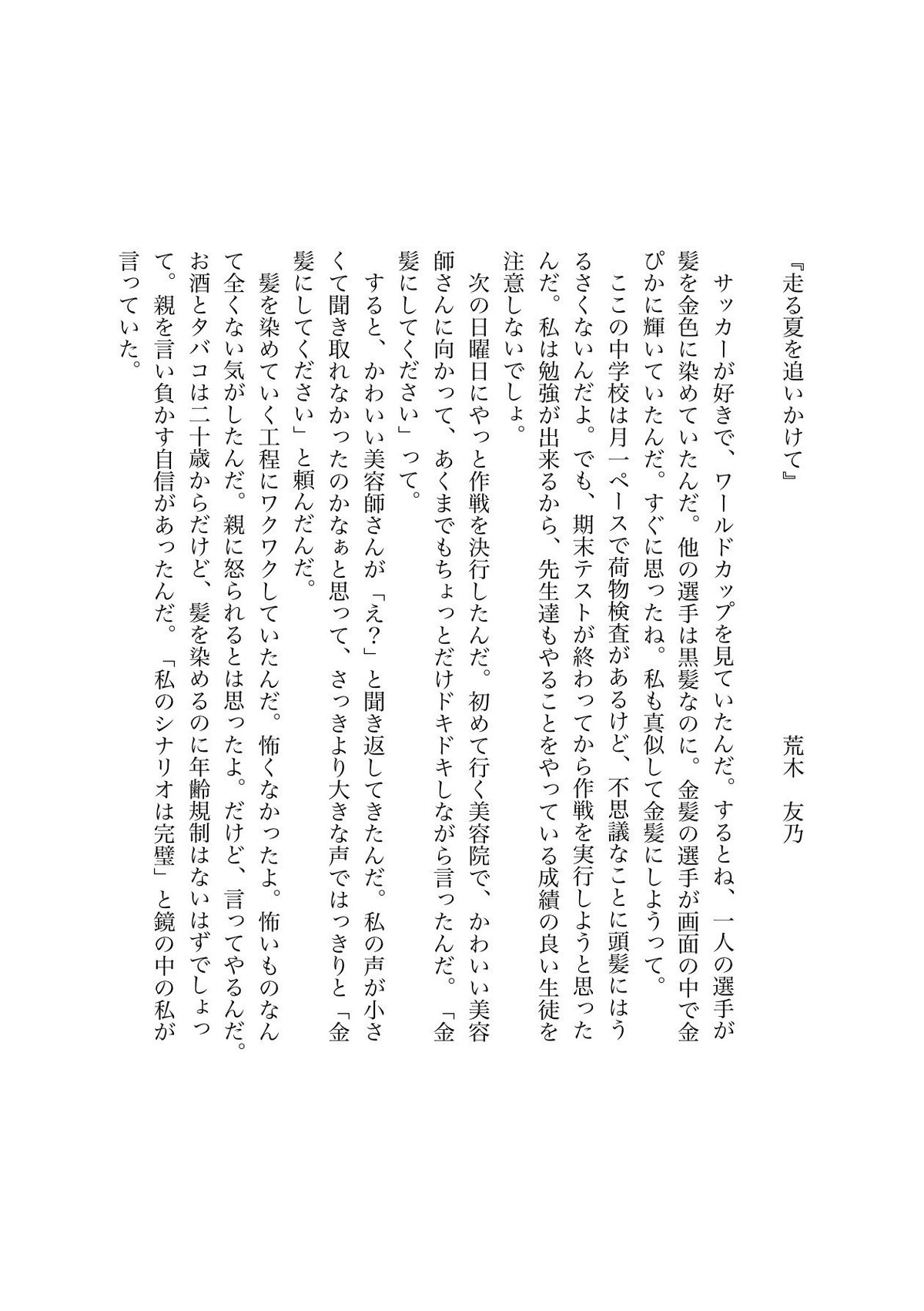
このBの場合、

内容は一緒なんですが、全然違います。
横山 睦という作家は、Bを書く人です。
例文だとわかりづらいかもしれませんが……。
ボクは、文字数や行数のフォーマットに合わせて書く人です。
この場合は、Bのフォーマットが先にありました。それに合わせて内容を書きました。だから、Aのフォーマットで書けと言われた場合は、それに合わせて内容を少し変えます。単語のチョイスだったり、言い回しを変えたりします。
ボクがAのフォーマットで書いたCの場合

フォーマットが同じAとCの場合を比べてみると、一目瞭然だと思います。
ここで誤解してほしくないのは、どちらが良いとか悪いという話をしたいのではありません。
ボクは、細かいところまでこだわるド変態ってことが言いたいだけ!(笑)
書いた本によってジャンルが違ったとしても、その作家の普遍的なものは何も変わらないとボクはそう思っています。
ちなみに、このnoteも工夫しています。ボクはiPhoneですが、スマホで見た場合とパソコンから見た場合、どちらでも見やすく見えるように書いてあります。ド変態なんで!
あと余談ですが、噂に聞いたところによると、作家の京極夏彦さんは雑誌掲載時のフォーマットや単行本化のフォーマットなど、フォーマットが変わる度に小説をそれぞれ書き直すらしいです。まさにド変態ですね!(笑)
えっと、話を元に戻します。
普段こういう感じで、こんなところにこだわりを持って書いている作家だということがわかる話が良いかなぁと思いました。
何回も言うようですが、あくまでもボクはこうしましたっていう話です。こんなことを無視してもOKです。どんな小説や詩や評論や絵を書いたっていいと思います。だって、それぞれが良いと思ったもの、自信作を持ち寄って、それらが合わさって開催される文学フリマは素敵だなって思うので!
ちなみに、文学フリマ京都にボクが持って行った話はこんな感じです。
『ほんのしるし-卒業文集-』から、サンプルとして、目次、1人目、5人目をどうぞ。





「文学フリマに参加して-作ること-」
- 作ること - について書く前に。
お笑い芸人さんについて書きます。
もちろん、比喩です。たとえ話です。芸人さんは、漫才、コント、リズム芸、フリップ芸など、得意なジャンルや苦手なジャンル、様々な種類のネタがあると思います。
書いたネタはどこで発表するでしょうか。
どこで発表すればネタが活きるでしょうか。
事務所や放送作家に見せるオーディション用のネタ、自分たちの持ち時間内であれば比較的自由に出来る劇場用のネタ、いろんな制約がある中で瞬発力が求められるテレビ用のネタ、人生を賭けて臨む賞レース用のネタなど。
自分が自信を持って書いたネタ、評価されたいじゃないですか。
だから、発表する場所に合わせて、ネタをそれ用に書くということは普通なことなんじゃないかなって思います。まぁ、何をもって評価とするのか、評価されることがすべてじゃないとか、いろいろあると思いますけど、ボクは素直に評価されたら嬉しいから。
で、何が言いたいかというと、お笑い芸人さんと作家は似てるところがあるっていう話です。
落語のマクラみたいなことはここら辺で終わりまして。
今回は、文学フリマ京都に向けて『作ること』について書きます。
文学フリマに初参加ということもあり、正直に言って、同人誌についての知識は何もありませんでした。
「書いて、売る」と思っていました。

でも、それは大間違いでした。

「書いて、作って、売る」なんです。
当たり前なことで少し考えればわかることですけど、改めて気付かされました。
「本ってどうやって作るの?」というところからスタートしました。
まず、同人誌を数多く手がけている印刷会社を調べてみました。
・しまや出版 https://www.shimaya.net
・ちょ古っ都製本工房 https://www.chokotto.jp
・株式会社ポプルス http://www.inv.co.jp/~popls
他にもありますが、キリが無いので…。
(文学フリマのホームページにも『印刷所のご紹介』欄に多く書かれてありますので、そちらもご参考までに。https://bunfree.net/link/printers)
・サイズ(A5、B5、文庫など)
・表紙のデザインや本文の用紙の種類
・冊数条件
・入稿方法
・納期スケジュール
・費用
など、それぞれの印刷会社によって違います。なので、自分に合った印刷会社を見つけることをおすすめします。
と、そんなことを言われても、初めてでどこが良いのか全くわからん!となります。ボクはそうでした(笑)
また話が少し脱線します。
作家は書くことだけが仕事じゃないんです。
例えばですけど、大手出版社から商業作家としてデビューをしていたら、別の人が印刷会社の人と打ち合わせをしてくれると思います。また別の人がプロモーションしてくれて、また別の人が本を売ってくれると思います。
それに比べて、同人誌はこうです。
・1人でやること多くない?
・求められるスキルの幅が広くない?
・書くことしかやったことないんですけど…。
そこで、ボクは思いました。
お笑い芸人さんに似ているなって。
売れる為に「ネタを書け!」と言われて必死に書いて。作ったネタが評価されて、やっとの思いでテレビに出られるようになったと思ったら、ひな壇からガヤしたりフリートークしたり。ロケに行って食レポしたり。しまいには、「芸人なのに面白くない」と言われて。面白いネタを書くだけが芸人じゃないと痛感させられて…。食レポする為に芸人になったんちゃうぞ!って、ビール片手に、夜中の公園で叫んで。
(完全にボクの妄想ですのでお気になさらず)
何が言いたいかというと、今の時代、1人の作家に幅広いスキルが求められる傾向があるとボクは思っています。同人誌では、サークルに入ることで個人ではなく、サークル単位で本を出すケースもありますが、基本は1人で全てをやらなくてはいけません。
(理解がある友人や家族が手伝ってくれる場合もあるかもしれませんけど)
えっと、ここで印刷会社の話に戻りまして…。
どこの印刷会社が良いのか、それぞれ比較して探していたボクは、(途中で面倒くさくなったボクは) この時、火がついちゃったんです。
D.I.Yだー!( Do It Yourself )
これも自分1人でやってやるよ!って。
いわゆるコピー本で作ってみました。
パソコンで作成しプリンターで印刷しました。


つづり紐で綴じています!(笑)
いや、でもボクは大まじめに作ったんですよ。
つづり紐も、書体も、フォントも、わざとです。こだわりを持ってこれにしたんです。今回、文学フリマ京都にボクが持って行った本のテーマが、『卒業文集』だから。少しでも雰囲気が出ると良いなぁと思ったので。
あと、もう1つ理由があります。
どうしてもコピー本にしたかったんです。
それは、ボクが初参加だから。
これは誤解してほしくないんですが、初参加の人だって印刷会社を通して印刷している人がほとんどだと思います。初参加はコピー本しかダメなんていうルールはありません。
(統計の数字がどこかに出ていたら知りたいです)
また話が少し脱線します。
ボクは昭和生まれの人間なのでこう思うかもしれませんが…。
昔、インディーズのバンドや歌手が自作の曲をパソコンに取り込んでそれをCD-Rに焼いて無料で配ったり手売りをしていました。もっと昔で言うと、カセットテープに録音してそれをダビングして無料で配ったり手売りをしていました。
ボクは実際に体感してみたかったんです。小説と音楽はジャンルが違いますが、でも、本質的な部分は同じだと思っています。
昔は良かったなんてことを言いたいんじゃありません。今の時代はとても便利になったと思っています。じゃあ、昔と比べてどこが便利になって、どう優れているのか。それを知りたくなったんです。初参加で何も知らなくて、まっさらな状態の時に、まずはコピー本で出してみようと思いました。
実際にコピー本を作ってみて、気が付いたことがあります。
・めちゃくちゃ大変
・素直に印刷会社に頼めばよかった
冗談じゃなくて、マジでそう思いました!(笑)
こんなにも時間と労力をかけないと完成しないなんて完全に想定外でした。1冊の本を作ることがこんなにも大変だということを体感しました。昔に比べて、印刷会社に頼んだとしても安い金額で本が出来ます。今の時代は、本当に便利になったなぁと思いました。
文学フリマや即売会に初参加の人や、参加したいと思っている人へ。
声を大にして言いたいです。素直に印刷会社に頼んだ方が良いよ。
あくまでも、ボクはそう思いました。
じゃあ、どこの印刷会社が良いの?
って言われても、ボクにもわかりません!(笑)
ボクは、次回は印刷会社に頼みます。
どうやって決めるかと言うと、候補を4つぐらい出して、あみだくじで決めようと思っています。どこも良さそうだし決められないので、あとは運というか、良縁があるところにしようかなぁって思っています。
「文学フリマに参加して-売ること-」
大きく2つのことについて書きます。「宣伝」と「接客」です。

まずは、「宣伝」についてです。
Twitter、Instagram、Facebook、YouTubeなどのSNS。やっぱり事前に、多くの人に向けて宣伝をする場合において、とても有効な手段だと思います。
どのSNSが1番、宣伝効果が高いかはわかりません。その人によると思います。もしまだSNSをやっていないとしたら、どれか1つだけはやっておいても損はないと思います。ここでも自分が何が得意で、どれに向いているか、どれだったら長続きができるか、そういうことを考えて決めることをボクはおすすめします。
ボクは、Twitterを選びました。
あくまでも、ボクがTwitterを選んだ理由は、
・不特定多数の人と気軽に交流ができること
・活用している人の年齢層
・ボクは文章が好きなので文章で表現できる場所
2020年の1月5日にTwitterを始めました。

「そんな日付までどうでもいいわ」と思うかもしれませんが、ボクは日付にもこだわったんです。だって、誕生日だったから。どうしてもこの日に始めたかったんです(笑)
ここから、ほぼ毎日ツイートをしていきます。
でも、全世界の人に向けて情報を発信していたわけではありません。
どういうことかと言うと、この時のボクの目的は、『文学フリマ京都』でボクのブースに来て、本を買ってほしいという目的があったわけです。だから、まずは『文学フリマ京都』に来てくれる人に向けて情報を発信することを心がけていたからです。
マーケティングでも言うじゃないですか。
ターゲットは? 誰に向けてなの?って。

ツイートには、ハッシュタグを付けて発信していました。文学フリマ京都に来てくれる人や興味がある人に向けて。
画像のツイートはプロフィール固定にしていたこともありますが、この数のリツイートといいねをいただきました。この数字が世間的に多いか少ないかはわかりません。でも少なくともボクは、多くの人に協力してもらって、助けてもらったと思っています。とても嬉しかったです。
あとは、文学フリマのwebカタログを最大限に活用しました。
(自分ではそう思っています)

webカタログを簡単に説明します。
・出店者名
・カテゴリー
・ブースの場所(配置図)
・SNS等のURL
・紹介文
ボクは、何回かwebカタログを更新しました。

次第に、ボクはこういう考えで臨むようになりました。


結果的に、多くの人に知ってもらえました。
当日、「Twitterをフォローしてくれていたので買いに来ました」と言ってくれる人や、「面白そうなツイートしていたので直接ブースを見に来ました」と言ってくれる人や、「Twitterで流れていた横山 睦ってあなただったんですね」みたいなことを言ってくれる人もいました(笑)
ボクは、宣伝ツイートを宣伝メインとしてではなく、交流のツールになるように使っていました。ブースに来てくれる動機であったり、会話のきっかけになるように。
あと、もう1つだけ「宣伝」について。
よくTwitterの名前の部分に、ブースの場所を付けるじゃないですか。
例えば、『横山 睦 う-38』みたいな。正直、僕はその効果がよくわかっていなかったんです。だから、僕は付けずに当日に臨みました。
hip hopとかである、a.k.a みたいなものなんでしょ? ぐらいに思っていました。そして当日、僕は実感しました。全然違いました。
それは、僕自身がTwitterで交流してくれた人のブースを見たいと、お客さんの立場になった時に初めてわかりました。
僕は今回、1人で参加しました。なので、他のブースも見たいとなった時に、自分のブースは誰もいなくなります。
紙に、「席を外します。Bダッシュで戻ってきます」や「〇時〇〇分頃に戻ります」と書いて、現金などの貴重品だけ持って他のブースを見に行きました。だって、自分も楽しみたいから!
でも、なるべく早く自分のブースに戻りたいわけです。自分の本も売りたいから。
あの人のブースどこだっけ? と探す手間と時間がもったいないと思いました。そんな時に、Twitterの名前の横にブースの場所が書かれていたら、すぐに向かうことが出来ました。
「宣伝」の効果というより、お客さんへの気遣いだと思いました。
なるべく、名前の横にブースの場所を付けた方がいいと思います。ボクは次回から付けます。
ボクの癖なんですが、人がやっていることをそのままマネすることをしないです。どうしてそれをやっているんだろう? それをやることによって何の効果があるんだろう? って、疑問を持ちます。そして、なるほど、これはやったほうが良いと納得して、自分に取り入れます。(自分が出来ることにカスタマイズします)
もちろん、文章をパクるとか著作権に違反することは絶対にダメですが、風習や習慣、考え方についてはいろんな人を参考にして、うまく自分の中に取り入れていけばいいのかなぁって思っています。
「接客」について。
千差万別なので、どれが正解というのはありません。唯一、即売会に初参加してみて感じたことを書きます。
ボクは初参加だったので正直不安でした。本当に売れるのかなって。自分のブースにお客さんが来てくれるのかなって。入場時間になってお客さんが会場に入ってきても、最初の10分~15分くらいはボクのブースにお客さんは立ち止まってくれませんでした。「まだ始まったばかりだから」と平静を装っていましたけど。
そして、ボクのブースにお客さんが来てくれて、「この本をください」と言ってくれた時に、ボクは嬉しさのあまりにテンパってしまって、おもわず、「え? いいんですか? 本当に本を買ってくれるんですか?」と言ってしまいました。
たぶん、最初の3人のお客さんにはこんな内容のことを言っていたと思います。でも、ボクは気が付いたんです。これは言うのやめようって。
次のお客さんには、「ありがとうございます。嬉しいです」って素直に伝えていました。
神経質かっていうくらい細かいことだと思うんですけど、ボクがお客さんの立場で考えたとして、「え? いいんですか? 本当に本を買ってくれるんですか?」と言われたら、この本売れていないのかな、人気ないのかなって思うからです。
売り手としたら、めちゃくちゃ嬉しくてそれを表している言葉にも関わらず。せっかく買ってくれたお客さんを不安にさせるのは良くないなぁって、ボクは思ったので、それからは素直に感謝の気持ちを伝えるようにしました。
「ブース設営」についてもちょっとだけ。
文学フリマ京都に来てくれて、ボクのブースを見てくれた人はボクがどんなことをやっていたのかわかると思います。一応、記念に写真も撮りましたけど、ここで載せるつもりはありません。理由は、文学フリマ京都でやったようなブース設営は、たぶんもうやらないと思うからです。
決して、失敗だったとか、後ろ向きな理由でもうやらないと思っているのではなく、他にもやりたいことがあるから、もっとネタがあるから(笑)
この『横山 睦の楽しくない話 vol.1』の最初でバンドの話をしましたが、バンドっていつ解散するかわからないんですよ。いつ活動休止になったり、いつメンバーが脱退するか誰にもわからないんです。行きたいと思った時に行かなかったとしたらもう見られないかもしれない。後悔するかもしれないんです。
何が言いたいかというと、会える時にボクに会いに来てほしいです。ボクは小説を書くことや文章を書くことを辞めるつもりは全くありません。でも、人生って何があるか、これから何が起こるかわからないから。
写真とかじゃなくて、実際に会場に訪れて生の雰囲気を感じてほしいと思っています。一期一会です。なるべくボクも多くの人に会いに行こうと計画しています。
ボクのことを知ってほしい。
ボクが書いた本と出会ってほしい。
長文を最後まで読んでいただいて本当にありがとうございます。
これからも、横山 睦を宜しくお願い致します。
2020.02.06
いいなと思ったら応援しよう!

