
「NPSって、結局何?」 友達に勧めたくなる会社が勝つ時代
NPSとは何か?
「NPS(ネット・プロモーター・スコア)」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。しかし、「具体的にどのような指標なのか」「なぜ重要なのか」を正確に理解している方は意外と少ないかもしれません。
NPSは単なる顧客満足度の指標ではなく、企業の成長やブランドの強さを測る上で極めて有効な指標です。本記事では、NPSの基本概念とその活用方法について詳しく解説します。
NPSとは? 「推奨度」を測る指標

NPSは、顧客が企業やサービスをどの程度推奨したいと考えているかを数値化したものです。
具体的には、顧客に対して「0〜10のスケールで、この会社(商品・サービス)を友人や同僚にどの程度勧めたいですか?」と質問し、その回答を以下の3つのカテゴリーに分類します。
- 9〜10をつけた人 → 「推奨者(プロモーター)」
- 7〜8をつけた人 → 「中立者(パッシブ)」
- 0〜6をつけた人 → 「批判者(デトラクター)」
そして、「推奨者(9〜10)」の割合から「批判者(0〜6)」の割合を引いた数値がNPSスコアとなります。
例えば、100人の回答者のうち「推奨者が50%、批判者が30%」であれば、NPSは「50−30=+20」となります。
この数値が高いほど「顧客からの信頼が厚く、推奨される企業」であると考えられます。
NPSの成り立ちと背景
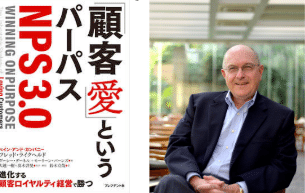
NPSは、2003年にフレッド・ライクヘルド氏によって提唱されました。従来の顧客満足度調査(CSAT)や顧客ロイヤルティ指標(CLI)では、顧客の真の忠誠度や企業成長との相関性が十分に測れないという課題がありました。そこでライクヘルド氏は、「顧客が企業を推奨するかどうか」というシンプルな問いかけこそが、企業の成長と強く結びついていることを発見しました。これにより、多くの企業がNPSを取り入れ、顧客ロイヤルティの向上を目指すようになりました。
私とNPSの出会いは2010年。当時国内で満足度調査を行っていたのですが、スコア化出来ない、業績相関しない、改善ポイントがなかなか見つけられないなど課題があり、困っていました。
その時にスカンジナビア航空のCEOヤン・カールソン氏の著書「真実の瞬間」を読んで、NPSの存在を知りました。その後連絡をとり資格認定のワークショップがシンガポールであるということで参加。私達の会社から以外は、東南アジアの郵政公社や航空会社、CXコンサルタント企業などでした。
ここでも日本の存在感は非常に小さかったことを記憶しています。

なぜ0〜10の11段階評価なのか?
NPSでよく聞かれる質問の一つです。
NPSが11段階の評価になっている理由には、以下のような背景があります。
1. 中間点を作らないため:奇数段階(例:1〜5や1〜7)の場合、真ん中の「どちらでもない」を選ぶ傾向が強くなります。11段階にすることで、より明確な意見を引き出すことができます。
2. 直感的に理解しやすい:10点満点評価は、多くの人が日常的に使用しており、直感的にわかりやすい尺度です。
3. *詳細な分析が可能:スコアの分布をより精緻に把握できるため、細かな顧客インサイトを得ることができます。
なぜ批判者が0〜6なのか?
「0〜6を批判者に分類するのは厳しすぎるのでは?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。しかし、この基準には明確な根拠があります。
1. 「やや不満」でも推奨には至らない
6をつけた顧客と0をつけた顧客では、表現の強さが異なりますが、「積極的に推奨しない」という点では共通しています。
2. ネガティブな口コミの影響を考慮
顧客の不満は、たった1回の悪い体験で生じることが多く、低評価の顧客は企業にとって重要なリスク要因となります。
日本人的には5・6をつけても、批判はしていないと言われる方は多いのですが、私達はこの標準を使用しています。
大事なことは、数字ではなく、推奨者を増やし批判者を減らすことの改善活動につなげることになります。
NPSは単なる顧客満足度の指標ではなく、企業の成長やブランドの強さを測る上で極めて有効な指標です。では、NPSの基本概念とその活用方法について詳しく解説します。
まとめ:NPSとは
✔ NPSは「顧客がどれだけ積極的に推奨するか」を測る指標であり、企業の成長と直結する。
✔ 11段階評価を採用することで、より精度の高い分析が可能。
✔ 0〜6を批判者とすることで、企業にとってのリスクを明確化。
✔ NPSの他社比較を行う際には、業界平均を考慮しながら評価することが重要。
✔ NPSの向上はリピーター獲得、ブランド価値向上、顧客体験改善につながる。
NPSの活用方法とビジネスへの影響
さて、NPSの概略がお分かりになったのではないでしょうか。ここからは、具体的にビジネスの現場でどのように活用できるのかを詳しく解説していきます。

1. リピーターの獲得とLTV(顧客生涯価値)の向上
NPSの高い企業は、顧客がリピーターとして定着しやすく、結果的にLTV(顧客生涯価値)が向上します。特に、SaaS企業やサブスクリプションサービスにおいては、顧客の継続利用が売上の安定につながります。
高NPS企業の特徴
- 顧客のロイヤルティが高く、解約率(チャーンレート)が低い
- ポジティブな口コミが拡がり、新規顧客獲得コスト(CAC)が下がる
- 顧客単価(ARPU)が向上し、LTVが最大化する
例えば、NetflixやAmazon Primeは、NPSの向上施策を積極的に行い、ユーザーのエンゲージメントを高めています。彼らは、コンテンツのパーソナライズ化や高品質な顧客サポートを提供することで、長期的な顧客関係を構築しています。
2. ブランドの信頼性向上
NPSの高い企業は、顧客の推薦によって新規顧客を獲得しやすくなります。広告やプロモーションのみに頼るのではなく、実際のユーザーによる口コミがブランドの信頼性を高めます。
NPSがブランド価値に与える影響
- 推奨者(プロモーター)の声が自然な広告となり、新規顧客獲得につながる
- ネガティブな口コミの拡散を抑制し、ブランドの評判を保つ
- 競合との差別化要因として機能し、ブランドロイヤルティを強化
例えば、AppleはNPSが非常に高い企業の一つです。同社の製品を使用した顧客は、その利便性やデザイン性の高さを周囲に伝え、結果として新規顧客が増えるという好循環が生まれています。
3. 顧客体験の継続的な改善
NPSは定期的に測定することで、顧客体験の向上に向けた具体的な施策を講じることができます。
- NPSを活用したCX(顧客体験)向上施策
- 低評価の顧客に対するフォローアップの仕組みを確立
- NPS調査結果を社内で共有し、商品・サービスの改善に反映
- カスタマージャーニーマップ(CJM)と組み合わせて、問題点を可視化
例えば、ホテル業界では、宿泊後にNPS調査を実施し、低評価の顧客には迅速に対応することで、次回の利用につなげる取り組みが行われています。
4. 競合分析と市場ポジションの把握
NPSは、自社の成長を測るだけでなく、競合との比較を行う際にも有効です。業界平均NPSと自社のNPSを比較することで、自社の市場ポジションを正確に把握できます。
- 競合分析におけるNPSの活用方法
- 競合と比較して強み・弱みを明確化
- 市場の動向を分析し、適切な戦略を立案
- NPSの推移を追跡し、ブランド価値の変動を測定
例えば、航空業界では、各社がNPSを競争力の指標として活用し、顧客満足度向上に努めています。
まとめ:企業成長におけるNPSの活用
✔ NPSは「顧客がどれだけ積極的に推奨するか」を測る指標であり、企業の成長と直結する。
✔ リピーターの増加やLTV向上に貢献し、ビジネスの持続性を高める。
✔ ブランドの信頼性を向上させ、口コミによる自然なマーケティング効果を発揮する。
✔ 顧客体験の向上に寄与し、商品・サービスの継続的な改善が可能となる。
✔ 競合分析にも活用でき、市場ポジションの明確化に役立つ。
これからの時代、広告やプロモーションに頼るだけではなく、顧客の推奨度を高めることが企業の競争力につながります。NPSを活用し、持続的な成長を目指していきましょう。
