
未顧客理解
こんにちは、ハリーです。
本日も、芹澤さんの書かれた「未顧客理解」を読んでいこうと思います。
ダブルジョバリティの法則に従うと、既存顧客のロイヤリティ施策を実施していてもロイヤリティは上がらない、むしろ新規顧客を獲得して浸透率を増やすことでロイヤリティが上がるという考え方、そして売上のトップラインも上がるという考え方が存分に勉強できました。
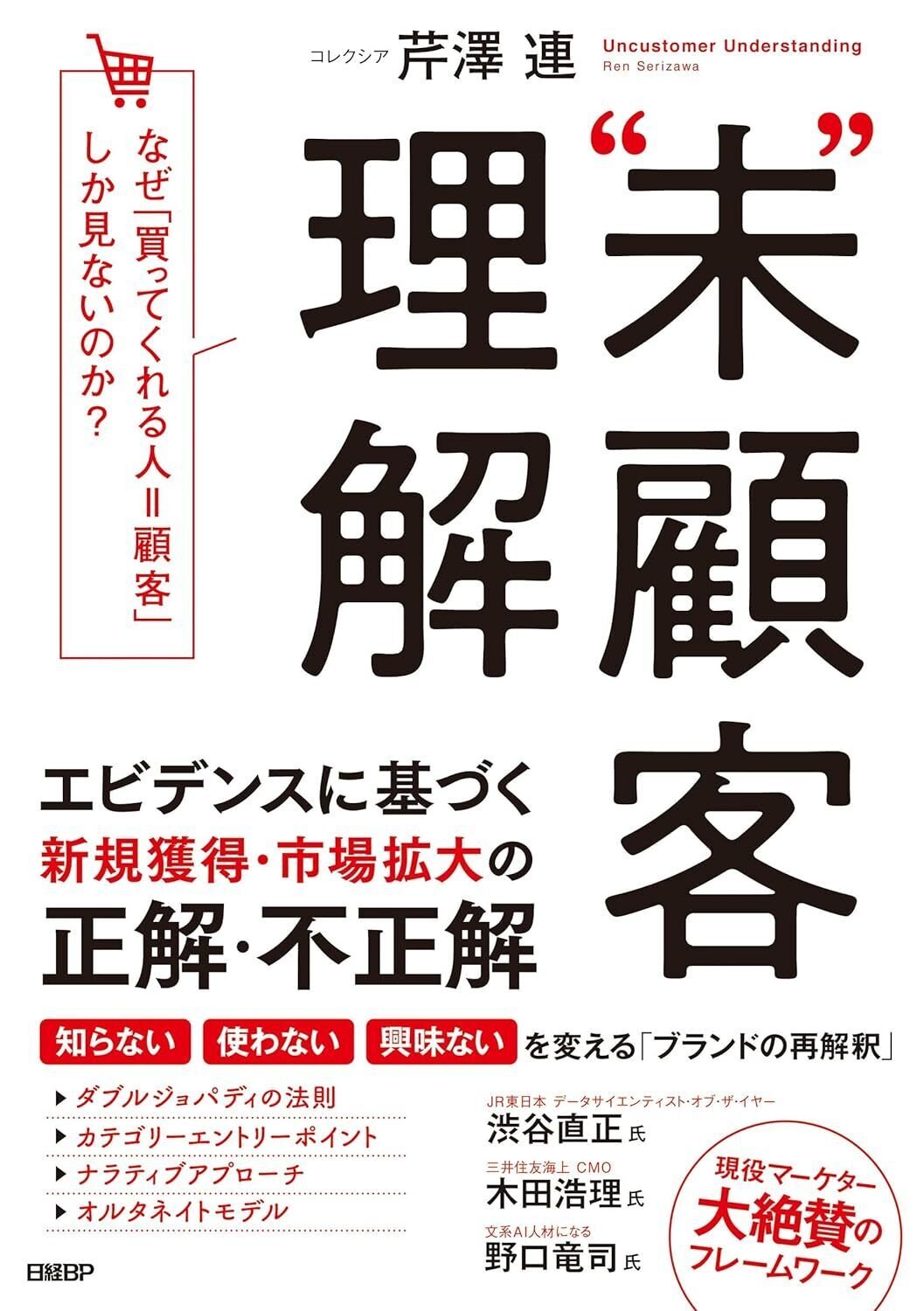
では、どうぞ。
■なぜ未顧客理解が重要なのか?
→ブランドの成長にあたり、既存顧客ではなく新規顧客を獲得することが必要だから。
・既存顧客向けのマーケティングだけでは十分でない理由
1)ヘビーユーザーは絶対数が少ない
2)ヘビーユーザーに更に購入してもらうのは難しい
3)既存顧客へのアクティベーション施策は効果期間が短い
4)既存顧客の認識や行動を広告で変えることは難しい
5)ROIを成果指標として追っても売り上げのトップラインが増えるわけではない
6)ロイヤルティはロイヤルティ施策によって高まるのではなく、浸透率の増加に伴って高まる
3)5)⇒短期的な売り上げには効果があるが、ターゲットが狭くなる傾向に。
コストを下げればROIは上がるが、長期的な成長に繋がらない。
また同じターゲットに施策を当て続けると効果は減っていく。
★事業成長はコストを減らして数字を大きく見せるではなく、コストを増やしてリターンを増やす、という順序でないと成り立たない。
■未顧客理解は難しい
→CRMやCDPなど世の中に出ているユーザー分析手法は全て"顔が見えているユーザー"のみ。
実務上大事なのは、未顧客の【文脈】に合わせてブランドを再解釈すること。
■従来のマーケティングと未顧客マーケティングの違い
・リサーチや分析に関する違い
×)1人の顧客を深く理解して、その人に売れる商品や刺さる広告を開発する
○)1人の深い理解は新しい機会に気付く為に行うもの。より大きな新しい市場を狙えるようにブランドを見直す手段
⇒1人の顧客の深い分析は、個人にモノを売るためではなく、個人の背後にあるより大きな市場や購買行動の規則性に気付く為に実施する。
多くの人に共通するニーズを見付けようとすると、平均的な話に着地してしまう。一方、少数の生活文脈を深く理解しようとすると、気付かなかった生活文脈に気が付くことがある。特定の状況で繰り返し行われる行動パターンや考え方の癖、文脈に依存する報酬など、マスに展開できる共通項として発見することが狙い。
×)人の理解が大切
○)文脈の理解が大切
⇒人と購買行動の関係性を文脈抜きで理解するのは無意味
その場その時の状況で、人間の行動や考え方はいくらでも変わる。
⇒文脈理解=CEP(カテゴリーエントリーポイント)をいくつも作ることが重要
ブランドへの入り口が多く、未顧客がブランドに辿り着きやすい状況がベスト
通常、人は理由が先で行動が後、だと思うが未顧客の場合は別
行動が先で、理由が後。
調査で出てくる理由は後付けの理由で、これを信じると惑わされる。
⇒行動の裏側にある顧客の合理を考察することが重要。
■STP戦略の違い
×)今ある市場を細分化してターゲットを絞りこむ
○)今ある市場の枠を撤廃して市場を再定義する
競合するブランド間において顧客プロファイルは変わらないという論文もあり、競合関係にあるブランドはどれも同じような人に買われている。
細分化されたセグメントに対して施策を売っていても、必ず獲得コストが大きくなる。未顧客獲得のためには、既存の枠を取り払い、初手で多くの顧客を視野に入れ再定義する目線が重要。
×)人をターゲティングして人にポジショニングする
○)生活文脈やシーンをターゲティングして、顧客が行う行動や活動にポジショニングする
ブランドの選択は人の属性や内面では決まらない。
そのときの文脈、状況によって思い起こされるブランド想起集団があり、その状況に合わせてブランド選択がされる。
⇒つまり、「人」ではなくこの「生活文脈やシーン」にターゲットを設定する
■未顧客理解の5原則
・文脈が変われば意味が変わり、意味が変わると価値が変わる=再解釈の重要性
・未顧客は本来戦うべき市場を見通すためのレンズである=市場の再解釈
・行動の背後にある欲求、抑圧、報酬から顧客の合理を理解する
・ブランドの特徴×未顧客にとっての報酬=文脈最適のベネフィット=ベネフィットの再解釈
・モノの売り方ではなく、モノが使われる行動の増やし方を考える=ポジショニングの再解釈
⇒ブランドを顧客価値に翻訳する5ステップ
では、CEPにおける顧客の合理はどうやって捉えるのか?
■顧客の合理を捉える4つのポイント
きっかけ:その行動はどんな状況で起こったのか?(What Where Who When)
欲求:その行動は、どんな欲求に根差しているのか?
抑圧:その行動は、どんな制限や条件付けを受けているのか?
報酬:その行動をすると、どんな良いことがあるのか?
■未顧客にとって大事なのは、簡単かつ確実に報酬を得られること
【購買行動のコスパ=商品から得られる品質/商品に辿り着くまでのコスト】
⇒多くの企業は分子にフォーカスしすぎていて、分母に注力していないパターンが多い。差別化は必要だが、未顧客はその場で思い付いたブランドの中から最も簡単に手に入れられるもので済ませることが多い。このことを「利用可能性ヒューリスティクス」という。
コストと言っても価格だけではなく、どこで買えるか、どんな種類があるか、どんな体験が得られるのか、差別化すると要素が増えて未顧客にとって負担が増える。
ブランドの役割は、消費者に「考えさせないこと」、こういうときはこれ、と選ばれるから「ブランド」である。
■未顧客理解のためのアスキング調査のコツ
・コンスタントサム(恒常和法)型アンケートが望ましい
実際の購買状況に近い形の設問にした上で、以下STEPで設問を設ける。
<STEP1>「想起集合にどのブランドが含まれるか」をブランド一覧から選んでもらう
<STEP2>想起集合に含まれるブランドに対して、「10回買ううち、どのブランドを何回買うか」もしくは「100点を各ブランドに振り分けるとそれぞれ何点になるか」といったコンスタントサム(恒常和)を聞く
※ダメなパターン
以下のようなスケールを用いると、主観の心理量には絶対原点がなく、基準がずれるため、後になって集計が大変になる。
・全く買いたいと思わない(0)
・あまり買いたいと思わない(1)
・どちらでもない、どちらともいえない(2)
・どちらかと言えば買いたいと思う(3)
・とても買いたいと思う(4)
・選択盲の影響を無くすため、「商品を使う文脈に関するファクト」を拾う
アンケートの回答の理由を後付けしてしまうという選択盲の影響で、回答の信頼性が下がることを少しでも、実際の文脈のファクトを聞くことで、補正する。
例)
・自主的な工夫
・代替品、代替手段の採用
・インターネットでの情報検索
⇒未顧客の解決したいジョブ(課題)がわかり、ブランドが購買検討される余地がある
・友人などへの相談
・WTP(商品にどれくらいお金を払えるか)
また、使用実態については、以下項目をヒアリングすることで深堀が可能。
CEPで思いつくブランドに入っていない=純粋想起群に入っていないので、改善が必要。
・各CEPで思いつくブランド
・前回どのブランドをいつ購入したか
・現在利用しているブランド
・次に買いたいと思うブランド
未顧客の理解では、人ではなく生活の文脈やシーンを中心に、
顧客の合理を追求することで、CEP発掘の助けとなることを勉強しました。
1人の分析は、1人に刺さる商品やコミュニケーションを開発するのではなく、
生活の文脈やシーンなどからマスに展開できるCEPを発掘し、新しい市場を再定義するため。という今まで全く考えたことのない新しい視点は、今後の仕事でも活用してみたいと思います。
今回も、ありがとうございました。
