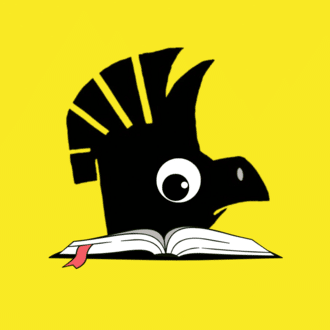読書 『マッドジャーマンズ ドイツ移民物語』
持たざるものが国境を超え、生きていくことの難しさ。
日本に生まれて、日本で育ち、日本でくらす私たちにとっては、知ることのない移民と外国人労働者のリアル。
そんな彼らの絶望や希望、悲しみや悔しさをうまく描写しているのが本書です。
マンガなのですぐに読めますが、社会がはらむ根深さに、読後、しばらくぼんやりさせられました。
日本でつつがなく暮らし、このままでいいのだろうかと漠然とした不安をかかえている人には、まちがいなく衝撃を与えてくれます。
もちろん、ドイツとモザンビークの歴史について知りたい人や、移民と外国人労働者問題に興味のある人にもおすすめです。
本書の舞台は東西ドイツ統一時代。
アフリカの旧社会主義国から、東ドイツへおもむいた外国人労働者の人生を描いています。
圧巻はそのストーリーテリングの巧みさ。
外国人労働者3人の、個人的な記憶のディテールにせまり、独創的なイラストで、ドキュメンタリー映画のように描ききっています。
歴史背景をすこし説明すると、1975年、アフリカのモザンビークは社会主義政権を打ち立てます。
同じく社会主義国の東ドイツは、当時労働力が不足していたので、モザンビーク政府は1979年に東ドイツと労働協定を結びました。
結果、1980年代に約2万人のモザンビーク人が、安い労働力として東ドイツに派遣されます。
彼らは、東ドイツにいけばエリート教育を受けられると聞いていたので、期待を胸に東ドイツへとむかいます。
しかし現実は真逆で、ろくな教育も受けさせてもらえず、仕事の選択肢もありません。
さらには給与の半分以上が天引きされます。
モザンビークに帰国する時に還付されるということでしたが、モザンビーク政府が国民をだましており、還付されることはありませんでした。
党はオレたちを売りまわしたんだ!
オレたちは、東ドイツで身を粉にしてはたらいた。
稼いだ外貨は、モザンピークの"同志"のカバンの中に入ったってわけだ!
また、東西ドイツが統一してからは、西ドイツにトルコ人労働者がいたので、帰国せざるをえなくなります。
西ドイツはオレたちを必要としなかったーーー
もうトルコからの移民がいたから。
何が正しいのか分からない状況の中、それぞれの信じる道にしたがって生き続けますが、本書に登場する2人は、モザンビークに帰国後も、故郷に居場所をみつけることができません。
モザンビークに戻ってからは、彼らへの羨みと嫉妬が溢れており、しまいには家に火をつけられてしまいます。
唯一の救いは残りの1人で、悲しい記憶を持ちながらも、たくましくドイツの社会に適応し、医師の職を得ることができます。
作者のビルギット・ヴァイエ (Birgit Weyhe)は1969年ミュンヘン生まれ。
幼少期をウガンダとケニアで過ごし、ドイツに帰国後、ハンブルグ大学応用科学科デザイン学部でイラストレーションを学び、現在はフリーランスのイラストレーター、漫画家としてハンブルクに暮らしています。
子供のころにアフリカで過ごした作者自身、「故郷とはなにか」を問い続けており、故郷をもたないモザンビークの外国人労働者を題材に選んだのは必然とも思えます。
どこか遠いところに移動して、そこで生きていくこと。
国に翻弄され、多くを失いながらも、記憶だけは積み重なりつづける残酷さ。
言葉を覚え、髪型を変え、習慣と学歴を身につけ、社会的地位を上げていく努力の清々しさ。
ドイツへの移住を決めたので、ドイツの歴史について知りたい思い、ヨーロッパで話題作という本書を手に取りましたが、移民問題に揺れる欧州について、腰を下ろして考えさせられます。
いいなと思ったら応援しよう!