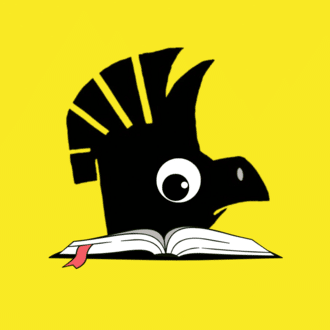プロンプト本の決定版!「問い」で生成AIの可能性を最大限に引き出す:『AI時代の質問力』
皆さんは、生成AIとどう付きあっていますか?
ChatGPTのようなAIに何かを質問すると、まるで人間が答えているかのように自然な文章で返ってきます。
でも、ただ漠然と質問するだけでは、AIの能力を最大限に引き出すことはできません。
今回ご紹介する『AI時代の質問力 プロンプトリテラシー』は、そんな悩みを解決してくれる一冊。
個人的には、プロンプト本として決定版なのではと感じています。
著者は、人工知能(AI)ではなく、人工生命(ALife)の専門家というユニークな経歴をお持ちで、その視点からもAIの仕組みをわかりやすく解説してくれています。
今回は、本書から学んだ3つの視点をご紹介します。
より本質的なこと
昨今、生成AIに関するハウツー本がたくさん出版されていますが、本書はそれらとは一線を画しています。
たんにプロンプトの書き方を解説するのではなく、生成AIの仕組みや、人間とAIの協働について、より本質的な部分から掘り下げているのです。
たとえば、生成AIからの回答は、こちらからの質問だけではなく、同じチャット内での生成AIの以前の回答もが、AIの新しい回答の作成に使われているということを、本書を読んで初めて知りました。
このように、本書はChatGPTに代表される大規模言語モデルの仕組みを丁寧に解説しており、AIの得意な部分、人間が補足すべき部分をわかりやすく整理してくれています。
論文から使えるプロンプトをピックアップ
本書では、実際に論文で発表され、成果がある10個のプロンプトが紹介されています。
それぞれのプロンプトがどのような意図で設計され、どのような場面で有効なのかが丁寧に解説されています。
ちまたには、コピペで使えるプロンプト集のような本があふれていますが、それらは小手先のテクニックなので、すぐに使い古されてしまいます。
反対に本書は、どのような考え方でAIと対話をすれば良いのかを理解することができる点で、自発的にプロンプトを開発できる考え方が身につくでしょう。
実際の論文から引用しており、AIの特徴をおさえた、応用性の高いプロンプトばかりなので、すぐにでも実践できます。
ステップバックプロンプト
それらのプロンプトのなかでとくに興味深かったのが「ステップバックプロンプト」というもの。
これは、具体的な問題解決をお願いする前に、問題の背後にある原則や概念を探り、物事の本質に迫るためのプロンプトです。
ステップバックプロンプトは2つの段階からなり、最初は「抽象化」のステップ。
本題を問うかわりに、より抽象的なことについて聞きます。
たとえば、物理の問題であれば、「以下の質問の背後にある物理的な原理について教えてください。」と問います。
次のステップは「推論」です。
最初のステップで得ることができた原理を質問に加え、回答を促します。
この「ステップバックプロンプト」を、ブログ記事のタイトルを考えるのに使う場合を考えてみましょう。
たとえば、「~という内容のブログ記事のタイトルを考えてください。」と指示するのではなく、たとえば、「○○という内容のブログ記事を書いていますが、読者の興味を引きつけるタイトルを考えるために、必要な要素について教えてください。」と、一度、読者を引きつけるタイトルとは何かを抽象化させます。
そして、つぎのステップとして、「それらの要素に基づき、以下のブログの記事のタイトルを考えてください。」と、アウトプットを求めます。
抽象化のステップを踏むことで、より説得力のある回答が生成できます。
まとめ
AIの可能性を最大限に引き出すためには、プロンプトを理解して適切に操る能力(プロンプトリテラシー)が不可欠です。
『AI時代の質問力 プロンプトリテラシー』は、ある程度様々なパターンのプロンプトを試してきた人にこそお勧めしたい一冊。
すでに様々なプロンプトを試してきた方にも、生成AIの仕組みをより深く理解したい方にも、そしてこれからプロンプトの世界に足を踏み入れようとしている方にも、ぜひ手に取って読んでほしい本です。
とりあえずこの本と、仕事の例が多く、実践的な『深津式プロンプト読本』を読めば、プロンプトに関してはよい気がしています。
\\ このnoteを書いた人 //
ホヴィンチ|📌フォローはこちら
・noteを愛する独立出版者
・本づくりのダヴィンチを目指しています
・ニュースレター「ぼっちスタートアップ」を発行
noteでできたこと
・1,000日連続でnoteに記事を投稿
・2年11ヵ月で3,000人の方とつながる
・公式noteに1年で3回ほど紹介される
出版したKindle本
・『Notion習慣トラッカー』
・『もろこしコーン』(ナンセンス絵本)
\\ \ / //
ー サイトマップ ー
// / \ \\
いいなと思ったら応援しよう!