
今年、読めてよかった本
占星術の資料本ばかりを読むようになってしまって、それは必要に迫られているし興味が尽きないからなのだけど、それにしても、ただただ読書の楽しみのための書物から遠のいてない? と気づいたのは今年の夏くらいだっただろうか。
そこから少しずつ、読書のための読書を意識して読んでみた本を記録しておきたくて、年越しそばとお雑煮の出汁を引きながら書き始めてしまった。
一冊目。
あらためて読んでみようと図書館で借りた本があったけど、あまりの分厚さに(こりゃ…当分読めんなと)すぐに返しに行った先で出会ったのが、吉本ばななさんと平良アイリーンさん共著『ウニヒピリのおしゃべり』。

おふたりの対談には、生きてヒトに触れ合っているともれなくついてくる(といっていいだろう)リアルな摩擦が匂い立つ。そういうことってあるよね、という、いっときの寄る辺になってくれてありがたいのと、それらを自分のなかでどのように扱ってゆくのかのケーススタディ。
なにより、冒頭の短編小説には一気に引き込まれた。ウニヒピリ、つまり自分の中の小さな子は何をおもって、何を欲しがっているのか。
~むだなものがいちばんキラキラしていて、人生はそういうものを食べたがっているってわかってるんだ。」
ときたま思い出すように読みたくなるだろう、と思えたので返却後、自分用に一冊取り寄せた。
そして『ウニヒピリのおしゃべり』を借りるとき、そして返すときにも書架から「・・・・・・・・・」と無言の圧というか語りかけを感じ、導かれるように手に取ったのがこちら。

二冊目は、内田洋子さんの『モンテレッジオ 小さな村の旅する本屋の物語』。
著者がヴェネチアの古本屋を通じて知った村、モンテレッジオ。村の事情が知りたくて、村に近づこうとするのに、地理的にも時間的にも一筋縄ではいかない。
(取材の車のなかで、同行者のひとりが犬といっしょに走るトレラン大会のお知らせを出してくるくだりとかは、陽気に感じつつも、目的地に向かっているはずが行き先を見失いそうな心細さが綯い交ぜになる。著者ではないが、どこか懐かしい感覚)
「また、山か」「また、本か」。なかなかたどり着かない。膨大な山と、本と、歴史とが立ちはだかって呆然とする著者。
なにかを始めたとき、「あれ? おもったより工程も関係者も多いし、複雑? …え? ほんとにコレやるのわたし?」と、気付いたときの心象そのもので、身に覚えがある。
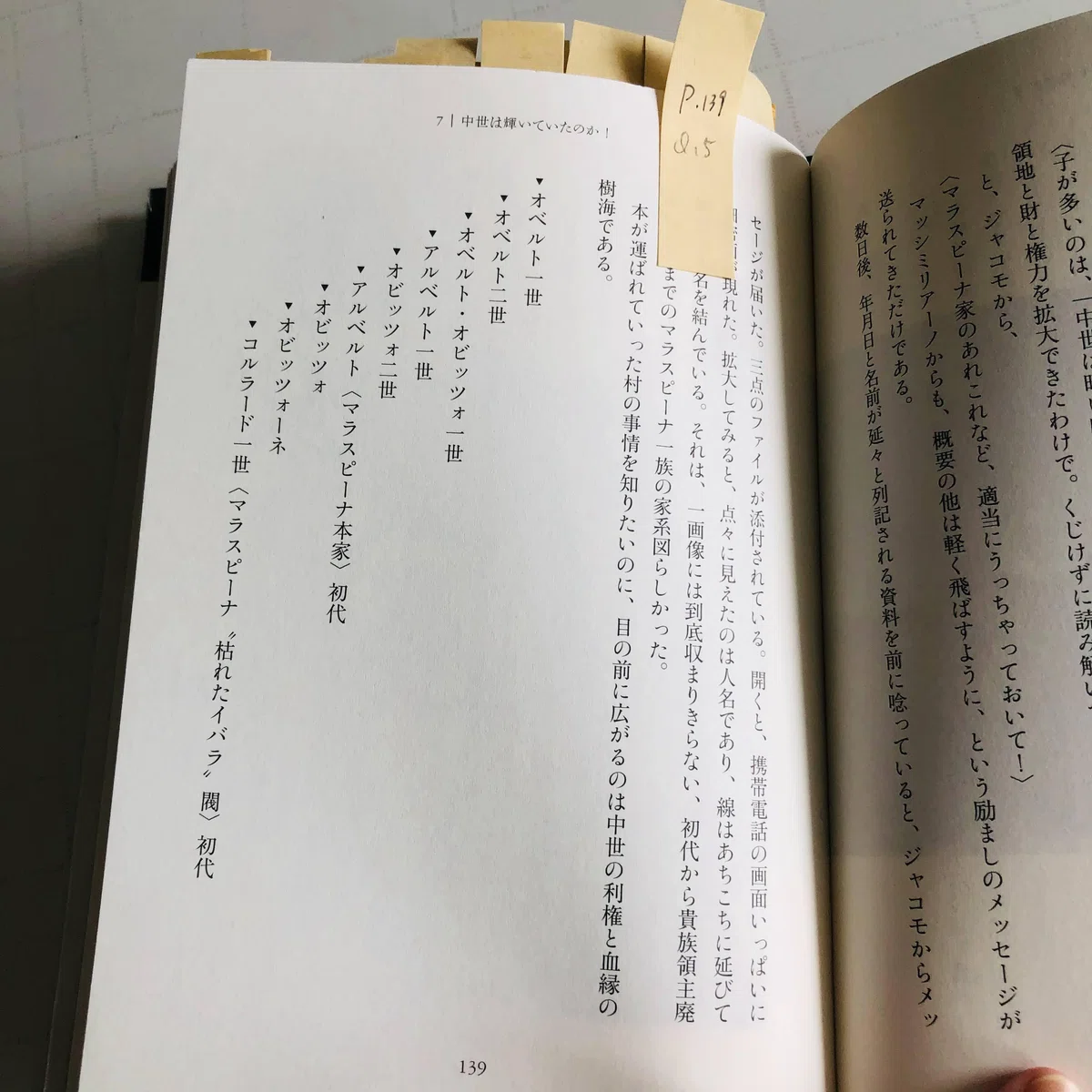


続きがとても気になりつつも、読了できず、「ここは」というところのメモを残して、一度返却した。続きは10章、【ナポレオンと密売人】からだ。
三冊目に挙げるのは、須賀敦子さんの『遠い朝の本たち』。

福岡で秋に開催される本のフェア、ブックオカ。期間中には参加する書店さんの店頭に『激オシ文庫』が並ぶ。選者は福岡の書店員と高校生のみなさん。
以前、新聞社にお勤めしていたころから仲良くしてもらっているライターの正井彩香さんがオススメされていたのでチョイス。
16のエッセイのうち、タイトルに惹かれてまず読み始めたのは『星と地球のあいだで』。この章では、サンテグジュペリの童話『星の王子さま』から、王子さまと狐とのエピソードが引かれていたり、アン・モロウ・リンドバーグの書いたものに揺りうごかされ、とあったり。どちらも自分の記憶の琴線に触れてくる。
須賀敦子さんの思い出話なのだけれど、読み進めていると、“遠い遠い、昔の子どもの憧れの世界”にスルスルと引き込まれる。
そのあと読んだのは、ひとつ前の章『葦の中の声』、ここにもリンドバーグ夫妻の冒険が出てくる。葦原のなかの息遣い、臨場感がものすごく伝わってきて、とても遠くに旅してる気分。これぞ読書の醍醐味。
須賀敦子さんが幼少期~学生時代を過ごした、ふたつのエリアのうち、ひとつがわたしの実家の近くで、見覚えのある街の名前や山の名前が、いくつかの章のなかにチラホラ出てくる。
わたしが暮らした時代とは違いすぎるのだけれど、もしかしたら、わたしの父母や伯父伯母たちの若いころと、袖の振り合いがあってもおかしくない距離感。
そのせいもあってか、著者の語りに耳を澄ませていると、、、絵本を慕って、大人たちに読み聞かせをねだっていた幼いころの自分までもが寄り添ってくるようであった。
須賀敦子さんも、『モンテレジッジオ』の内田洋子さんも、同じ関西のご出身で、それぞれ語学の勉強を志した人物、という偶然。こういう女性たちがおられることを、遅まきながらも知れて、ほんとよかった。読む前の自分と後の自分とでは、違う人間になってる、とおもえる読書だ。
須賀さんへのお目通りはもう叶わないけれど、内田洋子さんには、お目にかかるチャンスがあったら? 発したい言葉をまだ持たないけれど、わたしはとても喜ぶだろう。
四冊目、これはもう予約していたことを忘れたころに順番が来た本、『天才たちの日課 女性編 ー自由な彼女たちの必ずしも自由でない日常ー』。

全部で何人だったか、とにかくたくさん紹介されているうち、気になった14人分の作家のインタビューを拾い読みして、やはりいったん返却した。
『若草物語』の著者、ルイザ・メイ・オルコットは、“書き物着”を来ていたというエピソードがよかった。暮らしだ、書き手の暮らしがある。
ほか、エリザベス・ビショップという作家について、友人が語る内容もよかった。
「一篇の詩を書き上げるのに二十年もかけた」
「何日ものあいだ、一日中書いてばかりいたと思うと、そのあと何ヶ月も一行も書かなかったりする」
書くために、こうでなくてはならない、というスタイルはないのだとおもえる。
ほか、いずれの作家のエピソードも血の気が多そうだったり極端に少なそうだったり、変化に富んでいて、タイヘンだけど、みんな書いていたんだな。と、なんか安心した。途中で返しちゃったけど、一部でも読めてよかった。続きはまたいつか。
五冊目、これは別に記事を書いているけど、幸田文さんの『季節のかたみ』。
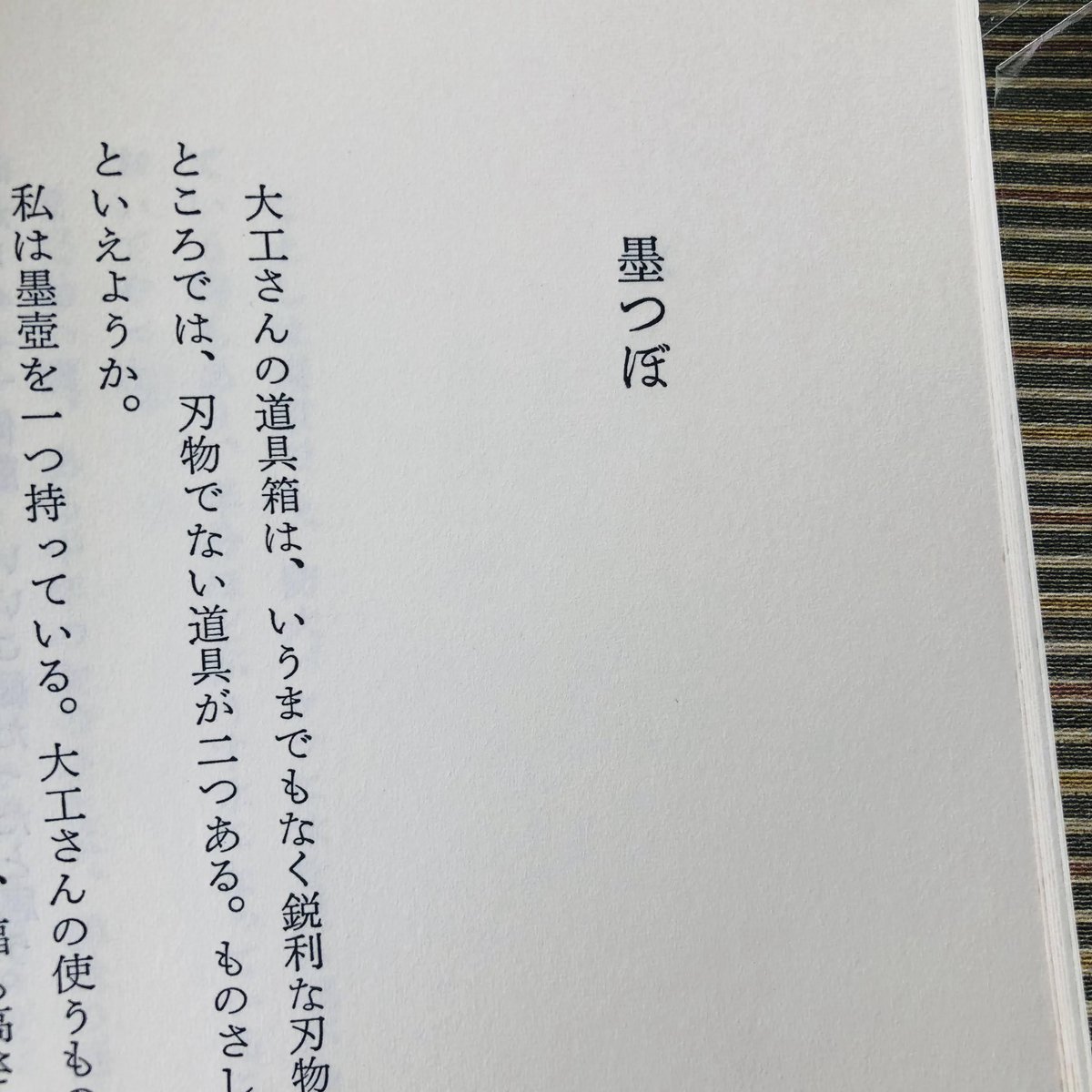
この、『墨つぼ』という章がとりわけ印象的だった。
(略)さしがね、ものさしは理であり、かりにも間違ってはいけないもの。でも、その理にはあくまでも従いながら、すみなわ(墨縄)には若干の情感があってもいいときく。
ちょうど、ある方のホロスコープを読ませてもらっているとき、バックグラウンドで読んでいたのがこの章。その方のチャートのなかでは、牡羊座の土星と金星の重なり(合)が際立っていて、まるでこの文章みたいだな、と、読み解きの参考にさせてもらうことになった。こういう巡り合わせはけっこうある。
ほかにも何冊かあるけれど、とくに読んでよかったものをピックアップしてみたら、女性作家の作品ばかり。自分はこういうところから栄養をもらって生きているのだ。
自ら書くなにごとかの文章であれ、チャート読みの文章起こしであれ、この作家のみなさんの残したもののように、広がりと深みのある世界を表せたらいいな。
途中になってるものは続きを読みたいし、来年はこういう記録を先にやってしまえる時間の使い方を身につけたい。やっぱ気、だよ、気の配り方。
星の一葉 ⁂ ほしのひとは
