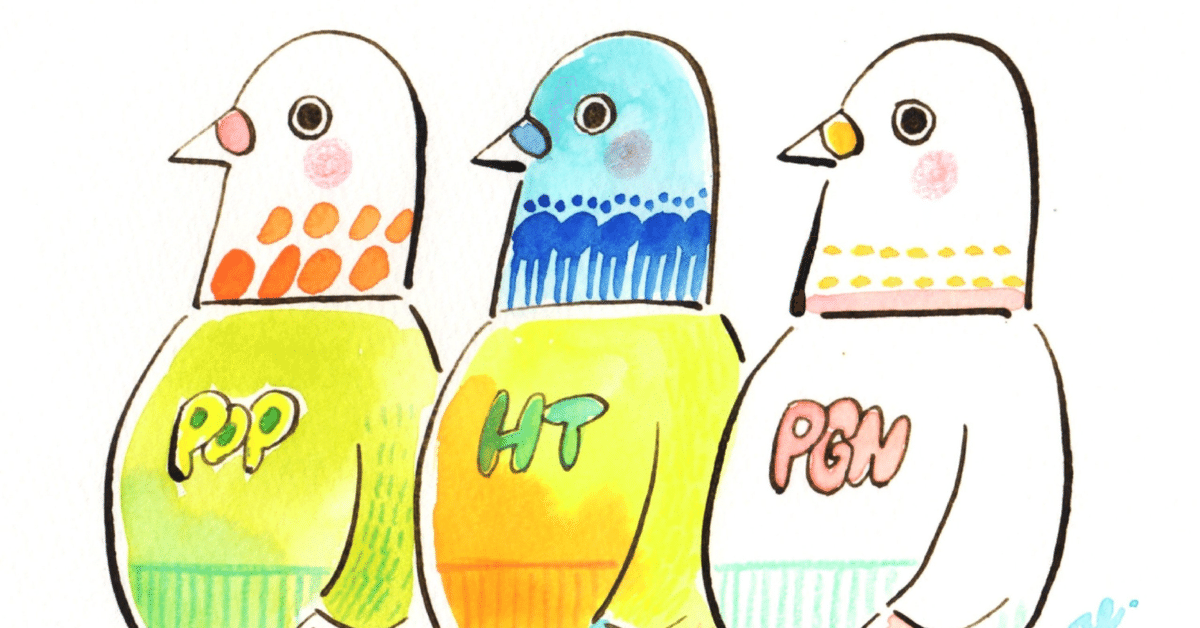
種明かしの「あざとさ」を、僕は残念に思う(映画「鳩の撃退法」を観て)
「映像化不可能な原作を映画化」
類似したキャッチコピーは腐るほどあるが、本作を観る限り、どこがどう困難を極めたものだったのかというのは皆目検討がつかない。
原作は佐藤正午さん、監督は「ホテル・ビーナス」のタカハタ秀太さんが務めている。
*
ミステリー作品の肝は、トリックを含めた構造設計および細部の作り込みだ。フィクションはたいてい物語が重視されるが、読み手の感情の浮き沈みまで細かくデザインするようなテクニックが何より求められる。
なので個人的には、話の面白さというよりも、いかに伏線が回収されていくかという点に醍醐味があって然るべきだと考えている。
本作も、そのセオリーに忠実に従っている。
緻密に時系列上の出来事を設置し、過去と未来を頻繁に行き来することで、留保事項をそれっぽく謎のままにしていくミステリー作品。
その辺りを前提におきつつ、僕が違和感を覚えたことについて書いていこうと思う。
*
謎は謎のまま、終盤にドカッと種明かしがされていく。
徹底的に謎らしきものを焦らし、極端に「分かりやすい」形で、種明かしを提示していく。
「いくらなんでも『いまから種明かしをします』って雰囲気があざとくないか?」というのが僕の正直な感想だ。ミステリー作品とはいえ、フィクションの最低限の要素は守らなければならない。(あえて破る場合は、それなりの意味づけが必要だ)
最低限の要素は守らなければならないのに、あまりに現実感を無視し過ぎてはいないか。リアリティに欠けるため、藤原竜也さん演じる津田の独り語りが、どこまでも嘘っぽく見えてしまう。
*
種明かしの不自然さで象徴的なのが、濱田岳さんが登場するシーン。彼が去った後に、こんな台詞が放たれる。
「彼がここに来たってことは、あなた(津田)がここにいることを倉田さんは知ってるってことだよね」
まあ、確かにこのセリフがあった方が分かりやすい。僕も「あ、確かにそうだな」と感じたのは事実だ。
だがそれって、あまりにもパズルのピースをくっきり組み立てるような描写の仕方ではないだろうか。
要するに「もっと自然に、意図を観る側に感じさせてよ」ということだ。現実からあまりに離れてしまう不自然な描写は違和感でしかないし、作品自体の格式を無意味に大衆化させるというデメリットにも繋がりそうだ。(※大衆化とは悪いことではないが、本作はどこか排他的というか、エクスクルーシビティを纏うべき作品ではないかと僕は感じている)
意図的なのだろうけど、観る者の心理状態を見透かしているような薄っぺらさを感じてしまう。もちろん観る者の心理状態を緻密に計算することは監督の責務なのだが、あたかも「計算してますよ」と言っているような「あざとさ」がどうしても気になってしまうのだ。
監督が、観る者を信頼していない。
原作を解釈しきれず、どうしたものか迷っている中で、つい過剰なサービスをしてしまったのではという印象を受けた。とても後味が悪い。
──
……かなり後ろ向きな言葉を並べてしまったが、もうひとつ致命的な問題がある。
ほとんどの役者が「何かの出演作品」の再生産に留まっていることだ。
たとえば倉田(演・豊川悦司さん)の子分、多々良を演じた駿河太郎さん。駿河太郎さんの演技は、他のバイオレンス系作品で観たことのある駿河太郎さんと何ら変わりがない。
言うまでもなく駿河太郎さんの力量のせいではない。監督や演出などスタッフ陣が、新しい試みを役者にさせることが全くできなかったに尽きる。
物語の構造をどう設計するか、伏線をどのようにデザインするかという、「策」に溺れた結果、物語を構成する「ひと」を蔑ろにしてしまったような。
救いは、物語序盤で出てきた石橋けいさん。主人公になされるがままに身体を委ねていくシーンの色香は見応えがあった。石橋けいさんの出演シーン以降の落差は残念だったが、ワンシーンだけでも美しい絵を観ることができて良かった。追い続けたい俳優のひとりになった。
(Netflixで観ました)
#映画
#映画レビュー
#映画感想文
#鳩の撃退法
#佐藤正午
#タカハタ秀太
#藤原竜也
#土屋太鳳
#風間俊介
#西野七瀬
#石橋けい
#Netflix
いいなと思ったら応援しよう!

