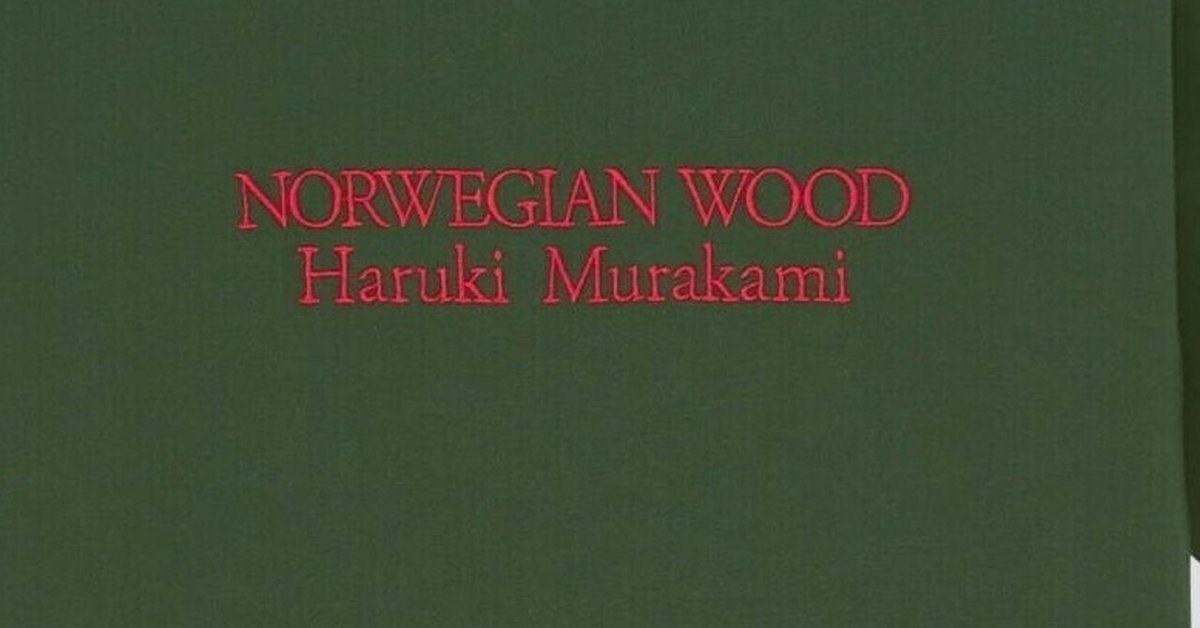
村上春樹の「ノルウェイの森」を再訪する(その1)〜「大学生が読むべき小説」か
先日、僕は平野啓一郎の「マチネの終わりに」について、村上春樹の「ノルウェイの森」(1987年講談社)と対比した。
「ノルウェイの森」の朧げな印象をもとに書いたのだが、久しぶりに読み返してみたくなった。そこで、Amazon Audibleに入っていた妻夫木聡の朗読を聴き始めた。
プロローグ的な第一章のあと、主人公であり語り手である“僕“、ワタナベ君が私立大学に入学、東京の学生寮に入って生活を開始する第二章から物語は本格的にスタートする。1967年の春の出来事であり、三十七歳のワタナベ君は当時を回想し、語り始める。
このワタナベ君が、多少なりとも村上春樹自身と重なっていることは明白である。本作に着手した当時、村上春樹は三十七歳である。聴き進みながら、大学生なら誰しもが感じること、あるいは周囲の知人の経験から間接的に考えさせられることが散りばめられていると思った。
それらは、おそらく村上自身も思ったことであろうし、彼の周囲に渦巻いていた思考だったろう。そのことを共有することは、今の大学生が生きていく上において有用なものではないか、「大学生が読むべき小説」の一つではないかと思ったのだ。
そんなふうに思いながら、僕はユニクロ製の“ノルウェイの森“ Tシャツを着て、近所の「立呑み 寅や」を訪れた。その日は、四十年前に同じ会社に入社した友人が、この酒場に来る予定だった。
既に呑んでいた友人は、僕のTシャツに気づき、こう話してくれた。かつて、娘さんがティーンエイジャーだったころ、「なにかお勧めの小説はないか」と訊ねられ、彼は「ノルウェイの森」を推した。しばらくして、娘さんから、「性的描写が多すぎ」と注意されたそうだ。
出版された1987年は、僕が二十六歳になる年で、その時は性的描写についてはあまり気にならなかった。多分友人も同じ印象だったから、十数年後に娘にリコメンドしたのだろう。
発表当時に、僕がこの小説から受けたことは大きく二つ。
一つ目は、“死“ということだ。身近に“死“というものを感じてこなかった僕だが、そのころに祖父母の死を含め、人間は死ぬということを実感し始めていた。さらに、父は食道がんに襲われ、五十代という若さで闘病生活に入った。
こうした僕の状況が、「ノルウェイの森」から受けたものを形成したのではないかと考えたが、本書の第二章には、次の一文が書かれ、紙の本を参照するとゴシック文字で印刷されていた。
<死は生の対極としてではなく、その一部として存在している。>(「ノルウェイの森」より)
二つ目は、「僕の好きな村上春樹はどこに行ってしまうのだろう」だった。「ノルウェイの森」はこうして再読するくらいだから好きな小説ではある。しかし、デビュー作から前長編作「世界の終わりとハードボイルドワンダーランド」(1985年)まで熱心に読んできた僕としては、本作は明らかに作風の違う小説であり、そのことに僕は戸惑った。同じように感じたファンを多かっただろう。一方で、本作は村上春樹の読者層を一気に拡大したことも確かである。
今、改めて本書を読むと、確かに性的描写は多いが、それはその後の村上作品にも通じるところである。そのことも含め、僕は「この小説を書かないと、著者は先に進めなかったのだろう」と感じたのだった。
その頃までに、村上春樹の中に蓄積していた思い、特に大学生だった頃のそれを、全部吐き出した。そのことによって、彼は新たなステージへと向かうことができた。「ノルウェイの森」には、そうしたことが込められていた、それ故、私の友人は娘に推薦し、私は「大学生が読むべき小説」だと考えたのだろう。
本文のために、講談社の「村上春樹全作品 1979−1989」第六巻を引っ張り出してきた。本書には、村上春樹が書いたリーフレットが挟み込まれている。
これがなかなか興味深かったので、明日はそれについて
(続く)

