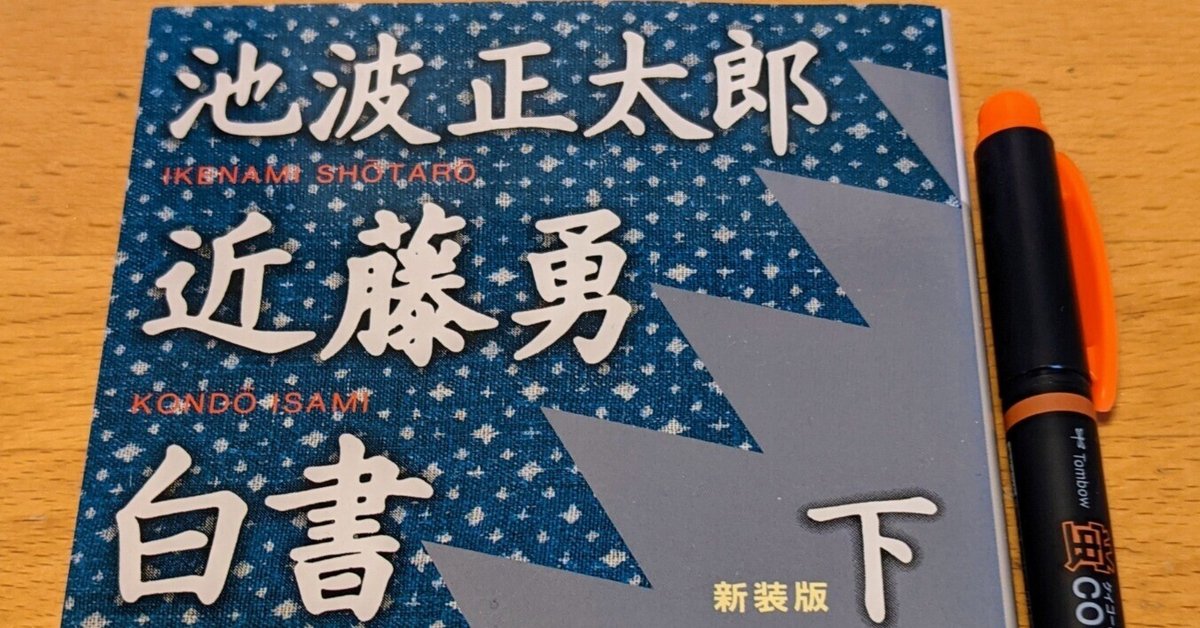
読書日記その542 「近藤勇白書 下」
うん、よかったッ!近藤勇の最期って描きかたによっては残念な印象になるので、本書ではどう終わるのか非常に興味があったのだ。その点で本書では、幕末を駆けぬけたひとりの漢(おとこ)の清々しい最期で終わっていてとてもよかった。
上巻では時勢の荒波へ乗り出し、突き進んでいくイキイキした姿。それとは対照的に、下巻は劣勢のなかで総長として苦悩する姿が描かれている。自分の信じた孝明天皇は崩御、将軍慶喜は政権を返上して京を去ってしまう。そのうえ伊東一派の残党によって勇は左肩に被弾するのだ。
この時すでに、新選組の隊士は半数が脱走してしまっている。これほどの劣勢と不運が重なれば、誰だってしょうすいしてしまうだろう。自分ではどうしようもないのだ。しかし勇はそんな劣勢の渦中でも、土方歳三や永倉新八を気にかけ、情のあることばをかけるところがこの男のもつ人間性なのだろう。
勇は、もと新選組・総長としての「過去」を、ずっしりと背負っている。この荷物は重い。きびしい重味であった。
この重い荷を捨て切れなかった人びとは、いやでも、徳川の栄光を、消えかかる残照の中に、ひたすら追いもとめてゆくことになる。
これは新選組あらため、甲陽鎮撫隊として巻きかえしをはかろうとしているときの本書の一文だ。勇も本心では逃げだしたかったにちがいない。また新選組をそのまま解散させることもできたはずだ。
しかし新選組・総長というずっしりと重い十字架を背負った勇は、その責任をまっとうするべく闘うのだ。その闘う相手は薩長でもあり、また自分との闘いでもあったであろう。
近藤勇の最期は、史料によって状況が異なるらしい。捕縛説もあれば投降説もある。大久保大和と名のることによって、わずかな可能性でも命を惜しんだのか、それとも時間稼ぎのために一貫してそう名のったのか。今となっては誰にもわからない。
そのため、近藤勇の最期の描き方はさまざまだ。ともすると描き方によっては残念な印象にもなりかねない。そのようななかで本書は、勇が歳三を逃がすための時間稼ぎとして、幽閉されたあとも大久保大和という名をつらぬき通すという描き方をしている。新選組・総長として、じつに漢らしく清々しい最期だ。
よくよく考えると、近藤勇という男は命をかけて朝敵と闘ってきたはずなのだ。それがだ。いつの間にか逆に自分が朝敵となって、賊徒として処刑されるのだよ。その間にどれほどの人間が勇を裏切り、去っていったことか。もはや男として、これほど愚直で哀しい生涯があろうか。
ボクは思うのだ。せめて小説のなかだけでも、威風堂々たる見事な生涯であってほしい。時代の荒波にほんろうされながらも、時には総長として、時にはひとりの人間として格闘する、どこか不器用だけど情にあつく憎めない男。ボクはそんな近藤勇が好きなんだなぁ〜
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
