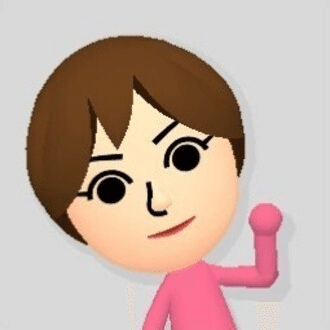解像度が高いの意味とは?〜「解像度を上げる」読書感想文
昨今、優秀なビジネスマンは"解像度が高い"という話を耳にしませんか?実際、解像度が高いとはどういう意味なのでしょうか。ビジネスマンの方は、なんとなくお分かりいただけるかもしれませんが、説明できる方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。
解像度を上げる思考法について説明された本「解像度を上げる」についてご紹介します。
こんな人におすすめ
起業したての人(起業を目指している人)
大企業の新規事業部門に所属している人
マーケティング部門の担当者
営業担当者
本の要約
「解像度が高い」とは
相手の持つ課題を時間軸を考慮に入れながら、深く広く構造的に捉えて、その課題に最も効果的な解決策を提供できていること。
解像度が高い人が持っている4つの視点
その解像度の高さが何によって構成されているか。→深さ・広さ・構造・時間の4つの視点で構成されている。
課題の深さ
課題の広さ
課題の構造
時間
1、課題の深さ
深さがなければ、課題を考える時も何が根本的な問題であるかが分からない。
例)売上が下がっているという課題を考えるとき、顧客数が減っているのか、 単価が下がっているのか、顧客あたりの購入頻度が下がっているのか…などの課題の原因の深掘りが必要。
2、課題の広さ
様々な物事を広く知っていて、美味しさを惹きつけることができる人は解像度の高い人。広く原因を把握し、異なるアプローチや視点を幅広く検討することで、元々考えていたのとは別のところにある原因や可能性に気づくことができる。
例)なぜその料理が美味しいかについて、それぞれの店の料理の特徴と比較する。
3、課題の構造
それぞれの事例の共通する部分はどこで違いは何なのか、どういった関係性にあり、その中でも最も重要なのはどれで、それはなぜなのか、を理解していなければ、それらの事例から新しい洞察を導くことはできない
解像度が低いとは、課題の深さが足りない場合が多い
例えば、スタートアップの新しい製品に関して、顧客の課題についてはほとんど掘り下げられていない場合が多く、解決策となる製品の内容もふわっとしているアイデアの提案は、かなり頻繁にある。
深さをチェックするには、5W1Hや6W3Hで分解し、具体的に説明できるかどうかをチェックしてみることをおすすめする。
ある程度の情報と思考力さえあれば、行動することで解像度は間違いなく上がる。一方、企業としての良いアイデアにたどり着けなかった人や大企業の新規事業でうまくいかなかった人は、情報・思考・行動の量と質(特に行動)が足りなかった人が多い。
解像度を高くするコツ
情報と思考に行動が組み合わさると優れた成果を獲得できる。ビジネス教育を受けた人がきちんと行動すると、そうでもない人たちが行動するよりも、その後のビジネスはうまくいきやすいことが過去の研究で指摘されている。情報を得たらすぐに思考→思考したらすぐに行動→行動して情報を得たらまた深く思考する…これを短時間で繰り返すことが解像度を上げるコツ。
ビジネスで上げるべき解像度は、課題と解決策。解像度は高ければ高いほど良いというわけではない。どの程度の解像度が必要かどうかは、最終的にどのような問いに答えたいか、つまり目的によって異なる。
解像度を上げたい時にはきちんと文にすることをおすすめする。また、主語が大きなもの(例えば、「日本人は」「男は」)といった大きな主語の利用にはかなり注意が必要。
課題が重要視される理由
製品やサービスから顧客が得られるメリットや満足感という価値と定義すると、何かに取りくもうとした時には、どの課題を選ぶかによって生み出される価値は大きく変わる。課題や問いが重要視される理由は、いい課題を選べるかどうかで生み出される価値がほぼ決まる、と言っても過言ではないから。
ただし、解決策が課題を完璧以上に解決していたとしても、課題の大きさ以上の価値は生まれない。つまり、解決策が課題に対して、オーバースペックであってもそのオーバーしている部分に追加のお金を払ってくれる人はほとんどいない。
いい課題の3つの条件
大きな課題である
大きな課題に挑むことは思っている以上に勝率が高い場合も多い。 誰もが目をそらしていて競合が少ないため、競合に勝つことをそこまで考えなくても良くなる。そして意義のある大きな課題に挑むことで、手伝ってくれる優秀な人も多くなる。合理的なコストで現在解決しうる課題である
課題を工夫すれば低いコストの解決策で価値を高める場合もある。実績を作れる小さな課題に分けられる
大きな課題を特定したら解決可能な小さな課題に分解し、その中でも大きな影響をもたらす課題に取り組む。解決可能な課題に分割できるかどうか。
症状ではなく病気の原因に注目する
他社と差別化ができるポイントはそうした誰でも手に入るデータではなく少数の人しか持っていない、顧客への課題の洞察が重要なポイント。顧客よりも顧客の課題のことを深く知っているカスタマーマニアになれているかどうか。
いい解決策の3条件
課題を十分に解決できる
合理的なコストで現在実現できる解決策
ほかの解決策に比べて優れている
特に3については、顧客が購入する際の選択肢を把握していることが大事。顧客が複数の評価軸で十分に課題を解決できており、総合的に優れている必要がある。いい解決策として評価されるには 顧客の重視する何らかの評価軸で買った上で、他の評価軸でも十分に評価される必要がある。
以下は私の感想です。
顧客の周りのことを知らなければ課題も見つからない
消臭力のCMを手がけた方として有名な鹿毛さん。日経クロストレンドの記事で紹介されていました。鹿毛さんは、お客様を理解することについて提唱されています。(著書:「心」が分かるとモノが売れる)
この本を読みながら、鹿毛さんが本で仰っていたことを思い出しました。過去noteイベントに登壇されていたので、よろしければ、そちらもご覧ください。
今ネットでもSNSでも、お客様の声はたくさん拾える時代です。けれど、ネットやSNSにないお客様の声も存在します。ネットやSNSであれば誰でも声を拾うことはできるけれど、ネットやSNSに存在しない声を拾うことは、そのお客様と向き合っている人(会社)にしか分かりません。
そうしたお客様の声を聞きながら、自社の商品やサービスの課題をまず見つけていくことで、解決策が見えてくる。と復習することができました。
合わせて読みたい
課題や解決策を考える上で参考になるフォーマットがあります。本で紹介されていた、amazonのプレスリリースのフォーマットです。「コンサル道具箱」さんのnote記事でも紹介されていました。
似たような結論が書かれていた本をいくつかご紹介。
ほかSNSでも、ぜひ繋がりましょう!
・X:https://twitter.com/ichito0123
・Treads:https://www.threads.net/@ichito0123
・Podcast「日常を旅するラジオ」https://note.com/nichitabi
いいなと思ったら応援しよう!