
ライプニッツ『モナドロジー』試論
はじめに
本稿では,ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ(Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646–1716)の手稿『モナドロジー』(Monadologie, 1714)を,エルトマン版(1839年)とゲルハルト版(1885年)のフランス語原文で確認しつつ,この手稿が最初に出版されたドイツ語訳であるケーラー訳(1720年)とも比較対照しながら,最新の邦訳である谷川多佳子・岡部英男訳(2019年)に従って読み解いていく.
ライプニッツのいわゆる『モナドロジー』
今日いわゆる『モナドロジー』(Monadologie)というタイトルで知られているライプニッツの手稿がある.フランス語で書かれたその手稿は,ライプニッツ没後にそのドイツ語訳が世に出るまでの間は,彼の親しい知人たちの間で読まれていたに過ぎない*1.
いわゆる『モナドロジー』というタイトルの名付け親は,ハインリッヒ・ケーラー(Heinrich Köhler)のドイツ語訳に遡ることができる.1720年にケーラーはいわゆる『モナドロジー』初稿のドイツ語訳を『〈モナドロジー〉に関する教説』(Lehr-Sätze über die MONADOLOGIE, 1720)というタイトルで出版している.今日この手稿がいわゆる『モナドロジー』と呼ばれる所以は,このケーラー訳のタイトルに基づいているのである*2.


谷川多佳子・岡部英男は『モナドロジー』(岩波文庫)の「訳者あとがき」で,「『モナドロジー』のフランス語原文が初めて刊行されるのは,一八四〇年のエルトマン版著作集のなかである」(228頁)と書いている.しかしながら,筆者がGoogleブックスで調べてみたところ,それが実は1839年に出版されていたことがわかった.この点についてもう少し詳しく述べておこう.

まずエルトマン版著作集の第一部(PARS PRIOR)は確かに1840年(MDCCCXL)に出版されている.しかしながら,『モナドロジー』が収録されているのは,エルトマン版著作集の第二部(PARS ALTERA)であり,第二部は第一部よりも先に1839年(MDCCCXXXIX)に出版されているのである.『モナドロジー』は,エルトマン版著作集の第二部705頁以下に収められている.

ライプニッツ研究者が参照するライプニッツ著作集は主にゲルハルト版である.しかしながら,筆者が『ゲルハルト版には誤植があるのではないか』という疑念を抱いたことから,ゲルハルト版に先行して最初にフランス語版『モナドロジー』を掲載したエルトマン版をGoogleブックスを通じて確認したところ,上述のことが明らかとなった.一次資料を確認する重要性については,これ以上言うまでもないであろう.

§1. 「単純な実体」としての「モナド」
(1)エルトマン版(1839年)

(2)ゲルハルト版(1885年)

1 私たちがここで論じるモナドとは,複合体のなかに入る単純な実体に他ならない.単純とは,部分がないことだ.
一瞥して分かる通り,ゲルハルト版にある隔字体の強調が,エルトマン版には存在しない.ゲルハルト版の強調は,後に見るケーラー訳の強調部分と近い(が違う箇所もある).
「諸々の複合体 composés」「単純 simple」「実体 substance」 「諸部分 parties」,これらはいずれも「モナド Monade」を理解するための重要なキータームである.「モナド」という「単純な実体」が「諸部分なしに sans parties」存在するということは,すなわち「モナド」が諸々の「複合体」を構成する要素とはなり得ても,「モナド」それ自体が「複合体」ではないことを意味している.
この箇所はケーラー訳では次のようになっている.


§1 私たちがここで語ることになる〈モナド〉とは単純な実体に他ならず,これによって複合物または複合体 composita は成立する.「単純な」という語の下に解されるのは,部分を持たないそれである.
ケーラー訳は,上のゲルハルト版と文意は同じだが,冒頭の「モナド Monaden」は複数形になっており,「単純な実体 einfache Substanzen」という箇所に強調が入っている.“composita”(羅)は“compositus”の中性複数主格である.これらの語はケーラーの解釈よって複数形へと翻訳されたのかもしれないが,他方でライプニッツ自身がフランス語では「モナド」を単数形で記述していることの意味についてはしっかりと考えなければならないであろう.
ここでケーラーは「モナド」に次のような注を付けている.


(a)〈モナド Monade〉 或いは〈モナス Monas〉という語は,周知の通りギリシャ語〔のμονάς〕に由来し,これは本来は〈一者 Eines〉を意味する.この語を残しているのは,イギリスやフランスの慣習に従い,諸々の造語を短音節の簡潔さのために残しておき,ドイツ語の語尾でいわば自然化する naturalisiren 高尚な学者を先蹤としているからである.セレナーデ〔serenata〕やカンタータ〔cantata〕,エレメント〔element〕のような語を,疎遠な外国語であるにもかかわらずドイツ語に無数に残している以上,短音節の簡潔な表現のために〈モナド Monade〉という語やその他同様の造語を私が用いても,それが不便な inconvenient 取り扱いを受けるわけではないと私は信じている.多数のものはまだ通例ではないが故に当初は音韻を踏まえていないように見えるのだが.しかし通例でないものが合理的な原因を根拠として持つならば,それが音韻を踏まえていないとみなされることはできないと私は考える.
「モナス μονάς」というギリシア語については,ライプニッツ自身が『モナドロジー』と同年に著した『理性に基づく自然と恩寵の原理(1714年)』(Principes de la Nature et de la Grace, fondés en raison, 1714)の中で言及していた*3.ケーラーは「モナド」という造語が,ギリシア語の「モナス」を語源とするのみならず,その音韻のレベルで連続性を保っていることを指摘している.このような指摘が行われているのは,「モナド」という音韻がドイツ語としては「通例ではない ungewöhnliche」,そしてどこか違和感を感じるようなものであるからだろう.だが「モナド」という音韻には,使用に堪えうるだけの「合理的な原因 vernünfftige Ursache」が十分に備わっているとケーラーは述べているのである.
§2. 「単純な実体」の〈集合〉としての「複合体」
(1)エルトマン版(1839年)

(2)ゲルハルト版(1885年)

2 複合体があるからには,単純な実体がなくてはならない.複合体とは,単純な実体の集まりないし集合 aggregatum に他ならないのである.
ここでは「集合 aggregatum」(“aggregatum”(羅)は“aggregatus”の男性単数対格)という言葉だけが隔字体で強調されている.この「集合」とは,数多くの「単純な実体」が群れのように集まって一つのかたまりを形成しているようなイメージであろう.
(谷川・岡部訳では«car»が訳出されていないが)「というのも car」以下の文は,その直前の「複合体があるからには,単純な実体がなくてはならない」という文の論理的な理由を示している.すなわち,「複合体があるからには,単純な実体がなくてはならない」という推論が成立するためには別の前提を必要とする.その前提とは,「複合体とは,単純な実体の集まりないし〈集合〉に他ならない」ということである.
ライプニッツにとって「単純なもの」という存在が「複合的なもの」を成立させる構成要素であるということは,『理性に基づく自然と恩寵の原理(1714年)』(Principes de la Nature et de la Grace, fondés en raison, 1714)では次のように述べられている.

複合的なもの,すなわち物体は,多である.そして単純な実体,生命,魂,精神は,一である.単純な実体は至るところにあるはずだ.なぜなら,単純なものがなければ,複合的なものもありはしないだろうから.したがって,自然全体は生命に満ちている.
ここで「単純な実体」が「生命,魂,精神」であり,「複合的なもの」が「物体」とされていることから,ライプニッツはある種の〈物心二原論〉を展開していると言えるだろう.加えてここでライプニッツは「単純な実体」と「複合体」の関係を,「一」と「多」の関係として捉えているが,両者は矛盾する対立概念というよりは,むしろ同一の存在が有している二つの側面として理解されるべきなのかもしれない.
この箇所はケーラー訳では次のように訳されている.

§2 複合体 composita があるからには,そうした単純な実体がなくてはならない.というのも,複合物とは,単純な実体のひとつの集合または総和 Aggregat に他ならないからである.
„Menge“というドイツ語は,数学上の概念としては「集合」を意味する.もしかするとケーラーは,ライプニッツが数学を得意とする万能人だったことを考慮しつつ,„Menge“という訳語を用いることによって,そこに数学上の含意を持たせたのかもしれない.
§3. 〈事物の要素〉としての「モナド」
(1)エルトマン版(1839年)

(2)ゲルハルト版(1885年)
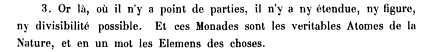
3 さて,部分がないところには,拡がり〔延長〕も,形も,可分性もない.そしてこうしたモナドは,自然の真の原子であり,ひとことで言えば事物の要素である.
ここでライプニッツは「モナド」を「自然の真の原子」だと述べている.いわゆる原子論の言説は,それ以上分割できない極小の「原子」からあらゆる事物が構成されているというものである.これに対して,ライプニッツの「モナド」は,それが部分を持たないがゆえに「可分性 divisibilité possible」を持たないという点で,いわゆる原子論における「原子」と同じ特徴を兼ね備えている.しかしながら,「モナド」はそれにとどまらず,「拡がり〔延長〕も,形も」ないのであるから,原子論のようにそれ以上分割できないものではなく,その自然本性からして分割できないものである.これこそがここで「モナド」が「自然の真の原子」といわれる所以であり,原子論における「原子」と異なっている点である.
この箇所はケーラー訳では次のように翻訳されている.


§3 さて,部分がないところには,縦・横・奥行きの拡がり〔延長〕も,形も,可分性もない.そしてこうしたモナドは,自然の真の原子 Atomi であり,ひとことで言えば事物の要素である.
ケーラー訳は,「拡がり〔延長〕 étendue」を,より詳しく三次元の空間として「縦・横・奥行きの拡がり〔延長〕 eine Ausdehnung in die Länge, Breite und Tieffe」と訳している.ケーラーによるこの補訳は適切である.というのも,「モナド」が三次元空間上に存在する物体とは次元の異なるものであるということが,ここでのライプニッツの主張だからである.
(つづく)
注
*1: 「ライプニッツが,いわゆる『モナドロジー』の出来映えに満足していなかったとは思えない.その証拠に,最初の草稿を親しい知人には見せている.だがそれを刊行するつもりはなく,最後まで手元に置いていた.」(ライプニッツ2019: 227).
*2: 「いわゆる『モナドロジー』が公刊されるのはライプニッツの死(一七一六)後まもなくであったが,それはフランス語原文ではなくドイツ語訳とラテン語訳であった.ハインリッヒ・ケーラーは一七一四年夏にライプニッツ自身から(最終稿ではなく)最初の草稿を入手し,一七二〇年ドイツ語訳を『モナドロジー』という表題で出版した.おそらくドイツ語訳をもとにしたであろうラテン語訳が現れるのは一七二一年の『(ライプツィヒ)学術紀要・補巻』誌上で,それには「モナドロジー」ではなく『哲学の原理』という表題が付されていた(ケーラーによる独訳は九〇ではなく九二の節,ラテン語訳は九三の節からできている).」(ライプニッツ2019: 228).
*3: 「モナスというのはギリシア語であり,「一」もしくは「一なるもの」を意味している.」(Leibniz1885: 598,谷川・岡部訳77頁).
文献
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
