
ルソー『言語起源論』を読む
はじめに
本稿では,ジャン゠ジャック・ルソー(Jean-Jacques Rousseau, 1712–1778)の手稿『言語起源論』(Essai sur l'origine des langues, 1781)の読解を試みる.
ルソーの『言語起源論』は死後出版であった.「訳者解説」によれば,この著作が書かれた時期は1750年代後半から1762年前半にかけてであったという(ルソー2016:138).
ルソー『言語起源論』
第一章 われわれの考えを伝えるためのさまざまな方法について
まず第一章では,タイトルにある通り「われわれの考えを伝えるためのさまざまな方法」が考察される.ここから言語とは考えを伝えるための手段であるということがわかる.しかしながら,興味深いことに,『言語起源論』の最終章である第二十章「言語と政体の関係」では,近代人が言語によってはその内容を上手く伝えることができない様が描かれている.つまり,『言語起源論』は,いかにして考えを伝えるのかの考察から始まって,いかに考えが伝わらないかという考察で終わるという,いわば逆説的な構成になっているのである.

われわれが他者の感覚に影響を与えうる一般的な方法は二つだけ,つまり動作と声だけである.動作の作用は触覚を通じて直接的なものとなるか,そうでなければ身振りを通じて間接的なものとなる.前者〔動作の作用〕は腕の長さが限界となっているので遠くに伝えられないが,後者〔身振りの作用〕は視線と同じくらい遠くに達する.そのように,散らばった人々の間での言語の受動的な器官としては視覚と聴覚しか残らない.
このパラグラフを表にまとめるとこんな感じだろうか.

ルソーは先の引用文で「われわれが他者の感覚に影響を与えうる一般的な方法は二つだけ」だと述べているが,そもそも章タイトルは「さまざまな方法について divers moyens」となっていたので,考察されるのが「二つだけ」では少ない.上の表で示したように,訴求される感覚別にみると,人間のコミュニケーション方法は大きく分けて三つ(「触覚」に向けてなのか,「視覚」に向けてなのか,「聴覚」に向けてなのか)である.
ルソーはこの第一章で「動作」を通じての言語コミュニケーションについて考察した上で,以降の章では「声」を通じての言語コミュニケーションの考察に入っていく.
第二章 ことばの最初の発明は欲求に由来するのではなく,情念に由来するということ
第二章の冒頭でルソーは「それ故,欲求が最初の身振りを語らせ,情念が最初の声を引き出した,と考えるべきである」(増田訳23頁)と述べている.これはほとんど「言語の起源とは何か」という問いに対する答えであるように思われる.第一章で見たように,「われわれが他者の感覚に影響を与えうる一般的な方法は二つだけ,つまり動作と声だけである」(増田訳12頁)とされていた.この区別に従うと,「動作」としてのことば(ボディランゲージ)の起源は「欲求」であり,「声」(パロール)としてのことばの起源は「情念」だということになる.
われわれに知られている最も古い言語であるオリエントの諸言語の精髄は,その形成において想像される学術的な歩みとは相いれない.それらの言語は,方法的で理論的なものが何もない.その諸言語は,生き生きとしていて比喩に富んでいる.最初の人間の言語を幾何学者の言語のようなものとする人がいるが,詩人の言語だったことがわかる.
ここで「オリエントの諸言語」と呼ばれているものが具体的に何を指しているのか,私にはよく分からない*1.とはいえ,その「オリエントの諸言語」は「最も古い言語である」とされる.現代の私たちが言語を新たに学ぼうとするとき,基本的には単語と文法によって学ぶであろう.しかし,その最古の言語は「方法的で理論的なものが何もない」.つまりそこには文法と呼ばれるような言語の理論がないという.最初の言語は「詩人の言語」であり「比喩に富んでいる」.この点については,次の第三章「最初の言語は比喩的なものだったにちがいないということ」で展開されることになる.
そこで「欲求」と「情念」がもたらす効果が考察される.「欲求」とは「飢えや渇き」などの生きるために必要なものであり,「情念」とは「愛,憎しみ,憐憫の情,怒り」(増田訳24頁)などの感情のことである.「欲求」は人々を遠ざけるが,「情念」は人々を近づけるとされる.

それはそうであったにちがいない.人はまず考えたのではなく,まず感じたのだ.人間はその欲求を表現するためにことばを発明したと主張する人々がいる.この意見は支持できないように思われる.最初の欲求の自然な効果は,人々を近づけることではなく、遠ざけることだった.種〔人類〕が広まり,すばやく地球全体に人が住むようになるにはそうでなければならなかった.そうでなければ,人類は地球の一隅に寄せ集まり,残りの全体が荒野のままだっただろう.
ここで言語の起源を考察する際に,ルソーは「思考」よりも「感性」が先行する点を考慮している.この点について私は個人的にはフォイエルバッハの著作(「哲学改革のための暫定的命題」など)を思い出さずにはいられない(が,今は立ち入らないことにする).
それはともかく,ルソーは「人間はその欲求を表現するためにことばを発明した」という主張を斥ける.一体何故であろうか.
そもそも「欲求」や「情念」といったものが人々を遠ざけたり,近づけたりするものだろうか,と私は疑問に思う.人々が互いに遠のいたり近づいたりするのは,場の要素(あるいは経済性とでも言おうか)が大きいのではないだろうか.衣食住を確保できるのは,土地柄(気候や風土)も関係していると思われるからである.人はどこにでも住めるわけではないのである.

生きる必要によって互いに避け合う人間たちを,すべての情念が近づける.
確かに「情念」はルソーの考えるように人々を近づけるかもしれない.だが,「情念」をこじらせてしまうと,近づこうとする相手がかえって離れていくこともあるかもしれない.
第三章 最初の言語は比喩的なものだったにちがいないということ
ルソーによれば,最初の言語は「詩」だったという.
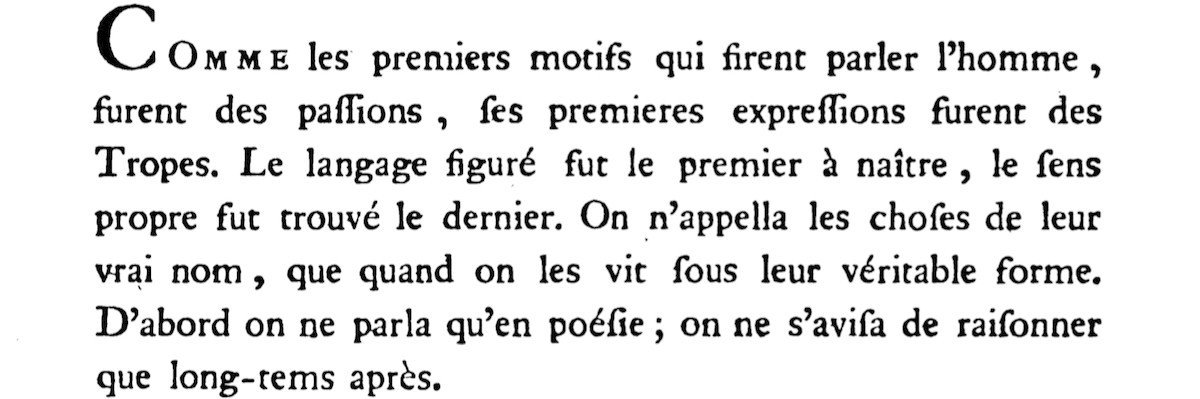
人間がことばを話す最初の動機となったのは情念だったので,人間の最初の表現は文彩だった.比喩的なことばづかいは最初に生まれ,本来の意味は最後に見いだされた.事物は,人々がその真の姿でそれを見てから,初めて本当の名前で呼ばれた.人はまず詩でしか話さなかった.理論的に話すことが考えられたのはかなり後のことである.
ここでは«Tropes»に「文彩」の訳語が採用されている.修辞学の伝統においては«Trope»は「転義(法)」と訳されてきた.他方,«figure»は「文彩」や「比喩」と訳されてきた.内容的には,この章でルソーが「比喩的なことばづかい la langage figuré」について論じていることを考慮すると,ここで«Tropes»を「転義(法)」*2と訳しても良いのではないだろうか.«raisonner»も「理論的に」というよりは「理屈で」という感じではないだろうか.「理論的」と訳すと,その対として「実践的」が想起されるのだが,ここではそうではないであろうから.

こうして情念がわれわれの目をくらませ,情念によって与えられる最初の観念が真理のものではないとき,比喩的〔フィギュレ〕な語は本来の語よりも先に誕生する.私が語や名前について言ってきたことは,言い回しについても何の問題もない.情念によって提示された幻想のイメージは最初に示されるので,それに対応する言語も最初に発明された.精神が啓蒙されその最初の間違いを認め,誤りを生み出したのと同じ情念でのみそれらの表現を使うようになり,その言語はそれから比喩的〔メタフォリック〕なものになった.
ここで«figuré»と«métaphorique»はどちらも「比喩的」と訳されているが,本来であれば両者を区別して後者(métaphorique)を「隠喩的」と訳すべきであろう.両者を混同してしまっては,それこそルソーの「文彩(ことばのあや)」を理解できなくなってしまうおそれがあるからである.少なくとも「隠喩」は修辞学の伝統において厳密に取り扱われてきたのであり,その区別はアリストテレス『詩学』にまで遡ることができる*3.
情念により不明な対象に対して抱かれた最初の観念によって付けられた名前が,その内実が明らかになるや否や実は不適切な名前だったことがわかり,訂正されて言葉が差し替えられる.初期の言語に見られるこのような言葉の転用から,最初の言語は「比喩的なものになった」とルソーはいう.
この箇所をよく読むと,〈比喩的な言語〉よりも前の段階として,情念によってもたらされた間違った観念に基づく暫定的な言語こそが最初の言語であったことがわかる.〈比喩的な言語〉が可能となるのは,その表現が誤りだと気づいてからのことであり,誤りだと気づくまでは誤りは認識されていないのだから,話者にとってその表現は比喩ではなかったはずである.まさしく「その言語はそれから比喩的なものになった」のである.比喩的な言語以前の原初的な言語は,情念がもたらした最初の観念によって発明された言語であり,いわば〈情念的な言語〉であろう.
このことを表で示すと以下のようになる.

時間軸として見れば,システム1(情念的)からシステム2(理性的)へと移行する.システム1は情念によってイメージが喚起されることによるものである.システム1の段階での判断は最速だが,ゆえに誤りが伴う可能性を常に秘めている.これに対してシステム2はシステム1の検証に基づく(エラー訂正的な)判断である.システム2はシステム1の後にやってくるため遅行性だが,理性的である.
第四章 最初の言語の特徴的性質,およびその言語がこうむったはずの変化について
ルソーは初期の言語の特徴を音の未分節の側面から考察する.

自然の声は分節されないので,語は分節が少ないだろう.間に置かれたいくつかの子音は,それによって母音の衝突が解消され,母音が流暢で発音しやすくなるのに十分だろう.逆に音は非常に多様で,抑揚の多様性によって同じ声が何倍にも増すだろう.音長やリズムが別の組み合わせのもとになるだろう.つまり自然のものである声,音,抑揚,諧調は,協約によるものである分節が働く余地をあまり残さず,人は話すというよりは歌うようなものになるだろう.語根となる語はたいてい模倣的な音で,情念の抑揚か,感知可能な事物の効果であるだろう.擬音語がたえず感じられるだろう.
この辺りは,言語と音楽の起源が同一という第十二章「音楽の起源」におけるルソーの主張につながってくる.
第五章 文字表記について

文字表記は言語を固定するはずのものと思われるがまさに言語を変質させるものだ.文字表記は言語の語ではなくその精髄を変えてしまう.文字表記は表現を正確さに置き換えてしまう.人は話す時には感情を表し,書く時には観念を表すものだ.
エクリチュールは正確さの面では優れているが,しかし同時にパロールがもっていた感情表現を失ってしまう.
エクリチュールとパロールのこのような違いは,次章でみるホメロスの詩の朗読者(アオイドスとラプソドス)の話にも関係してくる.音楽との関連で言えば,楽譜によって内容が固定化され作曲者によって楽曲が管理されるようになった近代音楽が言語同様に生気を失っていくことに似ているかもしれない.
第六章 ホメロスが文字を書けた可能性が高いかどうか
第六章ではホメロスが取り上げられている.というのは,『イリアス』と『オデュッセイア』に代表されるホメロスの著作こそが現存する最初期のエクリチュールであり,言語の起源をめぐる議論において,現存する最初期のエクリチュールを取り扱わないわけにはいかないであろうから.
さて,現代のホメロス学の観点から言えば,ルソーの述べていることは,ホメロス学の通説的見解とさほど変わらないかもしれない.しかし,ルソーの時代におけるホメロス学の観点から言えば,どうだろうか.ルソーは何か彼の時代において,彼独自の見解を示してはいないのだろうか.

『イリアス』が書かれたのなら,それが歌われることははるかに少なかっただろうし,吟遊詩人たち〔ラプソドス〕は求められることも少なく,それほど増えなかっただろう.ヴェネチアにおけるタッソー以外,これほど歌われた詩人はほかにいない,しかも〔タッソーの場合は〕あまり本を読まないゴンドラの船頭たちによって〔歌われたの〕だ.
ヴァルター・ブルケルト(Walter Burkert, 1931–2015)の提唱以来,古代ギリシアのラプソドスとアオイドスとは区別されている(Burkert1987=2001).ブルケルトによれば,文字がない時代の詩の朗読者をアオイドス(ἀοιδός、吟遊詩人)と呼び,文字ができてからの朗読者のことをラプソドス(ῥαψῳδός,吟誦詩人または吟唱詩人)と呼ぶ.両者は似ているが,ラプソドスは(文字が書かれたものに基づいた上演であるが故に)創造的な口承詩人ではなかったとされる*4.増田訳では"les Rhapsodes"は「吟遊詩人たち」と訳されているが,ここはむしろ「吟誦詩人(吟唱詩人)」と訳すべきではないか.
また内容を理解するのには差し支えない些末なことであるが,「ヴェネチアにおけるタッソー」とは,訳注にある通り叙事詩人トルクァート・タッソー(Torquato Tasso, 1544–1595)のことである.ゴンドラの船頭たちによって歌われたと思われる彼の詩には『解放されたエルサレム』(La Gerusalemme liberata, 1581)という叙事詩がある.この叙事詩に基づく楽曲やオペラ,絵画がいくつも作られてきた.例えば,フランツ・リスト(Franz Liszt, 1811–1886)の曲に『タッソー,悲劇と勝利』(Tasso, lamento e trionfo)がある.リストはかつてヴェネチアでゴンドラの船頭がタッソーの「解放されたエルサレム」を歌うのを聞いて大変感銘を受けたという*5.

ホメロスによって使われた方言の多様性も非常に強力な先入観となる.パロール〔話し言葉〕によって区別される方言は,エクリチュール〔書き言葉〕によって接近し混ざり合い,すべてが少しずつ共通のモデルにいたる.ある国民が本を読んで勉学すればするほどその方言は消え,民衆の間で訛りの形でしか残らない.民衆はあまり本を読まず,まったく書かないから.
ここでは「国民 nation」と「民衆〔人民〕 peuple」が区別されている.「国民」は読書を通じた教養形成によって,共通言語を習得し,これによって一つの近代国家を形成する.その際に,方言の多様性を根絶するような暴力的なはたらきをするのがエクリチュールである.エクリチュールは自らの文法体系を持っているので,エクリチュールの獲得が同時に,その文法に合致しない方言の多様性を止揚して,一つの共通言語へと還元してしまう.この運動を〈エクリチュール中心主義〉と言っても良いであろう.これに対して,エクリチュールによる方言の多様性の止揚に最も影響を受けにくいのが,読み書きを不得手とする「民衆」なのである.「民衆」は主にパロールの世界で生きている.「民衆」はリテラシーの低さゆえに,エクリチュールの暴力を受けにくい.文明化と文化とは似て非なるものである.エクリチュールを中心とした共通言語による文明化と,パロールを中心とした方言の多様性の文化とが明確に区別されるからである.
ちなみにホメロスの著作における方言の混交については松本1972を参照されたい.

この詩は長いこと,人々の記憶の中だけに書かれたままだった.かなり後になって,多くの苦労の末に書かれた形に編纂されたのだ.ギリシャで本と書かれた詩が増えてから,比較してホメロスの詩の魅力が感じられるようになった.
フリードリヒ・アウグスト・ヴォルフ(Friedrich August Wolf, 1759–1824)の『ホメロス序説』(Prolegomena ad Homerum, 1795)に,(「かなり後になって,多くの苦労の末に書かれた形に編纂された」という)ルソーと同様の主旨の主張が看取される.例えば,この点に関して,(和辻哲郎「ホーメロス批判」の要約としてであるが)佐藤義詮(1906–1987)は次のように述べている.
『イリアス』や『オデュスイア』はいずれも唯一の作者の作ではなくして,多くの歌人の作である.それらの多くの古い歌をと横溢的な全体にまとめあげたのは,作の出来上がった時よりも数世紀の後の有名でない人々,ペイシストラトスの任命した文学委員達であった.これがヴォルフの主張の主旨である.彼はこれを厳密な本文批判によって証明したのではなく古くから言い伝えられた疑しい伝説と文字のない時代にこんな長い叙事詩を制作することは不可能であるということに基づいて結論したのであった.
ヴォルフよりも先にルソーが同様の主旨のことを述べている点は,ホメロスに対するルソーの卓越した洞察が評価されても良いのではないだろうか.
第七章 近代の韻律法について
この章では主に「アクサン」に対する先入観が批判されている.



われわれには,声〔母音〕によってと同様に音によって話す,響きがあって諧調に富んだ言語という観念がまったくない.アクサン記号によって抑揚の代補としようとするのは間違いだ.抑揚が失われて初めてアクサン記号が発明されるのだ.それだけではない.われわれはわれわれの言語に抑揚があると思っているが,まったくないのだ.われわれの言うところのアクサンは母音か長さの記号にすぎない.それらはいかなる音の違いも示さない.その証拠は,そのアクサンがすべて,異なる音長か,声〔母音〕の多様性を作り出す唇,舌,口蓋の変形によって表され,音の多様性を作り出す声門の変形によって表されるのは一つもない,ということだ.たとえばアクサン・シルコンフレックスは単なる声〔母音〕ではない時,それは長母音であるか,何ものでもないかのいずれかだ.
「われわれはわれわれの言語に抑揚があると思っているが,まったくないのだ」とルソーは述べている.ここでルソーはある種の逆説を主張しているように見える.ルソーにとって「アクサン」とは一体何なのだろうか.それはアクサン記号(エクリチュール)として表記されているようなものではない.むしろ「音の多様性 la diversaté des sons」を表現するパロールにおけるものである.
ちなみにフランス語のアクサンは発音区別符号(ダイアクリティカルマーク)であり,その中にはアクサン・テギュ(accent aigu)やアクサン・グラーヴ(accent grave),アクサン・シルコンフレクス(accent circonflexe)がある.
アクサン・テギュとは,それを発音するか否かを記号的に区別するために,/e/ を é と表記することである.
アクサン・シルコンフレックスは,【â・Â・ê・Ê・î・Î・ô・Ô・û・Û】のように,5つの母音である a / e / i / o / u の上に付される「山」形の記号【ˆ】のことである.シルコンフレックス【ˆ】が a / i / o / u の上につく場合には発音はまったく変わらないが,それが e の上につく場合には é [ɛ] と発音が同じになる.
ルソーによれば,かつての非文字社会の言語には「抑揚」があったが,文字表記と文法を備えた近代語からは「抑揚」が消えて「冷たく単調」になってしまったという.
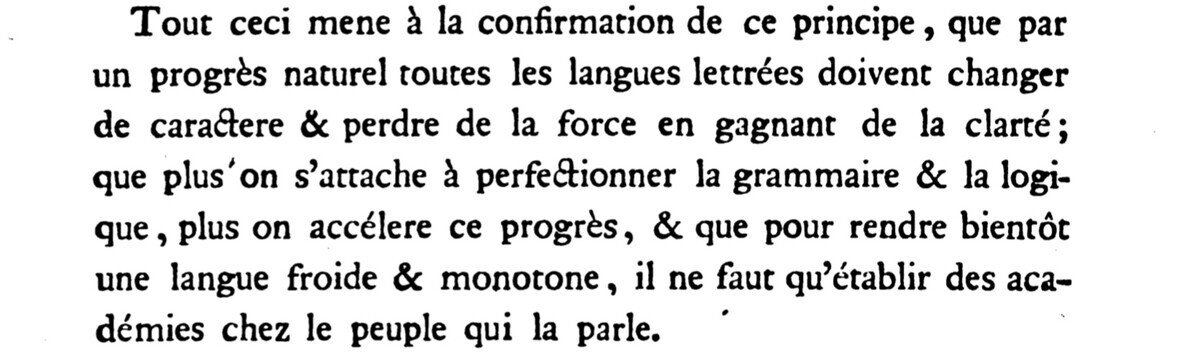
以上のことから以下の原理が確認される.自然な進歩によって,文字表記される諸言語は性格が変化し,明晰さを獲得する一方で力を失うということ,文法と論理を完全にしようと執着すればするほどこの進歩を加速させるということ,早くある言語を冷たく単調なものにするには,それを話す国民のうちにアカデミーを創設しさえすればいい,ということである.
第八章 諸言語の起源における一般的および地域的差異
第八章が前後を分ける一つの区切りとなっている.言語の起源をめぐる一般的な考察が前章まで述べられ,地域的な差異については次章以下で述べられる.
この章で注目すべきは,ルソーにおけるオリエンタリズム認識である.

ヨーロッパ人の重大な欠点は,いつも自分たちのまわりで起きることをもとにして物事の起源について哲学することだ.彼らは必ず,原初の人間が不毛で荒れた土地に住み,寒さと飢えで死にそうになり,常に住居や衣服を手に入れることに熱心であったというふうに示す.ヨーロッパ人はどこでも,ヨーロッパの雪や氷ばかり見いだしてしまい,人類やほかの種が暑い国々で生まれ,地球の三分の二では冬がほとんど知られていないことを考えもしない.人々を研究するには自分の近くを見なければならない.しかし人間を研究するには自分の視線を遠くにやらなければならない.特徴を発見するにはまず差異を観察しなければならない.
ルソーにとって「人間」とは,ヨーロッパ人の観察だけで得られるものではなく,ヨーロッパ以外の地域の人々をも観察することによって得られるものであった.
ルソーが認識していた,ヨーロッパ人が周辺地域の人々を観察する際に持っていた西欧中心主義的なまなざしは,後にエドワード・サイード(Edward Wadie Said, 1935–2003)が言語化に成功したいわゆる「オリエンタリズム」の先駆だと言えるかもしれない.
第九章 南方の諸言語の形成
第九章では,ルソーにとっての人類史が描かれる.

それ故,歴史で言及される最初の諸国民が肥沃な国々か暮らしやすい岸辺に住んでいなかったのは,そのような恵まれた風土が荒野だったわけではなく,その数多い住民たちが互いに相手を必要とせず,自分の家族の中に孤立して意思の疎通もない状態でより長く暮らしていたのだ.しかし井戸によってのみ水が得られる乾燥した場所では,それを掘るために集まらなければならなかった,あるいは少なくともその使い方のために合意しなければならなかった.それが暑い国々での社会と諸言語の起源だったに違いない.
この章を言語の起源というテーマだけに焦点を絞って読むと,次のように要約できる.人間の最初の共同体は家族であったが,家族内では「身振りや分節されていないいくつかの音」(家族内言語)でコミュニケーションをとっていた*6が,「国民的言語」*7は必要なかった.家族から出て社会的な決め事*8を行うために言語が必要となったので,そこに(単なる身振りや分節されていない言語にとどまらない)「国民的言語」の起源があるとルソーは考えた.
共同体間での合意によって生まれたのは,貨幣*9のみならず,言語もまたそうであったのである.
第十章 北方の諸言語の形成——不快で力強い声
ルソーによれば,南方(温暖)と北方(寒冷)との風土の違いによって,欲求が情念から生まれるのか,それとも情念が欲求から生まれるのかという因果関係が変わってくる.

しまいには人間はみな同じようになるが,彼らの進歩の順序は異なる.自然が気前がいい南方の風土では欲求は情念から生まれるが,自然が吝嗇けちな北方の国々では情念は欲求から生まれ,必要の陰気な娘たちである諸言語には,その激しい起源が感じ取れる.
すでに第二章で見たように,欲求とは「飢えや渇き」など生きるために必要なものであり,情念とは「愛、憎しみ、憐憫の情、怒り」(増田訳24頁)などの感情のことであった.欲求は人々を遠ざけるが,情念は人々を近づけるとされた.
ここでルソーの結論は至ってシンプルである.北方の国々の人々は,その風土が「悪天候,寒さ,身体の不調,さらに飢え」(増田訳83頁)をもたらす厳しい環境のもとで育ったため,彼らの声が「より不快でより力強い」(増田訳83頁)とルソーはいう.


しかし不毛な土地で住民が多くを消費する北方では,多くの欲求に服従している人間は怒らせるのがたやすい.彼らの周りでなされることはすべて彼らを不安にする.彼らは苦労しなければ暮らせないので,貧しければ貧しいほどもっているわずかなものに執着する.彼らに近づくことは彼らの生命を侵害することだ.彼らを傷つけるあらゆるものに対して激怒にとても変わりやすいあの怒りっぽい気質はそこから来ている.そのように彼らの最も自然な声は怒りと脅しの声であり,その声には常に力強い分節がともない,その声は固くて騒々しいものとなっている.
ここで「彼らの最も自然な声」というのは,その声の特徴がその地域固有の風土によって形成されたという意味での「自然」である.寒い地域では、彼らは常に生命の危機と対峙している.ゆえに身体的に強くなければ生き残っていけないということが,「自然な声」の力強さにも影響を与えている.
第十一章 この差異についての考察——オリエントの言語の「抑揚」
ルソーによれば,近代の言語は南方の言語と北方の言語の混合物であるという.

南方の言語は生き生きとしてよく響き,抑揚に富み,雄弁で,しばしば力強さのあまり難解だったに違いない.北方の言語は音がこもっていて固くて分節が多く,耳障りで単調で,優れた構文よりも語彙のおかげで明晰だったに違いない.近代の言語は何度も混ざり練り直されその差異の一部をまだ保っている.
ルソーによれば,南方の言語と北方の言語の特徴は対照的である.南方の言語は「難解」だが,北方の言語は「明晰」だという.言語のこうした違いは,その音が「抑揚に富」んでいるのかそれとも「単調」なのかという音楽性の違いにある.
フランス語・英語・ドイツ語のような近代語は,南方の言語と北方の言語の混合物であるが,オリエントの言語は「南方の言語」の特徴がより顕著だということを頭に入れて,次の箇所を読まれたい.


フランス語,英語,ドイツ語は互いに協力し合い互いに冷静に議論し合う人たち,あるいは怒っている激情家の私的な言語である.しかし神聖な秘儀を知らせる神々の使いや国民に法を授ける賢者たち,民衆を駆り立てる指導者たちはアラビア語かペルシャ語を話さなければならない.われわれの言語は話すよりも書く方が引き立ち,聞くときよりも読むときの方が快い.逆にオリエントの諸言語は書いてしまうとその生命や熱を失ってしまう.意味は半分しか語に込められておらず,その力はすべて抑揚にある.オリエント人たちの精髄をその本から判断しようとするのは,死骸をもとにしてある人の絵を描こうとすることだ.
フランス語,英語,ドイツ語といったこれらの西欧の言語においては,パロールに対するエクリチュールの優位という特徴が見られる.これに対してオリエントの言語は完全にパロール中心の言語である.
ちなみにルソーは「オリエント」という言葉で具体的にどの地域を念頭に置いているのだろうか.次のパラグラフで『コーラン』が取り上げられていることからすると,イスラーム圏が念頭に置かれていると言えるだろう.

アラビア語を少し読めるからと言って『コーラン』に目を通して微笑を浮かべる人がいても,マホメットがみずから,その雄弁で律動的なこの言語で,心よりも先に耳を魅惑する響きのいい声で,しかも常に熱狂の抑揚で教えに魂を込めながら預言するのを聞いたならば,次のように叫んで大地にひれ伏しただろう.「神に遣わされた偉大な預言者よ,栄光や殉教に導いてください.私たちは勝利するか,さもなければあなたのために死にたいのです.」狂信は常にわれわれにとって滑稽に見えるが,それはわれわれの間では,人に理解してもらうための声をもっていないからである.
先のパラグラフでルソーは「オリエントの諸言語は書いてしまうとその生命や熱を失ってしまう」と述べていたが,その意味を理解するにはおそらく『コーラン』読誦を聴くのが最も手っ取り早いだろう.
私もこの度YouTubeでコーラン読誦を拝聴し,そのあまりの荘厳さに驚いた.確かにルソーのいう通り,ムスリムの指導者の発する声の「抑揚」を無視して,日本語訳された『コーラン』のテクストをいくら研究しても,真の意味で彼らにとっての『コーラン』がいかに音楽的要素によって支配されているのかを理解できるようにはならないだろう*10.
第十二章 音楽の起源——言語・詩・音楽
この章で言語と音楽の起源が同一であったというルソー『言語起源論』の有名なテーゼが説かれる.注意しなければならないのが,その際の言語とはパロールとしての言語であるということである.

そのように詩句,歌,音声言語は共通の起源をもっている.上述の泉の周りでは,最初の弁舌は最初の歌となった.リズムの周期的で律動的な回帰,抑揚の旋律豊かな変化は,言語とともに詩と音楽を誕生させた,というよりその幸福な時代と幸福な風土ではそれらすべてが言語そのものだった.他人の協力を必要としていた差し迫った欲求は,心が生み出したものだけだったのだ.
さらにここで「共通の起源」として並列されているのが,「詩句,歌,音声言語」あるいは「言語,詩,音楽」という三つであることにも注意が必要であろう.つまり〈言語〉と〈音楽〉の二つについてはこれらが同一の起源であることがこれまでの研究で認識されていたが,〈詩〉もまたこれらと同等の地位を占める重要なカテゴリーであるということである.次の箇所でも〈詩〉が〈音楽〉と同等に注目されている.

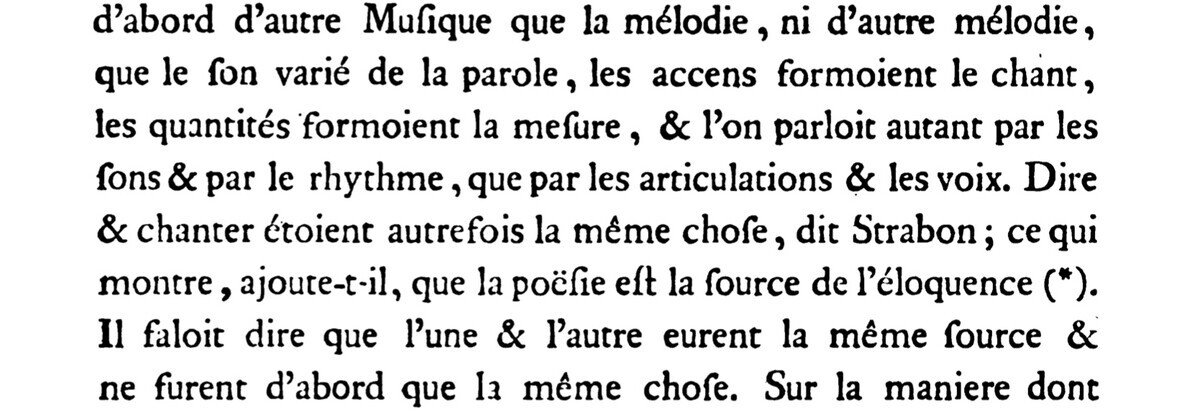
最初の歴史,最初の演説,最初の法は韻文であった.詩は散文より先に発見された.それは当然だった,情念は理性よりも先に語ったのだから.音楽についても同様だった.最初は旋律以外に音楽はなく,音声言語の多彩な音以外に旋律はなく,抑揚は歌を形作り,音長は拍子を形作り,人は分節や声〔母音〕によってと同じくらい,音とリズムによって話していた.昔は語ることと歌うことは同じことだったとストラボンは言っている.そのことは,詩が雄弁の源であることを示している,と彼はつけ加えている.詩と雄弁は同じ源をもち,最初は同じものだった,と言うべきだった.
ここでルソーはストラボンの言説に批判を加えている.すなわちストラボンは「詩が雄弁の源である」つまり詩が先にあってそこから雄弁が発生したと述べた(詩→雄弁)が,しかしそうではなく「詩と雄弁は同じ源をもち,最初は同じものだった」,つまりどちらかが他方の原因ではなく両者は起源において同一であり(詩=雄弁),しかもこれらの原因こそが「旋律」であったとルソーはいうのである.
第十三章 旋律について
私たちは絵画や音楽を鑑賞して感動することがあるが,その感動は一体何に起因するのか.ルソーによればその原因は,絵画における「色」や音楽における「音」ではなく,絵画における「デッサン」「模倣」であり,音楽における「旋律」だという.


絵画がわれわれのうちで引き起こす感情は色によるものではないのと同様に,われわれの心に対する音楽の影響力は音の仕業ではない.よく釣り合いの取れた美しい色は視覚を喜ばせるが,その快楽は純粋に感覚的なものである.その色に生命や魂を与えるのはデッサンであり,模倣である.われわれの情念を揺り動かすのはその色が表現する情念であり,われわれを感動させるのはその色が表しているものである.関心と感情は色に由来するのではない.感動的な絵画の描線は版画でもわれわれを感動させる.その絵画から描線を取り去ってしまえば,色は何の作用も及ぼさないだろう.
まさにデッサンが絵画においてしていることを旋律は音楽においてしているのだ.まさに旋律が線や像を描くのであり,和音や音は色にすぎない.しかし旋律は音の連続にすぎないと言われるかも知れない.しかしデッサンも色の配置にすぎない.雄弁家は著作を記すのにインクを使う.インクはとても雄弁な液体だということだろうか.
諸々の「音」や「色」は「旋律」や「デッサン」を構成する要素である.しかし,「旋律」や「デッサン」は人に感動を与えるが,「音」や「色」のような要素はそれだけでは人に感動を与えない.これは,人間の成分を分析して,窒素・リン酸・カルシウムのような構成要素を集めてきたからといって,それによって人間が出来上がらないのと同様である.「音」や「色」とは異なり,「旋律」や「デッサン」が芸術であるのは,「旋律」や「デッサン」が何かの表現であり「模倣」であって,自然科学ではないからだ.

つまり絵画は視覚に快いように色を組み合わせる術ではないのと同様に,音楽は耳に快いように音を組み合わせる術ではない.それだけなら,どちらも芸術ではなく自然科学のうちに含まれるだろう.絵画と音楽を芸術の地位にまで高めるのは模倣だけである.ところで絵画を模倣芸術にするのは何だろうか.デッサンである.音楽をもう一つの模倣芸術にするのは何だろうか.旋律である.
ルソーが音楽を絵画に喩えて説明したことは,音楽と絵画が非常に近いものを持っていることを意味しているかもしれない.両者の差異があるとすれば,作品を受け取る際の感覚器官の違いだろう.
第十四章 和声について
ルソーは「旋律」における表現力を次のように高く評価している.

旋律は声の変化を模倣することによってうめき声,苦痛や喜びの叫び,脅し,うなり声を表現する.情念の音声的記号はすべて旋律の領域に属している.旋律は言語の抑揚や,各言語において心の動きに用いられる言い回しを模倣する.旋律は模倣するだけでなく語り,分節はないが生き生きとしていて熱烈で情熱的なそのことばづかいは音声言語そのものよりも百倍も力強い.音楽的模倣の力はまさにここから生まれるのである.感じやすい心を持つ人たちに対する歌の影響力はまさにここから生まれるのである.
ルソーの考えでは,「旋律」の最大の特徴は「模倣」にある.「旋律」は「うめき声,苦痛や喜びの叫び,脅し,うなり声」などを表現することができる.このような表現力豊かな「旋律」とは対照的に,ルソーは「和声」について次のような否定的評価を下している.


和声はある体系では〔その影響力に〕協働することができる.それは転調の規則によって音の連続をつなぎ,抑揚をより正確にし,その正確さの確実なしるしを耳にもたらし,音符に還元できない抑揚を協和し結びついた音程に近づけ固定化することによってである.しかし和声は旋律を束縛することによって旋律から力強さと表現力を奪い,旋律から情熱的な抑揚を消し去りその代わりに和声的な音程を置き,弁舌の調子の数だけ旋法があるはずの歌を二つの旋法だけに従わせ,その体系に収まらない無数の音や音程を消し去り破壊してしまう.つまり和声は歌と音声言語を非常に引き離してしまうので,この二つの言語は闘い妨害し合い,互いにいかなる真実の性格も奪い合い,悲壮な主題において不条理なしに結び合わせることができない.
正直,私にはこの箇所を読み解く力がないが,差し当たりラモーの『和声論』と合わせて読解すべき箇所だと考えている.ルソーはラモーの『和声論』を若い時によく読み込み,そこから音楽理論を学んだという.しかし,ルソーはラモーの前で演奏した際に不評を買い,ラモーらと上演が決まった際にはプログラムからラモー以外の名前が消されてしまったという逸話がある.
第十五章 われわれの最も強烈な感覚はしばしば精神的な印象によって作用するということ
ルソーは音が「神経」に与える影響と「心」に与える影響とを区別している.

それがわれわれの神経に引き起こす振動のみによって音を考えている限り,音楽の真の原理も、心に対する音楽の力についての真の原理も得られることはないだろう.旋律における音は単に音として作用するのではなく,われわれの情緒や感情の記号として作用する.まさにそのようにして音はそれが表現していてわれわれがその像をそこに認める心の動きをわれわれのうちにかき立てるのだ.
旋律はわれわれの心に訴えかけるが,しかし,その旋律に込められた「情緒や感情の記号」を読み取るためには,その国民でなければ理解できないところがある.

各人はなじみ深い抑揚によってのみ感動させられる.各人の神経は精神によって準備させられてはじめてその抑揚を受け入れる.各人が言われることによって動かされるには,各人が話される言語を理解しなければならない.ベルニエのカンタータは,フランス人の音楽家の熱を治したと言われるが,ほかの国の音楽家ならどんな国の人でも熱を出しただろう.
言語がフランス語やイタリア語のように国民ごとに異なるように,音楽もまた国民ごとの文法を持っている.音楽はその国ごとのハビトゥスだと言えるかもしれない.
第十六章 色と音の間の誤った類似性
この章では,音楽と絵画,そしてそれらの構成要素である音と色とが——両者が類似のものとして捉えられていたにもかかわらず——いかに異なっているかということが示される.音楽と絵画はいかなる点で異なっているのだろうか.

このように一つ一つの感覚にはそれに独自の領野がある.音楽の領野は時間であり,絵画の領野は空間である.一度に聞こえる音を増加させたり,色を次々と展開したりしても,それはその構成を変えることである.それは耳の代わりに目を置き,目の代わりに耳を置くことである.
ここでルソーが「耳」と「目」を,すなわち視覚と聴覚を司る器官を挙げていることからも分かる通り,音楽は「耳」すなわち聴覚に独自の領野である「時間」に関わり,絵画は「目」すなわち視覚に独自の領野である「空間」に関わるものである.
音楽は時間の領野に属するからその音はしだいに消え去るという特徴を持っているのに対して,絵画は空間の領域に属するのでその色は持続性を持ち,音と異なって消え去ることはない.

聞くことができないものを描くことができるのは音楽家の大きな利点である一方,見えないものを表現することは画家にはできない.そして動きのみによって作用する芸術の驚異は動きによって安らぎの像さえ作ることができることだ.睡眠,夜の静けさ,孤独,静寂さえ音楽の絵画に含まれる.
ここでルソーが「静寂」さえも音楽の範疇に捉えていることは慧眼に値する.というのも,楽器を奏でるのでない静寂が音楽として考察の対象として認識されたのは,ようやく現代音楽になってからであるからだ(例えば,ジョン・ケージなど).
第十七章 みずからの芸術にとって有害な音楽家たちの誤り
この章は『言語起源論』の中で最も短い章である.

すべてのことがいかにして前述の精神的効果に帰着するか,そして音の威力を空気の作用と繊維の振動という観点からのみ見る音楽家たちは,この芸術の力が何に存するのかということをいかにわかっていないかということをわかってほしい.彼らは,この芸術を純粋に身体的・物理的な印象に近づければ近づけるほどこの芸術をその起源から遠ざけてしまい,原初の力強さをそいでしまう.声による抑揚を離れて和声の制度に専念することで,音楽は耳にとってよりうるさくなり,心にとって甘美さをより失った.音楽はすでに語るのをやめてしまった.やがて音楽は歌わなくなり,そのすべての和音と和声全体をもってしてもわれわれに何の効果も及ぼさなくなるだろう.
「すべてのことがいかにして前述の精神的効果に帰着するか,そして音の威力を空気の作用と繊維の振動という観点からのみ見る音楽家たち」が見落としていたのは「抑揚」の力である.
第十八章 ギリシャ人たちの音楽体系はわれわれのものとは無関係であったこと

われわれの和声が中世の発明であることは知られている.われわれの体系の中からギリシャ人の体系を見つけ出せると主張する人々はわれわれをばかにしている.ギリシャ人の体系は,われわれのいうところの和声的なところとしては,完全な協和音にもとづいて楽器の和声を固定するのに必要なものがあるだけだった.
ここで「中世の」と訳されている箇所は,原文では«gothique»である.これは本来「ゴシック(様式)の」と訳されるべきものだと思う*11.ゴシック様式とは中世の教会建築様式を指す言葉である.確かにゴシック様式は中世に属するが,しかし中世の建築様式のすべてがゴシック様式というわけではないのである.われわれはルソーが「ゴシック様式の gothique」と形容したところの意義を汲み取るべきである.
ここで一つ想起されるべきは,中世の音楽が教会音楽として発展していったことである.グレゴリオ音楽は単旋律から始まったが,9世紀末にはオルガヌムと呼ばれる二つの旋律を重ね合わせる技法が記述されている(『音楽提要』895年).12世紀にオルガヌムは本格的に頂点を迎えることになる.その代表の一つがサン・マルシャル修道院におけるサン・マルシャル楽派(École de Saint-Martial),いわゆるアキテーヌ楽派(École d’Aquitaine)であり,もう一つがパリのノートルダム大聖堂におけるノートルダム楽派(École de Notre-Dame)である.いうまでもなくノートルダム大聖堂はゴシック建築の代表である.ルソーが「ゴシック様式の gothique」と書いたときに彼の念頭にあったのはこのノートルダム楽派だったのではないか.だが,厳密に追求すれば解せない点もある.というのも,いわゆる「和声」は直接的には「ゴシック様式の発明」はなかったはずだからである.もし和声の源流が(対位法と重なる)オルガヌムにあると考えるならば,和声とは間接的にはゴシック様式の発明であるといえなくもないのだが*12.
第十九章 どのようにして音楽は退廃したか
もともと起源を同一にしていた音楽と言語とは,いつからか分離し,区別されるようになった.それはいかにして区別されていったのだろうか.

哲学の研究と推論の進歩は文法を改良し,最初は言語を歌うようなものにした活発で情熱的な調子を言語から奪ってしまった.
それまで韻文であった言語が,哲学者の言語使用によって散文になる.これにより,それまで言語が持っていた「旋律」という特徴が抜き去られ,生気のないものとなる.
それまで「情念」に向けられていた言語使用はソフィストの登場とともに終焉を迎え,以後「理性」に向けられた言語使用へと変わる.
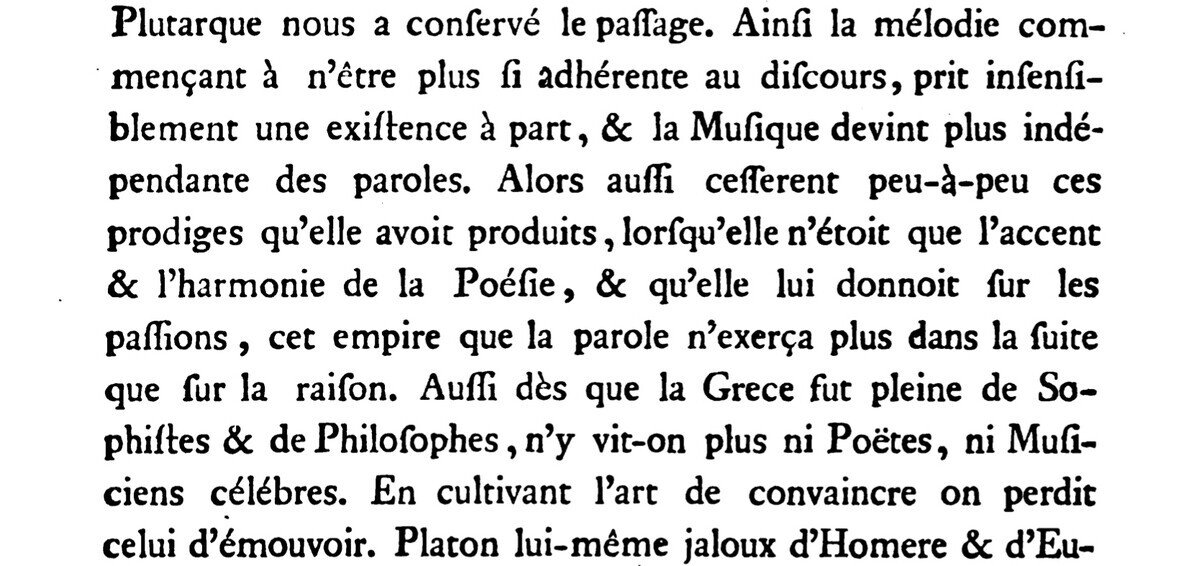
そのように旋律は言説に密着しなくなって,少しずつ独自の存在になり始め,音楽は歌詞からより独立したものになった.すると音楽が詩の抑揚と諧調にすぎなかった時に引き起こした奇跡も徐々に止んで行った.〔そして以前は〕音楽が情念に対する影響力を詩に与えていたが,その影響力は以後,ことばが理性に対して及ぼすだけになってしまった.それ故ギリシャがソフィストや哲学者で満ちてくると有名な詩人も音楽家も見られなくなった.説得する術を培うことで感動させる術を失ったのだ.
哲学者によって言語から音楽的要素が骨抜きにされ,その結果として近代人の言語からは弁論術が失われたとされる.この近代語における弁論術の喪失が,次章「言語と政体の関係」を読み解く鍵となる.
第二十章 言語と政体の関係
この章でルソーは古代と近代における言語(弁論術)の違いについて考察している.両者の違いはどこにあったのだろうか.


自由に好都合な言語がある.それは響きがよく,韻律や諧調に富み,とても遠くからでもその弁舌が聞き分けられる言語だ.われわれの言語は長椅子でのざわめきのためにできている.現代の説教師たちは聖堂で苦労して汗まみれになるが,彼らが何を言ったのか何もわからない.一時間叫んで疲れ果て,半死半生の状態で説教壇を後にする.たしかにそれほど疲れる必要はなかったのだ.
ルソーによれば,古代の弁論は人々にとってよく聞き取れたが,近代の弁論は人々の耳に届かない,聞き取りづらいものになっているという.これは前章における言語からの音楽的要素の喪失という観点とセットで捉えられるべきである.
では,言語がまだ音楽的要素を持っていた古代において弁論はいかなるものであったのか.

古代においては,公共の広場で簡単に民衆に聞いてもらうことができた.丸一日話しても気分が悪くなることはなかった.将軍たちは軍隊に演説をしていた.人々は彼らの話を聞き,彼らは疲れ果てることは決してなかった.
音楽的要素と一体であった古代の言語においては,弁論は聴取されやすく,聞き手と話者の両者にとってそれが長時間にわたっても疲れにくいものであった.これは先の疲れやすい「現代の説教師」と呼ばれる人々とは大違いである.
注
*1: 訳注では「ここでいう「オリエント」とは,古代の地中海世界東部,すなわち中近東を指す」とある(増田訳25頁).
*2: ルソーがこの『言語起源論』を書いていたのとちょうど同じ頃に,バウムガルテンは『美学』(第二巻,1758年)の中で「文彩 figura」と「転義 tropus」について述べている(バウムガルテン2016,第47節「転義」§783以下).バウムガルテン『美学』によれば,「転義(法)」とは修辞学の伝統において「その固有の意味から別の意味への,利点を伴う語,語法の変化」(クインティリアーヌス『弁論家の教育』8.6.1)と解されてきたが,それにとどまらない意義を持っているとされる(§780).この点について詳しくは井奥2016をみよ.
*3: 「隠喩 metaphora は,非本来的な意味へと適応される語の転用である.たとえば,類から種への,種から類への,ある種から他の種への,あるいはまた,類比に即しての転用である」(アリストテレス『詩学』1457b10).
*4: 「天才詩人ホメロスの出現以降は,その権威がもたらした影響でアオイドスの比較的自由な創作はなくなり,ラプソドスによる固定したテクストの正確な伝承の段階に入った.そしてこの段階では,すでに文字使用もさかんになっていたから,例えば書くことに堪能なラプソドスなどが,ホメロスのテクストを文字で固定したと考えられる」(小川1990:127).
*5: タッソー,悲劇と勝利 - Wikipedia
*6: 「原初の時代において,地上に散らばっていた人間には,家族以外に社会はなく,自然の法以外に法はなく,身振りや分節されていないいくつかの音以外に言語はなかった.」(増田訳58頁).
*7: 「何だって! その時代以前,人々は大地から生まれていたのだろうか.両性が結ばれることなく,誰も理解し合わないのに世代が相次いでいたのだろうか.いや,家族はあったが,国民はなかったのだ.家族内の言語はあったが,国民的な言語はなかった.」(増田訳76頁).
*8: 「真の言語は決して家族を起源としていない.言語を確立することができるのはより一般的で持続的な協約しかない.」(増田訳78頁).
*9: 「だが,貨幣は需要の代わりに申し合わせに基づいて生まれたのである.それゆえ,それはノミスマ nomisma という呼称を有している.それは自然の本性に基づくのではなくて人為的であり,これを変更したり,無効なものにするのはわれわれの自由なのである」(アリストテレス1971).
*10: そもそも『コーラン』とは「朗読されるもの」という意味を持っている.「周知のようにコーランの言語は「読まれるべきもの」である.この場合の「読む」とは書物を読むという現在一般に用いられている意味ではなく,往時どこの国でも口承的時代に於て一般であった「朗読する」という意味なのである.「読む」の義が「黙読」として一般化するのは口承的時代から書承時代に移って,書物がごく普通に個人の私有に帰するようになってからのことである.この当然の「読む」という概念もここでは大きな比重を占めていることに注意を喚起しておきたい.したがってコーランは「朗読されるもの」という謂であって,言わば「声の本」ということになろう.」(堀内 1971,190頁).
*11: 既存訳を参照したところ,小林義彦訳(1970年)では「われわれの和声はゴート人の考え出したものであることは知られている」(小林訳139頁)と訳されており,竹内成明訳(1986年)では「私たちの和声が中世の産物であることは知られている」(竹内訳199–200頁)と訳されていた.増田訳は,「中世の gothique」と意訳したこの竹内訳を踏襲した形になる.
*12: ノートルダム楽派の有名な人物であるレオニヌスは『オルガヌム大全』(Magnus Liber)を著したが,彼が作曲した音楽はまだ多声音楽(ポリフォニー)であって,(ルソーがいうような)和声(ハーモニー)ではなかった.レオニヌス『オルガヌム大全』の全曲が二声部で作曲されていたが,後のアルス・アンティクアの時代(12世紀中頃〜13世紀末)には声部の数が二声から,三声ないし四声以上に増えた.さらにアルス・ノーヴァの時代(14世紀)にはリズムが多様化していった.ルネサンス期(15世紀〜16世紀)には和音が意識されるようになった.
文献
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
