
育児書の活かし方
こんにちは。発達マップです。
本日はこちらのツイートについて、触れていきたいと思います。
育児書とあまりに違う発達障害の子の育児。「ほめたら伸びる」「自分で考えさせる」など。当てはまらないことが多い。育児書が親を苦しめることも。"前提" や"当たり前" は通じない。親の頑張りでは、どうにもならないことも。子は皆一人一人違うけれど。発達障害の子は、その "違い" が、特に大きい。
— 発達マップ🗺 (@hattatumap) April 19, 2022
普段の支援でも、育児書に苦しめられてる親御さんが多い為、育児書の活かし方を私なりにまとめました。
このような気持ちを抱えてる親御さんに向けて、執筆してます。
・育児書を読んでも、できてない自分を認識して辛い
・育児書を読むほど、自分が責められてる気持ちになる
少しでも参考になれば、幸いです。
「育児書=正解」ではない

育児書と読んでると「ああ...ここはできてない...」「私は育児に向いてないのかな...」と思うこともありますよね。
そんな真面目な方に、今回お伝えしたいことは、「育児書は参考にするものであって、正解ではない」ということです。
私が支援してきた方は、「育児書=正解(この通りにやらなくちゃ)」と考えてる方が多いです。
育児に本気で悩み、子どもの為に何かできないか...と真面目で、子ども想いの方が多いです。
その為、「育児書の通りにできないといけない」「育児書の様に出来てない自分はダメだ...」と自身を責めたり、落ち込むことがあります。
育児をする親として、この真摯な姿勢は、尊敬します。
ただこれは、親自身を苦しめることになり、かえって追いつめられてしまいます。
親の手助けとなる育児書が、親を苦しめてしまうなんて...。これでは育児書が何のためにあるのか、分からなくなってしまいますよね。
育児書は、"参考にするぐらい"がちょうどいい

育児書は、「こういう関わり方もあるんだ」と参考にするぐらいが、ちょうど良いです。
育児の価値観・考え方で共感できる方を見つけて、その方の育児書を読まれるのが、一番だと思います。
育児書を読む上で大切なこと
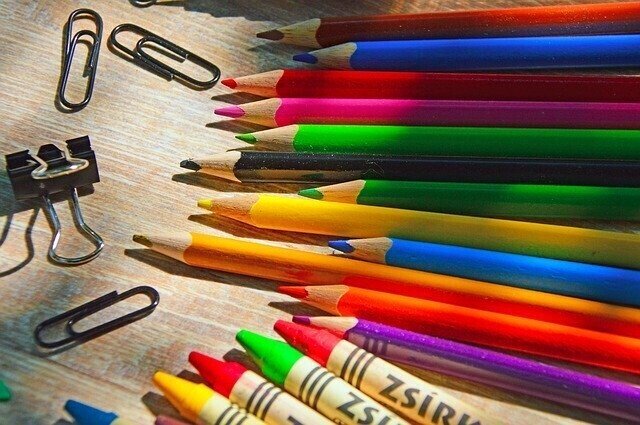
育児書の内容を100%できる人はいません。
「知識としてある」と「できること」は、似てる様で全く違います。
私も普段は、親御さんに関わり方などをお伝えする立場ですが、その私も、我が子の育児では、出来てないことばかりです。
できてない所は、人に見られたくないものです。周りの人はできてる様に見えるかもしれませんが、見えないだけで、皆一緒です。
その上で大切なことは「できてない所を探す」よりも「できそうな所を探す」です。
「ここは、取り入れられそうだな」と思える所を小さく始めてみるのが良いと思います。
小さく始めれば、親の負担も軽いですし、小さくできたことは、親のポジティブな気持ちに繋がります。
仮に上手くいかなくても、「この方法は合わなかったんだな」と、次に活かせます。
まとめ

今回のまとめになります。
・育児書は、正解ではない
・育児書は、参考程度がちょうどいい
・出来そうな所を、小さく取り入れてみる
以上になります。
ここまで読んで下さりありがとうございました。
育児書がみなさんの手助けになれば、幸いです。
