
書き手の語る『アフリカ』最新号(vol.35/2023年11月号)
現在、ノンビリ発売中の日常を旅する雑誌『アフリカ』最新号(vol.35/2023年11月号)ですが、書いている人たちに、自作や『アフリカ』について語ってもらいました。
編集人が書いた"ライナー・ノーツ"は、こちら。
彼(というか私!)ばっかり語っていて、他の人たちの声が聞こえてこない、とは誰からも言われてませんが、そんな気もしないではないので、もしよかったら…と腰を低くしてお願いしてみました。まだ全員からは寄せられてないのですが、小出しにしてみようと思います。
何回かに分けて、更新しようと思いますから、いったん読み終わっても、また覗きに来てください。
さ、始めてみよう!
良いですぞ、という話 - スズキヒロミ
昨年出た犬飼愛生さんの詩集『手癖で愛すなよ』は良いですぞ、という話を書いています。
今号は、何といっても、向谷陽子さんの切り絵ギャラリーです。将来、向谷さんの作品集とか図録的なものが出てくれるかどうか、それはまだ分かりませんが、それまではこの『アフリカ』が、その役割を果たしてくれるのではないでしょうか。今号は永久保存版です。

日常にそっと寄り添う『アフリカ』 - なつめ
日常を旅する雑誌『アフリカ』ですが、私にとって『アフリカ』は、日常にそっと寄り添う雑誌『アフリカ』でもあります。ある日の小さな旅の途中で、ある方にたまたま手渡された『アフリカ』は、子育てと家庭のことで、とにかくしんどかった私の日常にすっと入って来ました。そこには、私と似たようなことを考えている方の文章や登場人物が色々と描かれていました。日常のしんどさや、わかってもらえなさをそれぞれ抱えながら生きている不器用で、おもしろい登場人物たちに、困ったり、悩んだりしているのは、自分だけじゃないと、救われました。
私は、かさ張らない薄さの『アフリカ』を、遠くに出掛けるときや、旅に行くときは、いつも持って行きます。旅の途中で『アフリカ』を気軽に開くと、まるで一緒にとなりで旅をしているような気もしてきます。そのように私にとって、いつも心にすっと入って来る『アフリカ』には、毎回おもしろい文章や作品がたくさんあります。一人で読んでいても一人ではないということをいつも思い出させてくれます。これからも一緒に旅をしながら、そっと心に寄り添ってくれる『アフリカ』と、笑いあり、涙ありの時間を、これからも一緒に歩いて行きたいなと思っています。

(2024年2月9日更新)
その動きが - 矢口文
下窪さんより『道草の家のWSマガジン』2023年9月号の表紙画「夏草の勢い」を『アフリカ』35号に載せてみませんかとお話をいただきました。『WSマガジン』の読者だけでなく、『アフリカ』の読者の目にも触れる機会になるということで、快諾しました。
いつもはウェブ上にある私の表紙画が印刷され、本の見開きで載せていただきました。『アフリカ』誌面で見てくれた友人からは、いつもスマホ画面で見ていたので、大きい状態で見られてよかったと感想をもらいました。
絵の画面中央でページが分断しているのですが、この絵は右斜め上に向かって動線があるので、その動きが損なわれなかったと思っています。
なつめさんのエッセイ「バウムクーヘン」がとても好きです。子供の頃に夢中になって読んだ童話のようにも思えます。童話は時にとても哲学的でもあり、そんなところがこの「バウムクーヘン」とつながっていると思います。

楽しみなシリーズと - 犬飼愛生
こどものための詩シリーズ①「ドレス」
長く詩を書いてきましたが、最近は詩という文芸の今後に思いを馳せることが多くなりました。
今後、長く詩が読まれ、また書かれるためにはこどもたちに詩というものの存在を知ってもらうよりほかない。
そんなことを考えているときに関西弁でしゃべるこどもの声が降ってきました。
こういうことを、思っててん、(こういうことを思っていたの)というこどもの声が。
それを詩にしてみようと思いました。そして、シリーズとしてしばらく書いてみたいと思って、勝手に頭に「こどものための詩シリーズ」とつけました。
こどもにも読みやすい詩を書いてみたら、かつてこどもだった人たちにも読んでもらえるといいなぁと思える内容になりました。
めずらしく次作の構想もすでにできていて、私自身も楽しみなシリーズとなりそうです。
相当なアソート③「家出」
短いエッセイを目指して始まったこの連載。書いているとつい長くなってしまい毎回何度か書き直しています。
今回はタイトルずばりの「家出」について。みなさんは家出したこと、ありますか? 大人になってからの家出はさまざまな生活のしがらみがあり、実際は実行困難。けれど、やってしまうと結構遠くまで行くことができます。
果たして、わたくしイヌカイはどこまで行ったのでしょうか? イヌカイ的家出のススメです。家出をしたことがあるひとは、そのエピソード、ぜひわたくしに聞かせてください。
2023年11月の『アフリカ』
いつもはまっさきに「編集後記」から読むことにしている『アフリカ』。今回ばかりはそこにどんなことが書かれているのか、ちょっと読む勇気がでずにまずは表紙を眺めて1ページ目から少しずつ読んでいきました。いつものようでいて、いつもとは違う『アフリカ』です。今回ばかりは編集後記を最後に読んで、よかった、と思ったのでした。

(2024年2月11日更新)
バウムクーヘンを食べ終えて - なつめ
今回の「バウムクーヘン」という文章によって、こう見えて(どう見えて?)実は真面目に、そしてときには深刻に、さらにはときどきおかしなことを考え抜くことがある人間だということが少し伝わったかもしれません。あまり多くの人には理解してはもらえないようなことを、一人静かに、真面目に、考えていることもあるのです。もしかすると、バウムクーヘンと人生を重ねる心境など、わからない方には全くわからないことかもしれません。
この文章を書き始めたとき、私は小さい頃からの長年の夢だった仕事と、念願叶った生活環境を、手放さなければならないことが起きました。あまりにも突然のことで、それらを失った悲しみで、人生に大きな喪失感を感じていたところ、近所のスーパーへ買い物に行き、レジの列に並び、その脇にいつも置いてあったあのバウムクーヘンが、妙に気になりました。丸いバウムクーヘンの中心にある空洞が、まるで私の中心にある喪失感を表しているかのように見えたからなのかもしれません。買い物に行くたびに気になるバウムクーヘンに対して、もしかして「バウムクーヘンのほうから私に何かメッセージのようなものを送っているのでは?」という気もしてきました。今まであまり食べることなどなかったバウム―ヘンが気になる存在になっていました。なぜいつもレジの脇に置いてあるのが、どら焼きや、パウンドケーキ、ドーナツ、など色々なお菓子がある中で、あの層になった丸いバウムクーヘンなのか、という疑問も湧き上がってきました。「バウムクーヘンから何か私にメッセージがあるとしたらなんだろう?」と、さらに現実的にありえないことを真面目に考え始めたのです。私はこのときから悲しくて喪失感でいっぱいだった自分をどうにか救おうとしていたのかもしれません。
悲しんでいた私は、「バウムクーヘンの輪の中に入って考えてみようかな」と、いう気さえしてきました。そのようなこともまた現実的にはありえないことなのですが、物と自分を結び付けて、どこかシュールで、ファンタジー的なことを一人で考えてみたいと思ったのです。この話を現実世界で切磋琢磨して生きている人にしたら、何やら不思議でおもしろい話をのんきにしているなと思う人の方が多いかもかもしれません。中にはおかしな人扱いをする人もいるかもしれないので、私はただ一人で黙々とあのバウムクーヘンの輪の中で真剣に考えてみることにしました。ときにはシュールでファンタジー的なことが人の心を救うことがあるということは、このようなことなのかもしれないと、「バウムクーヘン」という文章を書いたことで始めて実感していくできごとでした。バウムクーヘンを通じて、現実とファンタジーの世界を行ったり来たりしていた私は、あの分厚い層に自分の人生を重ね、振り返り、輪の内側にいる小さな自分は静かにその層を眺め、今までの自分の人生は一体なんだったのかと考えました。とにかく考え抜きたくて、しばらく一人で休んだ後、だんだんバウムクーヘンの外側に少しずつ出たくもなり、気持ちを整理するかのように自分の内側のことを外側へと少しずつ発信し始めました。それはバウムクーヘンの空洞の中で、文章を書いたり、ウクレレで歌ったりすることで自分を慰めながら、本来の自分を取り戻していく行為でもあったようです。
最後に、これまでに起きたできごとと、積み重ねてきた人生の全てを受け入れるかのようにバウムクーヘンを食べ、呑み込みました。そのことによって、これまでの人生に一つの区切りがついたと同時に、私の内側と外側が融合し、これまでの人生のできごとと、自分の全てが一体化されたようでした。大きな喪失感を抱え、バウムクーヘンの空洞の中にいた私は、私の人生は今もこうして「ある」ということを、この「バウムクーヘン」を書くことによって、気が付くことができました。そんな私は今少しずつ、だれかのバウムクーヘンを外側から食べ始めているのかもしれません。

『アフリカ』を書く、ことについて - 戸田昌子
わたしが弟や妹にミヒャエル・エンデの『モモ』を読み聞かせていたのは、たぶん10歳頃のことだったと思う。自分の気持ちとしては、当時すでにすっかりおとなだったけど、実際にはだいぶ小さな子どもだ。毎晩、読み聞かせの途中で寝てしまう妹弟たちを相手に、同じ箇所を何度も読み返しながら2週間程度で読破したのだから、ずいぶんしっかりした子だったなあ、と今では思う。
「道草の家」さんこと下窪俊哉さんの個人誌『アフリカ』のことを考えていると、そのころの自分がよみがえってくる。「歩く速さで書いている人たち」と、わたしは『アフリカ』に寄稿している人たちのことを考えているが、『モモ』はまさにこの「歩く速さ」ということをわたしに教えてくれた本である。
「道路掃除夫ベッポ」は、モモの友達である。ペッポは、大通りを掃除している。いつ果てるかとも知れぬ道の先をふと見やると、ベッポはひどく焦ってしまう。だから早く終わらせたいと急ぐけれど、急ぐほどに、なかなか終わらない。でも、先のことを考えないで、ひとあし、ひと掃きのことだけを考えて進んでいくと、いつのまにか掃除は終わっているんだよ、とベッポはそんな風にモモに話すのである。
その感じを思い出したのは、『アフリカ」34号(2023年3月刊行)のなつめさん「ペンネームが決まる」という文章を読んでいたときだった。プロの物書きというわけではなさそうな一人の女性が、暮らしの当たり前とそこにある危機について綴ったその文を読んでいるうちにわたしは、「ああ、」と、ふいに息がつけたような気がした。それはきっと、人が歩いているテンポで書かれた文章だったからだろう。走らず、立ち止まらず、ただ、歩いている、そんな文。
そのことは、以前に、「道草の家」さんの文章についても同じことを考えていて、そのときわたしはこんなふうにわたしは書いた。
──この人の文は流れるようでどこにも飾りがなくて、滞りがなくて重たくもなく軽やかでもなくて、木訥でさえなくて、流れる速さが見事に一定で、見事だと言わせさえしない、希有なものです。──
なぜそんなふうに書いたのかといえば、それはこんなふうだった。SNSで流れてきた道草さんの文章へのリンクを、わたしは何気なくクリックした。あまり知りもしないその人が書いた文章を読んでいるうちに、例によってまたなにかについて焦っていたわたしは、いつのまにやら胸のはやりが消え、同じテンポを刻み始めたなあ、という感じを持った。そして、そのことについて表現するために、こんなことを書いたのだと思う。
たぶんわたしは、道草さんの文章を読んだ時も、そしてなつめさんの文章を読んだときも、お金をもらってものを書くことにちょっと飽いていて、そして仕事というものの幅の狭さにきっと、イライラしていたのだと思う。だから「書く必然性がある」のに、「求められて」書いているわけではないような、ちょっと途方に暮れるような自由さのなかで、一定のテンポを刻みながら書いている人たちの存在を強く意識した。そのころから『アフリカ』に書きたい、という思いが、わたしのなかにふわっと生まれてきていた気がするのです。
わたしは、文章を書くことをなりわいにしていて、文章を書くテクニックもタクティックもそれなりに持っていて、それゆえに人に感嘆されようが、けなされようが、屁とも思わないような鋼の精神も持っている。なのに、というか、だから、というか、しかも、そのことにすら飽いていました。それでいて、書きたいことを書きたいように書いてください、と言われたとしても、ほんとうにそんなふうに「自由に」書ける場があったためしはなかったのです。
そんなわけで、「書いてもいいですか」「もちろんです」という下窪さんとのやりとりのあと、わたしが『アフリカ』35号に書いたのは「喪失を確かめる」という文でした。それは22年前のアメリカ同時多発テロについて書いたもので、当時ニューヨークにいたわたしは、いつかそれについて書くだろうと思いながら、一度も書いたことがなかった。それがやっと書けたのは、こういう同人誌だったからこそじゃなかったか、と思っています。そこには当時、わたしが撮影した写真も掲載されている。自分が撮った写真を載せるなんていうのは、たぶん生まれて初めてのことで、きっと今後も、しない気がするのです。
『アフリカ』を読んでいて感じることは、とにかく書いている人たちのスピード感に安心できること。わたしは下窪さんの文章のリズム感がとても好きだけど、同人誌について言っておられることにも、いつも共感している。自分で作ること、続けること、書くこと、そして、自分で直接、ひとに伝えようとしていること。『アフリカ』は、見事に道草のテンポで編まれています。それは私が書く上で、つい忘れてしまっていることを、ちゃんと思い出させてくれる、生きているテンポを持っています。
その歩みのテンポは、じつは、下窪さんに読んでもらったときにも感じたことでした。わたしはこの文を書いた当時、ひどく切羽詰まっていて、これを書いておかなければ死ねない、というくらい、追い詰められていた。そのことは文章にはいっさい書かれていないけれど、それはこの文が書かれた理由でもあって。下窪さんの読みはその理由そのものに寄り添うような、確実な読みだった、とその時わたしは感じたし、そんなふうに文を読んでもらったことはそれまでなかった、とさえ思えたのでした。編集者としての下窪さんは、今までわたしが出会ったことのないような、とくべつな能力があるのでしょう。よりそう、というよりかは、ともに歩く、という能力。
歴史をやっている人間としてわたしが思うのは、あなたがどこかに書き残しておけば、いつか、誰かが、それを拾う、ということなのです。わたしは物心ついた頃から、自主ゼミや同人誌をやっている人たちを見てきたし、それを資料として読んできた。だからわたしは「書き残す」ということの意味を、そんなふうに考えています。伝えることや、人を変える、なんてことは、そのなかでは副次的なことでしかないのです。だから、自分が書いたことがだれにどう伝わるかなど、考えるまでもないことなんじゃないかな。「ただ、書く」ということは、「ただ、歩く」ことのように、確実で、切実なことなんじゃないかな。と、『アフリカ』を眺めていると、わたしはそんなふうに思うのです。

(2024年2月15日更新)
不思議な雑誌だな。 - スズキヒロミ
新しい『アフリカ』を読み終えた。読み終わってしまった。読み終えたくなかったようだ。いつもなら真っ先に編集後記から読むのに、亡くなった向谷さんの名前が目に入って閉じてしまった。今号の表紙に「アフリカ」の文字はない。でも『アフリカ』だとわかる。本当だ。
冒頭の詩、「晴れた雨の日」。作者のY・Mさんはあのひとなのかな。タイトルの後に示された(1999)を見て、今よりもう少し優しかった頃の夏の日を思い出した。「変わりたい」でも「変わらない」。
目次のページにも切り絵があることを、今までそんなに意識してなかった。今までの号ももう一度目次を見直してみようか。見直すと言えば、目次のスタッフクレジット的なページも、改めて見直すと面白そう(「粋に泡盛を飲む会」に入りたいんですけども)。「感謝」の中にRTさんのお名前が。
向谷陽子さんの切り絵セレクション。『アフリカ』初というカラーページがふんだんに使われている。いつかの表紙に使われていたあのシャツの色はこんなだったんだ。「手を繋ぐ」についた向谷さんのコメント「普段なら切らないようなものも、『アフリカ』だから切ろうと思うことがあります。」──そう言えばいつか戸田昌子さんも似たようなことをつぶやいておられた。『アフリカ』って不思議な雑誌だな。

下窪俊哉さん「ハーモニー・グループ」は、勝手に想像していた話とかなり違っていて、爽やかな短編。もうこんな気持ちは思い出せない。きれいな絵を前にした時のように、ただただ眺めた。冒頭のY・Mさんの詩とつながっているような気もした。
UNIさんの「日記と小説」は、下窪さんによるインタビュー。今年(2023年)出た『たたかうひっこし』の話から、UNIさんの子供の頃の日記の話、さらに遡った創作の原点の話まで出てきた。UNIさんは日常生活そのものが小説や映画の主人公のような方で、「書く人」というのはこんな方なんだろうな、といつも思う。
矢口文さん「夏草の勢い」。『アフリカ』の見開きいっぱいに印刷されたこの絵のタッチを観ていると、目がほぐされていくような気がする。庭や空き地の草花、世の悲しみに一切関わりなくどんどん伸びていくね。

導かれた運命の出会い『アフリカ』 - なつめ
私が初めて『アフリカ』と出会ったのは、2020年。当時の私は電車で1時間半ぐらいかけて鎌倉に行き、ウクレレワークショップに1ヶ月に一度参加することで、日常のしんどさから解放されるために、非日常の時間を定期的に作っていました。それは、家庭でも職場でもない、いわゆる第三の場所として、当時の私にとって必要な場所と時間でした。同時にその頃、私の中で個人的なおにぎりブームが起こり、おにぎりの魅力に心を掴まれていた私は、Instagramに色々なおにぎり屋さんのおにぎりの紹介と、自分で作ったおにぎりの写真を投稿し、おにぎりに特化したInstagramの投稿を頻繁に続けていました。私は東京の日本語学校で日本に来たばかりの外国人留学生たちに日本語を教えていたのですが、もっと身近な日本文化の一つである「おにぎり」についても、外国人にも紹介したいと思い、外国人と「おにぎりを作る会」をやってみたいと思っていました。一人でそれをするのは少し大変そうに思ったので、同じ日本語教師の友人を誘い、計画し始め、その最初の開催場所はどこにしようかと、考えていたとき、
「鎌倉がいいんじゃない? 外国人も多そうだし」
と、友人が提案した鎌倉で場所を探すことになりました。ネットで鎌倉のレンタルスペースを探していると、「ゲストハウス彩(イロドリ)」を見つけ、なんとなく気になって実際に行ってみることにしました。鎌倉に行くことをいつも楽しみにしていた私は、仕事が休みだった平日に、そのイロドリに、事前になんのアポイントをとることもなく、ふと思い立った日に電車に乗って鎌倉に向かったのです。当時小学校低学年だった息子が学校から帰って来る前に家に帰って来たかった私は、朝、息子が学校に行った直後に最寄り駅に向かい、朝の通勤通学で少し混んでいた電車に乗って鎌倉を目指しました。午前中には鎌倉に着き、歩いて散歩をしながらイロドリに向かいました。オーナーにはなんの連絡もしておらず、今日いるのかいないのかもわからなかったのですが、なんとなくイロドリに向かって歩いて行ってみました。もし、だれもいなかったら、気になるお寺やお店、おにぎり屋に行ったりしようと、その限られた時間の中で、鎌倉散策を楽しむつもりでした。今日ここに来た時間は何も無駄にはならないと思いながら歩いている内に、イロドリの玄関の前に着きました。
一見、古い和風の一軒家で、ここがゲストハウスかな、と思って上を見上げると、ベランダに男性用の浴衣のようなものが一つ干してありました。日本文化好きの私は、このいかにも和風を感じるこの家の佇まいから、なんとなく良い雰囲気が出ていることを瞬時に受け取り、なんだかワクワクしてきました。すでに玄関のドアが半分開いており、ゲストハウス(?)はもう開いているようでした。オーナーが武士だということは調べたときに知っていたので、浴衣のような和服が干してあるということは、たぶんここがイロドリだろうと思い、思い切って玄関のチャイムを鳴らしました。
「ピンポーン!」
しばらくすると、
「はーい、どうも、こんにちは?」
と、本当に武士の恰好をしたオーナーの武士殿が現れました。私は、武士の恰好をしている方が家から出てきて「おおおっ! 本当に武士だ」と思いました。
「初めまして。突然すみません。武士さんですか?」
と、その姿が自然体でなんの違和感もなく、私はもう「武士さん」と呼んでいました。
「はい、イロドリというゲストハウスのオーナーの武士です!」
「本当に武士さんなんですね?!」
「はい、武士です!」
と、終始にこやかに、そして堂々と、武士殿は「私は武士です!」とはっきりと自己紹介をされました。どうして武士の恰好をしているのかということや、ここはどんな場所なのかということをまだこちらから何も聞かないうちに、自ら話し出しています。少しその武士殿の話が落ち着いた頃、
「あの、突然お伺いしてすみません。少し、お話できますか?」
と、私が言うと、
「ああ、すみません。どうぞ、どうぞ、玄関先ですみません。中へどうぞ!」
と、話に夢中になっていた武士殿は、「はっ!」と今気が付いた様子で、玄関の中に慌てて私を迎え入れてくれました。家の中を見渡すと、黒電話や「温故知新」と筆で太く書かれた掛け軸などがあり、色々と興味を惹かれるものがたくさん置いてありました。
「ここは······古いものがたくさんありますね。とても興味深いです」
と、私が言うと、武士殿はイロドリ内に置いてある古い物についても説明をし始めました。その話の延長に日本文化好きの共通点が見つかり、色々と共感する思いで私は「ふむふむ」と、そのお話に聞き入りました。
「日本文化が好きなんですね。私もです。実は今、友人と鎌倉で、外国人とおにぎりを作る会というワークショップができる場所を探していたんです。それでこちらにレンタルスペースがあることを知って来たのですが······そのような活動を、こちらでさせていただくことはできますか?」
と、聞いてみました。すると、
「できますよ! おにぎりですか! いいですね! ぜひ、やりましょう。家には七輪もあるので、七輪で焼きおにぎりなんかも良さそうですね」
と、私の唐突なおにぎりの話についても、とても前向きに対応してくれました。その時、当時ハマっていた私のおにぎりのInstagramを見ていただき、色々なおにぎりの写真を見て「おおお~!」と色々なおにぎりの写真に驚いた様子で、
「おにぎりいいですね~! あっ! おにぎりの人だ!!」
と、私のことを「おにぎりの人」と認識した様子でした。
「こちらこそ、ぜひ、よろしくお願いします! また改めてご連絡いたします」
と言って去ろうとしたとき、
「あ、これよかったらどうぞ」
と言って最後に武士殿に、ふと手渡されたのが『アフリカ』でした。
「ここで、文章教室というのをたまにやっている方がいるのですが、この前もその文章教室があって、これはその方たちで作られている雑誌です」
と、たまたま帰り際に武士殿に渡されたのが『アフリカ』でした。これが『アフリカ』との最初の出会いでした。武士殿も参加したことがあるという文章教室についての話を聞き、
「なんだか、おもしろそうですね!」
と、早速私は興味を持ち、その『アフリカ』を受け取り、イロドリを後にしました。初めてお会いした武士殿は、なんのアポイントもなく突然来た私に対して、とても親切な方でした。
帰りの電車で椅子に座り、武士殿に手渡された『アフリカ』を読み始めていると、なんだか他人事ではないような登場人物が出てきました。その話の内容と私も似たようなことを考えているなぁと、思いながら読んで帰ったことを憶えています。その日から『アフリカ』は私のしんどい日常にすっと入って来たのでした。一緒に帰りの電車に乗って、いつものしんどい日常の環境へと帰り、文章教室とはどんなものなのかと、気になっていました。たまたま『アフリカ』と出会ってから、3ヶ月後ぐらいたったあたりに、文章教室の案内人で道草家の方に連絡をしてみました。気になったことをそのまま置き去りにしなかった私は、こうして『アフリカ』とつながっていったのです。
これが、私の『アフリカ』との最初の出会いであり、道草家の方と文章教室との出会いでもありました。この日の武士殿と話したこともよく憶えています。それから、コロナ禍が長引いて「おにぎりを作る会」は未定になりました。その後3年の間に自分の身の回りも心境も随分と変わっていきました。この激動の3年間、本当に色々なことが私にはあったのですが、しんどい日常の傍らで『アフリカ』を読みながら、道草家の方にお願いして始まったオンラインでの文章教室にも参加し、毎月の「WSマガジン」に移行した後も、なんとなく文章を書き続けました。じわじわと生活が崩れていくような変化が立て続けに起きていた私は、『アフリカ』の最新号が発売される度に買い、その中の登場人物たちと、しんどい日常を一緒に歩いて来ました。今にも悲しみに打ちひしがれそうだった私は、この『アフリカ』と、文章教室に参加することによって、だんだんと重たかった心が救われていくようでした。たまたま『アフリカ』と出会えたのは、好きな場所で訪れていた鎌倉で、好きなウクレレと、好きなおにぎりによって導かれた何か運命的な出会いのようにも思えてきます。

そして2023年には、私の文章も『アフリカ』に載せていただくこととになりました。あの頃、しんどい日常の中で読んでいた『アフリカ』という雑誌に、まさか自分の文章が載るとは思ってもいませんでした。とてもうれしかったです。しんどい日常の中で『アフリカ』を読む人だった私が、3年後、いつのまにか文章を書く人になっていました。それと同時に、いつのまにか、あのしんどかった日常からも解放されていました。
コロナ禍を過ぎ、約3年ぶりに再びイロドリに向かい、私は久しぶりに武士殿と再会しました。あの日の『アフリカ』がきっかけで、今、文章を書いているということを話したとき、武士殿は私にこう言いました。
「え! そうだったんですね。うれしいです。わあ~、文筆家だ!」
と、今度は「文筆家」と私のことを認識されたようでした。2023年の春、やむを得ず仕事と生活環境を失ってしまった私には、文章を書くことしか残っていませんでした。たまたま自分を救うように書いていた私の文章は、2023年の11月にも『アフリカ』に載せていただき、文筆活動だけが続いていました。また何か救われた気持ちになりました。窮地のときにいつも支えてくれた『アフリカ』。私もだれかの心をそっと支えるような文章が書けますように。そして、どこかの誰かのしんどい日常に、『アフリカ』がそっと届きますように。

(2024年2月18日更新)
広い空が見える。 - UNI
下窪さんからインタビューを受けているとき、わたしは北海道北見市にいた。
『アフリカ』は、その後、印刷されてわたしの新居に届いた。一人暮らしのポストに、ピザや新築マンションのチラシではない、わたし宛の郵便物が入っていることが嬉しかった。
ことばは文字になり、紙に刷られて記憶へと定着する。『アフリカ』を読んだとき、インタビューを受けていた時間の、ある数分間がやけに浮き上がってよみがえった。下窪さんとオンラインで喋りながら、元夫が台所の扉を開け閉めする物音が聞こえていたこと、それから玄関へと続く階段をおりていった音が聞こえたこと。
劇的なことが起きたのは『アフリカ』のほうだった。自分自身が起こした決別とそれはリンクして、何か大きな意味を持ちそうで、わたしは怖くなってしまった。心に波風を立たせないように、わたしは創作からそうっと離れようとした。
わたしは下窪さんの学生時代の話を聞くのが好きだ。根掘り葉掘り聞くわけではないけれど、つまみ食いのように「つまみ聞き」「つまみ読み」していたら、うっかり自分自身も同学年ではないにせよ同じ空間にいたような気になっていた。わたしがバスをおりてキャンパスの門をくぐるとき、そこに姿は見えなくても下窪さんはカフェテリアでうどんをすすっていた、ような。 だからインタビューでわたしの学生時代の話に下窪さんが興味を持ってくださったことで、そうだわたしはこれまで書いたり作ったりなんかしてこなかったんだ、と思い出した。下窪さんと同じ空間にはいなかった。芸大にわたしはいなかった。政治系の学部で勉強しているようなしていないような日々を送り、本は読むばかりだった。それも暗いロシア文学を夏に読んでしまってからはひと夏まるまる落ち込んでしまって何も読めなくなったりなど、創作物に振りまわされることもしばしばで、距離を置いていたりもした。
『アフリカ』最新号はいつも近くにおいてある。ワンシーズン落ち込んでしまうような雑誌ではない。でも最新号はガツンとくる。手元に置いている。今も続く、わたしの悪戦苦闘の日々の横にある。 インタビューを受けたときの、北海道の部屋を忘れたい気もする。忘れたくない気もする。南に二重窓があり、本州の田園風景とは違う広い空が見える。インタビューのメインは離婚の話ではなかったけれど、離婚を決めた時期のわたしをパッキングしている号だ。
表紙の切り絵が見つめてくる。極楽の鳥のような。喪失感とともに歩いていくと見えてくる風景、それが『アフリカ』の次号にあるのかもしれない。
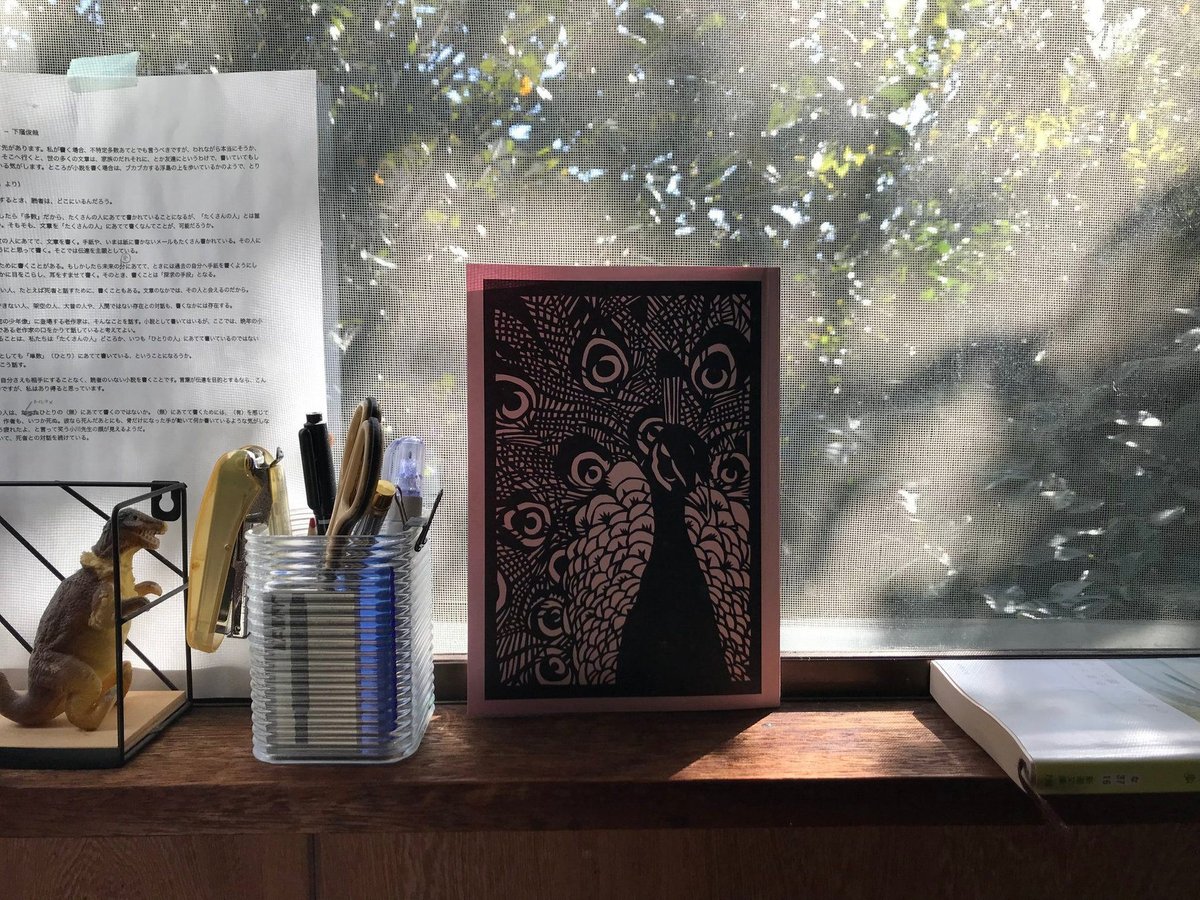
編集後記 - 下窪俊哉
というわけで、今回は、ここまで。
『アフリカ』をつくった後に、このような原稿(コメント)をお願いするのは、初めてのことでしたが、やっぱり、聞いてみないとわからないような話が続々と出てきて、私はとても面白かった。
出来うるなら、向谷陽子さんにもコメントを貰って、ここに加えたいところですが、叶わないことになってしまいました。
でも、本当にそうでしょうか?
文学には(そして、あらゆる芸術には)、死者と話せる何らかの隙間があると私は思っています。
これから私は、彼女の生まれ、育った、そして若い頃の一時期を除いて亡くなるまで暮らした広島を訪ねて、"会って"来ます。
次に送られて来るはずの切り絵を、私は永遠に待っているでしょう。"待つ"という時間の豊かさを感じます。
これからきっと、生まれ変わって、現れてくる『アフリカ』を、またぜひお楽しみに。私も楽しみです。
“セッション”という形 - 犬飼愛生
『アフリカ』は同人制をとっていないところが魅力です。
原稿を出しても、載らないかもしれないという緊張感。これが良い。
編集人の目が光っていて、“セッション”という形で、編集人と対話しながら原稿を直すところが醍醐味です。
いいかげんなものを書くとすぐに見透かされてしまいます。
見透かされるたびに、私はこの編集人はさすがだなあ、と感心しつつ、反省しつつ、ちょっと安心して原稿を直しているのです。
(2024年2月20日更新、これで、おわり)
