
民謡は世界の音楽をつなぐ「結合組織」。バルトークの発見に新たな視点! 『トランシルバニア舞曲』 8月30日リリース(ECM)
「遠い未来の音楽家たちは、わたしたちが見逃していた農民音楽の特質を発見し、彼ら自身の音楽の中で具現化するということがあるのかもしれない」(バルトーク、1921年)
タイトル写真(左)マット・マネリ、(右)ルチャン(ルシアン)・バン/ ©Mircea Albutiu
*この記事では、ルーマニア語の発音「ルチャン」を基本にします
『トランシルバニア舞曲』(Transylvanian Dance)は、100年前にハンガリーの作曲家、ベーラ・バルトーク(1881〜1945年)が収集した民謡や舞曲のtranscription(採録・採譜・編曲)を出発点としています。
2022年にティミショアラ(ルーマニア西部トランシルバニア地方の都市 )でライヴ録音されたもので、1909年から1917年にかけてトランシルバニアでバルトークが収集した民謡を、ルチャン(ルシアン)・バンとマット・マネリが再解釈しています。
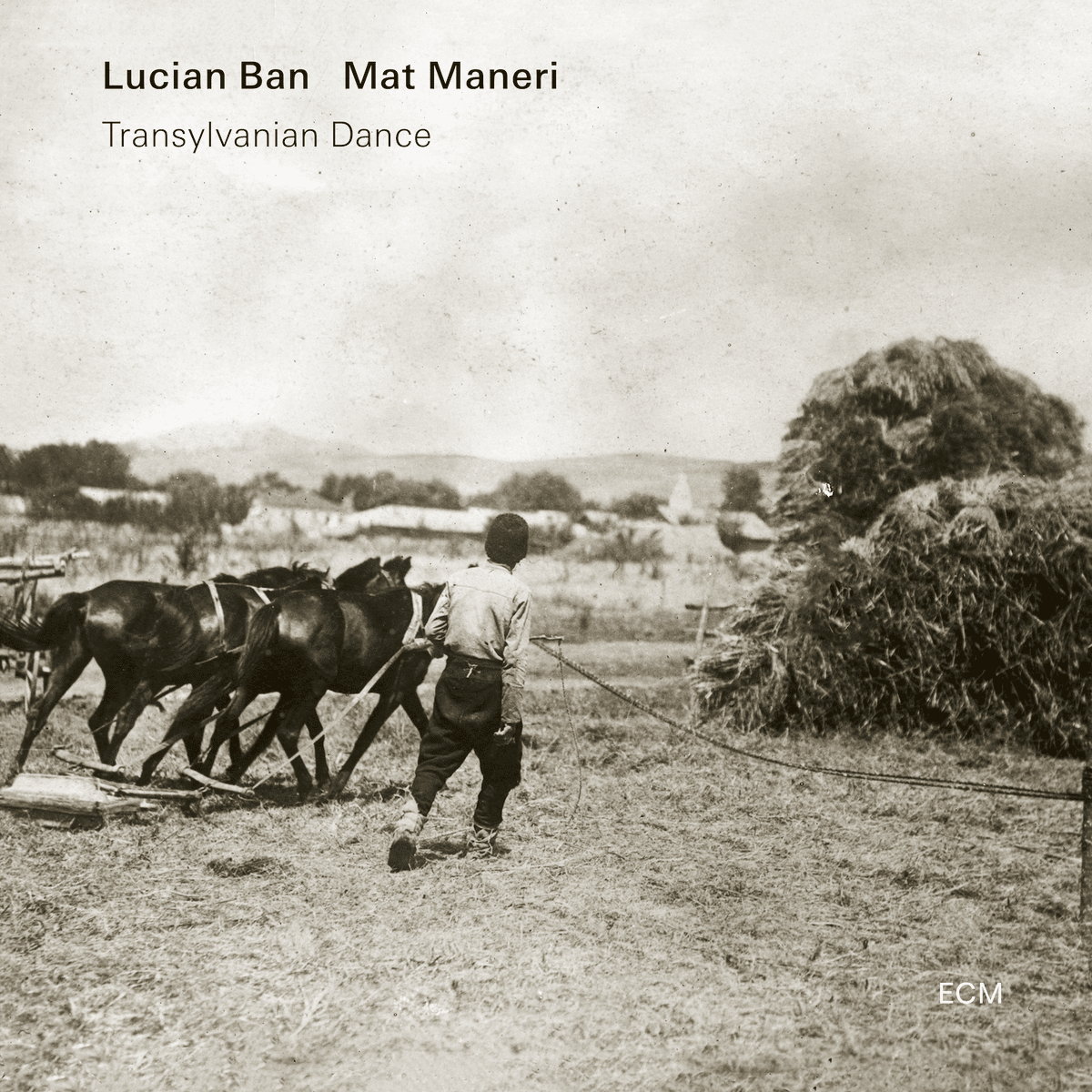
Cover photo: Romania farm scene, 1919
6月中旬、DL Media Musicから『トランシルバニア舞曲』の案内をもらい、宣材の中にあった「バルトーク」「民謡」「世界の音楽をつなぐ『結合組織(connective tissue)』」「クラシックおよび現代音楽」「即興」「ピアノとビオラ」といったワードに惹かれて、プレビュー用アセット(MP3、ブックレット、写真などの一式)を申し込みました。
以下はこのアルバムについて、二人のジャズ演奏家がここで何を実現したのか、ソース&インスピレーションとなったバルトークの民謡発見とは何だったのか、いま、音楽におけるジャンルとは何か、カテゴリー分けは誰のためのものなのか、などを思いつくままに書いていきます。
民謡の魅力、魔力(私的な視点から)
民謡(traditional folk song & music):ある地域で、地域集団により口承によって伝わってきた作者不明の歌・音楽・踊り。長期にわたり祭事などで慣習的に演奏・披露・奉納され、世代間で変化を遂げてきた音楽。(筆者の定義)
20世紀初頭の作曲家たちは、数百年つづいたヨーロッパ音楽の伝統に行き詰まりを感じ、新たな再生の道(方法論や様式)を探していました。無調、12音技法はその表れの一つですが、「民謡の発見」も再生の手がかりの一つとして多くの作曲家に引用されています。
それほど意識してこなかったものの、つらつら考えてみると、「民謡」という要素は、わたしが常に好奇心を刺激される因子となってきました。たとえばショパンのピアノ曲で何が好きか、と訊かれればマズルカを一番にあげます。中でも、演奏される機会は少ないけれど、民族色の濃い、素朴で土臭い曲に親近感をもっています(OP.68、no.2、no.3など)。マズルカはポーランドの舞曲、ワルツと同じ3拍子ながら第2拍、第3拍にアクセントがあり、つっかかるようなリズムが特徴です。またプロコフィエフの『ピアノ協奏曲2番』の第4楽章には、わらべ歌のような素朴な歌が中間部に挟まり(最初にピアノソロで、その後バスーンなどにより繰り返される)、不協和に満ちどこか壊れたイメージの、不穏かつ劇的な全楽章の中で、特別な効果をあげていて印象的です。
日本の民謡ということでいうと、本土のものではなく、アイヌと沖縄の子守歌に強く惹かれました。以前に大学の音楽学科で聴講生として民族音楽や日本音楽を受講していたとき、この二つを比較して類似点について論文を書いたことがあります。本土のものとは、音階や言語においてかなり違いがあります。少し前に偶然、シンガーソングライターの寺尾紗穂さんが、日本のわらべ歌について書いているシリーズ記事を読みました。寺尾さんによると、徳之島(鹿児島県)は、音階上、本土の南限にあり、それ以南の歌との境界線になっているとのこと。寺尾さんは日本中のわらべ歌を訪ね歩いたり、調べたり、自分で歌ったりしています。
民謡に惹かれ、あるいは影響を受けた20世紀の作曲家は、バルトークにとどまりません。ストラヴィンスキーやファリャも、自ら採集はしなくとも、直接・間接的に民謡を素材として、あるいは様式として扱っている、とバルトークは著書の中で指摘しています。(『バルトーク音楽論選』)
20世紀初頭のヨーロッパの作曲家にも、現代の日本のソングライターにもアピールする、面白さや美しさに溢れ、収集したり、アレンジしたり、演奏したりしたくなる魅力を、民謡はもっているということでしょうか。
ルチャン・バン(Lucian Ban)とマット・マネリ(Mat Maneri)
ルチャン・バン(ピアノ)とマット・マネリ(ビオラ)のデュオによる『トランシルバニア舞曲』は、ルチャン・バンがトランシルバニアの出身であることが、アルバムを生む大きな要因になっているようです。ルチャン・バンは1969年、トランシルバニアに生まれ、幼少期にこの地域の民謡を、結婚式や誕生のお祝いなどでたくさん聞いて育ちました。7歳のとき、ピアノと作曲を学びはじめ、その後もクラシック音楽の勉強を大学で続けています。ただ大学卒業後にはジャズグループを結成し、2枚のアルバムをリリース。そして1999年にアメリカに移住、ニュースクール大学で学び、ジャズでアメリカデビューを果たしています。(チャウシェスク政権下のルーマニアでは、ジャズを学ぶという選択肢がなかった、とブックレットにはありました)
一方のマット・マネリはアメリカのバイオリン奏者。5歳のときから音楽教育を受け、こちらもクラシック音楽を基礎にしています。が、その後ジャズの演奏家になり、楽器もある時期にビオラと出会ったことで、こちらを中心に演奏活動をしているようです。父親のジョー・マネリはサックス奏者。
マット、ルチャン、どちらもクラシック音楽の教育を受けたのちに、ジャズの道に入った人のようで、幅広い音楽への興味、基礎訓練や経験のもと、ジャズを本拠としながらも、ジャンルにこだわらない、ときに境界をこえる音楽活動をしてきたのではないかと想像します。
そういった音楽履歴をもつ音楽家が、バルトークの収集・編曲したルーマニア民謡から大きなインスピレーションを受け、新たな、現代の、自分たちがいま感じ、演奏したい音楽を生み出そうとしたのは自然なことに思えます。

Photo by Dani Amariei
ビオラという楽器の効果
『トランシルバニア舞曲』は全8曲からなるアルバム。5、6分前後の曲が中心です。ピアノとビオラ、二つの楽器しか使われていませんが、音色は多彩です。ピアノは鍵盤で音を鳴らす以外に、現代音楽などでよくやるように、(グランドピアノの中に手を入れて)直接弦を叩いたり弾(はじ)いたりしているようです。ビオラはバイオリンとチェロの中間の音域をもつ弦楽器ですが、バイオリンの澄んだ輝かしい音と比べると、渋みのあるややくすんだ落ち着きのある音が特徴です。わたしはこのアルバムの楽曲がバイオリンではなく、ビオラで演奏されているところに共感をもちました。民謡を奏でるのに、洗練度がバイオリンより低い(これは私見)ビオラはぴったりに思えました。
ビオラのような中間音域の楽器が、限度ギリギリの高音域の音を奏でるときの、雑音混じりの「悲鳴」に近い音色が非常に魅力的です。弦と弓がこすれ、物理的に激しく、または微かにこすれ合いながら上行し、なんとかメロディーを奏でているのを耳にすると感情が揺さぶられます。同じ音域の音を、バイオリンが楽々と、澄んだ輝かしい音で鳴らすのとは、色彩感がまったく違います。
外れた音で奏でる
わたしにとって印象的だった第7曲「The Boyar's Doina」を例にとります。タイトルの「ドイナ」はルーマニア語で民謡を表す言葉のようで、Boyar(ボヤール)はロシアなどの中世の貴族階級を指すようです。
冒頭、ピアノがごくシンプルに4つの音からなる短いフレーズをスタートさせます。シーレ(↑)♭ラ(↓)ーレ(↑)、シーレ♭ラーレ、シーレ♭ラーレ……シーレ♭ラーミ…(ハ調音名)、そこにビオラが乗ってくるのですが、調性感(ハ長調とかホ短調など)はない、もしくは感じられない、あるいは無視しています。
このことだけで不穏なムードがかもしだされます。さらにビオラによる民謡のメロディーが、西洋音楽の音程感からはかなり外れています。ドレミファのピッチに合っていません。中間音というのか、微分音というのか、ドとレの間、レとミの間といった、インドやアラブ世界の音楽にもある音程感に満ちています。弦楽器というのは、これが自在にできます。(うらやましい)
マット・マネリは微分音について次のように言っています。
(微分音は)人間の声を模倣するだけでなく、不快な緊張感を作り出しそれが優しい揺かごに行き着く、といった私のアプローチを強化してくれる。
私は、民謡における「音程の悪さ」に強く惹かれて、そこから独自の音楽言語を生み出した(サックス奏者である)父の能力に恩恵を受けている。
クラシックからポップスまで、西洋的調性感に慣れ過ぎた耳にとって、ピッチの外れた音というのは新鮮で、それだけで得体の知れないザラザラしたものに精神の中枢を撫でられている気分になります。
「The Boyar's Doina」では、ピアノのシーレ♭ラーレ、シーレ♭ラーレ……は永遠につづくのか、というくらい鳴りつづけます。こういう曲想の楽曲は、たとえばフィリップ・グラスの『エチュード』でも多用されています。ミニマルミュージックと言われているものです。短いフレーズのリピートによって静かな興奮が醸成され、その上にごくシンプルな「歌」がフリーハンドで即興的に重ねられます。
曲の半分あたりでピアノの即興演奏がはじまり、これはジャズの技法あるいは様式によるもの、そしてそれに寄り添うように、さきほどのシーレ♭ラーレ(ミ)のフレーズが、こんどはビオラによって奏でられます。この中間部あたりに数回、西洋音楽でいうところの「解決」のような短いフレーズがあり、両楽器が同じ音程感によるまとまりを一瞬見せます。アクセントというか休息のような効果。
そしてピアノによる冒頭のシーレ♭ラーレのフレーズがはじまり、西洋音楽でいうところの「再現部」のような様相を見せ、ビオラが民謡のメロディーを奏でながら曲は終わります。最後の方は、ビオラの音は木管楽器のような、あるいは尺八のような音を出していました。
調性を捨てる
普通、音楽といってイメージされるものは、その多くが現代においても調性感という枠の中に収まっています。古い時代のクラシック音楽はもちろん、ポップスでもレゲエでもラップでさえ、調性感がある程度、あるいはたっぷりあることで聞きやすくなっていると思われます。そこにはメロディーラインと背景にある伴奏的な音が、一つの調性(ハ長調、ト短調など)の規律の中で動いているということです。
さきほど第7曲「The Boyar's Doina」では、ピアノのフレーズの上に乗っているビオラのメロディーが、調性感としては外れた音で奏でられていると書きました。たとえて言うなら、ト短調の伴奏の上にハ長調のメロディーが乗っているというようなことです。ただこの曲・演奏は西洋音楽では(たぶん)ないので、外れているというのは間違っているかもしれません。そもそも民謡に調性感はあるのか?
最近発見したのですが、バルトークの若い頃の作品で『14のバガテル』というピアノ独奏曲があり、その第1曲が楽譜の上下段(右手と左手)が別の調性で書かれていました。

楽曲解析は自信ないですが、調号から判断するなら上段はホ長調、あるいは嬰ハ短調、下段は変イ長調、あるいはヘ短調と思われます。上段はおそらく嬰ハ短調、下段は変イ長調に見えます。調性があれば、の話ですが。これが合ってるとするなら、右手短調、左手長調ということになります。しかも調性も違う。
最初、うっかり調号に気づかずに(だって上下段で調号が違うなんて!)左手も上段に合わせて弾いていたら、普通に調性的でした。当然ですが。
バルトークはなんでこんな変なことをしたのか。調性逃れ? あり得ます。それとも、左端に置かれた♯、♭の調号は、調性を表しているわけではない?
ピティナ・ピアノ曲事典の解説をみると、
「第1曲:右手にはシャープが4つ、左手にはフラットが4つずつつく。嬰ハを基音とするドリア調と、ハを基音とするフリギア調の複旋法になっており、響きの上では、一つの中心性が認められる」
と書かれていました。
あ、やっぱり調性はないんですね。調性音楽以前の古い音階がここでは使われているようです。新しい実験的な作品を書く際に、バルトークは古い時代の教会旋法をもってくるという。面白いですね。
響きの上の中心性、これは演奏してみると違和感はありつつも、どこかまとまり(中心)があるような、小さな「安心感」があるのは確か。無調音楽の冷たさとは少し違うのがバルトークかも。
不明瞭、否! それに勝るスリリング
アルバム第1曲の「Poor Is My Heart」は、耳馴染みがよく、デュオが同じ音程感の中で歌っているように聞こえて、逸脱感は最小限です。(この曲は、現地7月19日にプレリリースされる予定なので、追ってnoteで紹介します)
ただ、全体としては、このアルバムでマット・マネリがビオラで歌うメロディーは、西洋音楽には聞こえません。古い時代の民謡は、西洋音楽発生以前のものです。音程感も違えば、調性感もない。ドレミファで歌っているわけではない。
以前にわたしがついていた作曲家の先生は、学生時代に日本の地方をまわって民謡の採集をしたのですが(たぶん戦後間もなく)、そのとき録音することのできた年配の方々の歌う民謡は、ほぼ昔の日本の音程感で歌える最後の生き残り人々のものだった、と言っていました。
現在歌われている民謡は、ほとんどがドレミファの音程感の影響を受けた歌い方。それは日本もヨーロッパも同じだと思います。
長々とここまで音程感について書いてきましたが、『トランシルバニア舞曲』で二人の演奏家が注目していたのは、一つには西洋音楽以前の音程感の中にある音楽(バルトークが採集した時代の民謡)を、今の時代だからこそ、探究することだったのかもしれません。ピアノという動かし様のないピッチの近代楽器と、ビオラという人間の声にも似て微分音程が自由に出せる楽器の対比により、過去の民謡がもっていた不明瞭な音程感を、誰の耳にも届くように表現する、といった。
近代楽器(ピアノ)とそれ以前の音に近づこうとした楽器(ビオラ)の対比、つまり100年という時代の対比を明らかにすること。その対比によって、「悪い(不適切な)音程」による不快感によって、近代の行き着いた先にある現代をあぶり出し、音楽によって世界を俯瞰すること。
この見立ては、すべてわたしの想像(妄想)に過ぎませんが。
このことは記事冒頭にあげた、バルトークの予言(予見・予知)と合致するでしょうか。

バルトークによる民謡採録(音源)
ベーラ・バルトーク:ろう管によるフィールドレコーディング
Bela Bartok - Field recordings of Folk Music on wax cylinders
『トランシルバニア舞曲』第8曲「Make Me, Lord, Slim And Tall」は、1914年にムレシュ県で、11歳と13歳のキオレアヌ姉妹がバルトークのために歌った録音がソースで、子どもの歌であり、また祈りの歌でもあるそう。
(『トランシルバニア舞曲』ブックレット)
マット・マネリはこう語ります。
これを聞いて、以前に聞いた西アフリカのメロディーを思い出さずにはいられなかった。と同時に、隣の村で録音された似たような歌との類似性も感じる。「連結・統合(connectivenes)」という考えが、メロディーを奏でるときの勇気になったし、さらにはもっと他の地域の伝統さえ引き出すことができた。
音楽にとってのジャンルとは
このアルバム『トランシルバニア舞曲』は、どこにカテゴライズされる音楽なのでしょうか。演奏者がジャズの人であれば、おそらく「ジャズ」に分類されます。しかし実際に音楽を聴いた印象としては、演奏中に一部、ジャズの様式を挟むものの、「ジャズを聴いた」という風でもありません。
タグ付けするなら、「バルトーク」「民謡」「ルーマニア」「現代音楽」「ピアノ」「ビオラ」などとともに「ジャズ」のワードが入ってくるのは間違いありませんが。
ジャンルは目安としては役にたちますが、音楽そのものを的確に表すかどうかは疑問です。マーケットや研究対象を分析する際の便利なツールなのかもしれません。ある意味、ビジネスのための業界用語であるとか。
カテゴリー分けはなくていいか、と言えば、あってもいいとは思います。ただ音楽をつくる人たちは、ジャンルをまず頭において曲作りをするかと言えば、そうではなくて、単に音楽をつくる、という行為をしているのだと思います。楽器編成や曲の構造、ソース、テーマなどをあらかじめプランしたとしても、何ができるかは結果。基本は、自分のこれまでの枠から出ていくことが、新しい音楽を生むエネルギーにつながっているのでは。
逆にいうと、⚪︎⚪︎というジャンルから一歩も出るつもりはありません、という音楽づくりは、過去の模倣や繰り返しであり、演奏者も聴衆も退屈してしまう可能性が高いです。
その意味で、『トランシルバニア舞曲』は、二人の演奏家がバルトークの採集した民謡にヒントを得て、音楽における何か新しいものを見つけようとしたプロセスの記録とも言えそうです。
ちなみに、このアルバムのソースとなった民謡は、ルチャン・バンが生まれ育った村のすぐ近くの村々のものだそうです。バルトークが録音機を手に民謡に聞き入った、その半世紀後、ルチャン・バンはそこで生まれています。
「Poor is my Heart」の冒頭部分のビデオ
以下のページにルチャン・バン提供のビデオを置きました。アルバム第1曲「Poor is my Heart」のファーストバージョンと、2022年、ティミショアラでのライブ録音の冒頭部分を聞くことができます。(50秒、51秒)
