
「魯山人への旅」 イマジネーション体験 銀座花伝MAGAZINE vol.25
#魯山人への旅 #イマジネーション体験の奇跡 #三つの「石橋」

明け方、人気の無い銀座中央通りの真ん中に立って、屈んで目線を限りなく地面に近づけると、蜃気楼のように見える建物と石畳に、歴史の息遣いが宿っていると感じることがあります。
江戸・明治と現代への400年の歴史、日本文化と西洋文化の交差点、江戸粋文化と京都雅文化の合流点、そんな多層な時間と空間が見えてくるからかもしれません。目の前にある現実は、人間にだけ備わったイマジネーションによってどこまでも無限にその姿を変えていきます。
イマジネーションによって「人生の経験値」を上げることが可能になる、そんな「旅」の物語りをお届けします。さらに、旅とイマジネーションの極め付け「能・石橋」にかけた三名の演能者たち(坂口貴信師/観世宗家観世清和師/坂東玉三郎師)の舞台レポートとともにお楽しみください。
銀座は、日本人が古来から持ち続ける「美意識」が土地の記憶として息づく街。このページでは、銀座の街角に人々の力によって生き続けている「美のかけら」を発見していきます。

Ⅰ 特集 イマジネーション体験旅の奇跡
あなたは旅が好きでしょうか?
コロナで旅に出られない、世界旅行はもとより国内旅行も躊躇してしまう、旅好きにはストレスが溜まる一方だ、と今の社会状況を嘆く声が多い。
そもそも、旅とは何だろうか。リアルに体を運ばなければできないものだろうか。古今東西旅にまつわる様々な情報と暮らしの進化を辿りながら、本当の意味の「旅の魅力」とは何か、銀座の体験とあわせて探ってみたい。
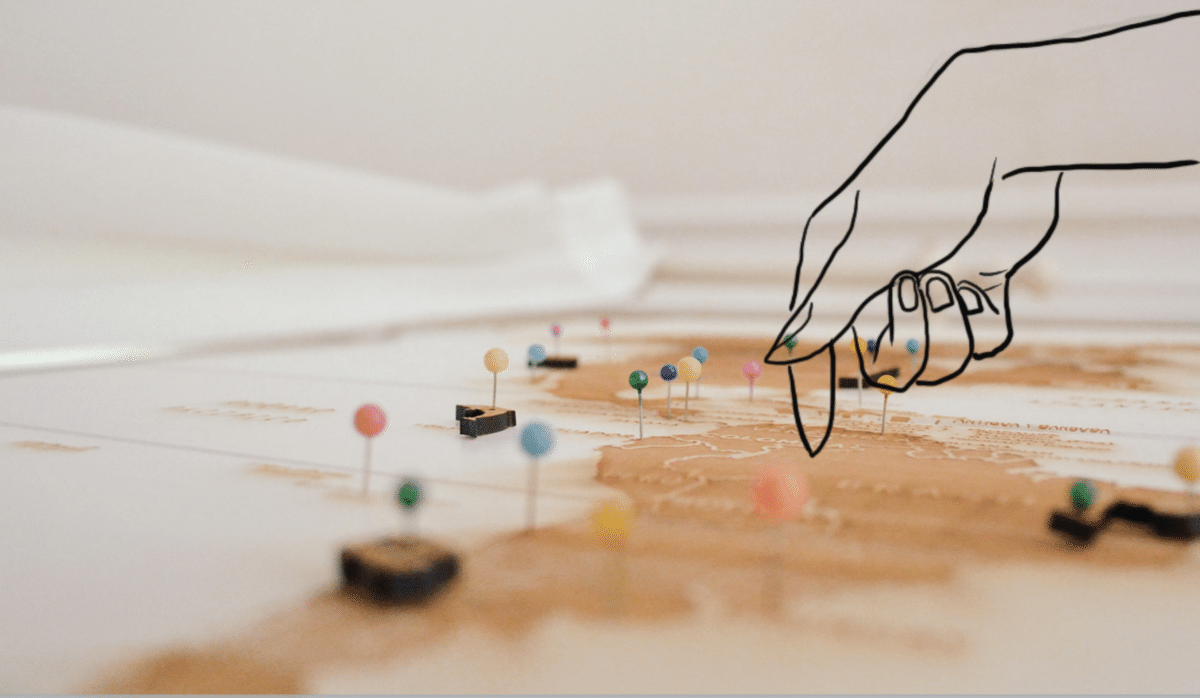
第1部 変わる旅のカタチ
・西洋では「苦」の代名詞
旅の語源を探ってみると面白いことが分かってくる。私たちがよく使うトラベルは、ラテン語の「3本の杭」を表す「トリパリウム」に由来する。「3本の杭」は古代で囚人の拷問に使われた道具で、転じて苦難の代名詞になった。やがてこの「トリパリウム」が、中世には「苦労」を表す「トラベイル」となり、トラベルが生まれたのだという。これは、当時は道中で盗賊に襲われる危険もあった上、交通手段も徒歩や馬、帆船が主なもので、1つ間違えると命を落としかねないほど、昔の旅は苦難と隣り合わせだった背景があったからだ。
トラベルの他の表現としてトリップがある。同じ旅でもトラベルは長期に及ぶ旅を、トリップは短い日程の旅を指す。トリップのルーツはもともと古フランス語で「軽く踏む」の意味を持つ「tripper」から来ていて、この「tripper」が時代が下るにつれて「少し足を伸ばす」に変化したようだ。そして「少し足を伸ばして出かけられる旅」を指す単語として、トリップが生まれるに至ったわけで、トラベルに比べて気楽なニュアンスを持つ単語として使われている。

・日本における「旅」の意味
では、日本語の「旅」にはどんな由来があるのだろうか。
語源には、「他日(たび)」「外日(たび)」「たどる日」「外辺(たび)」「飛(とび)」「発日(たつび)」「給(たべ)」「他火(たび)」と諸説あり明確な答えはないようだ。中でも他所で日をまたぐことを意味する「他日」と「たび」と読むことに由来する、という説が有力に思える。「他日」の背景には、旅は危険を伴うものであると考えられてきたことがあるとされており、トラベルの由来に通じるといえよう。
漢字の「旅」(りょ)は漢和辞典には、ふたつ以上の漢字を組み合わせて作った会意で、方偏(かたへん)は「のぼり旗」、旁(つくり)は「人が多数従う从」を表し、「軍旗を押し立てて戦争に向う人々」を意味するとある。それに対し、『世界百科事典』(平凡社)には、「多数の人々が祭祀を行うため、氏族の旗を立てて、祭祀の場に行く」こととある。
奈良時代の貴族であり、「万葉集」の歌人、大伴旅人(おおとものたびと)の名の由来について興味深い説がある。「旅人」という名から、「旅ゆく人」というロマンチックなイメージを描きがちだが、一方で政治家であった点を見落としがちだ。7世紀から8世紀の官人・大納言安麻呂の長男であり、養老2 (718) 年中納言,同4年征隼人持節大将軍に任じられ,隼人(古代の薩摩地域を指す)地方の反乱鎮圧に功があった人物である。武門である大伴氏の嫡流である以上、「軍旗を手にして遠征する立派な将軍になれ!」という気持ちでつけられた名前であったというものである。
この説に依拠すると、この旅人(たびと)から、日本語の(たび)の語源を改めて推量できるという。すなわち、それまでは、(たび)は「手(た)+火(び)」、(ひと)は「日(ひ)+と」であったが、旅人(たびと)という名前から、(たび)は、「た+日(び)」と変化したのではないだろうか、というのだ。甲(かん)音に対して「一段と低く下がるもの」、また、「低く、しんみりした音」であると解く人もいるが、「旅」の語源に関しては結局のところ悩みを深め、今なお諸説粉々の様相を呈しているようだ。
・「旅」を人生に準えた芭蕉
旅といえば、江戸時代前期の俳人・松尾芭蕉を思い出す。
月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり。
紀行文学の最高傑作と言われる「奥の細道」の冒頭には、「舟の上に生涯を浮かべ、馬の口とらへて老いを向かふる者は日々旅にして、旅をすみかとす。」と自らの人生を旅に準えている。船乗りや、馬子というような人は旅そのものが生活の場なので、定住する家を持たず、家を持たない、それは一種の自己解放で、何にも束縛されず、気の向くまま生きていける境遇こそが人世の愉しみだと語る。
しかし、一方で実際には旅の途上での孤独な死を覚悟するという代償を引き受けながら旅を続けた様子も垣間見える。芭蕉は野ざらしを覚悟することによって自由を手に入れたのだろう。
1689年の陽暦5月9日、芭蕉は弟子の曽良を伴い、深川を出立し、松島、平泉、象潟を目指す。やはり旅を栖(すみか)とした尊敬する歌人でもある能因法師(988年-1058年)や西行法師(1118年-1190年)の足跡を辿ることが元々は俳人・芭蕉の旅の目的だった。およそ2400km、150日に及ぶ行脚は、人生50年の当時、既に46歳の芭蕉にとって、どれほどの苦行だったか、想像に難くない。しかし、同年の陽暦10月11日、旅は見事に大垣(岐阜県)で完結を見るのである。
芭蕉は旅に2つの意味を込めた。
先人の旅跡を巡り、俳諧を極めること、そしてそれだけでなく歴史的な背景、倫理観を考える中で、「亡き人々への鎮魂」と「不易流行の境地」に辿りつくことにつながる徳性(倫理観・人生観)をも追い求めた。
「夏草や兵どもが夢のあと」(二十五「平泉」)
鎮魂歌の代表的な句としてよく知られている。史実に基づき源頼朝に滅ぼされた奥州藤原氏と義経主従を鎮魂する名句だが、芭蕉はそれを含めた長い戦乱の時代に散った多くの人命に対する鎮魂句として詠んでいると解釈されている。
「不易流行の境地」
芭蕉は辿り着いた俳諧の理念伝統を踏まえつつ、一方では新しいものを取り入れることが大切だと、その徳性を説いた。「不易」は時代の新古を超越して不変なるもの、「流行」はそのときどきに応じて変化して行くものを意味し、両者は本質的に対立するものではなく、真に「流行」を得ればおのずから「不易」を生じ、また真に「不易」に徹すればそのまま「流行」を生ずるものであるという。こうした理念の成立してくる背景には、易学、朱子学、宋(そう)学の思考法や堂上歌学の不易流行論があったといわれるが、その論は具体的には『去来抄』など門弟の記述によってみるほかはないために、それぞれ実際には芭蕉の旅の目的については、多様な解釈の幅を生じさせている面もある。
物理学者・寺田寅彦は、科学感を底流とした写生的描写の名随筆でファンも多いが、その彼は夏目漱石に英語と俳句を学ぶ中で芭蕉紀行文に出会う。「天文と俳句」(1932)の著書の中で、「芭蕉が解いた〈不易流行〉の原理は実はあらゆる芸術に通ずるもの」といい、「恒久なる時空の世界をその具体的なる一断面を捕えて、静けさやわびしさの中にあるものを美しいとする表現に脱帽する」とも述べている。
芭蕉が変えた「旅」の世界観。非日常の旅の中に、鎮魂や癒しを求める現代人の心の今に繋がっているような気がするのは私だけだろうか。心を整えるために「旅」することへの深い憧れを生んだ大きな理由になっているのではないかと思う。

・「こころの健康」を求めて 変わる旅のカタチ
時代は変わり近年、従来の物見遊山的な観光旅行からテーマ性が強い体験型・交流型への新しい旅行スタイルに人気が出てきているという。ニューツーリズムと呼ばれる。
「旅行は贅沢」「旅は不要不急ではない」という発想から、このコロナ禍でも自粛を求める大きな理由になっていたが、実は昨今の旅の動向を探ってみると「癒しを求めて」旅している人々が多いということが分かってきた。つまり「こころの健康」の観点からの旅を求める要因が浮かび上がってきている。これは、精神的健康を維持し、向上させることを目的とする旅行ということである。
現代心理学者・小口孝司(立教大学教授/「観光社会心理学」)によると「旅行のメンタルへの効果は実証されている」という。通常の週末を過ごす人と1泊2日の旅行に行く人という2群を作り、旅行群には旅館への宿泊や旅先でさまざまな活動を行うという条件を加えた上で、旅行に「行く前」、「最中」、「行った後」を調査したところ、旅行群は通常群よりも、コルチゾールというストレスホルモンが顕著に低くなっていたのである。メンタルヘルスを満たす要因としての、仕事等のストレス要因から距離を置く、いわゆる転地効果、非日常のリフレッシュ、リラックス効果が大きいという。
ストレスが高まるとコルチゾール値が高まることから考えると、例えば新型コロナウイルスの状況では、人々のコルチゾール値も高くなっている可能性がある。そのコルチゾール値が旅行によって顕著に低くなるという実証結果は、「不要不急」論を覆し、人々に健康で精神的安定、ひいては健康をもたらすという意味で「必要不可欠」であることを示している。
もちろん感染を広めないための厳しい対策は必要だが、「旅」自体を否定するのではなく、旅が必要不可欠なものとの認識の下、「どんな旅なら可能なのか」に視点を移す大きな端緒になることは間違いないであろう。
・進化する Grow up体験
一方でさらに積極的な意味を持つ、ポジティブツーリズムという新しい旅の形が生まれているという。個人の幸福感、能力、創造性などを向上させる旅行を指す。生産性が上がったり、新たな考えが浮かんだり、さらにはストレスに強くなるという、いわば人の力を「grow up(伸ばす)旅」。地域の特性を活かしたプログラムを組んで体験するとか、オフサイトミーティングを企業内で行わず、仕事場から離れた場所で会食やフリータイムを組み入れるなど、会議室で缶詰になって行う会議より遥かにクリエイティブになるし、これまで未経験の文化体験やボランティアをすることで、視野が広がり自己効力感(困難な状況になった時に立ち向かえる自信)につながるとも言われている。

・ウェルビーイング(Well-being)
一般に、幸せは“Happiness”と訳されるが、これはあくまでも感情的で一瞬だけの幸せのこと。一方Well-beingは持続する幸せで、いま幸福学に関する論文の多くでも、HappinessではなくWell-beingが使われてる。
2007年の国際会議「Beyond GDP」に始まり、2012年にスタートした「世界幸福度ランキング」、2015年9月に国連サミットで採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」でも言及され、より良い社会を築くための指標として注目されているウェルビーイング(Well-being)。1946年、世界保健機関(WHO)設立にあたって考案された憲章にある考え方で、人間の豊かな生活を表す概念と解釈されており、医学、心理学、経済学、デザイン学、コンピュータサイエンスなど多方面から研究が進んでいる。
今後世界のグローバル化が進んで行く中で、一人一人が能力を発揮し、コミュニュケーションを円滑に図り豊かに生きるためには、多様性(ダイバーシティ)を認めることと、ウェルビーイングが必要不可欠であるという考え方が背景にある。
個人レベルでも、ビジネスの場でも求められる良い生き方、ウェルビーイングが定義するところの「身体的、精神的、社会的に満たされている」はどのようにしたら測れるのか。科学的な要素として提唱しているのがマーティン・セリグマン博士によるポジティブ心理学の考え方に基づく5つの目安、これは頭文字を取ってPERMA理論と呼ばれている。
・Positive Emotion(ポジティブな感情)
・Engagement(事柄への自発的な取り組み)
・Relationship(他者との良好な関係性)
・Meaning and Purpose(行動の意味や目的をモチベーション高く追求)
・Achievement(達成感)
各要素のレベルを上げるためには、補助力として個々の柔軟な適応力やストレス耐性(レジリエンス)が重要だという。PERMAの5要素を科学的に測定・分析しつつ、心理学的なレジリエンス研究によって各要素のレベル向上を促進してウェルビーイングの実現を目指すという方法が、ポジティブ心理学の現在の考え方である。
つまり、「心」、「身体」、「知性」、「人間関係」、「感情」をバランスよく獲得するための大切な指標ということができる。先に述べた、ポジティブツーリズムへの時代の需要と、これから私たちが手に入れたいと願う「豊かな生活の実現」が旅の要素と大いに重なり合っていることを発見する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第2部 銀座の旅・魯山人ーイマジネーション体験
・ストーリーが語り出す 地図
旅のお供である地図には、昔から異なる社会を結びつけたり、美しい風景や理想郷的な街並みへの想像を駆り立ててくれる魅力があるものだ。地図は過去の記録であると同時に、これから起こることを予感させてくれるものでもある。手にしたことはないが、宝探しの地図は、伝説の秘宝を探し出せるのかもというワクワク感をもたらしてくれもするのだろう。今や芸術作品にまでなった作品的地図も含めて、地図はあらゆる視点から世界を読み解く大切な視野の広がりをもたらしてくれる。

筆者は銀座の街をインカムでアテンドする際の旅のキットとして、必ずオリジナルの手描きMAPを用意することにしている。目的は、街に降り立つ前に、地図を俯瞰することによって、一気にその街の世界観に没入するための入り口に立ってもらうことである。地図を俯瞰すること、つまり、鳥になって空中から街を眺めることには「世界が手のひらの中にある」という、感覚を高める効果があるからなのだ。
ある日、「和菓子」をテーマにした銀座旅を企画した時のことである。本業は建築家でありながら、革新性の高い和モダンをテーマにした和菓子店として名高いHIGASHIYAもコースに入っていたので、顔合わせの際に緒方慎一郎店主と銀座という街について語ったことがある。銀座には、昔からコツコツと和菓子文化をつなぐ店が多いという話になった。例えば、銀座一店主義を貫く「空也の最中」の潔さのこと、四季折々の景色を絵付けした瓦煎餅という知恵の詰まった「松崎煎餅の三味胴(しゃみどう)」のこと、四百年の歴史のある「あんこ専門店萬年堂」のこと、焼印でオリジナルどら焼きを作る「職人技のよしや」のこと、老夫婦二人だけで営んでいる「大福の小さな店柏屋」、銀座の片隅で芳ばしい「手焼き煎餅を焼き続ける吾作」、流石に詳しくご存知だった。「和菓子の世界では新参者ですから」と謙遜されながら、「でも場所はよくわからない」と苦笑されるので、今回の企画用に作成したMAPを広げてお見せしたのだが、その時のリアクションを今でも忘れることができない。
「これ、ご自身で描かれたのですか」とMAPを食い入るように覗き込んだあとで、大きく空を仰いで「歩く速度が見えるようだ」という。
「え?」と問い返すと、「だって、ほら、それぞれの店からストーリーが聞こえてくるようでしょ」。立ち止まったり、店に入ったり、道を進んだり、その姿が浮かび上がるというのだ。銀座旅に参加されたお客様から「いつも楽しい地図なので大事にしまってあるんですよ」と嬉しい感想をいただくことはあったが、これほど「地図の価値の高さ」について、臨場感を持った賛辞をいただくことは稀だったので、少々驚きながらも「旅と地図」の本質を見出す端緒になりそうだと直感したことを覚えている。
以前世界の地図を専門に研究されている学者のお話を伺ったことがあった。地図の作成というのは、3次元の世界を2次元に変換する技術的制約があるが、細部をどこまで忠実に再現するのかの判断を続ける作業だという。地図に記載する要素を簡素化したり、美化したり、テキストで補足したり、地図記号を使ったり、色分けもある。こうした地図の決まりごとに慣れ切ると、慣例に従った地図はそれだけで、「良い地図」と評価されたりする。
しかし、地図も生きているという。土台の道に重ね合わせたアイコンの表現の仕方によって、地図の印象はどんどん変わっていき、その道を自転車で走ったのか、気になるところを徒歩で見たのか、飛行機で上空から俯瞰したのかさえも浮かび上がることがあるという。
これは人間の脳細胞の働きに関係しているらしいが、「視野の大きさの違い」と「見て回る速度の違い」によって印象が全く違って見えるのは、脳細胞はこれらを統一したイメージとしてまとめることができないから、というのが理由らしい。空間表現と空間認知の違いの成せる技らしく、HIGASHIYA店主のMAP体感は建築家という空間設計感覚の鋭さからのアクションだったと後から理解できたのである。

・人間・魯山人に出会う 感動を生む「共創」
旅を色々な視点で見てきたが、筆者が銀座をさまざまなテーマでご案内する企画を立案するときに心に決めていることがある。それは「人間との出会い」こそが旅、というコンセプトだ。
銀座は著名な偉人と言われる人物がこの街を舞台に活躍し、文化を堆積させてきた歴史がある。今、古くて新しいライフスタイルを求める若者に器が人気だが、柳宗悦の民藝陶器、小津安二郎の美意識の器、そして魯山人の自然感を映し出す器、これらを誕生させた3大老舗が一つのエリアに軒を連ねるのも銀座の特徴だろう。中でも「美の巨人」とも称される魯山人の美意識に触れることはなかなか敷居が高いところだが、銀座中央通りで創業86年になる「黒田陶苑」での出会いは、「本物に触れる」他では味わえない体験として記憶に新しい。この場所でしか体感できない人との出会いの物語、リアル以上に迫る肌感覚、そしてそれをもたらす旅の在り方への提言をご紹介する。

銀座7丁目中央通り沿いの細高いビルの上を見上げると、「黒田陶苑」の文字が円形の中に意匠された看板が見える。北大路魯山人の篆刻に元を辿る筆跡がデザイン化されている。
間口一間ばかりの重厚な入り口の右側には小さな小窓があって、魯山人の小品がさりげなく鎮座している。その前を通るたびに、「今日の魯山人はどんな顔をしているだろう」と覗き込むのが筆者の密かな楽しみだ。
・魯山人との対話
少しだけその重い扉を開けて見ると、細長くのびた店内が見える。あまり人がいないことを確認して、ゆっくり中に入ると、長い壁に沿って魯山人のぐい呑みが所狭しと並ぶ。圧巻である。これほどの作品に一度に出会える機会などそう他にはない。
聞くところによると、魯山人の作った酒器には「ぐい呑み」「酒呑」「酒杯」「さけのみ」「サケノミ」「ぐいのみ」「グイノミ」など、様々な名称がつけられているという。なるほど、1点ずつに個性的な造形のそれらには、それぞれが輝きを持って世に発表されただけのことはある納得させる風貌がある。因みに、現在一般的に使われているぐい呑みという名称は魯山人による造語と伝えられている。
ある日、少し時間があったので、2階にある皿や鉢のエリアまで足を伸ばして見る。
部屋の奥に目をやると、一際存在感のある鉢が現れる。古を思わせる土色の地肌がほのかに桜色に染まっている。手のひらを広げたその中にすっぽり入りそうな大きさの器は「雲綿鉢」だ。桜と楓が器全体に表裏を飛び超えて大胆に、しかも微細に及んで描き込まれている。上から覗くと、美しい湖の湖面を取り囲むように、桜が咲き乱れ、真っ紅な楓が風に揺れている。真横から見ると、古く長く生きてきた証のような桜の太い幹が側面に沿って横たわり、ここにも楓の紅が群れをなして舞っていて、ただただ、美しい。
魯山人の言葉が聞こえてくるようだ。
「美の根源は、自然界が教師であり、お手本であるから、自然界そのものの美の姿に目も心も奪われるようにまず自分を養うべきではないか」
自然を師と仰ぎ、古陶を常に傍らに置き、審美眼を養い続けた魯山人の姿。その背中を見るような感覚に襲われる稀有な時間だ。

目を左面に少し移すと、壁の空間いっぱいを使って1点だけ置かれている。巨大な宇宙を感じさせる圧巻の器、大輪の椿がこぼれ落ちるように大胆に描かれている、「金彩椿大鉢」だ。
赤と白で花を、緑と金色で葉を描いたこの鉢は実は、直径八寸(24センチ)、サイズ感としてはとても実用的な感じで茶の湯の菓子鉢に似合いそうだ。ぼってりとふくよかな丸みは、思わず手のひらに乗せて頬を寄せたくなるような潤いに満ちている。やわらかな肌合いがより椿を大きく見せていて、宇宙を思わせる世界観の広さをここからイメージしてしまう。
魯山人は、江戸時代に京都で活躍した野々村仁清(ののむらにんせい)と尾形乾山(おがたけんざん)を尊敬しており、「雲錦鉢」や「椿鉢」はこの2人の影響を色濃く受けているという。晩年、銀彩や金彩もよく手がけるようになるが、志野・備前・信楽などの素地に見事な彩を施し、緑、赤、黄の色絵を重ねる手法を見出した。
「古来数ある名陶の模写も必要であると思います。絵画を持って陶器を表現し、次に土を持って陶器を作る。いい人の手になったものは不手際でもいいものが出る」ー北大路魯山人
魯山人の言葉を思い出させてくれる器。彼自身は伝統に習い、それを超えていく自由闊達な精神と手で作り上げた。その器には、深いエネルギーと遊び心が隠されている。

このフロアにはもう1つの名品があった。黄色、緑、青の水玉が銀色の素地に踊る器、「銀三彩カブ形花入」だ。最初この銀彩を見た時、息を呑む美しさに目が眩んだ。素地に銀彩を実に効果的に施し、さらに、点々模様の色絵をあしらったこの作品は、今までになかった幽玄でなお重厚という驚くべき境地を表現していた。発表された時、見るものの目を奪うほどの衝撃を与え、陶磁器の世界に革新をもたらしたとまで言われたという。その革新さゆえに批判的な評価も少なくなかったようだが、この作風の作品数が少なかったために、今なお気品と美を備えた逸品として新しい時代の陶芸の金字塔のように語り継がれている。
「あらゆるものの美を知って、それを通して陶器の美もわかる。そして本当にわかるということは、本当にそのものに惚れることである」

・女将との対話
「なんだか、赤子のような初々しさでしょ?」
時間を忘れて魯山人と対話を続けていると、店の女将が語りかけてくれた。普段はお店にはほとんど出ないが今日はたまたま魯山人に話しかけにきたという。
「いつも私思うんですけど、この焼き物の地肌、魯山人からは香りがするような気がするんですよ。感じませんか?」
「香り・・・・」
「魯山人のうつわ作りは最初に“形”から入ると言います。例えば、懐石に使うお皿を作るとすれば、古来伝統の陶磁器のうつわを参考にして、絵付けは、そのうつわにマッチしたものを考えていく。九谷、瀬戸、織部、志野、信楽、備前、銀彩....。義祖父によく話していたというのは “心の眼”を持って陶器と向かい合うという姿勢だったようです。掌に乗るほどのお手塩(おてしょ/小皿)一枚であっても、実用食器の域を超えて、一つの芸術作品として昇華させることに命懸けだったんでしょうね」
「注ぎ込まれた『気』が芳わしさになって伝わるのでしょうか」
「そうだと思いますね」
魯山人談義が白熱してくると、女将は一般人未踏の3階秘密のギャラリーに誘ってくれた。
螺旋階段を上がるとすぐに小さな茶室があり、右面には小さな花入が壁に飾られていて、5人くらいが座れる黒檀の風合いのあるモダンなカウンターが先に伸びていた。
茶室にかけられたお軸には、魯山人の手によるものだろうか、「福」の一字が書かれていた」。
「実際にうつわを味わって見ましょう」
そう仰ったかと思うと、座った席の前に「志野茶碗」が現れた。志野といえば、紅志野、赤志野と呼ばれるほどの魯山人が好んだ燃えるような赤の発色が特徴だ。白から赤へ変化する志野釉のグラデーションが実にドラマチックな波を見せる。茶だまりの渦はブラックホールに落ちていくような宇宙そのもの。
「正面」からじっくり拝見した後に、「背面」につづく。白く竹林を思わせる切り込みに迫力を感じる。お茶を入れたら全く隠れてしまう「見込み」をじっくり見てから、裏返して「高台」にたどり着く。
「どうぞ、掌に乗せてみてください」
そう言いながら、隣の席に座って、
「まず、器を前に置いたら、両肘をテーブルにきちんとつけてください。そこから、静かに器に手を回して掌にすっぽり入れてみます。肘をつけたまま、その肌を少しなでます。見た目と全く違う風合いでしょう?」
宝物のようなうつわを愛でる時の作法を丁寧に教えて下さる。
うつわを愛おしく扱うその姿が実に美しくて、思わず見惚れてしまった。恐る恐るながら、その所作を真似してみる。うつわがあたたかい、と感じたのはこの時が初めてだった。
初めに女将が語った「赤子のように初々しいでしょ」という言葉のわけがようやく分かった気がした。清らかで、生まれたての乳飲児であるようなのに人間臭くて、しかも優美だった。
「この世の中を少しずつでも美しくしていきたい。私の仕事は、そのささやかな表れである」
女将の好きな魯山人の言葉だそうだ。
見えるものと触れた時のギャップに驚いていると、
「結局、触覚が本質にたどり着く道かもしれません。でも、日頃からこの器の向こうにある人間の魂みたいなものを想像する力に磨きをかけると、共感の境地にたどり着く気がします。」
そして、女将はこの老舗がどんなふうに魯山人と縁を深めてきたかについて、語ってくださった。それはまさに、ここでこの時間でしか聞くことができない珠玉のストーリーだった。

創業時の黒田陶苑看板「風雅陶苑」/北大路魯山人作
・旅人のように、とっぷり「自由」に生きた人
魯山人とは誰か
北大路魯山人ー書家、篆刻家、料理人、陶芸家・・・世に広く名を馳せた芸術家であるが、その人生は数奇そのもの、人生を旅に例えれば波瀾万丈、人格的には傍若無人、芸術家としては狷介(けんかい)孤高。スケールの大きな「絶対自由人」「美の風狂人」という矜持を持ち続けた魯山人にとって、銀座は陶芸家としてのデビューを果たした美の求道者への入り口だった。
魯山人の「美の求道者」としての姿勢は、次の芭蕉の句に準えられる。
「 “古人の跡をもとめず、古人の求めたる所を求めよ”と
南山大師の筆の道にも見えたり 」
ー松尾芭蕉・柴門の辞よりー
書にはじまり、絵画、陶器へと幅を広げ、あらゆる陶器芸術を極めた魯山人の美の探求の信条がここにある。
天才のリアルな姿とは
戦前、赤坂の地に数寄屋造りの「星岡茶寮」(ほしがおかさりょう)があり、腕達者な料理人、美麗な食器、行儀の行き届いた給仕と、日本の中でも最高級の店だった。料亭のプロデューサーであり、皿・鉢はもとより掛軸から作庭まで、全てを手がけたのが魯山人だった。魯山人は風評の絶えない人物で、風呂上がりに、ビールを持ってくるのが少しでも遅れるとすぐにその使用人をクビにするかと思えば、一方では美への愛着は並外れていて、茶寮が傾くほどに骨董品を買い漁ったなどなど。美の探求に妥協は許さず、戦後、欧米旅行へ向かうが一億円の借財を背負い、そんな中でなお随行作品は全て寄贈してしまうという潔さを持つ面もあったという。晩年、重要文化財の指定や人間国宝への打診を全て蹴り、「絶対自由人」の誇りを保ち続けた。多くの敵を作り、死後毀誉褒貶(きよほうへん)に塗れた愛憎劇を繰り返した魯山人だったが、彼の人生を世に見える姿とは別の視点から関わり深く縁を持った銀座商人が、黒田陶苑創業者の黒田領治店主(女将の義祖父)だった。
3代目の女将にとって義理の父にあたる黒田和哉さんのお話によれば、「父領治は、魯山人の風評ついて “群盲、象を撫(な)ず” という古語を引き合いに出していた」という。“群盲、象を撫ず”ー視野の狭い者が多く集まり、銘々の視点から理解したことを延べ、結果として物事の本質が見失われている状態の喩えであるが、風評における多くの魯山人像は2代目が幼少期より父の近くで観察し、本人のそばで親しく遊ばせてもらった人物像とは全く異なるものだったという。
京都の杜家(しゃけ/神社を奉祀する世襲の神職の家柄)に生まれながら、貧しい境遇に置かれた魯山人は、自らの逆境を跳ね返し、陶芸をはじめとするあらゆる芸術に挑戦し続け、美の巨人と言われるまでになった。生涯「天上天下唯我独尊」(てんじょうてんがゆいがどくそん)の精神を貫いた姿に、陶芸の美意識に通じる店主ならではの思いがあったようだ。
魯山人が陶器を焼く星岡窯(せいこうよう)には、職人やお手伝いの人々の子供たちも大勢いて、仕事場や釜の周辺は子供にとって楽しい遊び場だった。魯山人が轆轤場(ろくろば)で仕事をしている時も、皆で騒ぎ、粘土の残りや削りかすなどをオモチャにしていたが、魯山人は製作中であっても、優しい眼差しでいつも楽しそうで、声を出して叱ることは一度もなかった。魯山人が狂気の芸術家であるとか、人に対して傲慢不遜な態度をとるとかといわれるが、和哉さんは「私が知る限り身近なお手伝いの人々を怒鳴り散らす所は一度も見たことがない」ということだった。
世界中を魅了した 言葉
2013年フランスの国立東洋美術専門の美術館であるパリ・ギメ美術館Musée Guimetにおいて、ヨーロッパ初の大規模な「魯山人展」が開催された。世界中の陶芸ファンを虜にした「魯山人の美ー日本料理の天才」会場の世界観を完成させたのは、次の魯山人のことばだったという。
二百年、三百年の昔の美術に注目せよ。
五百年、千年、二千年、否もっともっと先の年代になる幾多の作品に目を移してみよ。
そして、その年代の人間は、天地を貫く自然の美抄をいかに見たか。
そして、いかに道理に背く事なく、素直に美しいものを造り、残していったかに注目せよ。
料理は、自然を素材にし、
人間の一番原始的な本能を充しながら、
その技術をほとんど芸術にまで高めている。
自然の風向きと四季の移り変わりに敏感な感覚を持て。
真に美なるものは、必ず新しい要素を多分に有する。
食器は料理の着物である。
これほど深い、
これほど知らねばならない味覚の世界のあることを銘記せよ。

極めた、「器は料理の着物」
うつわに自然観ともてなしの精神を追求した魯山人。大胆で個性あふれる作風の底流にあった和食への思いはどの陶芸家よりも強かったに違いない。
「いうまでもなく、食器なくして料理は成立しない。
太古は食べ物を柏の葉に載せて食ったということであるが、すでに柏の葉に載せたことが食器の必要を如実に物語っている。しかるに、現代多くの専門家が料理を云々していながら、その食器について顧みるところがないのは、彼らが料理について見識がないか、ほんとうに料理というものが分っていないか、そのいずれかであろう。
料理と食器とは相離れることのできない、いわば夫婦のごとき密接な関係がある。
料理を舌の先に感ずる味だけとみるのは、まだ本当の料理が分らないからである。うまく物を食おうとすれば、料理に伴って、それに連れ添う食器を選ばねばならぬ。
もちろん、ひいては料理を食う座敷も、床の間の飾りもすべてがこれに伴って来るが、そのもっとも密接なる食器について意を用いることが、まず、今日の料理家に望まねばならぬ第一項であろう。」
女将のお話に聞き惚れ気がつくと日が暮れ始めていた。なんという至福の奇跡的な時間だったろうかと興奮気味の心を抑えつつ深いお礼を伝えながら店を出た。
その後、その時のご縁で「人間・魯山人に出会う」というテーマでの銀座おさんぽの企画をさせていただいた。稀有な体験に、ご参加の皆様に驚きと感動を味わっていただけたことは想像に難くない。
「短い時間、銀座の街歩きなのに、地球を一周してきたような壮大な気分になれた。偉人を通じて、人間を知り、命の輝きに共感する経験、脳と触覚のフル回転、これが旅なのですね」
ご案内した筆者自身がその体験者でもあった。
*「黒田陶苑」ビルは現在建て替えにつき、銀座6丁目にて営業中。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◇イマジネーション体験がもたらす「共創」
コロナ禍が続く今の世界は、私たちにリアルに体験することへの制限を強いている。リアルはリモートなどに代え難いリソースではあるが、それでも私たちには、イマジネーションという人間だけが持っている素晴らしい力がある。それを活用するためにこの時期にいかにそれを磨くか、その方法や仕掛けを弛まず切り拓き実践することこそ、コロナ後をより豊かに生きる条件のように思う。
そしてもう一つ大事なことは、一度視覚に頼らず触れることもせずにその街や作品を感じるにはどうしたらいいのだろう、と考えてみることだ。その時は、音だけが頼りだ。
銀座おさんぽにおける黒田陶苑での体験は、女将の声(物語)を通じて作品の裏側に潜む作り手・魯山人の人間そのものに触れる稀有な女将と私たち参加者の「共同作業」だった気がする。おそらくこれは、視覚だけの経験では得られない特別な体験であった。
語り手と聞き手、そこにある特別な化学反応があるからこそ、双方に無限の感動の波を起こすのではないか、唯一無二の体感として体に刻まれる理由はそこにあるのではないか、忘れられない思い出とはそうしたプロセスで生まれるのではないか、そうは考えられないだろうか。
イマジネーションの体験がベースになった、ウェルビーイングの新しい旅のカタチが普通になる、そんな時代が目の前に来ている。

Ⅱ. 能のこころ 三つの『石橋』ー獅子舞の迫力ー
おめでたさのあふれる演目「石橋」(しゃっきょう)を、能二舞台と歌舞伎、それぞれの形式で相次いで鑑賞する機会を得た。【MUGEN∞能】(11/19観世能楽堂、シテ/観世流シテ方 坂口貴信師)、【正門別会特別能】(6/20観世能楽堂 シテ /観世流宗家 観世清和師)、【2019年9月公開作品 シネマ歌舞伎 特別編「幽玄」】(主演/坂東玉三郎師 with 鼓童)である。能と半能、そして歌舞伎形式の違い、それぞれの美点がよく分かるという面白さもさることながら、主役の表現力の素晴らしさに感動した。その一部をレビューとともにご紹介する。
(文責 岩田理栄子)

旅にまつわる芸能といえば、能が最も代表的である。世阿弥が完成させた夢幻能では、主人公である「シテ」は、多くは幽霊、神様、動植物の精霊であるが、一方「ワキ」はこの世の住人、多くの場合旅人(僧)である。この世の人間(ワキ)の役割は、普段めったに会うことができない異界のもの(シテ)と遭遇して、シテが語る物語を観客に伝えることである。見えない異界の有り様を観客に示すことができるのは、ワキが旅人であり、あの世とこの世の「境界」にいる存在だからだと言われている。
今回取り上げる「石橋」は能の五番目物。これはめでたさのあふれる切能(きりのう)であり、さらに、特殊な型や表現が要求される披き物、つまり一定の修行を積み、宗家の許しを得た能楽師だけが演じることのできる特別な演目の一つでもある。
◇身体の限界を極める獅子舞 (MUGEN能から)
ー希望の舞 / 力強さとたおやかさとー

撮影 駒井壮介
『石橋』の〈前場〉にける(前シテ)は、山人(文殊菩薩の化現)であり、〈後場〉におけるシテ(後シテ)には前シテと同じ演者(坂口貴信師)が白獅子(文殊菩薩の使者)となって登場する。石橋そのものは、古の中国の天台山に架かる有名な石橋をモデルにしたものである。
中国・インドを遍歴するワキの寂昭法師(大江定基/ 森常好師)が中国の清涼山(しょうりょうぜん/現在の中国山西省にある)で「身命を仏力にまかせて」橋を渡ろうとすると、シテの山人に「これは人間がたやすく渡れる橋ではない」と呼び止められる。山人はこの橋の謂れを語り、文殊浄土の奇特を約束してその場を立ち去る。この〈前場〉のシーンは語りが主体であるが、神秘的な声色の謡によって深山幽谷の景色が描かれ、虚空に聳え立つ石橋の様子が際立っていて、これから始まる豪快な獅子舞の前触れとして、とても効果的に表現されていた。
〈後場〉では、この石橋を象徴する一丈台と白・赤の牡丹が舞台正面に置かれ、石橋(しゃっきょう)の向こう側に文殊菩薩の使いである獅子が現れる。
寂昭法師の前に獅子が出囃子の乱序(らんじょ)に乗り現れるシーンには心が踊った。乱序とは、獅子の出現の時に大小の鼓や笛で演奏する特殊な囃子のことだが、神々しさを伴うその音色は美しく、安倍文殊院にある文殊菩薩像(国宝)が浮かび上がって見えるほどであった。文殊菩薩像では獅子の上に文殊菩薩が乗っているのだが、文殊菩薩は実際にこのような音に導かれて現れたのではないか、と思えるほどこの秘曲には臨場感もあった。

「石橋」の後場・獅子舞のやり方については観世流では3通りほどあるというが、【MUGEN∞能】では、大獅子には白獅子(シテ 坂口貴信師)、赤獅子(ツレ 林宗一郎師)の他に、ツレ赤獅子2名(関根祥丸師、井上裕之真師)の若手能楽師が演じた。
大獅子の「白獅子」は、霊獣感漂う「獅子口面」を身につけ、緩急鮮やかな動きは実に力強くダイナミックさが際立っている。この獅子舞は、口伝や秘伝も多く、能楽師にとっては非常に重い演目だと言われ、普通あまり見たことのない、体全体を使った驚くような所作に思わず目を見張ってしまう。
↓ 気魄迫る 坂口貴信師の「白獅子」

撮影 駒井壮介
香り高く咲き誇る牡丹の花と戯れるように舞う「白獅子」は、大迫力の中に優美さも備わっていて、実に端麗だ。「赤獅子」と絡まる石橋の上での舞は、一丈台で飛び乗り飛び降りを繰り返す秘技が繰り返され、瞬きもできないほどだ。時々激しい装束の動きが牡丹の花びらを揺らし、まるでリアルな石橋の上で寿ぎを楽しんでいるかのように感じる。一方、能面の狭い視野からこの台はどれほど見えているのだろうか、などとハラハラしながら鑑賞するその時間もこの演目の魅力ではないかと改めて思う。大獅子の演出には白赤獅子を親子と見立てる設定が多いと聞くが、精悍さがほとばしる白獅子とたおやかさを忍ばせる赤獅子には活力がみなぎり、親子というより兄弟を思わせる瑞々しさが実に美しかった。
若い能楽師による「赤獅子」の橋掛り(はしがかり)や欄干(らんかん)を大いに活かした演技も素晴らしく、特に頭(かしら)を激しく振るシーンは、柔らかく鍛え上げた身体能力を遺憾無く発揮して、舞台全体を広く見せていてとても見応えがあった。
次世代の希望をまとった「石橋」は、どよめきが起きるほどの感動を呼んだ。フィナーレでは、見る人々に明るさと清々しさをもたせた舞台に惜しみない拍手が送られていた。
豆知識/切り能とは
江戸時代の正式な上演形式である「五番立」に従い、能の演目を内容別に「神(しん)・男(なん)・女(にょ)・狂(きょう)・鬼(き)」の5種類に分けた場合の、狂物に次いで五番目に演じられるべき曲。「五番目物」ともいい、1日の演能の終わりに演じられるため、物事の終わりを意味する「切り」をつけて、「切能」と呼ぶ。祝いを込めた曲、見た目の華やかさを演出する鬼退治的な物語が多い。

2021.11.19 MUGEN能 ©️能プロ
◇味わい深い親子獅子の妙技に出会うー「翁附五番能」ご宗家白獅子の「石橋」ー
観世ご宗家が満を持して挑戦された、正門別会特別公演「翁附五番能」五番目演目として、半能「石橋」が演じられた。大獅子には白獅子(シテ ご宗家 観世清和師)、赤獅子(ツレ 観世三郎太師、角幸二郎師、清水義也師)らが演じた。ワキは高僧・寂照法師(福王和幸師)である。
半能とは、能の略式上演方法の一つで、ワキの登場の後、前シテ部分を全て省略して、後シテによる後半部分を演ずることを指す。今回の半能は五番能の最後を飾るという意義深さとともに、1日の演能の終わりを慶事にて寿ぐということも兼ね備えていた。
ベテラン能楽師による壮大な地謡が、変化の拍子を際立たせる太鼓をはじめとする囃しの音色と激しく共鳴する圧巻の場面から始まる。
獅子団乱旋(とらでん)の
舞楽の砌(みぎん)
牡丹の英(はなぶさ)
匂い充ち満ち
大筋力(たいきんりきん)の
獅子頭
打てや囃せや(はやせや)
牡丹芳(ぼたんぼう)
牡丹芳(ぼたんぼう)
黄金(こうきん)の蕊(ずい)
現れて
花に戯れ
枝に伏し転び(まろび)
げにも上なき
獅子王の勢ひ
靡かぬ(なびかぬ)草木も
なき時なれや
萬歳(ばんぜい)千秋と
舞ひ納め
ー折からの、獅子、団乱旋(いずれも舞楽の名)の舞楽の場に、牡丹の花房も芳しい匂いを満たしている。その中を打てよ囃せよと勢いよく獅子が頭を振って舞えば、牡丹はますます花を開いて香高く、黄金の蕊を表す。獅子が牡丹の花に戯れ、枝に伏して転がるように舞い、獅子王の勢いを見せれば、なびかない草木はない。草木もなびく太平の世を寿ぎ、獅子は萬歳楽、千秋楽(いずれも舞楽の名)と舞ひ納め、元の獅子の座(仏の坐す所・獅子は文殊菩薩の乗り物)として(仏の下に)戻っていった。ー
観世宗家の前のめりの気迫が伝わる白獅子だった。特に目を引いたのは、赤獅子(ツレ 観世三郎太師)との一丈台の上での妙技である。初々しさと弾けるような赤獅子の躍動ぶりに対して、芸の積み重ねが凝縮された、充溢な芸のあり方を指し示すような演能表現であった。親獅子を思わせる泰然自若とした姿に、世阿弥の言葉が重なるようだ。
「花はいやましに見えし也。これまことの花なるが故に、能も枝葉も少なく老木になるまで花は散らで残りしなり」(花伝書)
年齢を重ねてからの芸がいかに大切か、人生の最後に向かって咲いた花こそ「まことの花」であると世阿弥は繰り返し述べているが、まさに人生を心の目で感じて謳歌する宗家の充実ぶりに圧倒された。
公演後、NHK・Eテレ「古典への招待」で、「翁附五番能」をやり遂げられた現在の心情についてインタビューに答えられていた姿が印象的だ。
「世阿弥は“稽古は強かれ 情織はなかれ”と風姿花伝の中で述べていますが、稽古は強いだけが大事ではなくて中身が大切。その子が正当の芸系の継承の稽古を受けているのか、一体能楽とは何か、そういう能楽の本質に切り込んだ稽古の積み重ねが大事なのです。奇を衒っての上部の美しさ、上部の強さでなくその子が受けてきた稽古の道筋こそが重要だという事です。今回は楽屋内においても古式の仕来り習慣で行いましたし、私自身も六十歳を過ぎて、自分自身の能楽人生の中で、父・二十五世観世宗家 観世 左近(1930-1990)にこうして教わってきたというのをお見せたかったのです。それが今回この「翁附五番能」を連続演能した挑戦の意味なのです」
ますます内的な力を漲らせ、鬼気迫る情熱を次世代に正当な芸として継承しようとする宗家の気迫を感じる言葉だった。
◇歌舞伎仕立て、優美な「石橋」 玉三郎✖️鼓童
ーシネマ歌舞伎 特別編「幽玄」ー
「幽玄」という世阿弥が能楽論で唱えた概念を元にしながら、その幽玄物の代表である「羽衣」と、精霊の獅子の幽玄さが際立つ「石橋」、そして歌舞伎の演目としても人気の高い「道成寺」を融合させた、シネマ歌舞伎「幽玄」が製作された。歌舞伎界の至宝である坂東玉三郎師が、かつて自ら芸術監督を務めたことのある和太鼓を中心に創作活動に取り組み新境地を拓いてきた太鼓芸能集団「鼓童」と組み、能楽と歌舞伎という伝統芸能と太鼓表現を融合させたものである。玉三郎自身が主演として舞台に立つだけでなく、演出、映像、監修まで手がけ、その才能と培った知識と経験を惜しみなく注いだ表現者としての集大成とも言える作品である。

シネマ歌舞伎 特別編『幽玄』予告より ©️松竹
「幽玄」は、「羽衣」から始まる。精悍さをうちに秘めた「締め太鼓」の規則正しいリズムが美しい。漆黒の舞台に下手から上手まで横一列に現れる総勢14名の鼓童メンバーたち。裃(かみしも)を身につけた勇姿が、締め太鼓をひたすら静寂に近づけようと打ち続ける。太鼓は叩くことで身体の近くの空気が強く振動するので、次第に身体の循環がよくなり気持ちも高揚していく楽器だと聞いたことがあるが、それを抑えるように時々奏でるチャイムや鈴の音色は、「静」の世界に引き戻す役割を担っていた。静けさから波立つように次第に早く打ち鳴らし、強打をひたすら抑えて我慢し静寂に戻っていくその流れ、太鼓のシンプルなパフォーマンスが見事だった。
当初、この「幽玄」は「石橋」のみで演ずる構想だったというが、この「羽衣」はその世界に入るプロローグのような効果を表現していた。
能を意識した削ぎ落としの美を昇華させた演出で、天女(坂東玉三郎)の優雅な舞は凛とした優美さで際立っていた。
最後に演じられた「石橋」は、笛と太鼓だけでリズムを刻む表現。黒の紋付に黒い襷掛け、銀色の袴に身を包んだ鼓童メンバーが現れ、斜がけ太鼓の音色は空間に響き放たれていくようだ。花道から登場した白獅子5名は、歌舞伎役者の所作そのままに見事な毛ぶりを披露した。舞台中央に位置する玉三郎の毛ぶりは、一層大きな所作で存在感を示していた。特に大太鼓の華やかなリズムに合わせ演者が一斉に呼吸を一つにする合わせ技は、本公演「幽玄」のフイナーレにふさわしく圧巻であった。
本公演の内容は、一貫して研ぎ澄まされた能へのリスペクトを感じさせるものであった。足運びまで能的に演出されていたが、日本舞踊(歌舞伎)との差は歴然で、さぞかし演者にとっては難しかったのではなかろうかと推察した。詞章がほとんどなく、その上囃子が笛と太鼓だけという構成による世阿弥の創出した「幽玄」の世界への新たな挑戦は、奥深くも情感豊かなイマジネーション作品として見事な芸術に昇華していた。坂東玉三郎の古典芸能の進化に心血を注ぐ情熱にただただ驚かされるばかりであった。
【シネマ歌舞伎 特別編「幽玄」】
演出:坂東玉三郎、振付:花柳壽輔(日本舞踊 花柳流宗家家元)
能指導:津村禮次郎(観世流シテ方) 能菅指導:田中傳十郎
能楽囃子指導は亀井広忠
シネマ歌舞伎 特別編「幽玄」予告より
Ⅲ 銀座情報
◇ 観世能楽堂で「小鼓」体験 ー「WHAT’S NOH」坂井兄弟会お正月特別企画ー
観世能楽堂で楽しむ能体験。新春の能舞台で小鼓の魅力をご体験ください。
と き:2022年1月8日(土) 開演 14:30 (開場 14:00) ところ:観世能楽堂 チケット:3,000円(全席自由)
【プログラム】
●仕舞 高砂 坂井音隆
●おはなし~能の中にある小鼓の魅力~ 清水和音 坂井音雅 ●小鼓の体験~リズムと掛け声~ 清水和音 ●謡と型の体験 坂井音晴
●連吟 高砂 ●能 殺生石(ダイジェスト版) 坂井音雅
●お申し込み
坂井兄弟会 NPO法人白翔會
03-6407-0520
info@hakusho-kai.net

◇イマジネーションの魔術師 ーソール・スタインバーグ展 Ginza gggー
スタインバーグは地球上に存在する事物、あるいは言語、概念、数字、メタ・メッセージなど、人間世界で了解されているものを「目に見えない」ものに変換し、ドローイングを通じて「私たちの存在理由」について迫って来るようです。刺激的な彼のアートで、イマジネーションを広げる時間をたっぷりご堪能ください。
【SAUL STEINBERG展】入場無料
と き:2021年12月10日〜2022年3月12日 開館時間:11:00〜19:00 休館/日・祭日 ところ:ギンザ・グラフィック・ギャラリー

Ⅳ 編集後記(editor profile)
度重なる疫病や天災に悩まされ続けた日本人にとって、自然は危険に満ちた存在であると同時に、四季を通じて愛すべき救いの対象でもあります。
鴨長明による「方丈記」は、環境文学の世界的古典だと言われますが、その前半では、京都を襲った大きな5つの災害を写実的な筆致で描き、後半では先の見えない都を捨て、都の外れで隠遁する自らの暮らしの様を描いています。
ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず
長明は混沌とした世の中を見るにつけ、自然や人生が儚いこと、変化は一瞬にして起きることを表し、一方で山里での平穏で美的にも心地よい四季の愛おしさを描いています。つまり、「方丈記」は、制御できない時間と空間(天災を被りやすい日本の自然環境)の厳しさに人生の無常を感じながら、制御できる時間と空間(四季の文化などの二次的自然)への憧憬という2つの時間を描いている点で、日本的ものの見方が凝縮された物語として今なお多くの人々に共感を与えているようです。
自然信仰が精神の中心である日本人だからこそ、自然によって「変化への耐性」が培われ、幾多の困難にあってもバネのように起き上がることができるのではないか、コロナ禍でのひとりひとりの奮闘を見るにつけそんな思いを強くし、私たちはその姿に勇気をもらっています。
本日も最後までお読みくださりありがとうございます。
責任編集:【銀座花伝】プロジェクト 岩田理栄子
〈editorprofile〉 岩田理栄子:【銀座花伝】プロジェクト・プロデューサー 銀座お散歩マイスター / マーケターコーチ
東京銀座TRA3株式会社 代表取締役
著書:「銀座が先生」芸術新聞社刊

