
Adobe Fireflyで生成した画像はChatGPTで再現できるのか?――ChatGPT×Dall-E 3で生成AI時代の創作活動!
生成AI時代の創作活動について考える
皆さん、こんにちは。早いもので8月もあと少し。ここ数年、毎年言っているような気がしますが、今年の夏は暑かった(そして、まだまだ暑い)ですね~
生成AIは日常生活に欠かせない存在になってきた
さて、2024年、生成AI旋風はまだまだ沸き起こっています。これはサービス提供側(Open AIChatGPTやAdobe Fireflyなど)だけではなく、私たち利用者の手元にも近づいてきました。
先日発売されたGoogle Pixel 9およびそのシリーズでは、Googleの生成AIモデル「Gemini」を搭載しており、世界初のAIスマホとして発売以降から注目を集めています(その凄さの一端が以下のYouTubeでわかります。ぜひご覧ください)。
前フリが長くなりました(笑)今回はまた、こうした生成AIを取り巻く状況をふまえつつ、「生成AI時代の創作活動」について考えて、実験をしてみました。
生成AIは創作活動(クリエイティビティ)にどう影響を与えるのか?
上述のYouTubeのように、いまやそこにないものを生成AIが補完し、私たち人間に新しい価値として提供してくれるようになりました。たとえば、集合写真や写真の背景の拡大など。
でも、これが進むと人間の創作活動ってどうなっていくのでしょうか?
これまでのAdobe Firefly、さらに前回のLuma AIのDream Machineの結果を振り返ってみると、人間からの指示、いわゆる「プロンプト」から画像や、その画像を加えての動画を生成することができました。
2024年現在、このプロンプトを上手に作ることができるかどうかが、生成AIでの創作活動にとってとても重要と考えられます。
そこで、今回はこのプロンプトの生成を、生成AIを使って行ってみます。
ミネオ君はミネオ君なのか?――Adobe Firefly→ChatGPTへの転生
今回は以下の手順に挑戦してみます。
生成AIで生成した画像を生み出すプロンプトを生成AIに考えてもらう
生成AIで作ったプロンプトで画像を生成する
技術評論社 デザイン・イラストnoteと言えばもちろんこの人(このキャラ?)、ミネオ君です。

今回は線画バージョンのミネオ君に出演してもらいます。
この画像を使い、今回はAdobe Fireflyではなく、今の生成AIブームの火付け役、世の中を牽引しているOpenAIのChatGPT(ChatGPT 4o)と、その画像生成AIのDALL-E 3を使ってみます。
Adobe Firefly(線画)を再現させてみよう
さっそく、ChatGPTへアクセス。
ChatGPT
https://chatgpt.com/

「ChatGPTにメッセージを送信する」の欄の、クリップボタンを押し、Adobe Fireflyで作ったミネオ君の画像をアップ。その際、「この画を書くための、ChatGPT用のプロンプトを教えてください。」というプロンプトを添えてみます。

すると……本当にすぐにプロンプトが出力されました。

プロンプトはどうなった?
では、そのプロンプトを詳しく見てみましょう。
A simple, cute robot with large, round eyes and a friendly smile. The robot has a rounded head with a small antenna on top, and its body is box-shaped with visible joints at the arms and legs. The robot stands on a flat surface, with its arms slightly bent and its feet firmly planted. The design should be black and white, as if it were a coloring page, with clean and bold outlines.
今回、とくに言語指定をしなかったところ英語で出力されました。英語が話せない自分としては一瞬怯みましたが、全然大丈夫!だって、ChatGPTはすぐに翻訳してくれるから。
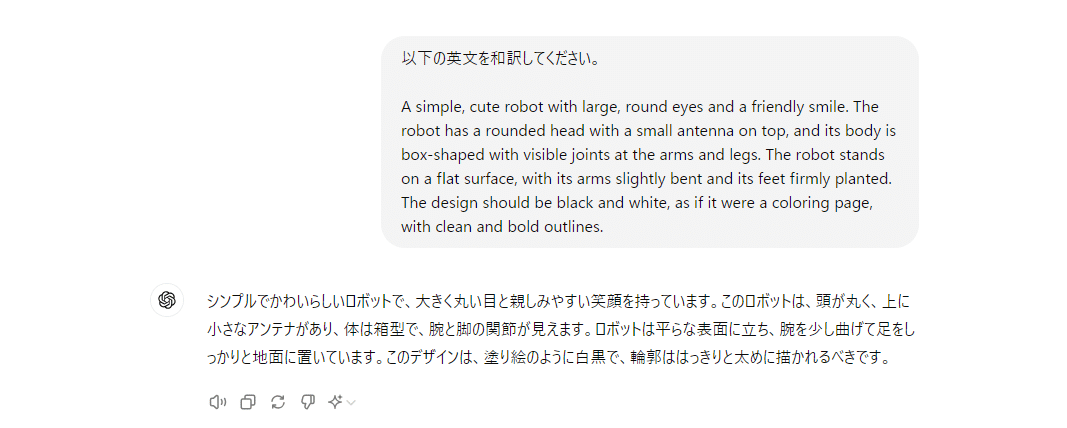
こんな感じに訳してくれました。文体や最後の表現などはちょっと気になりますが、いわゆるプロンプトに必要な単語がしっかり入っていますね。
シンプルでかわいらしいロボットで、大きく丸い目と親しみやすい笑顔を持っています。このロボットは、頭が丸く、上に小さなアンテナがあり、体は箱型で、腕と脚の関節が見えます。ロボットは平らな表面に立ち、腕を少し曲げて足をしっかりと地面に置いています。このデザインは、塗り絵のように白黒で、輪郭ははっきりと太めに描かれるべきです。
Adobe Firefly→ChatGPT(プロンプト生成)→DALL-E 3(画像生成)
あっという間にプロンプトができました。今回はこれで終了!……ではないです。このプロンプトで本当にミネオ君(Adobe Firefly)が描かれるのか、これだけではまったくわかりません。
ということで、さっそく生成されたプロンプトを、今度はそのままChatGPT 4oに入れて実行してみましょう。ちなみに、ChatGPT 4oでは「DALL-E 3」という画像生成AIを使うことになります。
ではさっそく。

こちらも数秒待ってみると……

拡大してみましょう。
じゃーん。ミネオ君(ChatGPTバージョン)の誕生です。

並べて比較してみましょう。どうですか?

細かな部分は異なるものの、線画であること、目がクリッとしているところ、手足と胴体のバランスと雰囲気など、似ていますね。
今後もしかしたらどこかでChatGPT版ミネオ君が登場するかもしれません。お楽しみに :-)
プロンプトを考えることもクリエイターの仕事?
以上、今回の挑戦でした。結果として、生成AIはプロンプト(テキスト)→画像だけではなく、その逆、画像→プロンプト(テキスト)も十分できることがわかりました。
今回、ChatGPT 4oが生成したプロンプト(日本語訳)を改めて見てみましょう。
シンプルでかわいらしいロボットで、大きく丸い目と親しみやすい笑顔を持っています。このロボットは、頭が丸く、上に小さなアンテナがあり、体は箱型で、腕と脚の関節が見えます。ロボットは平らな表面に立ち、腕を少し曲げて足をしっかりと地面に置いています。このデザインは、塗り絵のように白黒で、輪郭ははっきりと太めに描かれるべきです。
この中にある「シンプルでかわいらしい」「大きく丸い目と親しみやすい笑顔」「小さなアンテナ」「体は箱型」といったような、画が持つ特徴、形容詞(表現)を、しっかりと言語化してくれました。
これは、生成AIが画像を理解できることの裏返しでもあるわけです。
生成AI時代、創作活動に必要なものは変わるのか?
さて、最後に今回のテーマである「生成AI時代の創作活動」について考察してみます。
2024年8月時点では、プロンプトを上手に作れるか、活用できるか、それこそが生成AI活用の1つのポイントと言えます。つまり、画像や映像などの創作活動に生成AIを活用するにはプロンプトの作り方、「表現能力」と「言語化」が必須です。
あれ?でもこれって生成AI時代だからなんでしょうか。
たとえば、創作活動にとって大事なデザインの概念。ここ日本では、デザイン=ビジュアルデザイン(見た目)のイメージが強い傾向がありますが、広義のデザインは、設計や意匠といった意味を含み、いわゆる課題解決を行うための、計画や構想、その実装までを含みます。
今回は同じ画を描くためのプロンプトの出力を試したわけですが、裏を返せば、生成AIが「人間が考えうる表現」「人間でもわかるような表現」を言語化してくれたわけで、まさにデザインしてくれたとも考えられます。
最後の方は少し飛躍してしまいましたが、生成AI時代の創作活動では、このように本来のデザインを行うために、生成AIが人間の能力を補填してくれることを知っておくと、より一層、質の高い創作活動が行えるかもしれませんね。
たとえば、権利上問題のない画像をたくさん集めて、生成AIにその画像を描かせるプロンプトを作らせたり、その画像の論評を行わせれば、生成AIが利用者の知識の枠を越えた、新しい情報(表現)を教えてくれる、ということも可能です。
そうすれば、冒頭で紹介したYouTubeのスマホAI紹介動画の使い方に、「空気が澄んでいる状態で、壮大な山々がはっきりと見える山頂で撮った家族写真にして」とか「夕暮れどき、サンセットのタイミング、海が金色に輝く中での、ゴールドコーストのビッグウェーブに乗ったイメージで」など、ひと工夫(ひと表現)加えて、生成AIを活用した自分だけの写真づくりを楽しむことができるでしょう。
まだまだ進化中の生成AI。ぜひ皆さんも、いろいろな使い方でその実力を実感し、また、完成していない今だからこその楽しみを体験してみてはいかがでしょうか。
文責・担当ふ
