
エンタメ異人伝 Vol.2 藤村哲哉 フィソロフィア株式会社 代表取締役社長 (収録 2017_03_13)
音楽、映画、ゲームなどを総称するエンタテインメントは、人類の歴史とともに生まれ、時代に愛され、変化と進化を遂げてきました。
そこには、それらを創り、育て、成熟へ導いた情熱に溢れた人々がいます。これらの偉人であり、異人たちにフォーカスしインタビュー形式で紹介する「エンタメ異人伝」。今回のゲストは、株式会社ギャガ・コミュニケーション(現在のギャガ)の創業者であり、現在はフィロソフィア株式会社・代表・藤村哲哉氏です。
日本でのレンタル・ビデオ・ブームに先駆けて、洋画作品のビデオソフト向け版権の買い付けを促進し、インディペンデント映画会社として映画配給に着手、さらに、現在はスタンダードになった「製作委員会」方式を早くから着目し大きく成長を遂げました。現在は、ハリウッド映画製作現場と日本のコンテンツをブリッジするプロデューサーとして、辣腕を振るっています。
藤村氏は、2017年4月7日(金)より公開される「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」を原作に持つハリウッド版『ゴースト・イン・ザ・シェル』の日本サイドのエグゼクティブ・プロデューサーにクレジットを連ねています。監督はルパート・サンダース、出演は、スカーレット・ヨハンソン、北野武…という話題作を手掛けた藤村哲哉氏の半生を振り返るとともに、今まであまり語られることのなかったギャガ退任後の藤村氏の沈黙の6年と、日本とハリウッドをブリッジする仕事内容を追いました。
■広島被爆二世としての少年時代を振り返る

黒川:改めて藤村さんの少年時代や、ルーツからお聞きしたいと思います。出身は広島県とのことで、失礼にあたるのかもしれませんが、ご両親は被爆をされたのでしょうか?
藤村:母親は疎開していたから被爆していないんだけど、当時、父親は三菱重工の造船所で設計の仕事をしていて、市街地じゃなくて海に面しているところで被爆しました。建物が鉄筋コンクリートで壁が厚かったから致命的なことにはならなかった。そういう意味では父親は幸運でした。

黒川:子供の頃、広島の街を見て原爆について何か感じたことはありましたか?
藤村:いやいや、僕が生まれたのは昭和28年で被爆してから8年も経っていたから。物心がついた頃にはさらに年月が経っていて、もう広島の街全部がリセットされたような状態だったんでね。子供心に原爆を意識したことはなかった。
黒川:身体が弱くて喘息だったので、両親と離れて尾道で暮らすようになったということですが、そのあたりのお話しを聞かせていただけますか?
藤村:単純に転地療養だね。尾道は母の実家で、夏休みとか冬休みになると母は必ず帰省していた。それで、僕も一緒に行くんだけど行きの電車の中ではゼイゼイいっていたのに着いたらもう庭を走り回っていて。
黒川:そんなに違うものですか。
藤村:まあ、精神的なものも大きかったと思うけどね。母親の実家は尾道でも特に田舎で、半島の突端みたいなところにあって。海と山しかないような本当に自然に恵まれたところだったから。
■自立心が養われた尾道での転地療養
黒川:ご両親と離れてそこで暮らすようになって何か変わりましたか?
藤村:自立心がすごく養われた。両親と住んでいたときは体が弱いから、特に母親が過保護でね。(苦笑) それで実家のほうに預けられたわけだけど、やっぱり母親に育てられるのとは違うんだよ、環境も周りも…。田舎だから、みんなが家族みたいなところもあったし。自然も豊富で自分の好きなことができる環境があった。例えば、鳩を100匹くらい飼ったりとかね。
黒川:鳩を100匹ですか…?
藤村:母の実家はお寺だったから庭が広くて、そこに自分でゼロから鳩小屋を立ててね。海も近いから夏は毎日魚釣り。魚釣りの船も自作した。ドラム缶を溶接所に運んで上の部分を切って横にパイプでフロート付けて。それで、カヌーみたいにしてね。もう、それくらい好き勝手というか、自分の創造力を活かして好きなことができる環境で育った。
黒川:素晴らしいですね。
藤村:お寺には動物もいっぱいいてね。犬も猫もいたし、ウサギ、チャボ、ニワトリなんかも飼っていたし。一時はヤギもいたし、今考えるとすごくいい環境だった。
黒川:先ほど学生時代の写真を見せていただきましたが高校時代は卓球部に所属されていたんですよね?
藤村:卓球が好きでね。尾道の公民館に卓球台があって、小さい頃からそこでよく卓球をして遊んでいたんだよ。それで卓球が好きになった。
黒川:喘息だったということでスポーツとは縁遠かったのかと思っていました。
藤村:それが逆でね。親にも祖母にも体が弱いからこそ運動やれ運動やれと言われて。それで、運動神経はあるほうじゃなかったんだけど運動部に入ったんだよ。中学のときは軟式テニス部。
黒川:中学は卓球部ではなかったんですか?
藤村:本当は卓球をやりたかったけど小さい中学だったから卓球部がなかった。それで高校で卓球部に入ったんだけど周りは中学から卓球をやっている部員ばかりで……。
黒川:みんな上手いんですね。
藤村:上手いんだよね。だから玉拾いをしてた・・・(笑)。
■京都を目指した大学進学とフォークソングへの憧憬

黒川:その後、慶應大学への進学を選択されたわけですが、何かご自身の強い意志や意図があったのですか?
藤村:実を言うと僕は一浪していて、現役のときは京都の大学を志望していたの。もう、すごい田舎にいたから、なるべく都会に行きたいという気持ちが強くて。でも、父は「電電公社(注1)」の社員だったから・・・「電電公社」って公務員みたいなものだから東京の大学に行くにはお金がかかるし、あまり負担はかけられない。だから、行くなら関西かなと。僕はフォークソング世代だから京都への憧れが強かったしね。
注1) 現在のNTTで当時は国営企業だった。藤村氏の父は戦後この電電公社に転職した。
黒川:北山修さん(※)とか加藤和彦さん(※)とか。
藤村:そうそうそう。それから、はしだのりひこさん(※)とかね。ザ・フォーク・クルセダーズを生んだ京都は、まさにフォークソングのメッカみたいな感じだったよね。それで、京都の大学に行こうと思ったんだけど……要するに落ちたわけです。
(※ザ・フォーク・クルセダーズのメンバー)
正直言うと現役のときは受験勉強とは縁遠くて。当時の尾道には予備校が1校もなかったし。まったく勉強していなかったから、どっちにしても浪人するだろうと思っていたけどね。だいたい田舎の高校からいい大学に行くためには1年は浪人するというのがひとつのパターンでもあったし……なんて言い訳だね。勉強ができる友人たちはちゃんと現役で入っているから(笑)。ただ、広島で予備校に1年通ったけど、その1年間はちゃんと勉強した。
■「男なら中央へ行け」…父の言葉に背中を押される
黒川:それで京都を飛び越えて今度は東京の慶應大学への進学となるわけですが、何か心境の変化があったのでしょうか。
藤村:いや、単純に1年間受験勉強を頑張ったから成績が良くなって受かる可能性があったということかな。ただ、喘息があるから最初は想定していなかった。京都って空気がいいイメージがあるじゃない。逆に、東京はねえ…。当時は公害とかが問題になり始めていた時期だったから、広島でも喘息でゼイゼイ言っていたのに東京なんかに行ったらもっと苦しむんじゃないかと思って。
ところが父親がね。あまりそういうことを言う人ではなかったんだけど「男なら中央に行け」と。一言そう言われた。それで、東京に行ってもいいんだと。でも、母親は大反対。喘息が完治していたわけじゃないから、東京なんてとんでもないと。そもそも京都に行くことすらあまり賛成じゃなかったからね。もう親元を離れて欲しくない、広島の大学に行ってくれと。でも、父がそう言ってくれて……。

黒川:お父様に背中を押してもらったわけですね。
藤村:そう。だから、それまでまったく選択肢になかったけれど、「ああ、親父がそう言ってくれるんだったら東京に行ってみようかな」と思うようになった。
■不安感があると喘息が悪化する……
黒川:合格されてお父様はすごく喜ばれたんじゃないですか?
藤村:そうだね。あまり口数の多い人ではなかったけどすごく喜んでくれた。
黒川:それで慶應大学に入学されたわけですが、喘息は大丈夫だったのですか?
藤村:3年生くらいまではそんなに症状は出なかった。もちろん、季節の変わり目なんかはゼイゼイいっていたけど、あまり大きい発作は起きなかったね。やっぱり慶應に受かったことが大きかったんだと思う。東京に行こうとなってから、だんだん慶應に入りたいなあと。自分の中で第一志望になっていたから、そこに入れたことがすごくうれしくて。やっぱり喘息って精神的なものも大きいんだよ。
黒川:そういうものなんですね。
藤村:だから、3年生くらいまではよかった。ところが、就職活動が始まった頃からまた喘息の発作が出てきちゃって。社会人になって喘息でしょっちゅう会社を休んだりしたら、すぐにクビだと言われるんじゃないかというような不安感がすごく強くなってね。そういう不安が出てくると発作が起きるんだよ。だから、4年生のときは喘息の発作がけっこう継続して出るようになって、そこに面接とか就職試験が重なって大変だった。体重もかなり減ってしまってすごく体調が悪かった。
■オイルショック、就職氷河期 赤井電機 海外営業部志望
黒川:大変だったんですね。音響メーカーの赤井電機(※注2)に就職されるわけですが、入社試験は大丈夫だったんでしょうか?
注2)オープンリール・デッキやカセット・デッキで人気を博した音響機器メーカー。ブランド名は「アカイ」、「AKAI」
藤村:それが緊張のせいか面接の待合室でゼイゼイいっちゃって、もう息をするのも半分苦しい。ところが、面接室に入った瞬間からアドレナリンが出て、その瞬間だけもうビシッとして。面接の15~20分間は苦しい様子を微塵も見せなかった。でも、貿易部の部長に「君、顔色悪いけど大丈夫?」って言われちゃってね。
黒川:どう答えられたんですか?
藤村:いやもう「まったく問題ございません! 毎日マラソンしております!!」なんて真っ赤なウソをついて(笑)。それは今でも昨日のことのように覚えている。
黒川:すごいこと言いましたね(笑)、それだけ必死だったんですね。
藤村:赤井電気は本当に入りたいと思っていた会社だったから。僕が就職活動をしていたのは第2次オイルショックのときで、上場会社の3社に1社は新人を採用しなかった。そんな中で個性のある会社、自分がやりたいことができそうな会社はと自分なりに勉強して。その結果、赤井電機に入りたいとすごく思うようになったわけ。音楽をやっていたから音響専業メーカーに入りたいというのがあったし、小さい頃から海外に行きたいとも思っていてね。
■海外への憧れの原点はテレビ放送から
黒川:なぜ海外に行きたいと思われたんでしょうか?
藤村:それはテレビの影響だね。自分の生まれた年にテレビ放送が始まって、テレビが自分の生活に入ってきたというか……近所のテレビがある家に座布団を持って見に行ったりしていたからね。それで、小学校2年生のときについに家にテレビが来て、それから生活が一変した。
黒川:そうでしょうねえ。分かる気がします。
藤村:うん、もうかじりついて見ていた。で、その頃はまだ日本のテレビ制作会社が育っていないから、東北新社あたりがアメリカのテレビシリーズを輸入してバンバン放送していたのね。『ウチのママは世界一』、『ザ・ルーシーショー』、『ライフルマン』とか。そこには豊かな豊かなアメリカがあって「ああ、すごいな」と。その頃の僕にとってアメリカが外国で、そこに行ってみたいというのがすごくあった。
黒川:なるほど。でも、なぜ赤井電機と海外が結びついたのでしょうか?
藤村:赤井電気は海外営業部門だけ採用が別枠だったんだよ。人事の人を訪ねていったときに志望を聞かれて「できたら海外営業へ行きたい」と答えたら、「ああ、ウチの会社は海外営業だけ別採用なんだ」と言われてね。つまり、海外営業志望で入社できたら必ずそこに配属されるという。普通の大企業はどこに配属されるか分からないじゃない。経理かもしれないし、不動産かもしれない。国内のどこに回されるかも分からない。でも、赤井電気はそういう個性的な会社だったんだよ。何しろ当時、輸出率95%だったからね。
黒川:輸出率95%ですか。
■慶応大学 法学部政治学科という学歴の効力
藤村:その当時ね。赤井電気は海外で急成長した会社だけに海外営業は戦略部門だったの。それで、この会社に潜り込めたら確実に海外に行ける。しかも、自分の興味である音響製品を扱っている会社でもあると。あとね、僕が大学時代にすごく慕っていた先輩がコニカ(当時は小西六写真工業)の人事部にいたんだけど、その人の影響も大きかった。その先輩も、慶應の法学部政治学科で、今でこそ慶應の法学部は看板みたいな感じだけど当時は慶応の中では偏差値が低いほうの学部とされていてね。その先輩が言うんだよ。「俺もそうだけど慶應大学の法学部政治学科の卒業生が大企業に入って東大とか京大とかの優秀な連中と競争するより中堅の会社に入って好きなことをやったほうがいい」って。
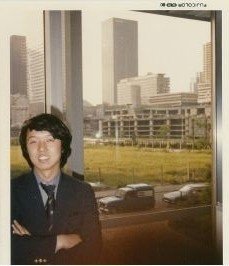
黒川:なるほど、説得力ありますね。
藤村:「とにかくお前は体が弱いんだからメーカーが一番いい」とも言われた。当時、メーカーは社風が一番穏やかというイメージだったから。その点、大手商社とか電通とかは当時からもうすごかった。「そんなところに行って体育会系の連中の中で、お前は絶対やっていけない」、「自分の好きな商品を扱っているメーカーに行ったほうがよっぽどいい」とか言われて。自分も全然健康に一番自信がないときだったし、その先輩のことも大好きだったので音響機器メーカーに。ちょうどシスコン(システムコンポ)が流行っていたし。
黒川:流行っていましたねえシスコン。分かります、分かります。
藤村:分かるでしょ? アンプはパイオニアで、スピーカーはサンスイで、デッキはアカイみたいなね。それで『FM Fan』とか読んでいる人がいっぱいいた頃だから赤井電機にすごく入りたくなって。しかも、さっき言ったとおり、入社したら必ず海外に行ける。自分の中で一番入りたい会社になっていたからもう必死だった。
黒川:その甲斐あって入社されたわけですね。
■新卒研修には早朝6時に行った、誰もいなかった…
藤村:だから、入れたことがすごくうれしくてねえ。新卒の研修の初日だったかな・・・朝8時半集合とかだったと思うんだけど、6時頃に行ったのを覚えている。その年は大卒以外も含めると新卒が何百人も入ったんだけど、当日はまだ誰もいなくて僕が一番だった。それくらい気合いが入っていた。しばらくは喘息も全然出なかったし。
黒川:やっぱり、緊張というかアドレナリンが出ていた感じですか。
藤村:そうだったんだろうね。喘息なんかになっている場合じゃないっていう気分になっていたから。絶対にしくじりたくないっていうのかな。もちろん、まったく症状が出なかったというわけではないけど、大学4年生のときみたいな状況では全然なくて。それに忙しかったしね。しょっちゅう深夜まで残業させられたし。
黒川:それで中近東課に配属になったということですが……。
藤村:最初、工場研修があって4月に入社。それで、10月に配属が発表されるんだけど、実は一番配属されたくないと思っていたのが中近東だった。だって医者とか病院とかどうなっているのかよく分からないじゃない。そんなところに行って喘息の発作でも起きたらどうしようと。医療とか全然ちゃんとしているイメージがなかったからね。そう思っていたら配属の発表がされてよりにもよって「中近東」(笑)。
黒川:大丈夫だったんですか?
藤村:そうしたら、これがまったくの逆で。喘息って気圧の変化とか季節の変わり目が発作を引き起こす要因になっているんだけど、中近東はそういうのがないの。季節がなくて天気は365日ほとんど快晴で、基本的に乾燥しているから全然喘息は出なかった。
黒川:かえって良かったんですね。仕事の環境的にはどうでしたか?
■藤村哲哉:中近東担当を命ず 「僕、英語が話せないんです・・・」
藤村:いろいろ大変だったよ。中近東課って発表されて配属と同時に担当する国が割り当てられるわけ。でも、なんの経験もないんだよ? 1~2年間アシスタントとして働いて、それから担当国をあてるとかなら分かるじゃない。でも、たった半年の研修で英語もほとんどしゃべれない、外国にも一度も行ったことのないヤツが配属されて、「はい、藤村君。君の担当国はこの9カ国だよ」と。で、僕が担当したのはクウェートを筆頭にオマーン、カタール、バーレーン。それからパキスタン、アフガニスタン、バングラデシュとか。イエメンやレバノンも入っていたね。その辺は全部自分の担当だった。
黒川:よくやりましたね~。
藤村:何が一番大変だったかっていうと配属されて1週間くらいだったかな? 国際電話がかかってきて課長が「ハイ、藤村君。パキスタンから電話」って(笑)。
黒川:いきなりですか!
藤村:「ええっ?」ってなったよね。「すみません。ボク、英語できないんですけど」って思わず言ってしまって。そうしたら「な~に言っているんだよ、お前がパキスタン担当なんだから取れ!」と言われて。それで電話に出て「ハロー」って言ったら、向こうがバーッとしゃべってくるわけ。もう何を言っているのかさっぱり分からないから固まってしまって。そうしたら周りからクスクス、クスクス女子社員とかの笑い声が。「ああ、藤村さんは英語が全然できないのに貿易部に入ってきたんだ」って。もう洗礼だよね。でも、そういう時代だった。
黒川:よく精神的に持ちましたね。もちろん、自分で志望したからというのはあるでしょうけど。

藤村:もう全然分からなかったし、どうやって乗り切ったかもよく覚えていない。で、配属から半年でもう出張に行かされるわけ。1回の出張は40日くらいで、その40日間に自分の担当している9カ国を全部回らなきゃならない。移動時間もあるから1カ国の滞在期間は2、3日くらい。その間にミーティングと市場調査なんかをやる。パキスタンの電気店とか回って、赤井電機の商品の値段がいくらでソニーとかの競合商品がいくらで売られているとか全部チェックしてね。それで商談をして、受注して帰ってくるという。

黒川:責任の重い仕事ですね。
■分からなかったら100回でも分からないって言って聞いてこい!
藤村:受注のための出張だから、頑張ってオーダーを取ってこないといけないわけ。当時の赤井電機ってけっこう猛烈社員みたいな感じでやっていて、営業は会議室に個人名と営業成績を書いたグラフが毎月張り出されるの。しかも、その大きな会議室はお昼になると、みんなが昼飯を食う場所になるんだよ。全員の名前がそこにあって自分の名前も出るから、頑張ってオーダーを取ってこなきゃいけない。
黒川:それは厳しいですね。
藤村:それで、出張に行くと現地の代理店の社長が迎えに来てくれて。向こうからしたら新卒だろうがなんだろうが、赤井電気本社の担当責任者だからね。それで、商談をするわけだけど僕は何を言っているのかよく分からない。でも、初めての仕事のときに上司から言われたのよ。「藤村、これは金がかかっている出張なんだからな。受注、お金の話をしに行くんだから、よく分かりもしないのにヘラヘラ笑ってイエスなんて死んでも言ってくるんじゃねえぞ。分からなかったら100回でも分からないって言って聞いてこい」って。それがしっかり頭にあったから、もうひたすら「パードゥン? パードゥン?」とか「プリーズ・スピーク・スローリー」って何度も聞き直すんだけど、それでも分からないわけよ。でも、「イエス」って言えないじゃない。そうしたら代理店の社長が怒っちゃってさ。
黒川:うわ~キツいですね。でも、相手にしてみればそれはそうですよね。
藤村:怒って机叩いて出て行っちゃったんだけどデカい紙を持って戻ってきてね。それで筆談。つまり、俺が言っていることはこういうことだと紙に書いてくれるわけ。それを僕が辞書を引きながら(笑)。今でも覚えているけど、それが生まれて初めての商談。
黒川:何から何まですごい話ですね。
藤村:それでなんとか乗り切って、40日間の出張の最後の方は対応の仕方とか要領が分かってきてだいぶ慣れた。結局、赤井電機には5年半いたんだけど、めちゃくちゃ鍛えられた。
黒川:そうでしょうね。すごい経験をされたんですね。
藤村:それでも後半になったら、けっこう認めてもらえてね。当時、「赤井電機/世界代理店会議」っていうのがあったんだけど、最後の2年はその事務局のメンバーに連続で選ばれて。
黒川:プレゼンテーションをされたんですか?
藤村:いやいや、事務局だから裏方。ちょっと自分が出ていって少ししゃべったりはしたけど、英語がかなりうまくなったというわけじゃないよ。でも、準備は大変だった。その時期は毎日、会社を出るのは本社ビルで一番自分が最後みたいな。それで、スライドを作るんだけど、当時はパワーポイントなんかないからね。絵に描いたグラフとかを写真で撮ってスライドにしてという時代だから。で、そのスライドにミスがないか暗室に入って毎日チェックするんだよ。僕は赤井電機に入る前は眼鏡をかけていなかったんだけど、これで一気に目が悪くなった。ホント心身ともに鍛えられた。

■中東の狂犬「カダフィ大佐」の支配するリビアでの恐怖の取り立て
黒川:リビアでのお話しを聞かせてもらえますか? 担当国じゃなかったんですよね。
藤村:そう、リビアはアフリカ課の担当だったんだけど焦げ付きが出てね。しかも、金額が半端じゃなかった。当時の赤井電機って年間売上が900億円くらいの規模の会社だったんだけど、それがリビア1カ国で46億円も焦げ付いたわけ。
黒川:それはとんでもない金額ですね。
藤村:当時はどこの家電メーカーも地元のフィクサーと繋がっていて、そのフィクサーにアンダーテーブルでお金を払ってビジネスしていた時代。もちろん、バレたら大変だよ…出張先で某電気メーカーの人が尋問を受けたとか、そんな新聞で報道されない事件もけっこうあったし。
それで、リビアの話に戻るけど、当時はカダフィ大佐(※) 政権下で治安が悪かった。そのうえ、そのフィクサーから「(今来ると)捕まるから絶対に来るな」っていう連絡が来た。でも、銀行の手前、債権の回収に誰かが行かなきゃって…ことで、アフリカ課の課長に出張命令が出たけど、その課長が辞表を出しちゃって。その結果、僕が行くことに。そのときリビアに間接的に関わっていたこともあって自主的に行って、いろいろと大変な交渉を重ねて、最後には債権を回収してきた。
(※カダフィ大佐:軍人であるがテロを支援するなど中東の狂犬と呼ばれた)
黒川:すごいですね。
藤村:いやいや、すごくはないよ。でも、あれは怖かった。
■会社を辞めるつもりは微塵もなかった
黒川:藤村さんの著作の中で「起業するなら32歳じゃないかって」という話があったのですけど、赤井電機での5年間で徐々に独立起業を考えるようになっていったのですか?
藤村:いや、自分で会社を始めるなんて発想は微塵もなかった。ただ、入社から3年経ったくらいから将来は転職するべきだろうと考えてはいた。赤井電機は赤井三郎という有名なオーナー経営者がいたんだけど、オーナーが心臓病でスキー場で急死してから経営が迷走した感じになってしまった。それで、この会社の先行きは厳しいかな…と。それで、自分はペーペーだから自力で会社を良くするよりも乗っている船を変えた方がと思っていて、そんなときにある人から声がかかったわけです。
黒川:そんな状態だったんですね。
藤村:それがトヨタ自動車のサウジアラビア担当だった人でね。当時サウジアラビはトヨタにとってアメリカに次いで世界第2位の輸出国だった。ヨーロッパではまだ日本の車があまり売れていない時代だったから。それで、サウジアラビアって出稼ぎの人たちが大量に入ってきていたんけど、その人たちが自分の国に戻るときに無税でもっていける枠があって、みんな車や家電を買って帰るわけ。すごい消費国でものすごく大きなシェアがあった。そのサウジアラビア担当のトヨタ自動車の人が現地のトヨタ代理店のジャミール社と日本で合弁会社を立ち上げたんだけど、僕のことを気に入ってくれていて「藤村君も来てくれないか」という話になって。それで面白そうだから発起人として、その会社の設立に参加することになった。
黒川:なるほど。
■ベンチャーキャピタルって何ですか……?
藤村:当時、ジャミール社は東芝の代理店だったので、同じ家電業界だから僕が東芝の事業を担当することになったんだけど、その会社の社長がやっていたもうひとつの事業がベンチャーキャピタルだった。ジャミール社は当時からものすごく資金を持っていたので、シリコンバレーにベンチャーキャピタルの会社を持っていてアメリカで投資していた。それを日本でもやりたいということになって。それで、僕もベンチャーキャピタルの仕事に関わるようになり、そこで初めて起業家の人たちと会い、ベンチャーキャピタルの仕組みを理解したわけ。でも、最初は何も知らなくて「ウチの会社はベンチャーキャピタルをやるから」って言われたときは、「すみません、ベンチャーキャピタルって何ですか?」って聞いたくらいだったからね。
黒川:なるほど(笑)。
藤村:それで、自分にお金がなくても、いい事業アイディアを持っていればお金を出してくれる仕組みが世の中にはあるんだということが分かった。で、ゲームでもルールが分かったら自分も参加してみたいと思うようになるじゃない。それで起業したいと思うようになって。
黒川:そうだったんですね。
藤村:それでさっきの32歳の話だけど、ベンチャーキャピタリストが投資をするときに一番重視することは創業者の年齢だと聞いたわけ。「32歳がひとつの評価基準だ」だと。つまり32歳以下であればより積極的に投資をする。32歳がベストで、それより年齢が上だとマイナス評価になっていくと。もちろん、50歳の人が起業して成功する場合もあるけど、ベンチャーキャピタルの人たちって確率論でやっているから、そういう割り切りをしていた。それで、「32歳」っていうのが自分の中にインプットされて、それまでに起業したいと思うようになった。ジャミールでベンチャーキャピタルに出会ったのが29歳のときで、30歳になったくらいから起業したいなと思い始めて、32歳のときにギャガを立ち上げた。ギリギリで間に合ったね。
黒川:日本テープの荻原正光社長が起業のご出資をされたわけですよね?
藤村:僕がビデオレンタル委託システムの起業を考えているということで、ある人が荻原社長を紹介してくれたわけ。当時はビデオの卸しの大手企業をやっていらしたからね。それで会ったときに、こういう発想をしていてビデオのソフトを仕入れたいんです、なるべくいい条件で売って下さいって話をして。だから僕が起業したいと思っているのはご存知だったたけど、まさかお金を出してくださるとは思わないからね。単純にビデオレンタルのビジネスをこれからやっていく上での……。
黒川:取引先だと。
藤村:そう、取引先としてお会いしたわけ。 ところが、最初にお会いした時にテレックス(※)を打つのを頼まれたことがあって、そうしたら「打つのが早いな」、「お前すごいじゃないか」って言われて、しょっちゅう頼まれるようになって。それがきっかけで親しくなっていった。
(※テレックス 電話回線で送信相手を呼び出し、テレタイプで通信する方法。FAXが無かった時代の通信手段)
■「哲っちゃん、お前そろそろ起業したらどうだ?」
黒川:荻原社長からの出資の話はどういったところから出てきたんですか?
藤村:出会ってから1年かけて段々僕のことを気に入ってくださって。それで、あるとき御飯に誘われて一緒に食べていたら、荻原社長は僕のことを「哲っちゃん」って呼んでいたんだけど、「哲っちゃん、お前そろそろ起業したらどうだ?」って言われて。
いや、「でもお金ないです」って答えたら「俺が出してやるよ」と。「…は?」ってなったよね。「この人はゲイかな?」って思っちゃったもん。だって、当時はまだ「エンジェル」(注3)なんて言葉もなかった時代だし、親戚でも親でもないオジさんが2人でメシ食っているときに「いや、金は俺が出してやるよ」って。
注3)起業家の創業や創業間もない企業に資金を提供して助ける個人投資家のこと。
黒川:何か他に目論みがあるだろうと。
藤村:「かな?」と思って。だって頼んでもいないんだよ? だから一瞬、言葉に詰まってしまって……「ありがとうございます」とは言ったよ? 言ったけど「今の仕事もありますしタイミングもありますから、ちょっと考えさせてください」って。別に向こうから今すぐ金を出すって言っているわけでもないのに、苦しまぎれにそんなことを言ったのを覚えている。でも、「別に今決めなくてもいいんだよ」って言ってくださってね。
黒川:当時としては破格のオファーですよね。それだけ評価されていたということですか。
藤村:評価っていうか信用してくださった。本当にありがたい、ビックリした。
黒川:それで海外のマーケットにまったくの未経験のまま映画の買い付けに行ったわけですよね。いろいろ逸話は聞いていますが、最初に行ったときってビジネスになったんですか?
■We are UIP(ウィー・アー・UIP) !
藤村:それがモロになった。ビデオソフトに対する爆発的な需要がスタートしたタイミングだったから。そういう仕組みがあるっていうのはもう分かっていたしね。それで、生まれて初めて映画の買い付けに行ったの。でも、ブースがたくさんあるじゃない。一体どこから回ったらいいかも分からない。とにかくデカいところから回ろうと思って「ユナイテッド・インターナショナル・ピクチャーズ」って書いてあるブースに行ったわけ。
黒川:ああ~、UIP(※)に(笑)。
(※UIP ユナイテッド・インターナショナル・ピクチャーズ:当時、ハリウッドを代表するメジャー映画会社である、パラマウント・ユニバーサル・MGMの合弁会社。日本支社は2007年に解散)
藤村:あのときのやり取りはよく覚えてる。最初から「あなた、誰?」みたいな怪訝な顔をされてね。それで「アイム・バイヤー・フロム・ジャパン」、「イフ・ユー・ハブ・リスト・オブ・ザ・タイトル・アベイラブル、プリーズ・ショウ・ミー?」とか言ったら、向こうの答えは「ドント・ハブ・エニイ・リスト」。でも、意味が分からなくて「ホワイ?」って聞いたら。「ウイ・アー・UIP!」って(笑)。

黒川:アハハハハ。
藤村:よく分からないままそれでも粘っていたら、面倒くさそうに「ウイ・ハブ・ア・ディストリビューター・イン・ジャパン(私たちは日本に配給会社があります)」って言われて。後になってUIPって何か分かった。そりゃ日本人が「売って下さい」なんて言ってきたら変な顔するよね。ホントになーんにも知らなかった。
黒川:すごいレベルからのスタートですね。じゃあ総当たりで、例えば、AFM(アメリカン・フィルム・マーケット)だとサンタモニカのローズホテルのフロアを全部回って買っていった感じだったんですか?
藤村:当時はサンタモニカではなくてビバリーヒルズのビバリーヒルズ・ヒルトンが会場だった。それで、ホラーがブームだったからホラー映画を持っていそうなところをかたっぱしから回っていった。そうしたら、日本大手のヘラルドさんとか松竹富士さんとかが配給した映画の権利がアメリカの権利元に戻っていることが分かって。あの頃って5年くらいで権利が戻ってきていたんだけど、それらの権利がガラ空きだった。そういう、昔、日本で公開された映画をホラーと一緒に買い付けて。
■買えば売れる、33作品連続黒字化達成
黒川:リイッシュー(復刻)タイトル、みたいなものですか?
藤村:とも言えるけど、日本では一度もビデオになっていなかったからね。ビデオっていうメディアが生まれたばかりの頃だから。それで、33作品を買い付けたんだけど、帰ったら32作品が速攻で売れた。それがスタート。トロマと出会ったのもそのときだね。
黒川:『悪魔の毒々モンスター』とかですね。やっぱりブースに行って初めて「あ、トロマだ」「ロイド・カウフマンだ」って感じだったんですか?
藤村:そうだね。『The Toxic Avenger』(『悪魔の毒々モンスター』の原題)っていうのがあって、それを見て。
黒川:それにしても、そんな右から左に売れちゃう時代だったんですね。
藤村:売れる、売れる。徳間コミュニケーションズ(現・徳間ジャパンコミュニケーションズ)っていう徳間書店の子会社さんが最初に大きなお客さんになってくださったんだけど、洋画のビデオをウチと組んで出し始めて33作品連続で黒字達成。そういう時代だった。 どこのビデオメーカーからもビデオの権利を持ってこい、持ってこいの嵐だった。次のカンヌ映画祭のときはひとりで行って100本買ったから。
黒川:おひとりで行かれて100本も?
藤村:会社ができて、まだすぐだったからね。当時のAFMは2月開催で、すぐに5月にカンヌ映画祭があって。だから、どちらもひとりで行った。
黒川:国内営業はどうされていたんですか?
藤村:それも最初は自分でしていたね。そのあと古谷(※)君とか、だんだん人を入れていったけど。フィンランド航空に勤めていた人を、たまたまある縁でウチに入れたこともあった。あまりの忙しさに悲鳴を上げて1年で元の会社に戻っちゃったけどね。
(※古谷君:古谷文雄氏 映画評論家であり映画製作者として著名な江戸木純氏)
黒川:激動の日々でしたね。

藤村:最初の4年間は本当にそんな感じだったね。面白くてしょうがなかった。社員もみんな土曜出社していたし。さすがに日曜しか休みがないって言ったらまずいから土曜は隔週にしていたんだけど、みんな休みの土曜日も出てきて仕事をしてくれて。
黒川:不夜城のようでしたよね。ナムコの中村雅哉会長(当時)との出会いというのはどういう形だったんですか?
■ナムコ 中村雅哉氏との共通点とは
藤村:91年にバブルが崩壊した。それまで資金を支えてくださっていた荻原社長も資金繰りが大変になって。あるとき呼び出されて……10月だったかな? 「哲ちゃん、ウチの会社が大変だ…」、「株も土地もアレだし、とにかく経営危機なんだ」という話を初めて聞かされて。「それで、ウチ(ギャガ)はどうなるんですか?」って聞いたら「いやー、それは親ガメがコケたら子ガメもコケるだろう」と言われたのを覚えている。でも、荻原社長的には自分の会社だけで精一杯の状況まで追い込まれていらしたから、そう言うしかなかった。
黒川:そうですね。
藤村:それで、僕の知っている人の中で、この状況を救えるような資金力のある人はひとりしかいなかった。それがナムコ(現バンダイナムコホールディングス)の故・中村雅哉会長。中村会長とはジャミール社のときに、ナムコのビデオゲームを扱った関係で、僕が起業する前から知り合いだった。僕が「藤村哲哉」、会長が「中村雅哉」で「村(ムラ)」と「哉(ヤ)」が同じ順番に並んでいるということで、すごく気に入ってくださってね。
それで、初めて会った日の夜に、一緒にいたナムコの外国部長から電話がかかってきた。中村会長が僕のことを気に入ってくださって「彼を口説いてウチに入れろ」と言われたから、藤村さんナムコに入ってくれって。それで「ありがとうございます。でも、僕はまだ、ジャミール社に移って間がないですし……」と。
それで1回縁が切れたんだけど、ギャガを立ち上げて僕がマスコミに出始めると電話をくださって。「僕は映画が好きなんだ」、「いろいろ話を聞かせてよ」と言ってくださった。 それで何回か会いに行ったんだけど、そのとき、いつも最後に「いいなあ、僕も藤村さんの仕事に興味あるなあ」、「僕も株主になりたいなあ」って言ってくださって。
黒川:中村会長がそうおっしゃっておられたんですか。
藤村:でも、荻原社長からお金を出していただいていたからね。イケイケドンドンでやっていたときだから、荻原社長もほかのスポンサーに入ってきて欲しいなんて思っていなかった。
黒川:それはそうですよね。
藤村:でも、中村会長は、また僕の記事が見ると電話をかけてきてくれてね。「また出てるね、頑張ってるね」、「また、ちょっと遊びに来ない? いろいろ聞かせてよ」と。それで、ときどき会っていたので、中村会長に自然にお願いすることになり、その後も株式上場を果たすまで、会長としてギャガの成長を支えていただくことになった。
■CCC 増田宗明氏は風のように去って行った(笑)
黒川:CCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)の増田宗昭(代表取締役)さんと出会われたのも同じ頃だと思いますが、ビデオの流通としてのお付き合いがずっとあったんですか?
藤村:いやまったくなかった。ギャガは版権商社でビデオメーカーではなかったから直接の取引はなかった。けど、僕がマスコミにけっこう出ていたので増田さんが興味を持って下さって。会いたいという申し出をいただいて、最初に会ったときはホワイトボードにわーっと自分の事業に対する考え方を書いて風のように去っていかれた(笑)。
黒川:そんな感じだったんですか。
藤村:だから、すごいあっけにとられた。で、「今度は枚方市に来てくれ」と。枚方市のツタヤの中にオフィスがあって、それくらい、CCCさんも、まだ小さい規模だった。それで、しばらくしたら株を持たせてほしいと言ってくださり、中村会長の次の大株主になっていただいた。
黒川:資金調達の件では、増田さんを頼ろうという考えはなかったんですか?
藤村:日本テープが銀行に対してギャガの資金を債務保証して資金を借りていた。それで、その金額が10億円くらいだったから。当時のCCCに10億肩代わりして下さいって話は現実的ではないと思った。それで中村会長のところにお願いに行くことになりました。
■ギャガ創業から15年目、ナスダック・ジャパン上場

黒川:このあとヒット作を配給して最終的にはナスダック上場まで行くわけですけど、やっぱりこの危機を乗り切って、ある程度資金調達もできたというのがひとつの大きなジャンプポイントだったんですか?
藤村:まあ、そうだねえ。
黒川:当時、僕はもうギャガにはいなかったので、第3者的視点になりますが、ナスダック市場への公開に向けてある種のこう……頂点を目指している感じを受けました。実際、どうだったんですか?
藤村:やっぱり会社をやるからには上場する、(株式を)公開するというのを実現したいと思って始めたからね。とにかく思わなければ夢は実現しないっていう、増田さんもよく言う言葉だけど、そう思って走り出したから。上場したい、上場しますと言って資金調達していたし。それで、15年で上場したわけだけど最後の5年はつらかったね。もうビデオ市場が伸びなくなっていたから。
黒川:そうでしたね。
藤村:だから、次の成長をするために映画配給事業に入っていったわけだけど、これがハンディだらけで。ここまで閉鎖的な業界なのかってくらい苦しんだから。5年近くかかって95年にようやくジム・キャリー主演の『マスク』がヒットしてくれて。それで翌年にはブラット・ピット主演の『セブン』で。
黒川:99年には、ジャッキー・チェン主演の『ラッシュアワー』がヒットしましたね。

藤村:そうだよね。それで2000年にはトム・ハンクス主演の『グリーンマイル』。『グリーンマイル』で上場できたようなものだから。興行収入が65億もいったからね。で、2001年に『ハンニバル』で、この年に上場を果たすことができた。ただ、その後は、大きな赤字を計上し、業績不振の責任を取って2004年に社長を退任し、2006年にギャガを離れることになった。
黒川:このときはどんなお気持ちでしたか?
藤村:自分の経営者として至らないことがすべての原因と思い、社員や株主、取引先のことを考えると、とても辛く申し訳ない気持ちだった。
その窮地を救ってくださった依田(巽)会長(※)、USENの宇野社長(※)、そして途中で大きな出資を引き受けてくださったオンキヨーの大朏(おおつき)会長(当時※)にも心から感謝しています。
依田(巽)会長 (※エイベックス・ディー・ディー株式会社 元会長兼社長/ギャガ株式会社 代表取締役会長)
USENの宇野社長 (※株式会社USENの取締役会長 宇野 康秀)
オンキヨーの大朏(おおつき)会長(当時) (※オンキヨー株式会社 大朏直人 元会長)

■フィロソフィア創業 日本のIPの可能性を信じて
黒川:ギャガ退任後に立ち上げたフィロソフィアについて聞かせてもらえますか。出版社やゲーム会社が持っている日本のIP(※)の映画化権を海外向けにライセンスするお手伝いをしたり、コンサルティングをされたりしていると伺ったんですけれども・・・。例えば、『鉄拳』や『バイオハザード』などがハリウッドで実写版になったりしていますが、そういったビジネスのコーディネートのお仕事だと思ってよろしいんですか?
(※IP 知的財産権Intellectual Propertyの略 文中での意図はコンテンツを総称している)
藤村:基本的には、日本のIPに関する仕事は、日本の会社との契約で動いているものはあまりないです。自分はこれから日本のIPの価値が高まってくる時代が必ずくるとギャガの頃から感じていて、ギャガの時代からそういう日本原作のものをハリウッドで映画化するってことにチャレンジしていました。でも、やっぱりものすごく難易度が高くてギャガ時代に花が開いたものはなかったけど、その志をまだ持っていたので、フィロソフィアではそれをメインの事業に置いてやっていこうと。そう思って今までもやってきた。で、そのときにどういうビジネスモデルがありうるか。やるからにはちゃんとクレジットで自分がやったことが残るようにしたいし、クレジットを取らないと日本のIPを守ることもできない。
黒川:それでエグゼクティブ・プロデューサーとして。企画やファイナンスに貢献した人がもらえるクレジットですよね。
■アヴィ・アラドとの出会い

藤村:それでいろいろ考えていたときにアヴィ・アラド(※)との出会いがあって、より現実的な話になったんだけれども、アヴィに「自分はエグゼブティブ・プロデューサーのクレジットをもらいたい。そして、エグゼクティブ・プロデューサー契約をしたい」、「日本の会社からお金を貰うんじゃなくて、ハリウッドのチームに入ってハリウッドから日本のIPを取りに行くという発想をしたい」という話をして、アヴィも快諾してくれた。
ハリウッドのスタジオやプロデューサーが日本のIPを取りに行くとき、日本とアメリカのエンタメ業界のカルチャーの違いを把握して、ちゃんとお互いを理解するための橋渡しをする人間が絶対に必要なんです。
それがないと、ハリウッドのから見ると、閉鎖的な日本の企業となかなか交渉のテーブルにつけないし、日本にとっても正しい相手とフェアな取引を実現させることは難しい。
(※アヴィ・アラド 映画「スパイダーマン」などのハリウッドを代表するエグゼクティブ・プロデューサーのひとり)
黒川:そうですね。
藤村:特に、日本のIPホルダーの人たちは、海外のプロデューサーと映画化する契約については知識も経験も不足している。そういう日本側の権利や契約を守るという志もあって、これを始めたわけ。だからハリウッドとの契約なんだけど、基本的には作品単位の契約で自分は作品のために働くと。作品にとってベストの形を作るっていう意味で、自分が入ることによって日本の皆さんも健全な状態でハリウッドと仕事ができる。それによって継続性のあるビジネスになると。アヴィともそういう話をして。
黒川:アヴィさんとの出会いというのはギャガ時代にさかのぼるんですか?
■『攻殻機動隊』と『メタルギアソリッド』の権利を取ってくれ

藤村:ギャガ時代に会ってはいるんだけど、そのときにはビジネスの接点はなかった。向こうはマーベル・スタジオズの会長で『スパイダーマン』シリーズをはじめ、どんどんメジャー作品を作っていたし。世界で仕事をしている超一流のプロデューサーなので、「すごい人と会った」っていうのはあったけどギャガが直接何か仕事をするってことは……。
黒川:なかったですよね。
藤村:だから、まったく接点はなかったんだけど、ちょうど僕がギャガを辞めたのとほぼ同じタイミングで彼もマーベルを辞めました。アヴィは「マーベルの会長でいる限り、マーベルのIPしか映画化できない」、「残りの人生は自分のやりたいIPで作りたい」と。彼はトイ・デザイナーとしてキャリアを始めた人なので、若い頃にしょっちゅう日本に来ていて日本のIPにもすごく詳しかった。それで、一緒にやろうとなってロサンゼルスでランチミーティングをしたとき、アヴィに『攻殻機動隊』と『メタルギアソリッド』を映画化する権利の取得を手伝ってほしいと言われました。
黒川:そんな頃から話が出ていたんですか。
藤村:もちろん。『攻殻機動隊』は僕がフィロソフィアを創業してすぐに取りに行った作品で、もう10年かかっている。契約するのに2年。「チェイン・オブ・タイトル」といって講談社さんが権利をクリーンな状態で持っていることを証明するプロセスがハリウッドとの契約では必ず必要なんだけどそれに1年。これだけでトータル3年もかかった。
■8年間収入ゼロ……!?
黒川:契約が成立したところからキャスティングに?
藤村:いや、映画制作の順番で言うと企画開発が最初。企画開発はほぼイコール脚本開発で、『攻殻機動隊』の場合はドリームワークスとパラマウントというふたつのメジャースタジオの共同制作になったんだけど、制作予算が大きいということもあって脚本家は6人雇った。この6人が脚本をリレーで書いていったんで結局5年かかった。『メタルギアソリッド』も最初のコンタクトからコナミさんと契約を取れるまで7年くらいで、こちらは今コロンビア映画で企画開発中。
黒川:すごい時間がかかるんですね。
藤村:フィロソフィアを始めたときは契約交渉から5年くらいで映画ができると思ってやっていたからね。キャッシュフロー的にこんなきついことはない。だってプロデューサーへの支払条件っていうのは通常、撮影が始まった日からとなっているからね。『攻殻機動隊』の場合、その撮影が始まるまでに8年かかったから普通でいったらそれまでの8年間は収入ゼロ。
黒川:では、その間はどうされていたんですか?
藤村:僕の仕事の中心は撮影開始の手前までだから、契約が成立したら前払いでいいから一部払って欲しいと。でも、あくまで一部だよ? とにかく、キャッシュフロー的には全然マイナス。ただ、ありがたいことにギャガ時代からお付き合いのあるところや海外のいろいろな会社がコンサルタント契約をフィロソフィアとしてくれた。ちょうど僕がギャガを離れた頃から、海外の会社が日本に映画を売るのが非常に厳しくなってきて、自分たちの作品を日本で売るためのコンサルを引き受けてほしいっていうことで10社以上と契約できました。
黒川:それはすごいじゃないですか。
藤村:しかも、ライオンズゲートとか大手がたくさん。それからギャガ時代に支えていただいた日本の企業も何社もコンサルビジネスのクライエントになっていただいて、さらに、「ラストエンペラー」のプロデューサーであるジェレミー・トーマスの日本の代理人にもなっていて、三池崇史監督の『13人の刺客』とか『一命』とか国際共同制作のお仕事もいくつか引き受けてやってきました。そんな感じでちょうど10年なのですが、借り入れもなく(笑)、ずっとやってこられた。だから、これから回収期というか収穫期。やっとこの『攻殻機動隊』が形になって、当然『攻殻機動隊』以降もいろいろ仕込んでいるものがあるので。
黒川:さしつかえなければ、どんなものか簡単に教えていただけますか?
藤村:まず、日本のIPをハリウッドで映画化。そして、アメリカでのテレビシリーズ化。これもすでにいくつか仕込んでいる。アメリカでテレビドラマ化された日本原作のものはまだ1本もないからね。
黒川:それも近いうちに分かるわけですね、楽しみです。
藤村:それと日本のIPをもとにした中国での映像化とかゲーム化とかね。これもある中国の大手メディア会社と契約をして動いている。だから発想としてはギャガ時代の原点に戻った感じだよね。当時はビデオの版権エージェントみたいなことを始めたわけだけど、今は日本のIPエージェント的な事業領域にいるっていう感じ。もちろん、エグゼクティブ・プロデューサーという立場でやっているから単なる右から左のエージェントではないけど。
■『攻殻機動隊』で苦労した点・プロデューサーに必要なものは「忍耐」
黒川:劇場版『攻殻機動隊』でご苦労された点はいっぱいあると思いますが、何か特に心に残られていることはありますか?
藤村:やっぱり契約をするときに何度もブレイク(※破談)しそうになった瞬間があって。アヴィが怒っちゃって「これ以上時間がかかるんだったらもうやりたくない!」、来日中に「オレは明日帰る!」とか言い出したこともあったし。だから、この仕事に何が一番必要かって言ったら「忍耐」の2文字。あきらめないであきらめないでやらなきゃいけない仕事だね。
黒川:藤村さんらしいお言葉だと思います。
藤村:契約できたあとも、例えば北野武さんのキャスティングの窓口もやったし。それから撮影がいざ始まると追加で権利をクリアしなければならないこともたくさん出てくる。また、IPホルダーとのクリエイティブに対するコンサルタント契約も契約書に入っているから、脚本の段階で翻訳してご意見をいただくとか、常に仕事が発生し、公開後も結果について全部報告することになります。
黒川:大変な仕事ですね。
藤村:北野武さんは昔『JM』(主演:キアヌ・リーブス)にも出られたことがあるけれど、ここまでの規模のスタジオが入ってくるハリウッド映画の出演は初めてでいらっしゃるのでスケジュールの調整も契約も実に大変だった。
■ギャガ創業からの21年間を振り返る

黒川:藤村さんにとってのギャガの21年間というのはどういったものだったでしょうか。 なぜ、これを聞きたいかというと藤村さんが起業して社長をやられたがゆえにたくさんの人が集まったし、巣立っていった。いろいろな人の人生とか作品とかに影響を与えていると思うんですよ。その21年間に対する思いを聞かせてもらえますか?
藤村:僕にとっては人生の中でもっとも大きな部分? もちろん、今日の自分はギャガの延長線上で存在できていると思っているし、ギャガのときにフィロソフィアの事業の発想も生まれたし。だから、自分の人生が映画に関わる仕事で世の中に貢献できるものだとしたら、自分が死ぬときにそう思えるとしたら、僕の人生そのものだったような気がする。今のフィロソフィアももう10年やればそう言えるようになるかもね。
黒川 そうか、あと10年で20年になりますからね。
藤村:フィロソフィアでは、ある意味ギャガで学んだことを反面教師としている部分もある。規模は追及しないとか。あの頃は若かったし信用もなかったからマスコミにもどんどん出て信用を作ろうとしたけど、今はそういう取材もよほどのことがないと受けないし。
黒川:今回は取材を快諾頂きありがとうございます。
藤村:それから人を採用することに対する考え方もすごく慎重になった。ギャガで学んだことをもとにしてやっているし、コンサル・ビジネスもギャガの時代の人脈。ギャガの延長線上でやっているわけだから僕の人生の礎というか。今はギャガの株をもう一株も持っていないし、直接ギャガの何かをしているわけでもない、ただ創業者っていうだけの関係ではあるんだけど、過去にさかのぼっての20年をどう思いますかって言われたら繰り返しになるけど「僕の人生そのもの」だね。
■依田巽会長に「絶対やめたほうがいい」と言われたこととは?
藤村:ギャガの代表取締役を退任して、次に自分が何をやるかということや、世の中に対してギャガと違う業態でできることは何かってということでは、すごく悩んだ部分があって、フィロソフィアを立ち上げるとき、最初は今とは違う業態を考えていました。その時は、映画のプロダクト・プレイスメント(注4)の代理店をやろうと思ったんですが、依田会長に「絶対やめたほうがいい」と言われてしまって…、今はとても感謝しているけど(笑)。
注4)映画やドラマなどの劇中で小道具や背景として実在する企業名や商品名を表示する広告手法
黒川:そうだったんですか。
藤村:それで、日本のIPをもとにしたハリウッドでの映画制作を将来的にやってみようと。それはまだ食える仕事じゃないから、まずコンサルタントから始めようと。どのプロジェクトも時間かかって、途中で何度も「これを続けていてもいいのかな」と思ったけど、本当に耐えしのいで継続してここまできた。やっぱり世の中って急激に動いているようだけど本質的なところは変わるまで時間がかかる。だから、それに対する忍耐力を持って長期的な見方をしていかないと。黒川もきっと黒川塾を続ける過程でいろいろ……。
黒川:5年かかりました。大変だな…と思うこともありましたけどね。(苦笑)
藤村:そうだろうね。でも、やっぱりそれを耐え忍んでいくことによって得られるものも初めてあると思いますよ。
■エンタテインメントを目指す人たちへのメッセージ
黒川:最後にクリエイティブやエンタテインメントを目指す人へのメッセージをいただきたいのですが。
藤村:今は過去のどの時代よりも世の中の変化が激しいし、これからもっと激しくなると思う。その中でクリエイターの皆さんも時代に対して変化していくという気持ちを持って。自分が果たすべき役割を時代とともに変えていく柔軟性、そして、それを実現するために自分も変わっていく勇気と最後まで成し遂げる忍耐力を大事にしてほしいというのがメッセージです。
黒川:本日は貴重なお話をありがとうございました。

出展:エンタメステーション 写真撮影:北岡一浩
以下はあとがきでこちらは有料部分になります。ご興味のあるかた、支援をして頂ける方はご購入いただけると幸いです。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
