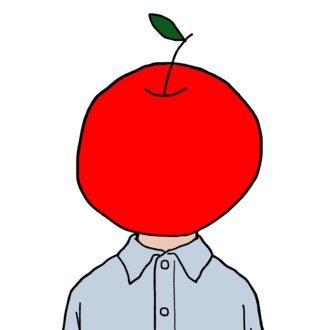Photo by
gentle_tern548
美術館を出た後、あなたは世界が違って見える
単体でも読めますが、先日の記事から何となく続いています。
「美術館とマインドフルネス」という観点からもう少し踏み込んだ話をするならば、美術館に並ぶ作品の数々、特に近現代のアートは、マインドフルネスの産物そのものだと言えます。
精神科医であり日本有数の美術コレクターでもある高橋龍太郎は
アートの歴史とはこんなマインドフルネスによってもたらされた、新たな気づきの歴史だったといってもいい。
と語っています。
では、マインドフルネスがアーティストに気づきをもたらすとはどういうことか考えてみましょう。
美術館で作品鑑賞をした後、単に心がスッキリするだけでなく、心なしか世界が違って見える、そんな体験をしたことがありませんか。実はこれは珍しいことではありません。
例えば、日本でも非常に人気の高い印象派のクロード・モネ。
モチーフの形を正確に再現するのではなく、ゆらゆらと揺らぐ光そのものを表現するように、鮮やかな絵具をキャンバスの上で塗り重ねていくモネの絵を見た後に一歩外へ踏み出すと、日常の中にあふれる光や色彩がまばやく目に飛び込んで来る気がします。
シュルレアリスムのルネ・マグリットやサルバドール・ダリの写実的かつ奇妙な絵を見た後には、身の回りの家具や道具が何かの暗喩であるかのような妙な違和感を感じるようになります。
また、水玉模様で埋め尽くされた草間彌生の絵に衝撃を受けた後には、一輪の花に艶めかしさと力強い生命エネルギーを感じることもあるでしょう。
こうした感覚の変化を芸術の異化効果と呼びます。