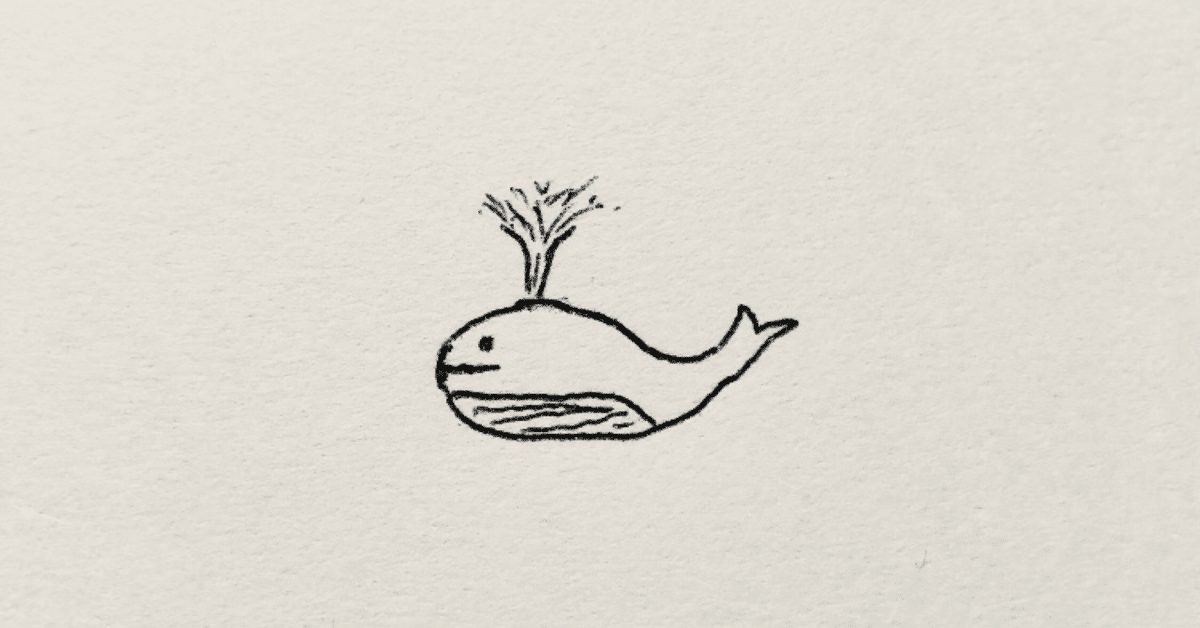
掌編小説(15)『赤い実』
空が青ければそれでよかった。
天気が良ければそれだけ実は成るし、両親の機嫌も良い。それに、穏やかな波が適度に塩気を含んだ海風を連れてきてくれるから。
私は島の外の世界を知らない。外の国の、名前も形もなにもかも。
生まれ育った小さな島。時折やっかいな嵐もやってくるが、優しい島人の性格と、それを育んだ温暖な気候や豊かな自然が好きだった。
島にはこれといった産業はない。島の外と交易などしなくても、遠浅な砂浜にボートを出せば魚はいくらでもとれたし、島の中心部にある森の中には農園もあり、枝先が地面に届きそうなほどに果物が実っている。自給自足の暮らしが島にはあった。
森の木の中で最も特別な木のことを、島の人々は「神の木」と呼んでいた。
神の木は一年に一度、赤く小さな実をつけた。時を同じくして開かれる『雨おくり』の祭りの席で、島長の収穫した実は煎じ薬にされ、皆に振る舞われた。薬は長寿をもたらすとされた。
私たちの島ではその日を境に、季節が【七色の芽吹くころ】から【海焦がす鬣のころ】に変わる。
ある年の祭りの日の朝。大きな船が島の沖合に現れた。
船に突き立てられた巨大な柱には、家一軒を丸ごと包めそうなほど大きな帆が張られていた。船から降ろされた一艘の小舟が数人の男を乗せて浜辺までやってくる。乗組員は、私たちと肌の色や顔の造りこそよく似ていたが、身につけた衣装や立ち振る舞いから外国で生まれ育った者であることがうかがい知れた。
彼らは「船の装具に不具合が生じたため、それが解消されるまで島に停泊したい」と島長に申し出た。島長は喜んでこれを承知した。島ではよそ者の来訪はむしろ吉兆とされていた。
その日の晩、『雨おくり』の祭りのあとに、外国船の船員たちをもてなす宴が開かれた。この年も赤い実から煎じた薬が皆に振る舞われたが、船員たちはさして珍しがるふうでもなく、すするようにして薬を飲んだ。
船員たちは、その日から三ヶ月ほど島に滞在することになる。
私は船員の一人と恋仲になっていた。
彼の名前はフーといって、農家の出とあってすぐに打ち解けた。彼はよく、私に外国の話を聞かせてくれた。
ある日、「良いものがある」と言って、フーは私を連れ出した。ふたりでボートに乗り、海に出る。
天気の話や家族の話をしているあいだ、フーはどことなく落ち着きがなく、しきりに顎を撫でていた。私はそれが彼の「大切なことを言う前兆」であると知っていた。
意を決したように、フーはどこからか丸い筒状の容れ物を取り出すと、木のカップに何かを注いだ。それは神の木の煎じ薬だった。
フーが神の木の実を盗んだのだと思った私は彼を問い質した。しかし、返ってきた答えは想像もしていないものだった。
彼らの国では、神の木の実の煎じ薬は日常の嗜好品であると聞かされた。この島では数本しかない神の木が、彼の暮らす「大陸」には人の数以上に生えているらしい。信じられない話だった。
彼は私にかみかざりを手渡し「求婚するつもりで海に誘い出したのだ」と打ち明けた。かみかざりは神の木の枝を模したものだった。
自分についてくれば、何ひとつ不自由のない暮らしをさせてくれるとも言った。貴重なものであるはずのヤギの肉を毎日食べることができ、同じく、神の木の煎じ薬も好きなだけ飲ませてくれるらしい。「不自由で退屈な生活」に別れを告げて、故郷を捨てさえすれば。
季節が【夢暮れる赤焼けのころ】には、フーと船員たちは島を出るらしい。それまでに答えを聞かせて欲しいと言われて、その日は別れた。
私は結局、その日以来フーとは会わずにいた。もう一度会ってしまっては、私はきっと島を捨ててしまうと分かっていたから。
船が発つ日の朝、海をよく見渡せる崖の上から、私は彼を見送った。船影が遠のいていく。
恨めしげに青空をにらんでも、景色が滲むばかりで嵐など起きそうにない。
握りしめたかみかざりの先で、鈴生りの赤い実が揺れていた。
***
このお話は、4月20日の『珈琲牛乳の日』にちなんで、『コーヒー牛乳』をテーマにして書きました。
