
変化の激流に立つ営業組織が目指すべき姿「属人化×型化」
初めまして、藤本です。ふじけんと呼ばれています。法人営業のキャリアを歩んできて、今はスタートアップで事業責任者を務めています。
これまでにキーエンスやリクルート、スタートアップで多くの営業パーソンを見てきて、時代の流れも直に感じてきました。その経験を活かして、今回のテーマに触れたいと思います。ポートフォリオは別途リンクを貼っておくので、興味があればそちらをどうぞ!
営業組織は変革期真っ只中
現代の営業組織は、これまで以上に厳しい環境だと思いますし、これからもしばらくは続くと思っています。市場トレンドの変化は急速、顧客ニーズの多様化も待ったなしです。
さらに、社内リソースが流動的(戦略変更による配置転換など)になり、自社製品やサービスも進化途中である場合、特にスタートアップは例外なく、営業担当は日々異なる課題に向き合っていかなければなりません。こうした状況で成果を出す営業組織を維持するためには、「KPIを徹底的に管理する営業スタイル」や「トップセールス頼みの属人化された営業モデル」では限界があります。
ちなみにここでいう”営業”組織とは顧客に直接関わるすべての組織を指します。マーケもISもFSもCSもすべてです。結局全部営業だよねって思っています。
営業活動を成功させる鍵は、「柔軟性」と「構造化」の両立です。
柔軟性=変化への迅速な適応を可能にするもの
構造化=再現性のある成果を生み出す土台
この2つは一見すると相反する要素ですし、大体の組織がどちらかに傾倒しているのが現状です。
日々営業組織のあるべき姿について先人たちの教えも取り入れながら考えています。
今回は、この柔軟性と構造化を同時に実現するための営業企画について考えてみようと思います。特に、PMF前後くらいの営業組織をイメージしながら、成長フェーズごとの課題や具体的な対応策を深掘り→これからの営業組織が進むべき方向性について書いてみようと思います。

柔軟性(属人化)×構造化(型化)
属人化と型化の融合による成果最大化
言葉にすれば当たり前なのですが、理想の営業組織とは「変化に対応しながらも再現性のある成果を生み出す営業組織」です。この組織では、営業メンバーが持つ「属人的なスキルや感覚」を大切にしつつ、それを型化することで、組織全体にとって価値ある仕組みとして活かすことを目指しています。
例えば、営業メンバー一人ひとりが顧客と築く信頼関係や、顧客ニーズに対して的確な提案を行う能力は、属人化された領域です。
このようなスキルを完全に標準化することは不可能(この領域を型化しようとするとロボット型営業組織の出来上がり)ですが、一定のパターンを言語化していくことでで他のメンバーが参考にできる「成功のベストプラクティス」として共有することが可能です。
それ以上の状態(誰でもできる、真似できる、のような状態)は目指すべきではありません。
一方で、営業活動の中には、プロセスやツールを統一することで効率を高められる部分もあります。
たとえば、商談準備のプロセスや顧客対応のフローは、属人化する必要がありません。このような部分を徹底的に型化することで、チーム全体の基盤を強化しつつ、柔軟な対応が求められる部分により多くのリソースを割くことができます。
このように属人化と型化を組み合わせることで、変化に柔軟に対応しながらも、再現性の高い営業活動を実現することができると考えています。
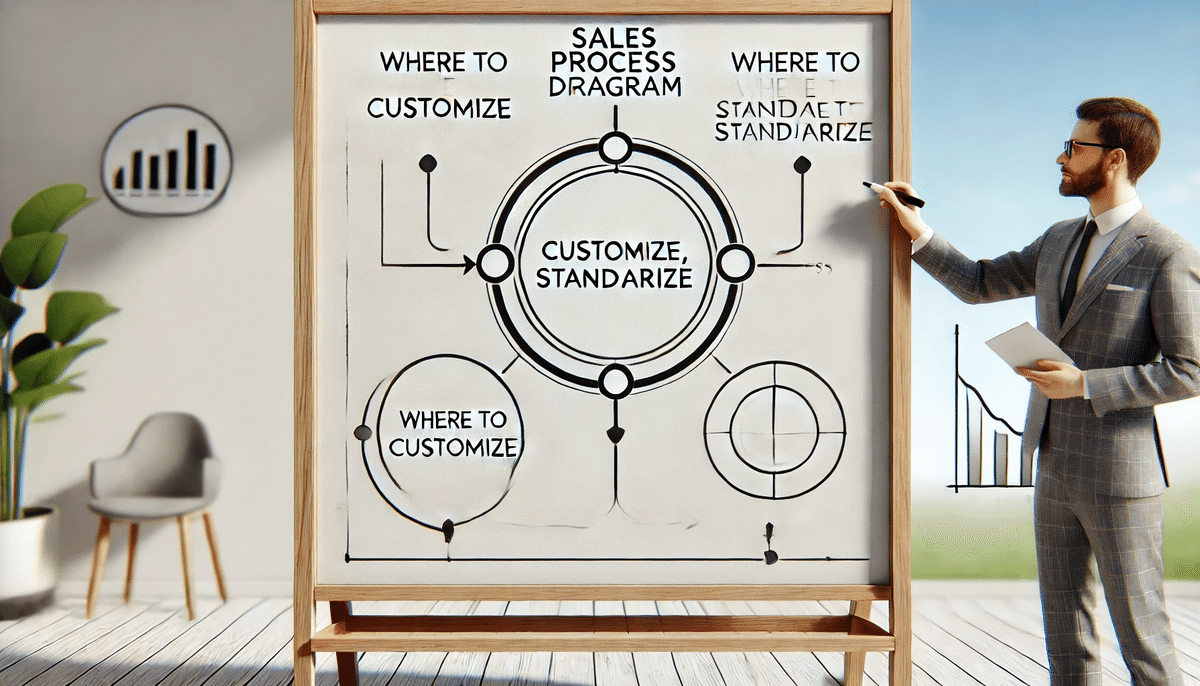
属人化と型化の切り分け
属人化と型化のバランスを適切に取ることは、成功に不可欠。ではその境界線はどこにあるのかが論点かなと。
①属人化される領域:個人の強みを活かす
属人化される領域では、営業メンバー一人ひとりが持つ「感覚」や「個性」が最大限に活かされます。これは顧客との信頼関係を築くために欠かせない要素であり、組織全体の成果を底上げする原動力ともなります。
例えば、ある営業メンバーが顧客の趣味や嗜好に基づいて共感を構築し、それをきっかけに深い関係性を築いたとします。このような属人的なスキルは、特定の顧客との長期的な関係構築に大きな貢献を果たします。また、顧客の隠れた課題を見抜く直感や、新しいアイデアを即興で提案する能力も、属人化された領域の一部です。
属人化される領域
=人間関係の作り方、趣味嗜好など性格や人間性が反映されている領域
だと私は定義しています。このスキルを尊重し、活用することで、営業メンバーが自分らしく成果を出せる環境を整えることが重要です。
②型化する領域:再現性を高める
一方で、営業活動の中には、標準化が可能であり、それによって再現性や効率性が向上する領域も存在します。例えば、商談準備のプロセスや顧客対応のフローは、誰でも実行可能な形で型化することが可能です。
具体例として、商談に必要な情報を事前にチェックリスト形式でまとめたり、フォローアップメールのテンプレートを作成するなど。営業メンバーが迷うことなく一定の品質を維持できるだけでなく、新しいメンバーへの教育コストも削減できます。
型化される領域
=PDCAを回すことができ、チーム単位で改善が見込める領域
だと私は定義をしています。型化すると決めた領域はパフォーマンスや組織の状況に関わらず徹底される必要があります。じゃないと意味ない。
属人化と型化のバランス設計
属人化と型化の切り分けは、営業組織の設計において最も重要な要素の一つです。例えば、顧客との信頼関係構築に必要な「加点要素」は属人化として残し、商談準備やフォローアップの「減点防止策」は型化を進めるべきです。
繰り返しになりますが、「これは必須じゃないけど、やれたらいいよね」というNice to haveの領域は属人化領域として営業担当に任せた方がいいですし、「これをやったら顧客の信用や信頼を失うよね」というmust haveは型化領域であり、例外なく全員が徹底できる環境を作る必要があります。

フェーズごとの営業組織設計の違い
1-10フェーズ:基盤構築期
1-10フェーズは、事業の基盤を構築する段階であり、顧客との密接な関係を構築することが最重要。この段階では、属人的なスキルが大きな役割を果たします。一部のトッププレイヤーに属人化させることを恐れず、とっとと成果を出せる仕組みにしましょう。
営業メンバーが持つ「営業感覚」を活かして、初期の成功事例を積み重ね、それを他のメンバーが共有できる形で形式化する必要があります。
このフェーズの重要アクションは,,,
初期顧客のフィードバックを徹底的に収集し、プロダクトに反映する
再現性を無視してトップラインを伸ばすことにフォーカスする
10-100フェーズ:スケール期
10-100フェーズでは、営業活動をスケールさせるための「型化」が重要になります。この段階では、標準化されたプロセスの導入に加え、データ分析が必要になる。ただ、前述の通り型化だけでは不十分であり、顧客ごとの特性に応じた柔軟性も同時に維持する必要があります。
このフェーズの重要アクションは,,,
営業活動を可視化するための基盤設計と導入
型化する領域、属人化させる領域を組織で定義する

雑まとめ
柔軟性と構造化を両立させた営業組織は、変化の激しい時代において企業の成長を支える柱となります。属人化と型化をバランスよく組み合わせることで、個々の営業メンバーが持つ「らしさ」を活かしながらも、再現性のある成果を生み出すことが可能です。
この記事が、営業組織設計に取り組むマネージャーや経営層にとって新たなヒントとなることを願っています。
記事の本題からはずれるのですが、私のライフミッションは「well-beingなrevenue組織(ここでいう営業組織)を作ること」です。これまでのようにプライベートを犠牲にして体力尽きるまで働くのではなく、うまくサボってなんとなく日々をこなすわけでもなく、全員が定時に上がって自分の生活を送りながらハイ達成するそんな組織を作ることです。
そのためにももっともっと思考を深めたいですし、同じ想いを持った人と対話を重ねたいと思っています。もし記事を読んで「藤本と話してみたいな」と思った方々、ご連絡お待ちしています。いつでも時間とります!

