
ファースト・カウ|あまりに資本主義的な一匹の牛さん
ファースト・カウ
First Cow
2020年 / アメリカ / 120分
監督 ケリー・ライカート
出演 ジョン・マガロ、オリオン・リー、トビー・ジョーンズ
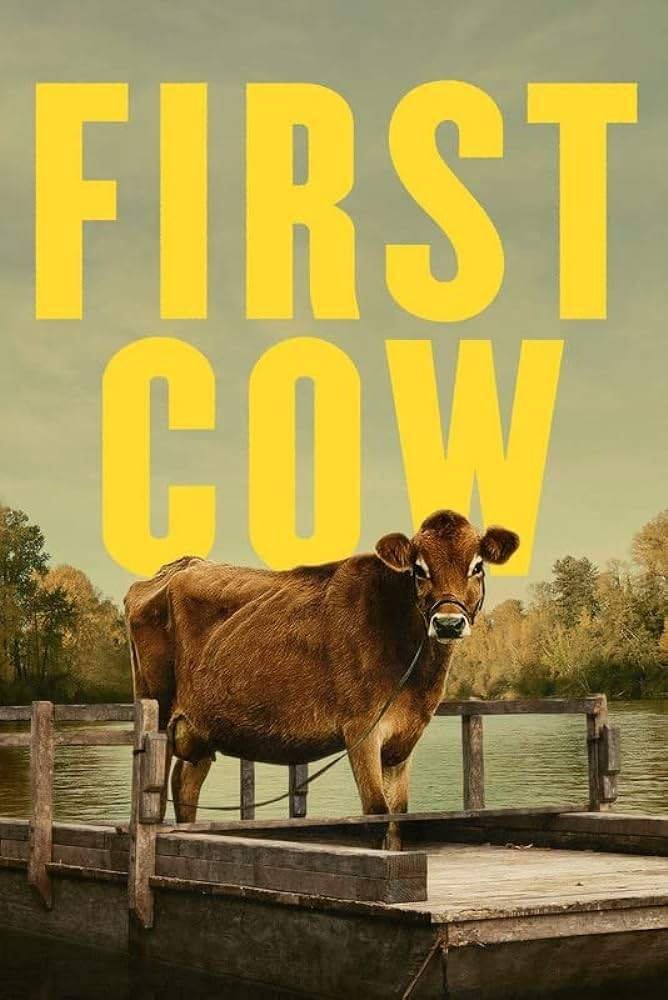
【story】
西部開拓時代、オレゴンは毛皮を狙う狩猟グループで賑わっていた。そこで偶然出会った気弱なコックのクッキーと中国人のキング・ルーは成り行きで共同生活をすることになる。その町の有力者である仲買商がはじめてオレゴンに牛を連れてきたという噂を聞き、二人は秘密でその牛のミルクを絞って、ミルク入りのお菓子を売る作戦を考える…
【review】
文責=1世
おすすめ度 ★★★★☆
「一匹の牛をめぐって攻防戦を繰り広げる西部劇!」
そう言われると荒野を舞台にカウボーイたちが銃を片手に決闘するような映画を想像してしまうかもしれない。
当然この映画はそんな話ではないわけだが。
ケリー・ライカートの新作は(とはいえ2020年の映画)はたしかに最初の一文で要約できるような西部劇ではある。だが舞台となるのは基本的にオレゴン州のジメジメした森だし、出てくるのはマッチョなカウボーイではなく明らかにひ弱そうな草食系男子たちだ。そして「牛をめぐる攻防」も銃を使ったものなんかではなく「夜中にこっそり乳搾りをできるかどうか!」という、なんともせせこましい攻防戦である。
ケリー・ライカートといえば、アメリカのインディペンデント映画界隈では生ける伝説のようになっている作家だ。男性優位だった映画業界において女性監督の道を切り拓いた第一人者としてグレタ・ガーウィグをはじめ後進の女性監督たちからは常に熱いリスペクトを受けている。日本においても数年前の特集上映をきっかけにその作品と功績にやっと光が当てられはじめたところだ。
アメリカの女性監督たちを牽引するライカートが、あえて西部劇という「男らしいアメリカ」の代名詞ともいえるジャンルで映画を作るのか。それは言うまでもなく、映画が作り上げてきた「男らしいアメリカ」のイメージを解体してみせるために他ならない。
その意味で、現代の女性が犬を散歩させて始まるオープニングはとても象徴的である。散歩中のワンちゃん(ライカート作品で犬はいつだって象徴性を帯びる)が偶然にも白骨死体を発見して、飼い主が掘り出してみる。するとその隣にも、もう一つ死体が。二人並んだ白骨死体、これはなに?というところから時制がさかのぼるこの作りは「西部開拓時代の最中で顧みられることもなく、ひっそりと死んでいった人たちの物語を発掘して語ろう」という表明とも読める。
そうやってはじまる二人の男たちの友情は、とても慎ましく温かい。
(それがゆえに端っこに追いやられるわけだが…)
コックのクッキーは暴力は苦手で、勝手に乳搾りをさせてもらってる牛にもいつも優しく語りかける。そんな性格なので、強くてマッチョな男たちの前では反抗もできずに暴力に屈するしか道はない。
相棒のキング・ルーはクッキーに比べればいくらか欲深い男で常にアメリカン・ドリームを求めているが、中国人である彼は白人中心の社会ではどうしても爪弾き者として生きるしかない。
この二人の爪弾き者の共同生活が中心となる作品なのだが、ライカートはこの二人をわかりやすい特別な絆が生まれたようにも見せないし、彼らの間に同性愛者としての恋愛関係があったかどうかもはっきりとは描かない。
ライカートは過去に『ミークス・カットオフ』(2010)という西部劇を作っておりこの作品もそれに連なる作品ではあものの、彼女のフィルモグラフィーだと最も近いのは『オールド・ジョイ』(2006)という作品になるだろう。久々に再開した男二人が温泉を目指してハイキングをするだけの映画だが、その曖昧で不明確な、それでいてとても繊細な筆致は『ファースト・カウ』とも共通している。
この二人の性格や属性をあえて断定しない描き方こそがライカート作品の不思議な味わいであり、彼女の映画作家としての品格だろう。そして、そんな曖昧で淡い語り口は爪弾き者たち二人の生活を描きながら、そこにおとぎ話のような象徴的なモチーフを潜ませることができる。
例えば、“ビーバー”というモチーフだ。
白人たちは毛皮商売のためにビーバーを乱獲していて「いつかビーバーがいなくなるのでは?」という問いに「ビーバーは無限にいる」とまで言ってのける。一方で白人以外の人々、例えば中国人のルーは「ビーバーは肝の油が漢方として売れる」と言い、その地に昔から暮らす先住民たちは「尾が美味いのに」と言う。
このビーバーをめぐってだけでも「資源」に対するそれぞれのスタンスが現れる。捕まえたビーバーを余すことなく使うアジアやアメリカ先住民に対して、そんな助言を聞き入れもせず白人たちには毛皮だけが目当て。それ以外の部分に価値は見出さない。そして掘り尽くすまで資源を乱獲し続ける。この倫理を欠いた大量消費の根っこには「資本主義」という巨大な論理が駆動している。「古き良きアメリカ」なんてものも、結局現代と変わらない「資本主義」に支配された世界でしかないと描き出す。。
そしてその「資本主義」の論理を最も象徴するのがこの映画のタイトルにもなっている“牛”だ。その地に一匹だけいる牛は、希少価値の塊、富の象徴そのものだ。だが「その地域に一匹しかいない」という状況がゆえにその”牛”には価値があるが、いずれ大量の牛がその地に流入していることは目に見えているわけで、”牛”の価値はほんの一過性のものにすぎない。
だからこそ、この映画の登場人物たちにとって”牛”は重要だ。主人公たちからすれば、この”牛”がもたらすビッグウェーブに乗るしかない!と思い、反”牛”の持ち主側は波が収まるまでなんとしても独り占めしたい!と思う。現代を動かす需要と供給の話の最もプリミティブな形がこの“牛”を取り巻く状況だろう。
そうやってケリー・ライカートはそういった童話的ともいえるモチーフから「古き良き西部」の時点から現代アメリカを蝕む病理は始まっていることを語る。しかしその一方で主人公のクッキーだけは全ての中心にある”牛”を生き物として、隣人として接する。彼だけは唯一アメリカ的な病理から抜け出している存在として描く。彼のような心優しき男が野蛮なほどの資本主義的論理で動く世界の中でどのように慎ましく生きていたのか。そしてどのように寂しく生涯を終えていったのか。その終わりはあまりに呆気なく、あまりに切れ味が鋭い。
