
本日の本請け(2024.4月)
本とそれに合う飲み物・食べ物を用意して読書しています。
『ここはすべての夜明けまえ』間宮改衣(早川書房)
SNSで評判が流れてきたので購入しました。
2123年、もうすぐ人が住めなくなりそうな環境下にある地球、九州の山奥に住む女性が主人公。25歳のときに老化しない手術を受け、長く生きてきた主人公が見送ってきた家族についての家族史を書いてあるのですが、ずーっとしゃべってる感じで書かれています。

ひらがなで読みにくいところもあるのですが、たまに漢字も差し込まれて冷静になってドキッとします。
感想としては、これまでたくさんの物語を読んで読み取ってきた「大事なこと」がぎゅっと凝縮されているなと思いました。
思春期にこの本を読んでいたらものすごく大切な本になっていたかもしれない。
でも、私にとってはタイミング的にはそうじゃなかった。
ちょっと落ち込んでしまいました。
うまく言えないのですが、主人公は被害者でもあり、加害者でもありそのことをこの家族史を書いている時点で自覚的です。
私自身は、加害者にならないように頑張って生きているのですが、最後に希望があり、彼女が救われていることに「ずるいな」と思ってしまった……気が、します。
まあ、自分だって罪に無自覚なだけかもしれないし、今後やらかしたときにこの本が救いになるかもしれない。どうだろう、言葉にしてみたのですがなんだか1割も感じたものを説明できた気がしない。そうじゃない気もする。うーん、タイミングが違った、と思う。
なので、確かにいい本でしたし「どうだった?」と尋ねられたら「よかったよ」と答えると思います。思いますが、not for meだな、と思いました。
『あかるい花束』岡本真帆(ナナロク社)
「ほんとうにあたしでいいの?ずぼらだし、傘もこんなにたくさんあるし」という短歌でバズって有名になった岡本真帆さん。下の七七を考える、というツイートを見かけ、私なら「ほんとうにあたしでいいの?ずぼらだし、傘買わないで濡れて帰るし」だな、とか思っていました(笑)。そうしたら傘増えないでしょ……?
以前に第一歌集を読んで次も楽しみだなと思っていたので、二作目が出ると知って発売日に購入しにいきました。サイン本を買えた!

いくつか好きなものを引用します。
どの道を選んでいても不安という悪魔にあうの?なんだ、よかった
風であることを選んで考えたこともなかった羽根の寂しさ
あったか〜い つめた〜い(しあわせになりたい)開けたらぬるいコーンポタージュ
花や風や雨や、自然をしっかり感じているところと、垣間見える生きてく上での寂しさ・しんどさに対する感度が好きなのかな、と思っています。
読み終わったあともふと手にとってぺらぺらめくる日があるのですが、日によって目に留まるものが違うときもあって、短歌面白いなあってなります。
『巴里マカロンの謎』米澤穂信(東京創元文庫)
小市民シリーズを、アニメ化・新刊発売の前に読み直そうキャンペーンを行なっておりました。
この本だけ読んだはずなのにどこにもない!と思ってふと電子書籍の中身調べたら以前電子で買っていました。すっかり忘れていた。

私、古典部のアニメのDVDを持っていまして、特典としてサントラが入っていたんですが、事件が解決したときに流れるBGMが「苦味が残る」というものだったんですね。そのタイトルがすごく好きで。古典部シリーズの特徴を表しているなと思えて。もっと言うと、米澤穂信作品のどれにも共通して言える気もして。
小市民シリーズも「苦味が残る」が多い気がするんですが、この番外編のような一冊は「甘味が残る」がぴったりかも!と思います。
もちろん後味の悪さというか、この人はこの後どうなったのかな、というのはあるんですがたぶん、この一冊では一貫を通して苦味を感じるのは小市民を目指す主役ふたりではない、というのが大きいのかもしれないです。もちろん、小佐内さんが甘味にありつく、というのもあります(笑)。
『愛蔵版〈古典部〉シリーズIII ふたりの距離の概算・いまさら翼といわれても』米澤穂信(KADOKAWA)
古典部の愛蔵版、3冊目。
もともとはハードカバーで揃えてたのですが、次の巻が出た後に愛蔵版の4巻も出るのかな?気になるところ。
ハードカバー2冊分でしたが、一度読んでいるのもありさくっと行けました。

最初に初見の米澤さんのエッセイを読んだのですが、これがすごくよかった。簡単に言うと、「いまさら翼といわれても」は、千反田に対して「自由」という翼を授ける話であり、「田舎のお嬢様」という記号を背負った千反田からそれを取って一個人とする、翼を奪う話でもある、というもの。
ああー、と合点が行ってしまいました。このエッセイを読んでから読む「いまさら翼をいわれても」、味わい深かったです。
「ふたりの距離の概算」は、実は最初発売されたときに読んで「なんだ。なんか何も起こらないで終わったな」と思ってたんですよね。
古典部に新入部員が入りそうだったけど、入らなかった、それだけじゃん、という。
でも今回読んでみて、勝手に誰かを脅威にしてしまったり、思い込みで怖がっていること、あるよなと思いました。それなりに自分も人生経験を積んだなと。
「鏡には映らない」の中学生時の男子コンビの暗躍や、「私たちの伝説の一冊」など、摩耶花がらみのお話が読み応えもありハラハラして、こういう女子の残酷さや派閥争いあるよなと胃がきゅっとなったりして。実は米澤作品の中では一番というほど「いまさら翼といわれても」がおすすめ!と思っているのですが、シリーズものの最新刊なので、これに辿り着く前に五冊読んでいただかないといけない……(笑)。
読み返していると、びっくりするくらい自分の脳内であのアニメの氷菓が浮かんできて、勝手に二期を再現できます。私好みの補正もかかっているんですが(笑)。DVDの特典映像で飛騨高山の景色を見たり、聖地巡礼したことがあるので、その記憶で勝手に再生できるんです。そういう余地があるくらい、あのアニメは再現性がすごかった、と思います。
読み方を豊かにしてくれるアニメをありがとうございますと言いたいです。
『冬期限定ボンボンショコラ事件』米澤穂信(東京創元文庫)
小市民シリーズ、最新刊。
ついに……!手にしたのですが、なかなか読み始めるのが惜しくて、ちょっと目次見て一旦置いて、とかやっていました(笑)。目次の章のタイトルを見て、予想以上にちょっと慎重になってしまったのもあります。あっ今回ここまで読ませてくれるのか!となって。
私にも、今回の小鳩くんのように思い出すとベッドの上をごろごろと転がりたくなるような「やっちまったな」という過去の記憶があります。
だから読み進めるのがちょっとしんどくて、のろのろのろのろと読みました。最後の4分の1くらいから一気に行った感じ。

以下、致命的なネタバレは書いていませんが、読了済みの人間が書いていますのでお気をつけください。
春期から巴里マカロンまで読み直したので、「どこに気をつけて読めばいいか」がちょっとわかっていたのもあり、読みながら推理したことがだいたい合ってた!となりました。米澤さんすごくフェアですよね。丁寧に読んで気がつけばわかるっていう。
あとたぶん、私にはわかって中学生の小鳩くんにわからなかったのは、やっぱり小鳩くん中学生だったんだな……と胸がきゅっとなりました。
結局関係はなかったのだけど、「この登場人物とこの登場人物、関係あるのでは?」というのも見つけたのですが、本命を隠すためのブラフかな?
自分の思う善意は、それがどれだけ本気であったって当事者にとっては相入れないこともある。青春の終わりは、ひとりで立てるようになること、とそう思いました。
犯人さんの叫びががっつり聞けるの、米澤作品では珍しい気がしました。
うーん、いい終わりでした。だいぶ余韻が残っています。しばらくひたひたとその余韻の波間で揺れたい。
これで小市民シリーズは終わりなのかな?巴里マカロンの雰囲気も好きだったので、外伝をまたやってもらいたいと願ってしまいます。とりあえずはアニメ楽しみ。
『算数文章問題が解けない子どもたち ことば・思考の力と学習不振』今井むつみ、楠見孝、杉村伸一郎、中石ゆうこ、永田良太、西川一二、渡部倫子(岩波書店)
以前に『言語の本質』を読んでから、今井むつみさんの本をもっと読みたいと思いオーディオブックで探したらあったので聴くことにしました。
しかし、聴き始めてからすぐにこの本が、教育委員会に要請されて作ったテストをもとにして書かれていることがわかり、「問題や表がわかる図がないとしんどいなー!?」となりました。
観念して電子書籍を購入しました。かなり論文ぽい語り口だったので、読みにくい、頭に入ってこないところはオーディオブック聴きながら、後半あたりは電子で読んで、といろいろ工夫して読み切りました。
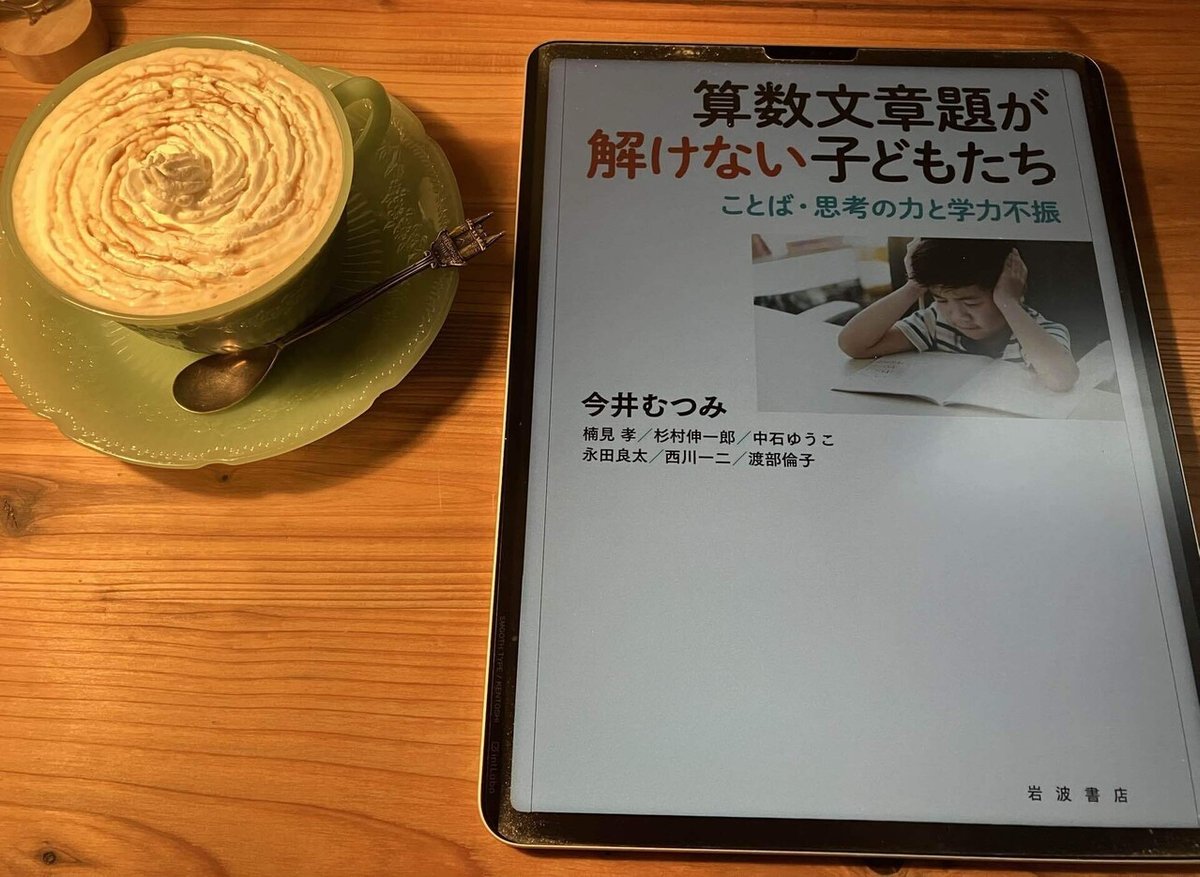
子どもたちがした間違いから、どうして間違いをしてしまうのか、というのを分析しているのですが学習支援をしている身からすると「あるある〜!」となることばかりで何度も膝を打ちました。
「根本的な問題は、子どもたちが、算数の文章問題を、自分にとって解く意味があることだと思っていないので、数字を使って思いつく演算をし、答えを出せればよいと思っているということ」という記述があって、「そうなんだよ〜!」と何度も頷いてしまいました。
答えが大きくなりそうなときは出てきた数字をたすかかけるかすればいいんだー、と思って全然読まずに式を立ててしまう。ひくとかわるでも同じ。それで○になることが何度もあったから。
たし算やひき算は、それが出てくるとこうなるよ、というようなシステムであるのに、「システムである」ということが落としこまれていない。また、分数はピザやケーキを分けるためのものと思っていて、分数とは何なのかわかっていない。
1というのはひとつ!とかの他に、12で1とする、なんかの機能もあるのだけどそれはピンとこない。
文章問題を読んでも、一体どういう状況なのか想像がついていないので、人数なのに小数でも違和感を持てない。
などなどなど……(私の解釈です)。
最後に原因をまとめてくれていて何度も読み返したのですが、結局教える立場の身として、「ではどうするか?」というところは自分で考えないといけないんだよなあ、と思いました。
『学びとは何か――〈探究人〉になるために』今井むつみ(岩波新書)
上記の『算数文章問題が解けない子どもたち』を読んでいて「スキーマ」という言葉が出てきてわからず、うーんとなったので、こちらも読んでみました。

参考文献の量が多過ぎて、電子書籍の60%で「おわりに」になって「!?」となりました(笑)。
記憶力の話が興味深かった。
「どうやったら記憶力がよくなりますか?」と子どもたちに聞かれることが多いのです。
社会が苦手、英単語を覚えるのが苦手、という子に特に。
じつは「記憶力」がよい」ということは、もともとは意味のなかった情報に意味づけをする能力だったり、必要な情報を見極めてそれを細かく観察する能力だったり、目の前の情報をすでに頭に持っているデータベースと関連づけて分類する能力だったりすることがわかる。
という部分に確かに……と思ってしまいました。これを子どもたちに伝わるように説明して、ではどう勉強すればよいか?ということを一緒に考えてあげるのはまた別の話なのですが……。
スキーマについても理解できた気がします。
私実は、幼い頃に野球のバッターについて、「来たボールに対し、バットを振ったらアウトになる、バットを振らなかったらセーフになる」と思っていました。
だから、全部バットを振らずに見送って出塁した方がいいのになんで誰もそうしないの?と思っていて、そう言ったら「は?」と言われて、無駄だと思われたのかその後もルールをちゃんと教えてもらえませんでした(笑)。
誰もルールを教えてくれなかったので、自分なりに野球の試合を見て学んだんですよね。
これって「誤ったスキーマ」だなと。修正してほしかった。そうすればもう少し野球見るの好きになったと思うんですが……。
『つながる読書――10代に推したいこの一冊』小池陽慈(編)(ちくまプリマー新書)
小池さんの本を以前読んでからとても好きで、新刊が出るたびにチェックしております。
こちらでは編集。いろんな人が10代に読んでほしい本をプレゼン形式で紹介しています。最初に小池さんと紹介者による会話があり、それから紹介に移る……というかたち。他に対談や、エッセイも入っています。

どうにも捻くれている人間なので、教科書にあった「推薦図書」は大嫌いな人間だったのですが(笑)(「推薦図書」として紹介されている本が嫌いだ、という意味ではなく、押し付けられる「推薦図書」というものが好きになれなかった、という意味です)ひとつひとつの読んでもらいたい、という理由に感じいってしまいました。
特に三宅香帆さんのお話に出てきた「傷つく読書」という言葉。
以前、「人生を変えた一冊はありますか」と訊かれたことがあり、パッと思い当たった本があったのですが、「好きな本」とは言い難く、答えていいものか、こんな話されても相手も困るかも、となんとも答えられなかったことがあります。
ちなみにその本は米澤穂信『ボトルネック』です。
私はその本を読んで「傷ついた」のですが、その傷ついた部分をどうしたらいいのか、まだ処理していなかったのもあると思います。その後、たくさん考えてnoteを書きましたが、きちんと処理するまでにずいぶんかかった気がします。
だけど、それは必要なことだったと今でも思います。だからこの言葉がぐっときたのかも。
対談の「型」を壊すという話もよかった。なんだか文学への入り口、という気がしました。ああ、自分が10代の頃にこの本があったら、文学部ってどういうことをする場所なのか、もう少し最初からわかってもっとちゃんと意思を持って学部を選べた気がします。
また、最後の草野理恵子さんのエッセイにはうるうるしちゃいました。
『歌われなかった海賊へ』逢坂冬馬(早川書房)
オーディオブックの新刊ラインナップを見ていて発見!
本屋さんで見て読みたいなと思っていたので、嬉しい。

戦争末期のドイツの地方で、ナチに対抗した少年少女たちの物語。
逢坂さんは結末の描写がすごくしっかりしているので、読み応え(聞き応え)があるなあと思います。
「文化」とは何なのか、ということにひとつの回答を出していてそれも深みがありました。
MIU404というドラマを見たときに、ある登場人物が「俺はお前たちの物語にはならない」と言うセリフがあったのですが、それを思い出してしまいました。
読了後いてもたってもいられず探して読んだインタビュー。
『銀河英雄伝説4 策謀篇』田中芳樹(東京創元社)
4巻は5巻に向けての準備段階といったかたち。
皇帝の誘拐、イゼルローン要塞での陽動、フェザーンから同盟を攻撃しようとするラインハルト。
ルパートがどうなるのか気になっていたので、ここで!となりました。
民衆は王族(王子様やお姫様)が好き、というようなセリフがあって、うーん、と思ってしまいました。本当に、かなり昔の作品とは思えない。
トリノメ商店に行ってきました
クラウドファンディングで棚オーナーになっている、浦幌町のトリノメ商店さんに行ってきました。


とても雰囲気がよく、実際いた時間の2倍くらいの滞在時間をまったりと感じていました(笑)。たまたま偶然クラウドファンディングを見かけて棚オーナーになったのですが、本屋さんがなくなってばかりの昨今、町にひとつ、こういう本屋さんがあるのはすごく素敵なことなんじゃないかなと思います。なかなか北海道に住んでいても、遠出する理由がないのでいったことない場所だらけなのですが、今回行けてよかったです。

お近くに行かれた際にはぜひ覗いてみてください。
