TOC(制約理論)で行政を改革する by Kristen Cox ⑥
こんにちは。
『行マ研サポートライター』の狂さん(Linkedin HN)こと、山﨑です。
本日は、投稿時間を変更して、記事を更新させていただきます。よろしくお願いします。
いつもお知らせしている『行マ研(全体最適の行政マネジメント研究会)』の4年ぶりのリアルセミナー
『仕事の生産性は上がってますか? 行政課題解決セミナー』
がついに明日の開催となりました👏👏👏。
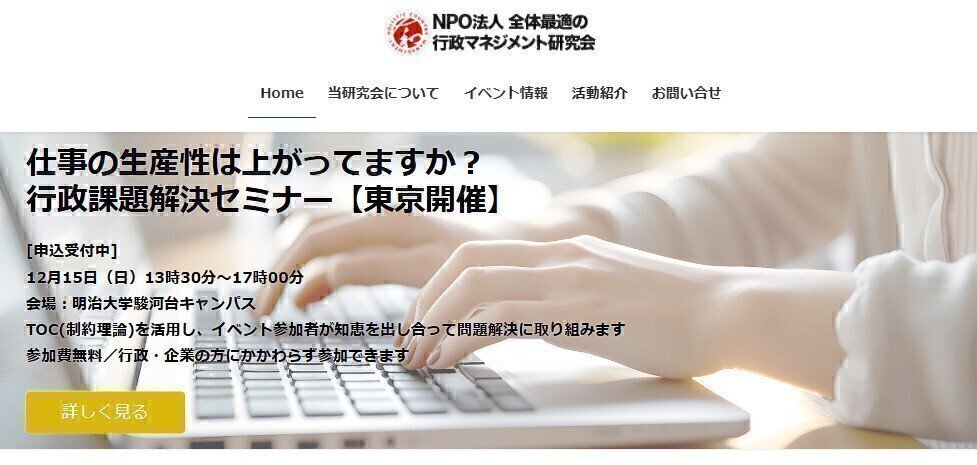
お申し込みがまだの方は、是非お申し込みいただければと思います。
さて、クリステン・コックスさんが日本に来られた際に講演された動画を、本日もご紹介したいと思います。
この動画ですが、TOCクラブの会員(登録無料)であれば誰でも見られるものなのですが、YouTubeなどでの一般公開はされていません。
ただその内容は、正に『TOC(制約理論)で行政を改革する』という、とてつもなく大きなチャレンジそのものであり、そしてそれを成し遂げられた実践報告でもあります。
発表の中でクリステン・コックスさんがいくつかの章に分けて発信されていますので、その章ごとに分けて記事を書いていきたいと思います。
動画の視聴方法
目が不自由でありながら、米国のユタ州の行政改革をリードし、Business & Enterprise Awardを受賞した米国を代表する女性経営者の一人、クリステン コックス・エグゼクティブディレクター。
納税者から託された貴重な、そして限られた予算でいかにして住民のためのマネジメントをするか、この課題に真正面からTOCで取り組んだ事例を紹介しています。
コンテンツはもちろんですが、明るい人柄と目が不自由であることを感じさせないプレゼンには、いつも圧倒され、勇気をもらえる素晴らしい内容となっています。
この動画に行き着くには、まずTOCクラブの会員登録(登録無料)をしていただいてから、トップメニューにある
[TOCクラブ・アーカイブ]
を選択してもらい、そこにドロップダウンリストがでるので、下から3番目の
[行政・社会貢献]
を選択してもらって、その後で開かれるページの一番下。
[TOCで行政を改革する by Kristen Cox]
を選んでいただくと、動画が視聴出来ます。
と、とりあえず紹介させていただきましたが、コレってどれだけ興味がある方でも、TOCクラブのサイトに行って、会員登録をして、その後動画まで辿り着くのに、これだけの数のリンクをクリックしなきゃならないというのは、余りにハードルが高すぎると思ってます。
(だから記事にしようと思ったってのもあるんですが・・・(😅))
しかしその内容は、特に行政職員の方であればあるほど、一見の価値ありとオススメ出来るものです。
また民間の方であっても、会社が官僚的な組織になりつつあるなどのお悩みがある方にとっては、本当にヒントになる内容が満載です。
1時間少々の動画ですが、ぜひ一度、ご覧いただけたらと思います。
「『ゴールを何で測るか?』を明確にするだけで、組織に集中のメカニズムが自然にできてきます。
「ゴールを何で測るかは、『品質』『スループット』『業務費用』です。
それによってゴールや優先順位が決まり、時間と共に良くなっているかどうかが分かるのです。」
「部局と仕事をする場合、プロセスの評価尺度がたくさんあり、『評価尺度の山』状態に入り込んでしまいがちですが、集中すべきところに焦点を当てた、一貫性のある数少ない評価尺度を選ぶことが大変重要です。」
「これが評価尺度に対する、私たちの取り組みです。」
ただ単に解決策・改善策を使うだけでなく、その解決策・改善策がどれだけの効果を発揮しているかを測る『正しい評価尺度』を選ぶこと。
これが、クリステン・コックスさんが選んだ、3つ目の問い
3.How do we know if we have improved?
改善しているかどうかを、どのように認識するのか?
に対する答えでした。
4.How do we sustain the effort?
どのように努力を継続するのか?

クリステン・コックスさんは、最後の質問に映っていきます。
最初に上げられた『4つの質問』の最後。
4.How do we sustain the effort?
どのように努力を継続するのか?
という問いに対する答えを、彼女は語り始めます。
「これは難問なので、少し時価を使います。」
「こんな格言があります。
どなたか『エッセンシャル思考』という本を読んだことがありますか?
(中略)
グレッグ・マキューンという人の本で面白いです。こんな格言があります。
分厚い本ですが、集中・マネジメントの時間と注力について、実にいい点を突いています。」
「彼はこういっています。
『100万通りの方向へミリ単位の進歩をしてしまいがちですが、他の選択肢も存在しています。
より少ない労力で、結果として相対的に大きな貢献をすることが可能です。』
この仕事をしていて、リーダーの優先順位が、組織の優先順位になるとますます確信しました。
リーダーが明晰さを持たず、集中していなかったら、その組織は明晰さがなく、集中していない。
明晰さを持っていなければ、希少なリソースを無駄遣いしてしまいます。
持っていたとしても、それを実現する規律や仕組みを整えているでしょうか?
とても大変なことです。」
彼女が引用した、『エッセンシャル思考』の格言にある、『100万通りの方向へミリ単位の進歩をしてしまいがち』の一節には、思い当たる節がありすぎます。
何か問題が発生しても、その解決策を意見としてぶつけ合うだけで、
「本当にその問題をどうしたいのか?」
という問いに、全く答えが出ない状況に陥ることは、珍しいことではありません。
そのような状況に陥ってしまったら、現場は次の指示が出るまで(否、次の指示が出たとしても、言っていることがそれぞれ違うので)混乱を続け、何から手を付ければ良いのかすら、分からない状況になってしまいます。
これでは、継続的改善活動を持続するなど、夢のまた夢でしょう。
「スタッフに仕事の負担をかけすぎないように、盾になったり、仕事を調整するように努めています。
プレッシャーがある時は本当に大変ですが、絶対に必要です。
いくつかの重要なことに触れた上で、そろそろまとめに入りたいと思います。」
1.集中できる仕組み
「第一に、あなたがリーダーの立場だったら、集中できる仕組みを持っていますか?」
「集中に関して、口先ではうまいこと言うことが出来ますが、本当に、集中できる意志決定が成される仕組みになっていますか?
スタッフやチーム、組織が悲鳴を上げてしまうほどに、仕事が次々と舞い込まないようにすることが・・・、とても重要なことです。」
2.継続的改善の文化を創る
「次に、継続的改善の文化を創っていますか? 継続的な訓練がありますか?」
「職員が組織的な仕組みに参加して、流れの法則に沿って、変革を起こせるようになっていますか?
本当に重要なことです。」
「訓練というのは、TOCの基本的な概念のことです。これは行政にとって重要なことです。
個人的な見解ですが、リーダーシップを持つには、一定の訓練を受けることが必要です。
社内専門家になるには、さらに必要です。
現場の職員向けには別の訓練があります。
それは誰が、どんな情報を、どんな頻度で得るべきか、など体系化されています。」
「私たちはこれを始めたばかりで、6週間以内にTOCの、基礎教育課程のウェブサイトを立ち上げようとしています。
職員たちはそこでTOCを学ぶようになります。」
3.予算はあるか?
「次に、予算があるかどうか。行政ではとても重要です。
予算。この話だけでも4時間のワークショップになりますが、部局の仕事に従事していたら・・・、その予算は本当に、組織のゴールとスループットの整合性がとれていますか?」
「予算の決定はどうやって行われていますか?」
「運営部門はこちら、予算部門はあちら。ということがよくありますが、実際には分けて考えるべきではありません。
業務を知らないで予算を立てることは、できませんし、予算なしに、実際の業務はできないのです。
それらは切っても切れない関係にあるのです。」
「ではどうやって連携していけば良いのか?
どうやって組織全体のスループットを、増やしていけるように、予算と運用を連携していけば良いのか?」
TOC(制約理論)で行政を改革する

「こう言う仕事をするのは、とても素晴らしいことです。
エキサイティングで、チャレンジングですが、困難で時間もかかるし、苦労も耐えません。
でも、とても働きがいがあります。」
「しかし、時として、TOCを単なるプロジェクトの一つとして、扱っているのを見かけることがあります。
『ここではTOCを適用して、こっちは私のやり方で』
という感じです。」
「私にとってTOCは、仕事のやり方そのものです。
単なる改善プロジェクトの一つではありません。
『どうやって仕事をするか』を考える方法なのです。
仕事の仕方の文化を変えることなのです。」
「私にとって、TOCは行政に影響を与えることができる、ベストの方法なのです。」
クリステン・コックスさんのこの言葉は、本当に彼女の人生をかけた重みがあると思います。
病気で徐々に視力を失い、今は完全に見えなくなってしまった彼女が、世界を見るために、TOC(制約理論)で行政を改革するというゴールを達成するために、彼女は学び続けるのでしょう。
同じTOC(制約理論)を学ぶものとして、私自身も彼女の背を追い続け、TOCを学び続けたいと、決意を新たにさせていただきました。
最後に

「たくさんのことを知っているように、話してきましたが、そうではありません(笑)。
学ばなければいけないことが、まだたくさんあります。
もっと磨きをかけて、改善していこうと思います。」
「最後に、私にもっとも影響を与えた話をしたいと思います。
これまで何度もこの話をしてきましたが、たくさんやるべき事があると、私を奮い立たせてくれました。」
「目が見えなくなり始めたのは11歳の時で、20代でほとんど見えなくなりました。
ある日、帰宅の途中に杖を使っていなくて、マンホールの中に落ちました。
でも、幸いなことに水か凍っていて、底まで落ちず、脚を骨折しないで済みました。
とても寒い日でした。」
「これは私にとって、大きな警鐘でした。
視覚障がい者として、どう生きていくか。答えを見つける必要があると悟ったのです。
視覚障がい者のブートキャンプと呼んでいる訓練センターに4ヶ月間行きました。
そこでは、アイマスクをしないといけないのです。
それは、まだ少し残っている視力を、使わないようにするためです。
左目は少し見えるのですが、今までと違った生活を送っていける術を学ぶために、使ってはいけないのです。」
「電気ノコギリを使い、家具を作り、極限まで追い詰めて、人生がどうあるべきかの、あらゆる過程を検証させられるのです。
この経験があるからTOCが自然に身に着いたのでしょう。」
「人生で、何ができて、何ができないか。
あらゆる過程を検証してみました。
大抵の場合、思い込みにすぎません。
だから、あらゆる過程を検証しないといけないのです。」
「私に強く印象を与えたある日のことです。
このプログラムを卒業するために、アイマスクをして、大音量の音楽がかかった車で出かけたのです。
車で街を走り回ります。
(中略)
車で走り回って、降ろされ、そこから一人で、訓練センターに戻らないといけないのです。
でも帰る途中では、一回の質問しかできません。
そこで、帰り道を見つけるのに、その他のスキルを駆使しないといけないのです。」
この訓練の途中、クリステン・コックスさんは講演に迷い込んでしまい、何度も十字に交差した道に方向を見失ってしまいます。
そして立ち止まり、動く気力をなくしていし待って、立ち止まってしまったそうです。
そんな時、彼女を見守っていた先生、トニー・コップ氏に声をかけられるのです。
「私の先生である、トニー・コップには、本当に感謝しています。
付き添ってくれた先生ですが、私からは少し離れたところにいました。
私が自分で答えを見つけられるように、ちょうど良い距離で見守ってくれていました。
必要な時はいつも側にいてくれましたが、甘やかすことはありませんでした。
側に立って、見ていてくれたのです。」
「私のところに来て、言うのでした。
『クリステン、混乱の中に入って歩くことを学ばなければいけないのだよ。恐れを乗り越えて歩き方を学ぶのだ。』」
「とても心を打つものでした。
『クリステン、立ち止まっていても、何も新しいことは得られないよ。未知のことに踏み込むことでしか、新しいことは得られないんだ。』」
「これが私のTOCの旅です。
まだTOCの多くのことが分かりません。
学んでいないことも、違ってやっていることもまだあります。
でも、この旅を始めると誓って、決意することが大切です。
この分からないことへの不快感。
失敗への恐れや、正しくできていないことといった、歩むことを妨げているものを、押しのけてしけるという決意ができるなら、TOCの学びの旅を続けることができ、ひるまないで進んでいけるのです。」
「何故なら、このTOCの旅は、職員、納税者、そして人々に、とてつもないインパクトを与えることができるからです。」
「本日は、お招きいただき、本当にありがとうございました」
講演を終えて(岸良CEOの総括)

クリステン・コックスさんが講演を終えられた後、Goldratt Japan CEOである岸良裕司氏が、この講演の総括をされています。
「彼女の言ったことで、これを思い出したんですけど・・・。」
『生産性とは、
目標に向かって会社を近づける行為そのものだ。
その反対に目標から遠ざける行為は、
すべて非生産的なんだよ。』
「どうでしょう。これ『ザ・ゴール』の中で、ジョナが語っていることなんですけども、本当に行政の方が目的を明確にして、それに近づいているのかどうかを、ちゃんと見て仕事をしていったら、どれだけ良い国になるかと、それも成果も出すというね。
これ、民間でもちゃんとやってるかどうか、分かんないですよね。それをやり切ってしまう。
もちろん目が見えないという問題があるんですけれども、彼女のキャッチフレーズで
" Focus on Ability " できることに集中する。
集中って言葉がまた、TOCですよね。
この課題が、本当に納税者にとって成果を出せるように集中していくようなこの仕事の仕方っていうのが、大変参考になったと思います。」
いかがだったでしょうか。
最後に、岸良CEOが仰っているように、一人一人がクリステン・コックスさんのように仕事が出来たら、本当に日本は良い国になると思いませんか?
行政・民間の垣根を超えて、一人一人が
" Focus on Ability " できることに集中する
ことができたら、素晴らしい未来が待っていると思いませんか?
今回、クリステン・コックスさんの講演を、ほぼ文字起こし形式でまとめさせていただきましたが、一番勉強になったのは、他ならぬ自分自身だったなぁと、改めて感じさせていただきました。
仕事の生産性は上がってますか? 行政課題解決セミナー

行マ研では、『セミナー』や『オフ会』を通じて、TOC(制約理論)の問題解決を学び、それを現場に活かしていきたいと考えています。
『全体最適のマネジメント理論』TOC(制約理論)を一緒に学び、実践する仲間を一人でも増やしたいと考えています。
そしてこの度、「仕事の生産性は上がってますか?」というテーマで、
4年ぶりにリアルの『行政課題解決セミナー』が明日、開催されます。
12月15日(日)13時30分~17時00分
会場:明治大学駿河台キャンパス
TOC(制約理論)を活用し、イベント参加者が知恵を出し合って問題解決に取り組みます。
参加費無料/行政・企業の方にかかわらず参加できます。
『セミナー』のお申し込みは、
こちら(👇)からお願いいたします。
この4年ぶりのリアルセミナーに、1人でも多くの方が集まっていただきたいと、切に願っております。
官・民の枠を超えて、メンバーを募集していますので、是非このセミナーにご参加いただきたく思っております。
