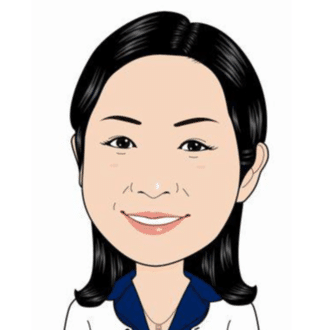「痛さは人それぞれだから」と握ってもらった手を忘れない
先日、長男の出産にまつわる痛みについて書いた。帝王切開の後陣痛で、「子宮壁をエイリアンにバリバリ食べられ、 腰をハンマーで思いっきり連打されている」ような痛みを味わった。
そんな痛みの記憶も薄れた数年後、次男の妊娠がわかった。
子どもが一人増えるのならと、都内から、埼玉県の実家の近くに引っ越すことになった。
よく子ども2人を自転車の前と後ろにのせているママさんがいる。それに加えて、抱っこひもで3人目の赤ちゃんを抱えて(おぶって)いる人もいる。おっちょこちょいの私には見ているだけで恐ろしい光景だ。自分だったら絶対に転ぶ自信がある。
かといって、都内では車生活は何かと不便だ。道は混んでいるか狭いかのどちらかだし、駐車場代も高い。なので、同じ家賃で、もっと広くて、駐車場つきの部屋が借りられないかと、都心からすこし離れたところで、あれこれ物件を探した。
実家の近くにしたのは、地元愛からというんではまったくない。都内より家賃や駐車場代が安く、かつ都心のどこへでも1時間以内で行けて、見ず知らずの場所に住むよりは知っている場所の方が何かと手間が省けるという合理的な理由からだ。そうして、やっと馴染み始めた町から、生まれ育った町に、12年ぶりくらいに戻ることになった。
次男の出産予定の病院は、私が生まれた病院だった。
1人目が帝王切開の場合でも、自然分娩ができないわけではないと主治医の先生に言われた。だが、一度切って縫った部分は、皮膚が伸縮しないので、赤ちゃんが大きく育った場合、そこから子宮壁が破裂する可能性がある。だから、2人目も帝王切開を勧めますと言われた。そんな恐ろしいこと聞いたらそりゃあ素直に手術を選ぶ。よって、次男のときはあらかじめ手術日を決めての帝王切開となった。
当日は朝から病院に行き、手術は午後の早い時間だった。2回目だったので手術前の段取りはわかっていたものの、尿道にカテーテルを通すのは寒気が止まらないくらい気持ち悪い。これは痛みとは別の苦しさだった。できればもう二度と味わいたくない。その後、手術室に入りあっという間に麻酔で意識がなくなった。
目が覚めると病室(回復室)のベッドに寝ていた。相部屋だが、私以外は誰もいない。長男のときのように手術中に目が覚めることはなく、赤ちゃん誕生の瞬間も目撃していない。「無事に生まれたんだろうか?」それさえもわからないまま、子宮に鈍く重い痛みが襲ってくる。きた。後陣痛だ。太鼓をかき鳴らすように、子宮を叩かれているような感覚になる。
痛みと闘いながらも「私の赤ちゃんは?」とずっと思っていた。
夜、だんなさんと長男がお見舞いにやってきた。長男は初めて母親と離れることに不安だったのか、まったく目を合わせない。
「赤ちゃん見た?」と訊いたら、「見たよ」と言われて、「ちゃんと元気だった?」「うん、元気だった」という会話で、無事に生まれたことを知った。
結局その日は、赤ちゃんと対面することはなく、前回同様、子宮収縮剤による後陣痛の痛みの波に翻弄され続けた。2回目は多少は慣れるものかと思っていたが、甘かった。同じようにどころか、前回よりも痛いんじゃないかと思うほどの強烈な後陣痛だった。小さいエイリアンが何匹も、バリバリと私の子宮壁を食べている。
夜中に何度もナースコールを押して、痛み止めをもらった。
ベテラン風の看護師さんには、「もう規定の量を超えているので、これ以上の痛み止めは出せません」と、あきれたような、強い口調で言われた。
こんなにも痛くって、なのにまだ赤ちゃんにも会えていない。
痛さと不安となんだかわからない感情が混ざり合って、私は泣きながら「痛いよ~、痛いよ~」とうめいていた。まるで子供のように。
するとそこに、70歳くらいに見える結構なご年齢の婦長さんがやってきた。髪の毛はほとんど真っ白で、体はぽきっと折れそうなほど細かった。ナースコールで呼び出され続けて困った看護師さんがヘルプを出したようだ。
「痛いわね・・・。痛みって本当に人それぞれだから。他の人より痛みを感じやすい人もいるし、その人にしかわからない痛みよね」
婦長さんはそう言いながら、乾いたしわしわの細い手で、私の手を握ってくれた。
そして、ベッドのそばでしばらく、
「痛いわね。痛いわよね。変わってあげられないのよね」
と繰り返し言葉をかけ続けてくれた。
不思議なことに、その少し冷たい婦長さんの手と、その穏やかな言葉は、子宮の収縮する痛みを、少しずつやわらげてくれたのだった。
きっとこの人は、私がこの病院で生まれた頃にも、看護師さんをしていたんじゃないか。私が生まれたときにも、見守ってくれていたんじゃないか、ということを思った。
どのくらいの時間かわからないけど、そうやって手を握って声をかけてもらえたおかげで、その夜は痛みとたたかいながらも、眠ることができた。
翌朝、看護師さんに「赤ちゃんにあわせてもらえませんか?」とお願いして、やっと病室にも連れてきてもらえた。だが、その後にまた、違う痛みとのたたかいが始まる。
長男のときは個室だったので、自分の病室で授乳をしていたが、このときはその後6人部屋に移って相部屋だったので、1日に何度も、点滴をカラカラと杖のように持って押しながら、授乳室に通った。
自然分娩をした産婦さんたちはみな、ドーナツのような形をしたクッションを椅子におき、「いたたたた」と言いながら椅子に座っているのがお約束の光景。手術をした私は、縫った傷がいたくて前かがみで「あいたた」と言っていた。
そんなふうに授乳室は、痛がる女の人たちと、生まれたばかりで生命のオーラがあふれまくっている新生児ちゃんたちでいっぱいだ。
次男のときは、手術後の授乳を始めたのが長男のときより遅かったので、丸い石の円盤が胸に入っているかのように、乳腺が固まってしまった。自分ではどうしようもできなくて、看護師さんにマッサージでほぐしてもらったのだが、これもまた、つながっている筋繊維や血管が「ぶちぶち」っとちぎれるんじゃないかと思うほどの壮絶な痛みだった。「いたたたた」と叫びながら、またボロボロと涙を流して泣いた。「もう無理です。ミルクでいいです」とあきらめそうになったほどだ。
「女性は痛みに強い」とよく聞くが、たぶん「痛みに強い女性がいる」というだけじゃないのか。私は痛みにすごく弱い。痛みに慣れることもない。痛いものは痛い。我慢できない。だから本当に、お子さんがたくさんいるお母さんは、それだけですごいと思う。どんだけあの痛みを潜り抜けてきたのかと尊敬のまなざしで見てしまう。
そして、痛みに弱い自分だからこそ。
婦長さんに握ってもらったときの手の感触と、言葉をかけてもらったときの心持ちは、絶対に忘れないでいたい。
婦長さんがやってくれたことは、相手の声をそのまま受け止めることだ。その人がそう受け止めているということを、受け止めること。このときの体験は、そういう「受け止める」ことの貴重な原体験になっている。誰かの痛みに、そんな風に寄り添うことができたらと思っている。
いいなと思ったら応援しよう!