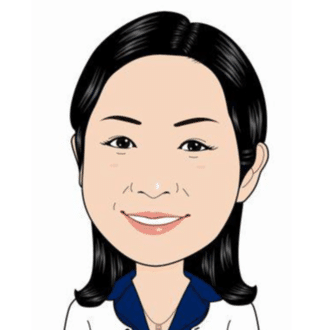『本を読む本』について(M.J.アドラー & C.V.ドーレン著)
ショーペンハウエルの『読書について』について書いた投稿が、毎週必ずダッシュボードの上位に入るくらいアクセスがある。
そうするとちょっと焦って、「あれ、私ってば何を書いたっけ?」と自分が書いたものを見返して、「そうそうそうだった、これを気をつけようと思ったんだった」と思い直す。だが、また少し経つとそんなこともすっかり忘れて……ということを何度か繰り返して今日にいたっているという状況のなか、今回は『本を読む本』について。昔のブログメモを元に。
本書は、本を読む姿勢に関して、心構えから実際の方法までがわかりやすく説明されている。読むに値する良書を知的かつ積極的に読むための方法を述べているが、すべての本がこの本の奨めるような読み方に値するわけではないとのこと。
著者のモーティマー・J・アドラーは、シカゴ大学の教授とエンサイクロペディア・ブリタニカ編集長などを歴任。もう一人の著者チャールズ・V・ドーレンはコロンビア大学教授を経て、エンサイクロペディア・インコーポレイティッド副社長。第一版は1940年にアメリカで刊行され、以来世界中で読まれているそうだ。
以下、抜粋。
●読書の目的:
・情報を得るための読書
・理解を深めるための読書
(娯楽のための読書はここには含まれない)
●読書の4つのレベル:
1.初級読書
子供が読み書きの技術を習得するための方法
2.点検読書
大きなテーマや著者の意図を見出すための方法
・拾い読み、下読み
・表面読み
3.分析読書 理解を深めるための読書法
・何についての本か
・内容を解釈する
・知識は伝達されたか
4.シントピカル読書
同一主題について、二冊以上の本を読む方法
○準備
・主題に関する文献表を作成
・文献表の中から、主題に密接な関係を持つものを調べ主題の観念を明確につかむ
○シントピカル読書
・関連書を点検し、最も主題と関連の深い箇所を発見する
・主題について、特定の著者に偏らない用語の使い方を決める
・どの著者にも偏らない命題をたてる
・さまざまな質問に対する著者の答えを整理して、論点を明確にする
・質問と論点を整理し、論考を分析する
積極的な読書をするには、読んでいるあいだに質問をすること。その質問には、さらに読書を続けているあいだに、自分自身で回答するよう努力すること。
1.全体として何に関する本か。
2.何がどのように詳しく述べられているか。
3.その本は全体として真実か、あるいはどの部分が真実か。
4.それにはどんな意義があるのか。
1冊の本全体が、その本すべての文脈であるように、関連のある何冊かの本は、これから読む本の理解を助ける大きな文脈になるのである。
振り返ってみると、以前はこの『本を読む本』の主張のような読み方をしていたことも多かったが、今は雑多にこまぎれに読み散らかしている。最近は特にそうだ。腰を据えて本と向き合えていない。
ただ、このアドバイスだけは守っている。
難解な本にはじめて取り組むときは、とにかく読みとおすことだけを心がける。理解できることだけを心にとめ難解な部分はとばして、どんどん読み続ける。脚注、注解、引用文献もここでは参照しない。いまそういうことにこだわっても、どうせわかりはしないのだから、こういう「つまづきのもと」はなるべく避けて、とにかく通読することだ。最初の通読で半分しかわからなくても、再読すれば、ずっとよくわかるようになるに違いない。
そのおかげで「読む」ことがぐっと前に押し進められたように思っている。
とはいえ、通読したとしても、再読しないのでまったく頭に残らず、内容をほとんど思い出せないまま「読んだ」という記憶だけが残っている本も少なくない。
書くことに反映させていくためにも、やはり、「読み抜く」ということが重要だろう。
すぐれた書き手は、常にすぐれた読み手でもあったが、これはむろん当時の必読書を残らず読んだということではない。読んだものはすべて、徹底的に読み抜いたのである。本を本当に自分のものにしたから、読み手は書き手の水準に到達できたのである。
「本当に自分のものにした」と言える本を、せめて3冊くらいは持ちたい。いや、でも、1冊でもそんな本があれば、それでもう充分なのかもしれない。今のところの自分には、1冊もないから。
文学に関しては、少し異なる姿勢が勧められている。
文学の影響力に抵抗してはならない。いわば、積極的な受け身とでも言うべき姿勢が必要である。物語が心にはたらきかけるにまかせ、またそれに応じて心が動かされるままにしておかなくてはいけない。つまり、無防備で作品に対するのである。
物語を読むということは、きっと小舟に乗って川に流されるようなことなのだろう。だから忙しいときや余裕がないときには、物語から少し遠ざかってしまう。物語に翻弄されるほどのバッファがない。
ここ最近、『ザリガニの鳴くところ』という作品をAudibleで聴いているが、だんだんと物語が自分の中に立ち上がっていることを感じている。
聴いているときだけでなく、日常のふとしたときに、作中の光景を思い浮かべたり、主人公のことを考えたりするのだ。まるで友人のことを思い浮かべるかのように。
物語がどこに進むかまだわからないけれど、自分が少しずつ物語の世界の住人になりつつある。物語の結末とともに、自分の体験がどういう結末を迎えるのか、楽しみである。
いいなと思ったら応援しよう!