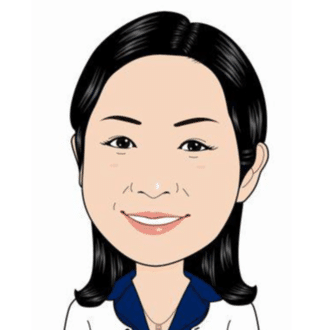フォークナーの『八月の光』を読んで
読み終わった直後の衝撃があるうちに、ざっくりとした感想だけでも書こうと思っていたが、ずるずると1週間が過ぎた。読後感を寝かせたと言えなくもないが、実際のところは、書く時間が取れていないだけだ。
自分にとっては貴重な読書体験だったので、せめて読んだ痕跡だけでも書いておきたい。書いておかないとすぐに記憶はするすると消えてなくなってしまうだろうから。
まず、フォークナーについて、Wikipediaから。
ウィリアム・フォークナーは、ヘミングウェイと並び称される20世紀アメリカ文学の巨匠であり、南部アメリカの因習的な世界を「意識の流れ」を初めとする様々な実験的手法で描いた。代表作に『響きと怒り』、『サンクチュアリ』、『八月の光』、『アブサロム、アブサロム!』など。1949年度ノーベル文学賞受賞。
フォークナーはその生涯の大半をミシシッピ州ラファイエット郡の田舎町オックスフォードにある自宅「ローアン・オーク(英語版)」(Rowan Oak)で過ごしており、彼の作品の大部分は同地をモデルにした架空の土地ヨクナパトーファ郡ジェファソンを舞台にしている。これらの作品はオノレ・ド・バルザック的な同一人物再登場法によって相互に結び付けられ、その総体はヨクナパトーファ・サーガと呼ばれる。
フォークナーに手を伸ばしたのは、数年前に中上健次の作品に触れたからだ。何で目にしたか忘れてしまったが、中上健次がまだデビュー間もない頃、柄谷行人に「フォークナーを読むといい」とアドバイスをされ、そのことが壮大な紀州サーガの作品群につながったというような記事を目にしたことがきっかけだ。
フォークナーの代表作がいくつもあるなかで今回『八月の光』を読んだのは、Kindle Unlimitedで光文社古典新訳文庫版があったからという理由からだが、結果として初めてフォークナーを読む際の入り口としてちょうどよかったと思う。
中野学而氏は、文庫版解説でこんな風に書いている。
文体や構造の面でも、きわめて難解かつ実験的な作風で知られるフォークナー作品の中ではシンプルで、総じて最も「大衆受け」しやすい作品と言えよう。
600頁くらいと結構長いのだが、物語の流れにからめとられていくように、最後まで読むことができる。
『八月の光』は、お腹の子の父親を捜して今でいうヒッチハイクを繰り返す臨月間近のリーナのストーリーから始まり、肌は白いけれど黒人の血が入っている労働者クリスマスのストーリーを主軸に、1人家に引きこもり想念の中に生き続ける牧師ハイタワーのストーリーが撚り合わさっていく。
妊婦のリーナは何があっても、他の人にどう思われようとも、いつも前を向いて文字通り進み続ける。新たな生命を宿し、決して後戻りしないリーナの姿は、未来に向けた希望的な存在ととれる。
一方で、クリスマスとハイタワーは「なんでそんなにまで……」と思うほど、自分で自分を呪っているように思える。実際は家の血であったり、人種の血であったり、古い因習であったり、呪いの理由はさまざまだが、歴史的な背景知識の浅い身からすると「自分で自分を呪う」と感じてしまう。
それにしても、相当な「呪い」だ。日本でいうと、近代文学や戦後文学にも共通したテーマは描かれていそうだが、どちらかというともっと『平家物語』のような怨念渦巻く世界、という感じがしてしまった。
特に、作品の中心となるクリスマスの行動は、自分の意思や意識からというよりは、何かの怨念に突き動かされているように思える。どうしてそんなにも自分を痛めつけ、周りの人を傷つけるのかと、読んでいてハラハラしてしまう。事実、この作品は、自分が白人か黒人かわからずにもがき苦しみながら生き、最後は残酷な殺害のしかたをされるクリスマスの悲劇の物語ととらえられることが多いという。
だが、解説の中野学而氏は、
だからこれは、決してアメリカ南部ミシシッピの悲劇にとどまるものではない。第一次世界大戦前後の西欧を震源とし、全世界にいよいよ抗いがたく広がっていった近代の力によって<ふるさと>をなくして(殺して)しまったあらゆるもののこころの痛みにまつわる、普遍的な悲劇である。
と書いている。
どれだけの歴史や時代の痛み、悲しみが、クリスマスやハイタワーの行動を通して描かれているのかと考えると、まだまだ自分は表層的な部分、文字として書かれた部分しか読めていないと痛感する。
作者のフォークナーは、1955年の太平洋戦争敗戦10年を経た日本に来て講演を行ったという。
人間はみずからの忍耐と強靭さの記録を必要するものだということを最も強く人間に思い起こさせるのは、戦争と破壊である、そう私は信じています。私の国「南部」にあっても、まさに破壊のあとにこそ、すぐれた文学がよみがえってきたのですから。
(中略)
私はこれととてもよく似たことが、ここ数年のうちにこの日本でも起こるだろうと信じます。あなたがたの破壊と絶望のなかから、全世界がその声を待ち望むような、日本だけの真実ではなく普遍的な真実を語るような一群の作家たちが誕生するだろうと信じているのです。
その一人が、間違いなく中上健次だ。自らの生まれた被差別部落を「路地」と名付け、その共同体を中心にした「紀州サーガ」の作品群を産んだ。その「血の呪い」も、数々の悲劇を生む(今はその作品群を読んでいる途中なので、これについてはまた改めて書きたい)。
フォークナーのいう「戦争と破壊」は、あの戦争に限らないだろう。日本が直面してきた多くの「破壊」――大震災やサリン事件、今私たちが潜り抜けようとしているコロナ禍など――も、普遍的な真実を、世界に向けて語るような作家が生まれるきっかけとなる(なった)はずだ。
訳者の黒原敏行さんはあとがきでこんなことを書いている。
フォークナーは、自分はたまたま南部に生まれたから南部について書いただけで、いちばん関心があるのは「人間の状況」だと述べたが、『八月の光』に登場する人物は現代の日本人にも「共感」や「理解」が充分できる人たちではないかと思うのだ。
一度と言わず、二度三度と読み返せば、登場人物どうしの魂が響き合い、アメリカ南部の架空の人物たちと世界中の読者の心が響き合うこの小説の豊かさが一層よくわかってくるはずなので、ぜひ再読をおすすめしたい。
本作品では「意識の流れ」という実験的手法によって、人物の内面の心理がかなり仔細に描かれている。読者はそこに自然と引き込まれていくので、あまり時代や地域の乖離を感じずに読むことができる。確かに黒川さんの言う通り、現代の私たちでも、十分に「共感」や「理解」ができる作品となっている。
今回は輪郭的な感想になってしまったが、全体の流れがわかった上で細部を感じることができる本当に豊かな読書体験は再読にこそあると思うので、これっきりとならないよう、腰を据えて再読したいと思う。
いいなと思ったら応援しよう!