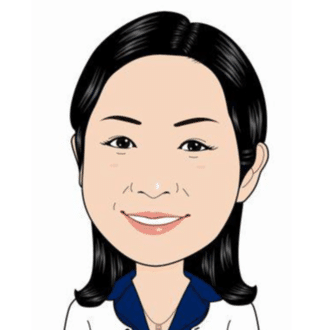「読むことは、本にのこされた沈黙を聴くことである」
遠藤周作の『沈黙』という作品を読んでいます。
マーティン・スコセッシ監督の映画『沈黙‐サイレンス-』を観て、小説を読んで、また映画を観て、今2回目の小説を読んでいるところです。
読んでいるうちに圧倒されて、なかなかページが進みません。
ネットで調べれば、いろいろな解説が読めるでしょう。だけどそれはあくまでも、自分の外にある情報でしかないし、わかった気になる危険がある。今は変に分析をしないようにして、どんなところに自分が圧倒されているのか?と問いを投げかけ、自分の中に耳をすましているところです。
作品としての『沈黙』と、言葉になっていない自分のなかの「沈黙」の両方に耳をすますと、何が聞こえてくるのか。そのうち、noteに書けるくらいにまで、言葉になってくるといいなと思っています。
さて。
沈黙というのは、とても大切なものです。
それを強く思ったのが、長田弘さんの詩集『世界はうつくしいと』(みすず書房)を読んだときでした。
偶然手にとったこの詩集は、文章がとてもリズムよく、さらに、短い文章の連なりによって、目の前に光景がくっきりとたちあらわれてきます。
そして、その光景を目にして感じるであろう感覚や感情が、自分の中に起こってきます。おそらく、著者は光景の「ありよう」を丁寧に描写することを通して、世界の本質のようなものを、伝えてくれているのではないかと考えています。
そして何より感銘を受けたのは、普段、あまり意識できていない「うつくしさ」や「はかないけれど大切なもの」などが、著者の言葉によって自分の中に「実感をともなって蘇ってくる」ような感じがしてくるところです。
その「蘇り」によって同時に、「それでいいんだよ」と、何か「大いなる承認」を受けたような気になるのです。
特に印象に残ったのは、下記の「沈黙」に関する文章です。
世界を、過剰な色彩で覆ってはいけないのだ。
沈黙を、過剰な言葉で覆ってはいけないように。
(「2004年の冬の、或る午後」より)
読むことは、本にのこされた
沈黙を聴くことである。
無闇なことばは、人を幸福にしない。
(「聴くという一つの動詞」より)
言葉を紡ぐ詩人である著者が、「言葉を紡ぐ以上に大切なことがある」と、力強く語りかけてくれています。
「読むことは、本にのこされた沈黙を聴くことである」
と考えると、遠藤周作という作家が、『沈黙』という作品を通して本当に表したかったこと。長田弘という詩人が行間に込めた思い。それらを聴けるかどうかが、作品を味わう上で大切になってくるのだと思います。
この詩集を読んで、かなり前に日本を代表する思想家 吉本隆明さんの講演「芸術言語論」が、NHKで放送されたときの言葉を思い出しました。
吉本さんがおっしゃられていたことの全体は残念ながら覚えていないのですが、印象に残った言葉をメモしました。
コミュニケーションは枝葉であり、言語の幹と根は沈黙である
言語は2つの「表出」から成っている。
花や葉、実にあたる部分で、人に伝えるためにあらわす「指示表出」。
幹や根にあたる部分で、伝達目的ではなく、自然にあらわれる「自己表出」。
日本の芸術は、短くなることで価値を新たにする言語の根幹(沈黙)に近い芸術
「言語の根幹は沈黙である」という言葉。
これも、長田弘さんの詩と通じるものがあります。
今の時期だからこそ、じっくり本を読みながら「本にのこされた沈黙」や、「著者の言語の根幹にある沈黙」に耳を澄ませてみることで、何か新しいものがたちあらわれてくるかもしれません。
いいなと思ったら応援しよう!