
【#図解のプロ】大概のことはパワーポイントと図解で解決する
こんにちは。日本を図解先進国にするMetagram代表取締役の髙野です。
日本の経済を牽引するビジネスリーダーたちには「図解が大好き」という共通点があります。
一体、図解のどのような特性がビジネスの成功に欠かせないのか、図解にはどのような魅力があるのか、一流のビジネスリーダーにインタビューしました。
今回お話をお伺いしたのは、電通で数々のアワードを受賞し、自宅に酒屋を誘致してそのまま社外取締役を務めているという一風変わった経歴をお持ちの、株式会社いまでや社外取締役で株式会社kojimake代表取締役の小島雄一郎さん。

小島雄一郎さんプロフィール
立教大学法学部を卒業し、2007年に電通入社。3年間の営業経験を経て、第1回販促会議賞(現:販促コンペ)の受賞をきっかけにプランナーに転向。 その後、同賞で5大会連続入賞。電通では社内ベンチャーとして新規事業を立ち上げ、2014年のグッドデザイン賞ビジネスモデル部門を受賞。その後は若者研究を専門としながら、子ども向けゲーム開発などで、世界3大デザイン賞であるRed dotデザイン賞(ドイツ)や、D&AD(イギリス)、キッズデザイン賞(日本)などを受賞。また「アヤナミブルー」という新しい色の概念を開発。 2023年に立ち上げた事業を売却し、電通を退社。株式会社kojimakeを設立。2024年より、自ら企画書を送って自宅に誘致したお酒のセレクトショップ"IMADEYA"の社外取締役に就任。著書は「広告のやりかたで就活をやってみた(宣伝会議)」。日経新聞とnoteである「日経COMEMO」で新時代のキーオピニオンリーダーとしても連載中。
・ ・ ・
なぜ幅広い領域でマルチに活躍できるのか
――まずは小島さんがされているお仕事について教えてください。
現在は株式会社いまでやの社外取締役として経営全般、特にブランディングとECサイト、会社内のDXを担当しています。また個人会社のkojimakeでも講演会やコンサルなどを行っておりますが、今はほとんどIMADEYAの仕事ですね。
――領域の幅が広いですね。それぞれのお仕事に共通している部分はあるのでしょうか。
仕事の種類は多いのですが、基本的な流れはどれも共通しています。人の話を聞いてパワポで企画書をつくる。企画書があることで事業やプロジェクトが動き出す瞬間が好きですね。そのためにもまずは皆さんに好き勝手言ってもらうことが大事です(笑)。そこからwordで項目を1行ずつまとめていきます。そして最後に”絵解き”していくスタイルです。
”絵解き”とは
1.絵の意味を説明すること。また、その説明。特に、仏画・絵巻などの内容を説明すること。
2.絵をかいて説明を補うこと。「絵解き事典」
3.事情や推理の過程をわかりやすく説明すること。「事件を絵解きする」
パワポはかれこれ18年くらい触り続けています。若手の頃に「僕はどうやって生きていけばいいんだろう」って悩んでいた時期があったのですが、その時に先輩から「パワポじゃん」と言ってもらったのがのめり込むきっかけだったかもしれません。思えば当時から資料作成を褒めてもらうことは多かったですね。資料作成するときは中学生が見てもわかるレベルの説明になるように心がけています。

図解は紙芝居形式だとわかりやすい
――小島さんは普段からどのように図解をしているのでしょうか。
伝えたいメッセージに当てはまるようなフレームを探すところから始めています。フレームっていうのは、これからする話の全体マップみたいなイメージです。例えばこの記事(下記リンク参照)だったら、アイデアA~Cのベン図的なフレームで最初から最後まで語れるようにします。逆に話の途中で別のフレームが必要になってしまう場合は、たぶんそのフレームが間違っているか、足りない部分があるかのどっちかなのだと思います。フレームが気に入らない時は何回でも書き直します。それくらい図解のベースとなるフレームは重要ですね。
あと図解にメタファーを用いることも意識しています。例えば採用をテーマにした図解をするときに、「池で釣りをしている人」のイラストを使って図解をしました。採用にはスカウトがするような一本釣りという比喩があるじゃないですか。だから採用を担当している人にとってもわかりやすいビジュアルが生まれます。そして紙芝居形式で話を進めていくと、採用手法をMECE(抜けなく漏れなくダブりがないこと)に分解していって「タコ壺型」とか「投網型」などの新しい比喩も生まれます。
――作図にはどのようなツールを使われていますか。
いきなりパワポを使うのではなく、まずは手書きから始めていきます。と言っても鉛筆とペンではなく、iPad miniを使うことが多いです。このサイズ感が好きなこともあるのですが、途中で描いた図を動かしたり、色を付けたりできるのがアナログにはできないメリットですね。あとは、そのままキャプチャを撮ってメールやチャットで共有できることも魅力的な機能です。

最近はパワポだけでなく、Canvaもよく使っています。使い分け方としては、パワポは複雑な構造を書き込みたいときに、Canvaはグラフィカルにシュッと図を描きたいときに触りますね。もっと大げさに表現すると、パワポは図、Canvaは絵というイメージですかね。
図解はファシリテーターにもなる
――チームでお仕事をする時にも図解は活躍されていますか。
会議にはほぼ毎回、図を持ち込んでいます。同じ図を見ながら議論をすると、図の一部を指さしながら「ここの話ですよね?」とか「こっちまでいくとどうなりますか?」とように同じ認識を維持したまま会話を進めることができるようになります。よく「小島さんはファシリテーションが上手だよね」と言われるのですが、どちらかと言うとファシリテーションは図が勝手にしてくれている感じです。
会議に図を持ち込むメリットは他にもあって、会議の質が向上すると思っています。図があることで余計な話をしないで済むというか、議論の的を絞って論点を集中させることができるんですよね。さらに、図を準備しておくと全部の声を拾うことができる。色んな人のたくさんの議論を受け入れることができるフレームを用意しておくことが大事だと思います。
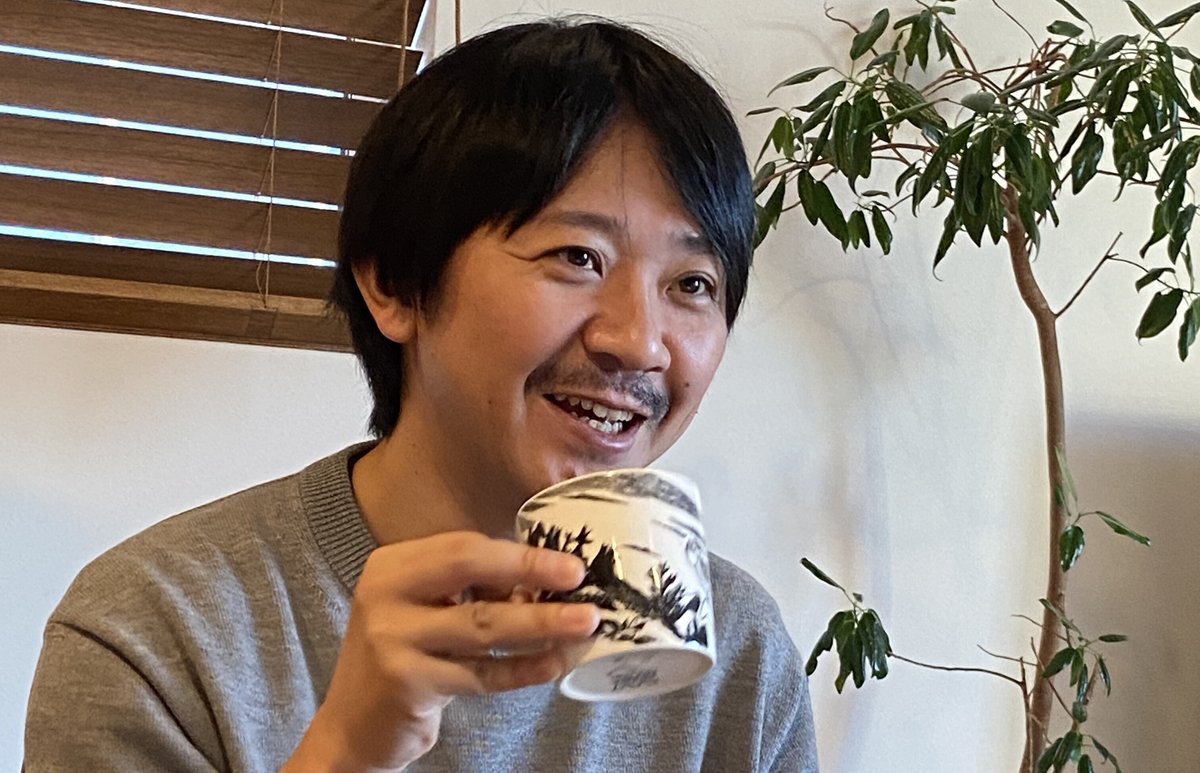
――お仕事ではたくさんの図解が登場しますね。図解はプライベートでも使いますか。
仕事では伝えるための図解の場合が多いですが、プライベートでは自分の頭を整理するために図解をすることがあります。例えば、会社を設立した時に税理士さんと相談したのですが、最初は何を言ってるか全く理解できなかったんです(笑)。それで、会話を図解して持って行って「この図の認識で合っていますか?」と聞いたらOKだったので助かりました。
他にも自分でわかりづらいと感じることを図解することはよくあります。この「うどん図解」も自分が香川県に行ったときに、うどんの種類の多さにびっくりしたのがきっかけで図解しました。
明日からの #GoToトラベル を活用して香川に行く方へ。僕が以前行った際に大混乱したので、まとめておきました。楽しい旅行になることを東京から祈っております。#香川県 の方々、パワポをご確認の上、修正・加筆いただけると幸いです。 pic.twitter.com/8xP1ZIKbm6
— 小島 雄一郎 (@you1026) July 21, 2020
――小島さんは図解のプロですが、どんな人に図解が向いていると思いますか。
片付けをしてスッキリさせたい人におすすめです。私も片付けが好きで佐藤可士和さんやこんまりさんの影響を受けているのですが、図を描くという行為は全体を見渡しながら構造化して整理することが求められます。なので、頭の中をスッキリさせてフラットな視点を獲得したい人や、モヤモヤを解消しないと気持ち悪いっていう人には持ってこいですね。
あと、図解ってノンバーバルなコミュニケーションじゃないですか。私もアメリカにいるエンジニアと仕事をする機会があるのですが、英語が苦手なのでほとんど図を使って会話しています。拙い英語でも共通言語としての図があればコミュニケーションできるんですよ。なので英語が苦手な人、グローバルでお仕事をしている方にも図解がおすすめです。

図解とは「楽しいこと」である
――最後に、小島さんにとっての「図解」とは?
私にとっての図解とは「楽しいこと」ですね。図解は楽しいことであり、嬉しいことだと感じています。モヤモヤが晴れてスッキリした瞬間を思い出すと図解してよかったなぁと感じます。

――貴重なお話をありがとうございます。
Metagramでは、図解を習慣化している方々へのインタビューを継続して参ります。「なぜ、優れたリーダーは図解するのか」を多視点から構造化して可視化することで、図解によって次世代リーダーを育成する活動を強化していきます。
株式会社Metagramとは
Metagramは「日本を図解先進国」にするために代表取締役:髙野雄一が立ち上げました。図解には「あらゆるモノゴトを多視点から構造化して可視化する」チカラがあります。『ダイアグラム思考』を用いることで、個人の思考を深めるだけでなく、 人々のコミュニケーションを認識のズレなく円滑にすることができます。図解が強みとなることで、国や地域、業種や業界、年齢や役職を問わずに、 誰もが図解でコミュニケーションできるリーダーの育成を目指します。
代表取締役:髙野 雄一

