「私を幸せにしてくれない」という言葉への違和感
こんばんは、ファーです(^-^)
お盆の絶賛7連勤中です(´・ω・`)
今日は、「私を幸せにしてくれない」っていう言葉について。
幸せは、「してもらうもの」なのかな。
幸せは、誰かが供給してくれるものじゃない。
周りに居る人間は、自分の幸せ供給機じゃない。
幸せは、自分で調達して、感知するものだと思う。
だから、幸せを増やしたいなら、
・調達する手段を増やす
・感知する範囲を広げる
この2つだとおもう。
そしてそれは、他人がしてくれることじゃなくて、自分でやること。
反論として、
「恋人は幸せをくれるやん」
とかあると思う。
確かに、
「愛してる」と言われること、
プレゼントをくれること、
スキンシップ、
そういうたくさんの“要素”をくれる。
でもそこで、それをしっかり味わえるかは、
自分による。
しっかり味わえなかったり、
恋人を「私を幸せにしてくれる」
“幸せ供給機”と思ってる人は、
すぐに「足りない、もっと」となる。
自分で調達して、
感知することが出来ないと、
与えられるのを待つことになる。
そして不平不満を漏らす。
だから「私を幸せにしてくれない」という言葉に対しては
「自分を幸せにするのは、自分の課題のなのでは?」
というのが、今のところの、考え。
アドラーの「課題の分離」で考えると、
こんな感じ。↓
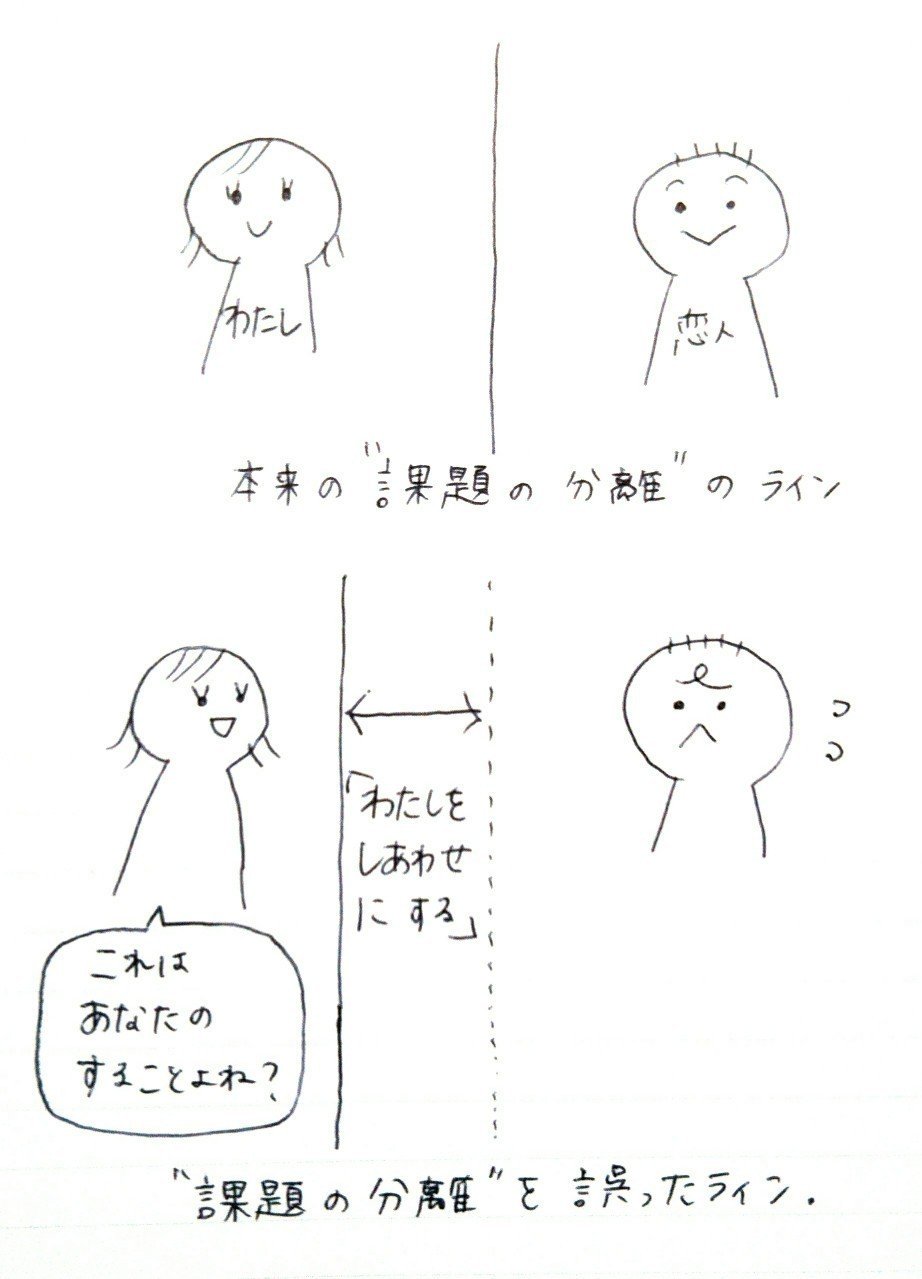
ところで
「恋人」と「幸せ」の関係は、
にわとりを育てることに似ている気がする。
ex)にわとりのお世話をする
=恋人との関係を、良好に維持する。
=自分の人生に存在してもらうためのメンテナンス
ex)たまごがうまれる
=好意を示してくれたり、力になろうとしてくれる
=人生に存在してもらうために、
メンテナンスした結果。
※強要しても生まれない、“たまたま”
相手が生んでくれたもの。(ここ重要)
今日は、こんなもんで!
ではまた会いましょう~(^-^)
