
あなたは培養肉を食べますか?

第90回アカデミー賞でゲイリー・オールドマンが主演男優賞を受賞した映画「ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男」(2018年に日本公開)をご覧になったでしょうか。第2次世界大戦中にイギリスとヨーロッパを救った英国首相チャーチルの決断を描いた映画でした。その優れた先見力は、1931年に発表したエッセー「Fifty Years Hence(50年後)」にも表れています。
同書でチャーチルは1980年代までに世界がどうなっているかを予想していますが、その中に「畜産と決別した食肉生産の方法を人類が考え出す」という一節があります。「胸肉や手羽を食べるために、鶏を1羽丸ごと育てるような不合理は終わる」「部位ごとに適切な培養地で育てるようになるだろう」そうすれば「家畜飼料用の作物栽培に使われていた土地は畑や公園、庭園となるだろう」と書いています。残念ながら1980年代にそれが実現することはありませんでしたが、チャーチルが予言した未来はもうすぐそこまで来ています。

培養肉とは?
私達はこれまで狩猟、栽培、飼育、合成、発酵(醸造)の5つの方法で食料を手に入れてきました。そして「培養」は6つ目の食料生産方法です。具体的には、動物の幹細胞をインキュベーター(培養器)やバイオリアクターと呼ばれる大きなタンクの中の培養液で育て(増やし)ます。次に、増えた細胞(バラバラの肉)を色々な形に作り上げます。ハンバーグやナゲットのように挽肉を固めた形にすることは比較的簡単です。将来的にはステーキ肉のような厚みがある肉や手羽先のような骨付き肉をダイレクトに培養形成することができるようになると思われますが、それまではハンバーグやナゲットのような形態や、3Dフードプリンターを使用した立体成形培養肉が主流になるでしょう。尚、培養魚肉も技術的にはすでに完成しています。

培養肉のメリット
現在の畜産では1㎏の牛肉を生産するには約10㎏の穀物と2000Lの水が必要だと言われています。もちろん穀物と水をこねて牛肉を作るのではありません。10㎏の穀物と2000Lの水を与えると牛が成長し、結果的に食肉部分が1㎏増えるということです。しかし、牛の体には皮や骨等、食べられない部位が多いので、食肉を得るという観点からはロスが多いと言わざるを得ません。
その点、「培養肉」はロスがありません。また、無菌状態で生産することが可能なので食中毒のリスクが劇的に低くなります。飼料が原因だったBSEも培養肉なら心配ありませんし、畜産で使用されるホルモン肥育剤や抗生物質も必要ありません。必要なら特定の栄養素を添加したり、抗体を組み込むこともできるようになるでしょう。そして何より、短期間に大量生産することが可能です。

培養肉の二次的メリット
従来の食肉生産から培養肉に切り替えると様々な二次的メリットが期待できます。まず現在、家畜の飼料にしている穀物と水を人間の食用に回すことができます。また、家畜を飼育する土地もいらなくなります。WWF(世界自然保護基金)の調査によれば、現在、全世界で家畜を飼育している土地は地表の25%を占めているそうです。もしその土地が空けば宅地や他の産業に充てられます。
その上、家畜を飼育することで発生する廃棄物が無くなります。嘘のような話ですが、全世界で発生するメタンガスの15~20%は牛のゲップによって発生しています。メタンガスは二酸化炭素の20数倍も温室効果が高いので、家畜の牛の数が減ると環境負荷が大きく軽減されます。そして最も大きなメリットであると言われているのが「動物を殺さなくても肉を食べられる」という倫理的・精神的メリットです。
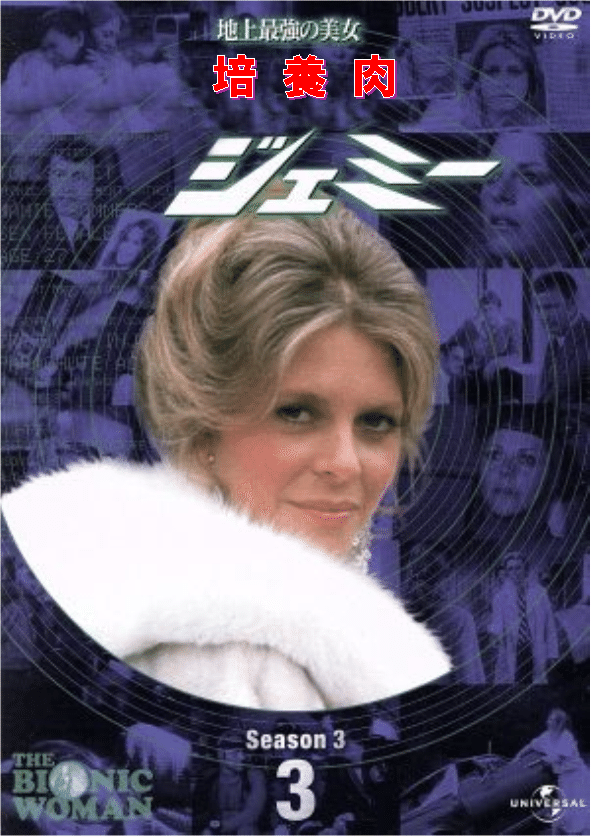
培養肉のデメリット
メリットがあればデメリットもあるのが世の常です。まず、培養肉は高い! 2013年、オランダ・マーストリヒト大学のマーク・ポスト教授が世界で初めて「培養肉のパティ」を使ったハンバーガーを発表しましたが、このときのパティ1枚当たりのコストは約3000万円でした。その後、研究技術の発展により、2020年には約4万5000円にまで下がり、現在はさらに安くなっていますが、それでも既存の食肉に比べれば高価です。とはいえ、長い目で見れば価格は必ず下がります。
問題なのは、培養肉を拒否して生きる人達のために継続して生産される、従来の畜産肉の価格です。どれぐらいの需要があるのかは分かりませんが、培養肉の価格が下がれば下がるほど、畜産肉の価格は上がるはずです。
次に、エネルギー問題があります。既存の畜産肉には穀物や水が必要ですが、培養肉を作るには膨大なエネルギーが必要です。そのために化石燃料が大量に消費されれば環境への影響は深刻なものとなるでしょう。将来的に画期的な再生可能エネルギー技術が登場しない限り、培養肉が畜産肉に取って代わることはできないでしょう。
最後に、忘れてならないのは既存の畜産業界に大きなダメージを与えることです。それは畜産業界に留まらず、食品業界全体の再編につながる可能性も有ります。

未来の話ではない
2020年、シンガポール食品庁(SFA)は世界に先駆けて培養鶏肉の販売を承認しました。許可を受けたのはアメリカのスタートアップ(先進的なテクノロジーや優れたアイデアでビジネスモデルを創出する成長速度の早い企業)であるイート・ジャスト社です。同社は2023年1月から12月まで、フーバーズ・ブッチャリー(シンガポール最大の精肉店)内のレストランで、培養鶏肉を不定期に予約販売していましたが、今年5月16日から、培養肉と植物由来の素材を組み合わせた代替鶏肉「グッド・ミート3」の予約なし店頭常時販売を開始しました。
グッド・ミート3(120g)の小売価格は7.2シンガポール・ドル(約835円、1Sドル=約116円、消費税別)です。ジャスト社によると、1パッケージ当たりの培養鶏肉の含有割合は3%で、残りは小麦、大豆など植物由来だそうです。ずいぶん培養肉の含有量が少ないと思うのですが、販売価格を抑えると、現状ではこうなってしまうとのことです。
この他に、今年4月、オーストラリアのスタートアップであるバウ社が開発した培養うずら肉がSFAの承認を受けました。同社は5月から培養うずら肉を、シンガポール都心部の高級レストランで予約販売しています。

シンガポールの危機感
なぜシンガポール政府は積極的にフードテック企業を支援し、他国に先駆けて培養肉を受け入れたのでしょうか。その背景には、国土が狭い(東京23区と同じぐらい)シンガポールが食料の90%を輸入に頼っているという事情があります。自給率の低さはこれまでも懸念されていたのですが、輸入食料に頼る現状がどれほど危うい状況であるかを、コロナ禍で気づいたのです。
狭い国土で自給率を上げるには、培養肉や野菜栽培での技術革新が必要です。その技術を持たない国は、世界中のフードテック企業を呼び込むしかありません。これは他人事ではありません。狭い国土で自給率が低いのは日本も同じです。しかし幸いなことに日本の企業には技術力があります。ベンチャーも含めて多くの企業がすでに走り出しています。
消費者として
すでに日本でも、関係省庁や食品業界で培養肉の扱いについて議論を始めています。培養肉を「食肉」として認めるのなら、その衛生基準はどうなるのか? トレーサビリティ(生産・流通プロセスの透明化)はどうするのか? 消費者に受け入れてもらうにはどうすればいいのか等、問題は山積みです。

興味深いのは、どんな観点から議論をしても「そもそも肉とは何なのか」、そこに行きついてしまうらしいのです。動物を解体して得られる物が肉なのなら、培養肉は肉ではないということになります。肉ではあるが、培養肉は自然な肉ではないという意見もあります。しかし、人の都合で人工的に産ませ、人工飼料で育て、人の都合で命を奪う既存の畜産肉が自然な肉なのかも疑問です。
培養肉を「肉」として何の違和感もなく受け入れられるのか、それは極めて個人的な感覚の問題です。先にも書きましたが、宗教や倫理観から培養肉を受け入れられない人が必ず現れるはずです。その時に、どんな意見の人も迫害されることなく、食べるものを自由に選択できる社会であって欲しいと願うばかりです。
おまけの妄想
培養肉の技術が進歩すれば、鯨やマグロ、ウナギなど、絶滅が危惧されている動物を遠慮なく食べることができます。また、パンダや象、サイ、カバなど、これまでは食肉として見なかった動物を食べることも可能です。心理的抵抗がなければですが。もっとも、ステーキにして出されれば、おそらくパンダも牛も見分けがつかないでしょう。いかがですか? 霜降りパンダ。

