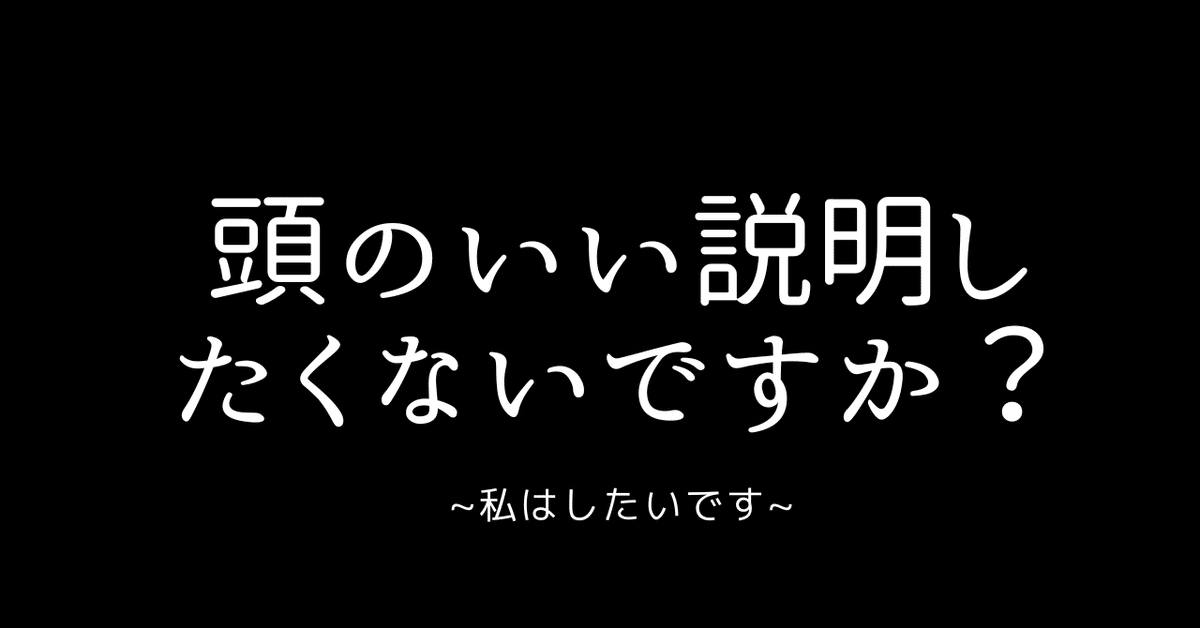
#2 頭のいい説明「すぐできる」コツ
読書#2 頭のいい説明「すぐできる」コツ
【著者】鶴野充茂さん
はじめに
私は説明が下手です。
色々知識を入れてもやっぱり下手なんです。
図で説明しようとしても図が下手なんです。
頭で思ってることをうまく図にすることもうまく出来ません。
事前に用意した資料を配っても
その資料にないことを話そうとしてしまいます。
周りの人は皆優しいので拙い説明で理解してくれます。
理解する努力をしてくれます。
私に関わる皆さんありがとうございます。
本書を読んで少しでもわかりやすい説明を出来るように頑張ります。
最近はまっている目次読みで記事にしようと思います。
本書は目次をみるだけでも手に取りたくなる本です。
第1章 「わかりやすい説明」は結論から始まる!
1.「頭のいい説明」とは「相手が行動する説明」だ
2.「大きな情報→小さな情報」の順で説明する
⇨全体を話してからその中のこの部分の話ですと説明するのが分かりやすいです。上役であればあるほど細かい部分はしらないけど全体の部分は知っているので理解して頂けると思います。
3.「ここまで、よろしいですか?」呼吸を合わせるコツ
⇨人に配慮したこういう言葉を私は発することができません。
心の中では思っているのですが、いらないかな?と思ってしまいます。
4.「部下の意見」は聞くな。「部下が見た事実」を聞け
⇨この言葉を目にし、私はまず事実だけを答えるべきだと気付かされました。返す言葉で意見を求められた場合に答えるべきだと思いました。
5.「事実+意見」が説得力の基本だ!
6.人は「正論」では動かない。「お願い」で動く!
⇨共感です。ただ正論を話しても動いてはくれません。
「それでどうしてほしいの?」となります。
正論はどちらかというと追い込むイメージがあります。
7.「結論で始まり、結論で終わる」と、わかりやすい!
⇨PREP法です。最近よく目にします。
①Point (ポイント・結論)
②Reason(理由)
③Example(例)
④Point(ポイント結論)
8.「自分の要求を強く正確に伝える」一番いい方法
⇨自分が話相手に何をお願いしたいのか強く意識すること
お願いは多々していますが、強く意識はしていない気がします。
今後お願いすることを意識して話を組み立ててからお願いしに行こうと思います。
9.「大事なことが三つあります」ー冒頭で大事なことを言う
⇨この手法はメールなどでよく使います。
相手に心の準備をしてもらい、
お願いの内容を見逃さないでもらうことができます。
10.会議で「想定外の説明」を突然求められた場合
⇨前置きをしてから自分の思っていることを話す。
「事実確認は出来ておりませんが、~のような理由で発生していると考えています。」
11.「売上を1.5倍にする」説明とは?
第2章 頭がいい人は例外なく「説明が短い」
1.「長い説明を短くする」と中味がグンと濃くなる!
⇨出来るだけ短く、不要な言葉を取り除くように努力したい!
2.「背景情報=いらない情報」の見分け方
⇨お願いされるときに背景情報は確かにあまり気にならないですよね。
誰かに説明するときに背景情報が必要になると感じます。
なんでこの作業をやっているかわからないとなります。
3.他社の動向・顧客の関心・・・「相手が聞きたい情報」から話す
4.「短い文章+短い文章」が一番聞きやすい!
「サウンド・バイト」というようです。格好いいので覚えたい!
5.エレベーター・ピッチ ー「一分間で上手に説明する法」
⇨話を短時間でまとめて話す方法、エレベータの一分間なので
実質30~45秒で話して相手のリアクションを伺い、
「後でメールします」などでまとめられるとよい。
私はエレベータであっても話題をもっておらず、
話しかけられない事が多いです。
エレベータの中に二人しかいないとき(部外者がいないとき)は何かしらの話が出来たら良いなといつも思っています。
6.「リマインド言葉⇨現在地⇨方向性」が最高の流れだ!
⇨~の件でお話があります(リマインド言葉)
現在の状況は~ (現在地)
何をしたいか (方向性)
どんなときにも使えそうな話の構成です。
意識して話をしたいです。
7.頭のいい人は「相手に考えさせない。選択肢から選ばせる」
⇨選択肢を与えるというのはあまり意識していませんでした。
選択肢がある場合は用意しますが、相手に考えさせないために
選択肢を用意するという意識を持つようにします。
8.「ビフォー・アフター」をはっきり対比させるー説得力のコツ
⇨必ず求められます。
「それでどうなるの?」「今まではどうなってたの?」
第3章 できる人は「箇条書き」で説明する!
1.「相手がメモをすることを前提」にはなせ ーわかりやすさのコツー
2.数字・固有名詞は「書いて説明する」ーメリハリのコツー
間違えて覚えるのを防ぐため。印象にも残る。
3.「サインペンでメモをする」と、なぜ記憶に焼きつく?
⇨そもそも資料を置きっぱなしにしては行けない世の中ですが、
サインペンでメモするのは本当に記憶に残ります。
インパクトあります。ボールペンよりも目に止まりますし、
視界にもよく入ってくるようになります。
4.説明「タイトルをつけてみる」引き寄せのコツ
自分の説明にタイトルをつける。
「今の説明を一言でいうと?」といわれると
難しい場合があります。常に意識することが大切です。
自分の説明に常に「一言でいうと?」を意識したいです。
5.できる人は「上司がどんなときにイエスというか」を読む
6.主語「私は」を増やすと、同じ話が力強くなる!
7.「良い・悪いを分けて話す」と、聞きやすい+わかりやすい!
第4章 「いい言葉」が「いい人間関係」を生む!
1.「一分間で信頼される人」のコツ
2.「私がやっておきます。」という魔法の言葉
⇨これを言える人は仕事ができる人だと思います。
私はそれは「ちょっと。。。」ってなってしまうことが多々あります。
自信がないのでYESと言えることは少ないです。反省です。
3.「CCメール」に即答する・しない ー意外な分岐点
4.「自己PR用のエピソード」頭のいい使い方
5.「この人の話をまた聞きたい」を思わせる心理術
6.説明上手な人は、例外なく「語尾がハッキリしている人」
7.「話の締めで相手の目を見る」ー信頼のコツー
8.「でも」「けど」・・・頭のいい人ほど「逆説語」が少ない!
⇨できる人は否定をしないです。肯定して、うまいこと話を進めるなぁといつも関心します。
第5章 信頼される人は「本気の伝え方」がうまい
1.「説明をきいた相手が協力したくなる」仕組み
⇨応援するとき、お返しをするとき、利用するとき
2.できる人ほど「自分の本気」を伝えようとする!
⇨応援するときです。ずっと練習するのをみてきたり、
身内だったりすると応援します。そういうときは協力したくなります。
これが「応援する」場合
3.「自分のこだわりを話す」習慣を
⇨普通の人はそこまでしないけど、
自分はここまでするぞというアピールをする。
4.「存在感のある笑顔」のコツ
5.「自分が仕事で成長した話」が意外な感動を呼ぶ
6.「足を運ぶ」説明術
7.「相手との接着剤になるネタ」の上手な見つけ方
⇨自分の個人的な関心に気づいてくれると、相手にも興味をもつ
これを「お返し」となります。相手に関心を持つと相手が自分のことも興味をもってくれます。まずは自分が相手に興味をもつことから始めます。
8.「あなたが得すると誰が得する?」という発想法
この発想も出来ていませんでした。自分にメリットがあると感じたことを
相手にもメリットがあると感じてもらえる内容であれば、話が通りやすいですし、相手の動きも活発になるはずと思います。これが「利用する」場合
9.「人の個々をくすぐる言葉」の法則
10.「相手を先に好きになった人が勝つ」と考える
さいごに
本書は取り入れたい内容が多すぎます。
購入してよかった。
1つずつチャレンジし、何度も読み直し
改善して行きたいです。
短い言葉が記憶に残るとありますが、
本書に出てくる以下のメッセージが記憶に残ります。
「サウンド・バイト」
「事実+意見」
「応援する。利用する。お返し。」
「返報性」
「一言でいうと?」
本書をひとことでいうと?
「今日から始める説明術」
