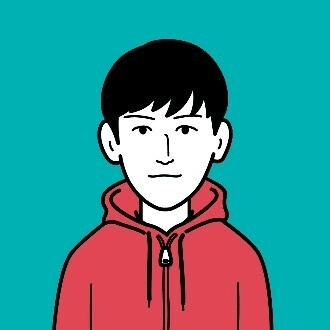30日間の革命 #革命編 130日
加賀は教室を出て高橋の後を追った。これは自分の思い過ごしなのかもしれない。高橋が革命に賛成していたなんて確証は全くない。でも、なぜか足だけは前に進んでいく。さっきまで坂本のことで自己嫌悪に陥っていたのに、今は不思議と気持ちが前向きになっている。
「絶対先生なら何か知ってるはずだ」
加賀は少し息を切らせながら、廊下を走った。そして職員室へとたどり着く。息を整えてから職員室をノックした。
「失礼します。高橋先生いますか?」
ドアを開け、職員室へと入っていく。職員室の中ではいつも通り教師たちが忙しそうにしている。電話をしている先生もいれば、パソコンに向かって何やら書類でも作成している先生もみえる。加賀は職員室を見渡した。しかし、そこに高橋の姿はない。すると、1人の教師が加賀に気づき話しかけてきた。
「あら加賀君、どうしたの?」
「すいません、高橋先生はどこにいるか知りませんか?」
「あー、高橋先生ねぇ……」
教師は職員室を見渡した。
「そういえばまだ職員室には戻ってきてないみたいよ。放課後ホームルームをやるって言ってたけど、もう終わったの?」
「……そうですか。ありがとうございます。他探してきます!」
「あ、ちょっと加賀君?」
教師の話が終わる前に、加賀は職員室から出ていった。とにかく今は高橋を探すしかない。加賀は一心に学校を駆け巡った。
「先生のいそうな場所ってどこだ? 部活の顧問もやってないし、職員室以外に行く場所なんてあるのか?」
加賀は校内をうろつきながら考えた。
「……そうか。屋上だ」
坂本と最後に話していた場所も屋上だった。確信はないものの、加賀は急いで階段を駆けあがり、屋上へと向かった。
息を切らしながら階段を駆け上がり、屋上へとたどり着く。もうすぐ日が暮れる時間となり、沈みゆく西日が校舎を照らしていた。そこで思い出すのは、あの坂本の涙だ。高橋と一緒にこのドアを通り過ぎたとき、確かに坂本は泣いていた。加賀はぐっと胸に手を当て、屋上へ出る扉を開いた。冷たい風が加賀の頬を撫でる。西日が街をオレンジ色に染め、どこか不思議な世界へと迷い込んだような気分となる。加賀は周りを見渡した。しかし、やはりここにも高橋の姿はない。
「……ここにもいないのか」
加賀はそうつぶやきながら屋上をゆっくりと歩いた。グラウンドでは相変わらず運動部の掛け声が響いている。加賀は屋上から校庭を見下ろし、運動部の姿を眺めた。再び冷たい風が吹き抜けていく。そのとき、後ろから何か物音がした。加賀は思わず振り返ると、屋上のベンチへと続くドアが半開きになっている。恐らくさっきの風で開いたのだろう。しかし、加賀が下りた時には確かに扉は閉めたはずだ。もしかしたら他の生徒にあの場所を気づかれたのかもしれない。加賀にとって屋上のベンチは坂本や白の会との大事な思い出の場所である。誰がいるのか確かめるべく、加賀は屋上のベンチへと向かった。
▼30日間の革命 第一部
まだお読みでない方は、ぜひお読みください!
▼30日間の革命 ~第二部革命編~
マガジン作成しました! 第二部はコチラからご覧ください!
takuma.o
いいなと思ったら応援しよう!