
やってるつもりのすべてのマネージャーへ 脱“文鎮型組織”のススメ【コインチェック株式会社】
暗号資産取引サービス「Coincheck」を主力に、NFTマーケットプレイス「Coincheck NFT(β版)」 バーチャル株主総会運営支援サービス「Sharely(シェアリー)」など様々なサービスを運営するコインチェック株式会社。2018年のマネックスグループ入りから約3年、急成長を遂げる同社の執行役員である大塚氏が、EVeMを導入した背景に迫る。
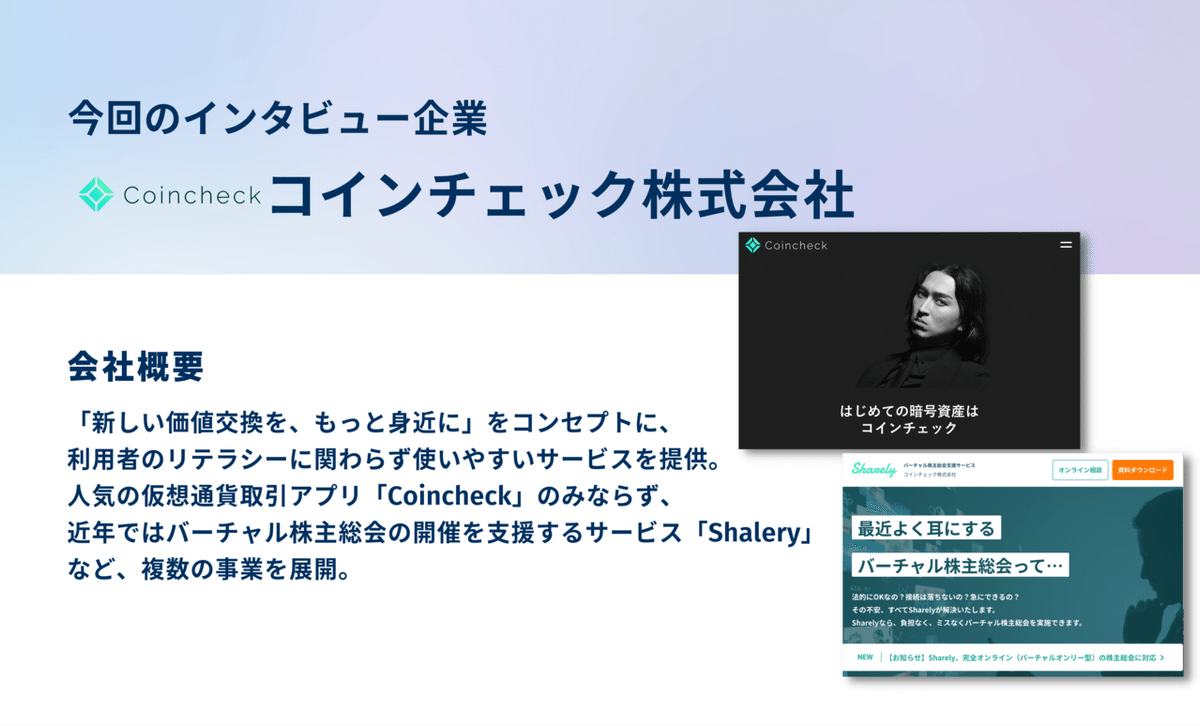
▼お問い合わせはこちら
社員数160名。ミドルマネジメント層の底上げが急務だった
ーーまず、EVeMを知ったきっかけ、および当時の貴社の状況をお聞かせください。
EVeMを知ったきっかけは、SNSだったように記憶しています。タイムライン上にはたくさんの情報が流れてきますので、大抵のことは流してしまうのですが、当時の自分は心のどこかにマネジメントに関する課題感を抱えていたのでしょう。SNSのフィード上に大量に流れる情報の中から、EVeMのプログラムについて興味を抱き、問い合わせフォームからコンタクトしました。
当時のコインチェックは150〜160名くらいの規模。しかし、実際は社員数が50名くらいの時からマネジメントの強化はしなければならないと感じていました。他のインタビューでも経営者の方たちがおっしゃっているように、会社や事業の成長スピードと、会社の中にいる人の成長スピードが合わず微妙にズレが生じてきている…という感覚がありました。
実は、会社のメンバーの数が50名までの間、私自身が全員と1on1をしていました。そのせいで、自然と1on1と採用面接だけで私のスケジュールは全て埋まっていました。
ーー50人と1on1は大変ですね。もちろん、マネジメント以外の業務も抱えている中で…
「大塚が朝8時から夜3時までずっと会社にいる」ことでなんとかカバーしていました。自分自身、アドレナリンが出ていたのか「マネージャーの自分が一番頑張ってる!」「俺、仕事してる!」という錯覚に陥ってしまっていたのですが、いま振り返ると、それは継続可能な姿ではありませんでした。実際、同じような状況にある経営者やマネージャーの方も多いのではないでしょうか。
当時の私は、文鎮の頭となるリーダーがいて、その下のメンバーは全員フラットな立場…という組織が良いと考えていたため、チームはいわゆる「文鎮型組織」でした。ただ、それでは事業のサイズ拡大に伴ってリーダーの稼働時間がボトルネックになる時がきてしまいます。ですから、チームメンバーが50名になる前の適切なタイミングで、「構造型組織」へ移行することが必要だったのだと思います。
私は実際に自分の失敗を経て気づくに至りましたが、EVeMのプログラムをもっと早くに受講していれば、組織の形を変えるべきタイミングを見逃すこともなかったかもしれません。

ーー 150人くらいの組織にマネジメントレイヤーを設ける際、組織の中の若手を引き上げる方法と、外部から新しくマネジメント経験者を採用するという2通りの方法があると思います。
前提として、アーリーステージのベンチャー企業に「マネジメントがやりたい」という人が応募してくることは少ないと思います。ベンチャーに飛び込んでくるという事は、自分自身で「手触り感」のある事業がやりたいと思っている人が多く、他人の管理や教育に興味があるという人は少数派ではないでしょうか。ですから、コインチェックでは本人のWillと会社としての必要性、または本人の将来のキャリアパスを考え合わせて、 マネージャーを経験することがその人にとってプラスであると判断できた場合は「マネジメントに挑戦してみないか」とこちらから声をかけ、意向が合致した人をマネージャー候補として扱っていくようにしています。
また、外部からマネージャー経験者を採用してくるというのは、一見手っ取り早いようで、内部のメンバーを昇格させるよりも難易度が高い挑戦だと考えています。 私は、どんなにマネージャー経験が豊富な方であっても、入社時点でマネジメントポジションとして入ってもらうのではなく、一定の期間は現場メンバーとして手を動かす作業を経験してもらうようにしています。なぜなら、現場業務の解像度が高ければ高いほど、マネージャーとしてパフォーマンスが高くなることが、自らの経験則でわかっているためです。2〜3ヶ月、オンボーディングを兼ねて現場に入り、メンバーからの信頼が得られたタイミングでマネージャーに就任する…それが1番良い導入方法だと考えており、私のその価値観を理解していただいた方にマネージャー候補として入社していただくようにしています。
ーー 外部の企業でマネジメントを経験している方を、役職付きで採用することはベンチャーではよくあると思います。ただ、そうなると即戦力としての期待も高まりますよね。
はい。私も過去にその期待を大きくしすぎて、本人にとっても過度なプレッシャーになり、組織全体が負のスパイラルに陥ってしまうという苦い経験もしました。そのような経験から、コインチェックでは、極力「役職採用(肩書を確約した採用)」は避けるようにしています。
コインチェックの大切にしている組織の価値観として【役職は役割】というものがあります。会社にとって必要な役割を果たしていたら、自然に役職がついていた、というのが理想の姿だと考えているのです。極端な話ですが、この会社において私の果たすべき役割がなくなったとしたら、明日から執行役員を辞めてもいいと思っています。
マネジメント経験者も唸る、体系的に整理されたプログラム
ーー 大塚さんご自身は、マネジメントに関する知識や経験も充分だったのではないでしょうか。EVeMのプログラムを受講して新たに気づいたことなどは、ありましたか。
自分自身、マネジメントは我流で、かつ自らの経験則に基づくものだったので、体系的/論理的に学び直してみたいと考えていました。、このタイミングでのEVeM受講は有意義なものとなりました。1回のプログラムでの学びも多く、EVeMの学習動画については予習と復習をおこなっておりました。プログラムが網羅的に「型化」されているので、自分が"できているところ”、“できていないところ”を振り返りながら改善につなげていくことができた点もよかったです。
また、自分がこれまで無意識にやってきていることや感覚のようなものが多いということも、プログラムを受講したからこその発見でした。その感覚を言語化できていないと、ミドルマネジメントから相談を受けたときに、アドバイスも説明できませんよね。「言語化」の大切さも、EVeMのプログラムを受講したからこその気づきです。
ーーEVeMのプログラムの中で、印象的だったパートや言葉はありましたか。

先程の「言語化」という話にも通じますが、EVeMのプログラム全体を貫くメッセージとして、「組織の存在意義や目標、方針といったことは、しつこいくらいに話して、意識的に伝えていくべきだ」と学びました。ベンチャーでは、マネージャーもメンバーもとても忙しく、ついつい「言わなくてもわかるだろう」「うちの会社にいるなら当たり前だよね」と説明を端折ってしまいがちですが、そこを明文化する努力を怠ると、アウトプットが大きくずれてきてしまうことがあるというのは私も思い当たるところがありました。
ーーEVeMのプログラムは、どのような企業の方におすすめでしょうか。
まさに弊社と同じように、「 事業の成長に組織が追いついていない」という悩みを抱えたすべての企業におすすめします。ただ、受講するタイミングについては、受講者本人がマネージャーになりたいと思ったタイミングと重ねられると、よりプログラムの効果が高くなるかもしれません。
また、よく「1ダース」などと表現されますが、ひとりの人間が見きれるメンバー数は多くても12人程度ではないでしょうか。それ以上の数のメンバーを1人でマネジメントしていて、自分自身が長時間働くことでなんとか回している、全てのマネージャーにEVeMを受けてみてほしい。これは、かつての自分への自戒を込めて…ですが。
ーー最後に、EVeMの導入を検討している企業様へ向け、ひとことお願いします。
実は、長村さんをはじめ、EVeMのトレーナー陣は明日にでも弊社に採用したいと思っています。(笑)
それは冗談だとしても、EVeMのプログラムを受講済みの方はぜひマネージャー候補として弊社で採用したい!と表明できるくらい、優れたプログラムだと言えます。個人・法人問わず、マネジメントに課題感を抱えている方は、説明だけでも聞いてみるといいと思います。
ーー大塚様、ありがとうございました!
EVeM HERO INTERVIEW
インタビュイープロフィール
コインチェック株式会社
執行役員 大塚 雄介氏
早稲田大学大学院修了、物理学修士号取得。リクルートから分社独立した株式会社ネクスウェイでB2B向けITソリューションの営業・事業戦略・開発設計を経験の後、レジュプレス株式会社に参画(2017年4月よりコインチェック株式会社)、2014年2月に取締役に就任。2018年4月にコインチェック株式会社がマネックスグループ株式会社の子会社となると同時に執行役員に就任。その後、2020年1月より専門役員に就任し、暗号資産の啓蒙や業界のトレンドに関する解説などの活動に従事。2021年4月より執行役員として、マーケティングや広報、株主総会支援事業などを統括する。
▼コインチェック株式会社様について詳しく知りたい方は、下記からご覧ください。
▼EVeMの法人向けプログラム(マネ型)についてのご相談・お問い合わせは、下記からお気軽にご連絡ください。
