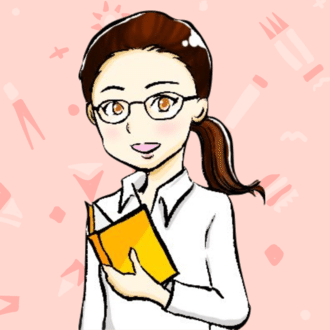180年動き続ける電池?オクスフォード電鈴とは?
世界一時間のかかるラボ実験として「ピッチドロップ実験」のことについて記事にしました。
「ピッチドロップ実験」を調べたときに、100年以上動いている実験装置として「オックスフォード電鈴」と「ビバリークロック」が出てきました。
今回は、「オックスフォード電鈴(Oxford Electric Bell)」について調べてみようと思います。
オックスフォード電鈴は、世界でもっとも長く作動している電池としてギネス記録に登録されているようです。
—————
◇ オックスフォード電鈴とは?
イギリス、オックスフォード大学のCalrendon研究室には、電池で動くベルの実験装置があります。(これがオックスフォード電鈴:Oxford Electric Bell, Clarendon Dry Piles)
このベルの装置に入っている電池が不思議なもので、1840年に設置されて以来180年にわたり動き続けているようです。(英語のWikiでは”still running”と書いてありました)
装置は、2つの電池と2つのベルがあり、電池の下にはベルが取り付けられています。ベルの間に金属球(直径約4 mm!めちゃくちゃ小さい)が吊るされていてベルを鳴らす仕組みになっています。
静電気の影響で金属球は交互にベルを鳴らしますが、金属球がベルに触れるとベルの上に取り付けられている電池が充電されて、金属球は帯電します。
帯電した金属球は静電気の作用によってもう片方のベルに吸い寄せられて鳴らしています。振動は2Hz。
電鈴自体がすごいのではなくて、中に入っている電池がすごいってことなんです。
ではこのすごい電池の中身ってどうなっているんでしょう?
◇ オックスフォード電鈴の仕組みは?
中に入っている電池は、ザンボニー電池だと言われていますが、実は誰も中身を知りません。
ザンボニー電池は、1812年にザンボニーにより開発された「静電気電池」で、銀箔、亜鉛箔、紙の円板で作られたものです。
直径約2 cmの円板を数千枚積み重ね、キャップ付きのガラス管で圧縮し、溶けた硫黄やピッチ(「ピッチドロップ実験」で使われた)に浸すことで絶縁します。
◇ 何のために作ったのか?
この実験は、the theory of contact tensionとthe theory of chemical actionの異なる2つ電気作用理論を区別する上で重要だとされています。
The theory of contact tensionは静電気原理に基づく理論ですが、1840年代に普及していた考え方で、現在となっては古い考え方となっているようです。
電気系のことはさっぱりなので、この辺で...
「実際に動いているところを見てみたい」と思って、動画を探していたら、こんな動画にたどり着きました。
こんな長い間動く電池があって、しかもなるたびに充電されるなんてすごいですよね!
もう少し、どういう目的で設置された装置なのか知りたかったのですが時間切れ...
苦手分野は言葉が入ってこないので一苦労でした。
それでは、また!
ビバリー・クロックについての記事はこちら
ギネス記録についての記事はこちら
「ピッチドロップ実験」についての記事はこちら
参考文献
いいなと思ったら応援しよう!